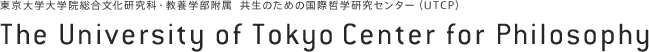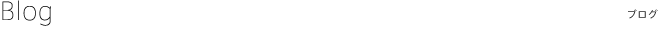【報告】「哲学を事業にすること」――株式会社TETSUGAKUの小林氏を迎えて
|
11月21日金曜日19時より、株式会社哲学の代表である小林和也さんをお迎えし、「哲学を事業にすること」と題したオンラインイベントが開催された。 株式会社TETSUGAKUの代表である小林さんは、同社の設立経緯、サービス内容、そして哲学を社会に普及させたいという情熱について語った。北海道大学発のベンチャーとして設立された同社は、世界的現象学者である田口茂氏をCPO(チーフ・フィロソフィカル・オフィサー)に迎え、企業や個人向けに哲学コンサルティングや研修などを提供している。議論は、小林氏個人の哲学への目覚めから、ビジネスにおける哲学の役割、そして今後の展望にまで及んだ。 小林さんは北海道大学発ベンチャーとして、本年6月に設立された株式会社TETSUGAKUの取り組みを紹介しながら、哲学実践を社会に開いていくことの可能性と課題について語った。同社は企業・個人向けに哲学コンサルティングを提供しており、北海道大学の現象学者・田口茂氏との協働関係のもと、学術的な専門性に基づいたサービスを展開している。 サービスとしては、主に以下の4つを提供する。 1. 哲学コーチング: 個人が抱える問題について深く考えるための対話。 2. コンサルティング: プロジェクトなどが抱える課題解決に向けた対話。 3. メディエーティング: 組織内で生まれた理念などを浸透させるための媒介的な対話の場作り。 4. 研修: 哲学の専門知識に関する講義や演習。 お話の中で印象的だったのは、小林さんが自らの現在の状況を、ハンナ・アーレント『人間の条件』の概念を通して語った点である。アーレントは人間の営みを労働(labor)、仕事(work)、活動(action)に区別したが、小林氏は今まさに会社という形で「世界に現れる」ことを試みている自分自身の状況を、アーレントの言う「活動」として捉えていた。活動とは、言葉と行為によって人が公共の場に現れ、その人のユニークな存在が暴露されることである。この実存的な自己理解のもとで会社を立ち上げたという語りには、哲学を生きることと実践することの密接な結びつきが表れていた。 彼が強調したのは、「一緒に考え抜く」ことの重要性だった。人生における大きな問いに連れ添い、共に驚き、共に探求する。答えを与えるのではなく、その人が向かうべき問題の入り口まで一緒に到達すること。彼自身、学生時代の仲間と今も読書会を続けており、哲学のテクストを共に読み、語り合える友人がいることの幸福を語った。その幸福を社会に普及させたいというのが、彼の根本的な動機となっている。小林氏の様々な実践形態は、この根源的な哲学することがたまたま異なる形を取ったものに過ぎないようにも感じられた。 |