【報告】 ハビエル・ペレス・ハラ氏講演会「Beyond Nature and Nurture: Perspectives on Human Multidimensionality」
|
2025年6月13日に、ハビエル・ペレス・ハラ Javier Pérez-Jara氏をお招きし、「Beyond Nature and Nurture: Perspectives on Human Multidimensionality」というタイトルで講演をしていただいた。 続きを読む |
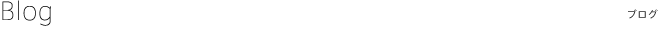
|
2025年6月13日に、ハビエル・ペレス・ハラ Javier Pérez-Jara氏をお招きし、「Beyond Nature and Nurture: Perspectives on Human Multidimensionality」というタイトルで講演をしていただいた。 続きを読む |
|
2025年5月31日、企業内哲学の資格について考えるワークショップが開催された。なお本ワークショップの内容は、別個所で詳細に取り上げられて出版される可能性もあるため、本報告は、当日の模様をごく簡単に報告するにとどめる。 本企画は、企業において哲学を実践する人の「資格」とは何か、その要件や背景を問い直し、議論する場として企画されたものである。企業の中で哲学を行うことの意味、哲学教育と実務の接続、哲学的知識と実践的知見の関係性を中心に、熱のこもった議論が展開された。 冒頭、稲岡大志(大阪経済大学)は、企業内哲学という実践が現実に存在する以上、その実践を担う人に求められる資質や資格要件について検討する必要があると述べた。博士号や修士号といった学位は必須なのか、大学の哲学教育で培われる知識やスキルは企業現場でどのように役立つのか、また、哲学を専門的に学んでいない者が企業内哲学を実践できるのかといった問題提起がなされた。 続いて、堀越耀介(東京大学UTCP特任研究員)が、企業における哲学実践の自身の事例を共有した。組織開発やコミュニケーション改善、研究開発への哲学的知見の応用、パーパス経営支援など、哲学が企業活動に寄与する多様な形を示し、特に「理念を押し付けるのではなく耕す」という姿勢の重要性を強調した。初年次研修における哲学対話実践や、「遊びとは何か」という問いを通じた製品開発支援など、具体的な事例を交えて語った。 大前みどり(ダイナミクスオブダイアログ)は、哲学対話の意義を「深く考える力を育む場」と位置づけ、対話を通じて問いを立て直し、表面的な課題を超えた根本的な問題を探求する必要性を訴えた。現場の感覚を理解し、経営理念の再定義や対話文化の醸成を支援することが企業における哲学実践の目的であり、哲学的思考力はすべてのビジネスパーソンに求められる基本的なスキルであると主張した。 佐々木晃也(大阪大学大学院)は、企業内哲学者の資格要件を考える上で、まず「今日的な哲学者」の要件を明確にする必要があると指摘した。その上で、哲学者の要件として、哲学コースの履修、注釈テキストの読解、哲学史における聖典との向き合い、概念化と問題化の技法の習得を挙げた。哲学史を学ぶことの重要性を強調し、過去の哲学者の概念を学ぶことで「私たちは別様に考えることができる」可能性を切り開くと述べた。 議論では、資格制度の必要性や具体的な要件について、学位や実務経験の有無、哲学的思考力と現場感覚のバランス、ビジネスの語彙への習熟度など、多角的な視点から意見が交わされた。哲学教育の制度的枠組みが一定の保証を持つ一方で、企業内哲学は現場の具体性に根ざし、問いを立て、構造を批判的に見直し、新たな価値を創造する営みであることが確認された。 企業と哲学の接続をめぐる探究は、なお続いていく。企業内哲学者の資格とは単なる肩書きではなく、哲学的知見と実践知を媒介し、現場に根ざした思考を育むための通路である。そのあり方は一様ではなく、多様な経路と形態を含みうることが示唆された。本ワークショップは、そうした未来像を模索する貴重な対話の場となった。 |
|
ブログ前編はこちら。 〈当日の流れ〉 |

|
2024年12月7日日曜日。銀杏の紅葉のピークをほんのすこし過ぎた快晴の午後、「幸福知のためのアート・ワークショップ・シリーズ standART beyond」の第四回「なにげないけど、いとおしい」が開催された。 続きを読む |
|---|
|
井川丹(いかわ・あかし)さんとの出会いは2021年8月に東京都美術館で行われたTURNフェス6の会場だった。TURNとは、障害の有無、世代、性、国籍など、背景や境遇の異なる人たちが出会うことで起こる相互作用を、アートを通して行うプロジェクトである。私は2019年、第8回TURNミーティングに、ライラ・カセムさん(現在UTCPのメンバーで、当時TURNプロジェクトデザイナー)に誘われて参加した。 |

|
(前編よりつづく) |
|---|
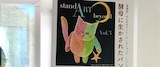
|
2024年10月20日日曜日。ずいぶん遅ればせながらやっと秋らしいさわやかな風が吹く、青く晴れた美しい日に、「幸福知のためのアート・ワークショップ・シリーズ standART beyond」の第三回「酵母に生かされたパン屋のパンの話」が開催された。 続きを読む |
|---|

|
2024年9月16日から18日にかけて愛媛県松山市、今治市、新居浜市を訪問した。UTCPからは梶谷真司先生、上廣共生哲学講座特任助教の山田理絵さん、報告者の桑山が参加し、多文化共生・統合人間学プログラム(IHS)からは大学院前期過程の鈴木里奈さん、祁卉さん、張文渓さん、そして東京大学教養学部の研究生の劉欣然さんが参加された。 続きを読む |
|---|

|
2024年9月16日から18日にかけて、IHS(多文化共生・統合人間学プログラム)の学生研修が愛媛県・松山市での研修が行われた。この研修はUTCPのセンター長であり、IHSのプログラムの教員でもいらっしゃる梶谷真司先生が主催された。IHSから3名の学生、総合文化研究科の研究生が1名参加し、UTCPから桑山裕喜子さんと報告者の山田が同行した。 続きを読む |
|---|
|
2024年10月14日ドイツ語哲学カフェ「Kaffeekränzchen: Philosophie-Jause」が開催されました。このイベントは、ドイツ日本研究所(DIJ)のゼバスチャン・ポラック・ロットマンさんとUTCP特任研究員の桑山裕喜子による運営で、関東に居住中のドイツ語母語話者・ドイツ語話者が集まり、共に決めたテーマ「前進・進展」(Fortschritt)について議論が盛り上がりました。 |
|
↑ページの先頭へ |
|---|