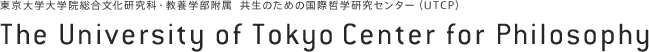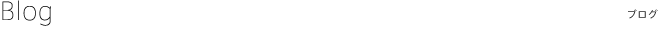【報告】2025年度 UTCPキックオフシンポジウム「共生の物語 Stories of Empathy」(後半)
2025年7月6日(日)2025年度UTCPのキックオフシンポジウム「共生の物語 - Stories of Empathy」が開催されました。この報告では、後半の村瀨孝生さんと國分功一郎さんの対談の内容をまとめます。(前半はこちら)
キックオフシンポジウムの後半では福岡県にある「宅老所よりあい」の統括所長である村瀨孝生氏にご登壇いただいた。UTCP所属教員である國分功一郎氏を聞き手に、老いと認知症を切り口とした対談が行われた。
冒頭で國分氏は、村瀨氏の著作の内容にふれ、「認知症の症状ばかりを追うあまり、人間理解の時と場を失っているのは、むしろ我々健常者ではないか」と問いかけた。それに対して村瀨氏はこれまでの現場での経験をふりかえりながら、國分氏の問いに応答された。
村瀨氏がこれまで関わった入所者のなかに、自分が食べこぼしたスパゲッティを介護者に食べさせようとした方や、身体の自由が効かないにもかかわらず、入浴介助中の村瀨氏を洗おうとする方がいたそうだ。これらの行動は、一般的に「認知症の症状」として片付けられがちだ。しかし、村瀨氏はこれを「できる・できない」の能力を超えた、他者を気遣う純粋な気持ちの表れだと捉えているという。つまり介護される側から介護する側へのケアということだ。一見逆説的なこの行為に、介護者である村瀬氏はむしろ救われ、自身の存在を肯定される瞬間があると述べた。
また、村瀨氏は認知症の人の行動が、その人自身のリアリティや、個人的な人生の物語に深く根ざしていることがあると語った。次のようなエピソードがあったそうだ。ある時、村瀨氏は利用者からリポビタンDを買ってくるよう頼まれた。そこで村瀨氏は「リポビタンD」をスーパーで購入し、利用者に渡したところ、「それは効かない」と拒否されたというのだ。利用者が求めていたのは、スーパーで売っている「リポビタンD」ではなく、その方が長年、畑仕事の帰りに寄っていた「安藤商店」で買った、茶色い紙袋に入れてもらうリポビタンDだった。どちらも商品としては同じ「リポビタンD」なのであるが、利用者にとってはスーパーで手に入れた商品と、「安藤商店」で手に入れたそれは、異なる意味を持っていた。一見不可解と思ってしまう利用者の態度の背景には、その人の人生の文脈が存在するという。介護とは、こうした個々の物語を尊重し、謎を解き明かすようにその人らしさを読み解く作業だと、村瀨氏は述べている。
私たちは、認知症の症状だけでなく「老い」に対してもポジティブなイメージをもちにくい。これに関連して國分氏は、「朝は四本足、昼は二本足、夕は三本足で歩くものは何か?」と問う、「スフィンクスの謎」に言及した。この答えは「人間」である。私たちは生産年齢人口の視点から老いを「衰退」と捉えがちだが、人間の一生は四つ足から二本足、そして三つ足へと、単一の存在が成長・衰退するのではなく、全く異なる存在へと「変容」していく過程だと捉え直すことができると國分氏は述べた。
國分氏に応答して、村瀨氏は、老いた身体には標準化された思考から解放された、私たちには持ち得ない「躍動」があると述べた。打ち上げで挨拶を頼まれたお年寄りが、未完成の天井を見て、即興で「この家が完成の暁には、また集まりましょう」と語ったエピソードは、その象徴だと紹介された。その柔軟で自由な発想は、合理性や効率を重んじる現代社会の思考様式とは一線を画すというのである。また、「ミスターマックス」を「マスターミックス」と言い続けるおばあさんの事例は、自分の信じるリアリティを揺るぎなく貫く、強靭な「思い込みの力」を示しているという。
終盤で國分氏は、村瀨氏の著作のタイトルでもある「シンクロ」という言葉に村瀨氏がこめた思いについて問いかけた。村瀨氏によると、介護における「シンクロ」とは、相手のペースやタイミングに自分の波長を合わせる「息を合わせる」行為を指す。これは、食事や入浴といった一つの行為を二人で行う際に特に重要となる。互いのタイミングがピタッと合った時、スムーズに物事が運ぶ。このシンクロが成功した時、介護する側は「良い介護ができた」と感じるという。
他方で村瀨氏は、著書の中で「シンクロしそこなった時にこそ、その人の輪郭が見える」とも述べている。國分氏はこの言葉に強く惹かれたという。なぜなら、シンクロがうまくいかない時、つまり相手から拒絶されたり、こちらの思い通りにならなかったりするとき、初めてその人の固有の「輪郭」が見えてくると考えるからだそうだ。このことについて國分氏は、人間は一人で生きているのではなく、常に他者との関係性の中で存在していることを示す「行為のコミュニズム」という概念と結びつけて論じた。
村瀨氏によれば、実際、介護の現場ではシンクロが失敗する場面が多々あるそうだ。例えば、利用者に「施設に帰ろう」と説得しても、聞く耳を持たず施設を出ていこうとする場面が多々あるそうだ。説得し続けてもどうにもならない時、介護者が説得という目的を放棄して、ただ付き添うだけの存在になることがある。この時に、介護者と利用者の双方の目的が潰え、両者はとらわれから解放される。このように目的がなくなった先に、「じゃあどうしようか」と、共に新たな地平を探す「第二の自由」が生まれるのだという。
つまり、シンクロの失敗は、一見ネガティブな出来事に見えるが、実はそこに「自由」が見出されるというのである。村瀨氏は、相手から拒絶された時、介護する側は一旦引くことで、互いの独立した存在を認識し、ホッと一息つくことができると説明した。そして、目的が潰えた時、両者が目的から解放され、共に次の次元へと進むことができる。この状態について、対談では「万策尽きた自由」と表現した。
対談の終盤に、村瀨氏自身の死生観が語られた。看取りの経験を通じて、死は「最後に死ぬ」ことではなく、身体が「最後まで生き切る」ことだと捉えるようになったと述べた。また、自身の理想とする死として「野垂れ死に」を挙げた。火葬されず、昆虫や微生物によって分解され、大地に還ることで、命が他の命に受け継がれていく循環の一部となる。この発想は、私たちの死に対する恐怖や清潔観念を乗り越え、より大きな自然の一部として生きるという、深く穏やかな思想を示しているという。
この対談は、認知症を「病気」としてのみ捉えるのではなく、人間の多様なあり方の一つとして、そして現代社会が失った自由や柔軟性を問いかける存在として捉え直す機会となったと、両者は述べた。また、介護という行為は、単に身体介助をすることを指すのではなく、哲学的な営みであるということであった。村瀨氏の介護現場での具体的な経験談と、それを哲学的に読み解く國分氏の視点が交錯し、私たちが持つ老いや認知症、ケアに関する固定観念を根底から揺るがし、新たな人間観と世界観が提示された対談であった。(報告:山田理絵)
--------
<関連イベント紹介>
村瀨孝生さんのユーモラスな介護や老いに関する語りを聞いてみたい方は、ぜひこちらの動画もご覧ください。
「老人性アメイジング!寿ぐ老いとベートヴェン」
出演:村瀨孝生、伊藤亜紗(美学者)
演奏:クァルテット・エクセルシオ
「老人性雨ジング!vol.2 寿ぎと分解」
出演:村瀨孝生、藤原辰史(京都大学人文科学研究所准教授)
ピアノ:坂本彩、坂本リサ
主催:公益財団法人せたがや文化財団 生活工房
協力:東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属共生のための国際哲学研究センター(UTCP)
---------