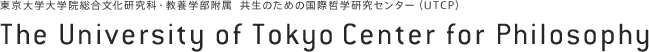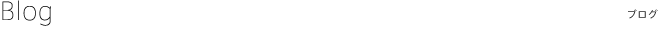【報告】智頭町訪問その3ーー哲学カフェ@タルマーリー
2024年3月17日、鳥取県智頭町の自家製天然酵母パン&クラフトビール&カフェのタルマーリーの一室にて、哲学カフェが開催された。レトロな家具がバランスよく取り揃うカフェ内から会場へ進むと、ずらっと参加者の皆さんが並んで座っている。会場には美味しい朝のコーヒーの香りが漂う。企画は関西学院大学の岡田憲夫先生と、有志で10年ほど前から耕読会と哲学カフェのファシリテーターとしてご活躍されているエンジニアの鈴木裕二さんであった。実際にパリで哲学カフェを体験し、過疎化問題に取り組む日本中の諸地域にてその実践を続けてこられた同大学の山泰幸先生も同伴された。参加者は、智頭町から10人ほど、関西学院大学・京都大学の教員・研究員が5人、また関東、関西圏から個人的興味と研究の関心から参加された方々が5人ほど集まった。オンライン参加者も含めると、全員で20人以上が集まった。UTCPからは梶谷真司先生、山田理絵さん(上廣共生哲学講座 特任助教)、宮田晃碩さん(上廣共生哲学講座特任研究員)と報告者の桑山裕喜子(特任研究員)の4人が同席した。
まずは場所の印象についてから始めたい。木々に恵まれた山々に囲まれ、町の真ん中に千代川という美しい川を持つ智頭町は、空気が美味しい。中・西部ヨーロッパの山景を思わせるかのような山々の姿は、町全体をいつも見守っているかのように見受けられた。屋外に出ると、どこを見ても山が見え、どことない安心感を覚える。ゆっくりと時間が流れるかのように感じられたのは、山に囲まれた町の静けさにもあるかもしれない。かといって、人気のないゾッとするような静けさはなく、どこか土地全体からバランスのとれた活気のようなものが感じられる。色々なところに住民の注意が行き届いているのが見てとれた。
今回哲学カフェに場所を提供してくださった自家製天然酵母パン&クラフトビール&カフェのタルマーリーの中には、アンティーク調の家具が調和を保ちながら揃えられている。日中は外の光が十分に入り、とても居心地の良い空間であった。入り口から入ると、キッチンの横にあたる場所に注文を受ける場があり、カフェの中は奥行きがある。奥に大きなアンティーク調の暖炉が置いてあり、とてもおしゃれである。
今回の哲学カフェは、この暖炉のすぐ左にある戸の先の一室にて開催された。参加者全員でぐるりと空間を囲み、前方にズーム参加者の先生方が映る。参加者全員は隣り合わせに座り、それぞれに朝の飲み物を注文してから始まった。報告者が座ったのは、京都大学防災学研究所教授のアンナ・マリア・クルーズ先生とミランダ・ダンドゥラキ先生の間、お二人が問題なく哲学カフェの対話に参加できるよう、呟き通訳を担当した。少し離れたところには、研究滞在中であったコロラド大学デンバー校コミュニケーション学科教授のハミルトン・ビーン先生が、ドイツ日本学研究所専任研究員のセバスチャン・ ポラック=ロットマンさんの通訳を交えながら参加された。
まずはテーマを決めるために、一人一つキーワードを出していく、というステップから始まった。リズムよく参加者はその場で思い立ったタームを発表していく。何度か、すべてのアイデアを確認した後、司会者の鈴木先生が一語一語挙げていき、参加者の賛同の意を表す拍手の音の大きさでテーマを決める、と言う方針が取られた。そして、いくつもの面白そうなテーマの中から「忘れる」が今回の哲学カフェのテーマに決定した。
当報告書では、どの参加者がどのような発言をしたかについては言及しない。常に訳に徹し終わったに近い報告者自身の感想としては、文字通り大盛会であったという点である。特に興味深かったのは、「忘れる」という誰にでも起こる現象が、単純なるネガティブな意味合いのみならず、ポジティブな意味合いをも持ちうる点が強調された。「忘れる」ことでできるようになったり、見えるようになったりすることがあるのみならず、一度「忘れた」ものを何かの拍子に思い出した時に、当時経験したときと比べその経験の意味合いが変化していた、といった話も印象的であった。
哲学カフェの進行の仕方として興味深かったのは、テーマ決定後すぐに参加者全員が発言をする時間があり、それによってその後自由に一人一人が発言していく際にも、とても盛り上がった点である。皆モチベーションを持って参加されていたのもとても魅力的であった。参加者の年齢層に比較的厚みがあったのも、異なる視点から「忘れる」ことについて考え、話し合うことができた一つの秘訣であったかもしれない。また、日本語を母語話者としない参加者たちも積極的に聞き入り、意見を発してくれたことも、対話にさらなる活気をもたらしたように思われた。
哲学カフェの後は、仲の良い参加者同士で集まって、タルマーリーさんご用意のチキンカレーをいただいた。タルマーリーさんの所では、何を食べても美味しかった。小麦粉を食べると体に反応が出る報告者のこともいつも配慮してくださって、お米物も用意してくださった。帰りに東京に持って帰ったお土産のタルマーリーのパンを食べた周囲の人々は皆「美味しい」と言ってくれた。その中でも西欧出身の一人が特にそのパンに驚いて「これ本当に美味しい、どこで見つけたの」と言って喜んでくれたのも印象深い。お昼ご飯終了後は、有志でタルマーリーの工房を見学し、解散となった。
今回の智頭での出張で報告者は、「コモンズ」としての「コミュニカティヴ・スペース」というキーワードを学んだ。どのような信条や政治的思想を持つ人々であれ、集まって対等に話し合えるといった「場」など、日本では公立の小中学校ですら実現が難しくなって久しいように見受けられてならない。哲学カフェや哲学対話は、そういったもはや「不可能」と思われがちな対話の場所を提供することができる。それはある種の、人々が共有し、共に運営する一つの財産としてみなされて良いのではないだろうか。もちろん、どのようにしてこういった「場」を生み出していくのか、あるいは続けていくのか、といった問いには、企画者と参加者の個々人がそれぞれに、そして共に、経験を積み、毎回のディスカッションの「場」を豊かにする、時間をかけた働きかけなしには答えられないものである。智頭の町活性化活動は、既に40年もの歴史を有している。近年の眩しいほどの智頭町の発展や活気も、たとえそれぞれの活動がそれぞれに違った思いのもと実現しているにせよ、その40年間の努力があって生まれている変化なのかもしれない、と一訪問者でしかない報告者は考えた。
帰りの電車から緑豊かな山道を見ながら、岡田先生が1日目に残した言葉を思い出した。「自然にできている(ものがあって)、(それには)その良さと、それで(=それによって)起こる問題もある。どうしてそれが自然にできているのか、別の視点から見ることで、その(自然に機能している何かの)ルーツを無くさないようにする(ことが大切だ)。」今自分の置かれている現状に何の問題を感じない場合も、感じる場合も、その「現状」はいずれにせよいつもあって「当然」なものではない。「現状」の持つポテンシャルも、またその限界状況も、どちらについても考える視点は、今その「現状」を受動的にのみ享受する自分の持つ視点とは区別されうるはずだ。「現状」を享受するすべての人が、「享受する」視点とは違う視点から「現状」を捉えた時、自分の生活の中にどんな変化や努力が可能か、きっと既に考え始めているはずだ。その変化がどのような可能性を持ち、また良い意味でも悪い意味でもどのような影響を及ぼしうるのか。少なくともそこまでは考慮した変化について話し合ったり考えたりする場が必要に思えてならない。今の智頭の町の活気は、この40年前に始まった町おこしと、新しく智頭のポテンシャルに着目し、やってきた若い世代の個々人の努力の積み重ねのもとにある。東京のような大都市こそ、街の歴史を大切にしながらも、様々な変化に対し背を向けなかった智頭に学ぶものがあるのではないだろうか。
報告: 桑山裕喜子
写真: 山田理絵