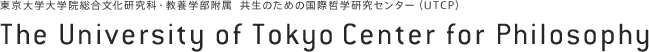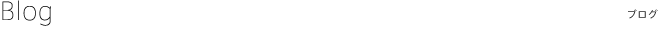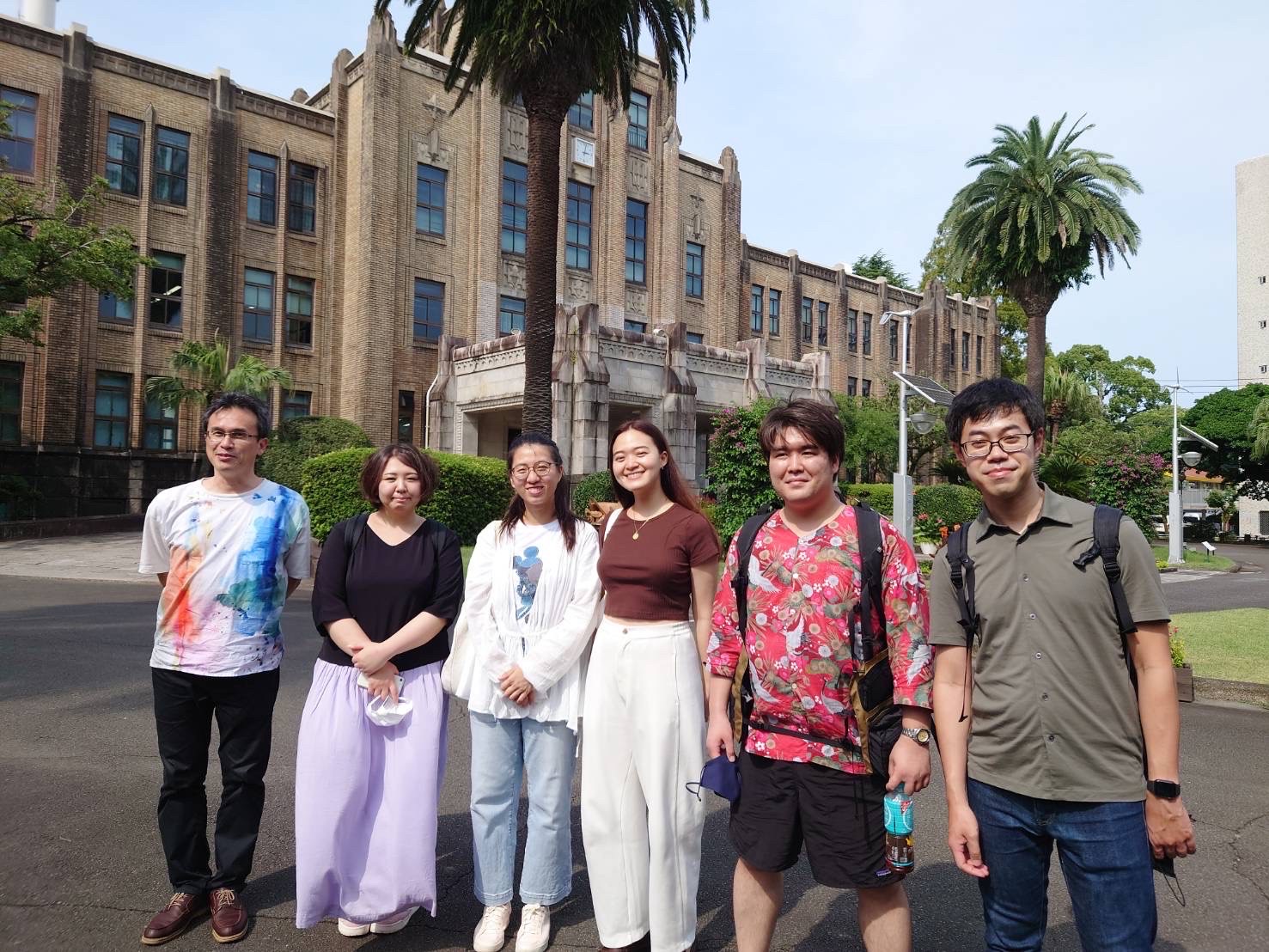【報告】こぼれ落ちてしまうものの肯定・探究・再発見——宮崎の「探究学習」と「地域づくり」の現場から(倉科俊佑)
2022年8月の22日から25日にかけて研修として宮崎を訪れた。研修は県内の高校や地域財団の依頼を受けて梶谷先生が哲学対話を行うのに同行するかたちで行われ、意見交換会や視察なども催された。こちら側から参加したのは、UTCPの梶谷真司先生、山田理絵さん、総合文化研究科 「多文化共生・統合人間学プログラム」(IHS)所属の井坪葉菜子さん、太田陽さん、佐藤寛紀さん、戸巻晃徳さん、ピー・ピヨ・ミッさん、文学部哲学専修所属の倉科俊佑(筆者)の計8名だった。ここに4日間の研修の様子と所感を記したい。
前半の2日間は宮崎東高校の定時制夜間部の教員である西山正三先生のアテンドのもと、宮崎市内で研修を行った。1日目は、宮崎県の教育庁を訪問し、教育委員会の上水陽一先生と、西山先生の両氏からインタビュー形式で話を伺った。西山先生からは全日制と比べた定時制高校の良さや、定時制ならではの探究の取り組みについて、上水先生からは、宮崎県全体を通した高等教育の現状や、行政の立場から教育に携わることの難しさについて、現場の視点からのコメントを伺う事ができた。
2日目は実際に宮崎東高校を訪問し、探究活動の授業を行った。今回は梶谷先生が講師を務める1年生向けの授業の初回として哲学対話の導入が行われた。授業では、自分で考え、問いを立てる、という探究の基本的な姿勢についての軽いレクチャーを踏まえて、一問一答形式のアイスブレーキングと、生徒全員で輪を囲んで自分の問いを発表するワークショップが行われた。なお、今回の授業は公開授業で、県内外から教育関係者が集まった。他学年の生徒による成果発表も同時に行われていたほか、授業の前後には宮崎東の先生による発表やラウンドテーブルも行われた。

宮崎東高校を訪問して驚いたのは、定時制ならではの探究学習の可能性だ。私は探究学習についてはあまり良いイメージが無かった。探究学習(「総合的な探究の時間」)は、教員が決められた内容を一方的に教える従来の科目とは違って、生徒が自ら課題を発見し、それについて自分から考え、課題解決に導くような、学びの主体性を育むための科目とされている。具体的には、生徒ひとりひとりが自分でテーマを設定し、それについての学習や調査を進め、スライドや小論文の形で成果を発表する、というのが一般的だ。しかし、自分や周囲の高校時代の経験や、大学生になってから高校を訪問した経験からは、いかにも教員受けが良く、推薦入試等に有利なテーマ(SDGs、地域振興、グローバリゼーション、連携大学や志望先の大学で行われている研究など)を半強制的に選択させられるのが実態であると感じていた。実際、公開授業に来ていた先生方の話を聞いた限り、結果的に「主体的な学び」から乖離した探究学習を行わざるをえなくなっている高校は少なくないようだった。
その点、宮崎東高校は生徒自身の興味や自己決定を徹底して尊重した探究活動を行っており、探究のテーマも「メイク」「子どもと大人の境界」「ギリシャ神話」「ラーメン作り」といった、先述したテーマや既存の教科の枠組みに当てはまらないものばかりで、内容も非常に充実していた。これは普通の高校ではあまり見かけない新鮮な光景で、子どもたちが心から面白いと思えるものを追求しているのが伝わるものだった。西山先生は、定時制高校に通う子どもたちの大半は不登校やいじめ被害の経験があり、自分の好きなところ、やりたいことを見つけられなくなってしまうほどに自己肯定感が傷ついている点を問題視しており、宮崎東の探究学習では「生徒の自己肯定感を高める」ことを根底に据えているとのことだった。そこから自分の好きなところ、興味関心、将来やりたいこと(進路)と徐々に探究の範囲を広げて、生徒たちが自分の人生を自分らしく生きられることへと繋げているそうだ。先生方が語るエピソードは、生徒一人ひとりを粘り強く支え、力強く彼らの人生へと送り出していることが伺えるもので、学校教育の枠組みの中で、これほどまで真摯に生徒たちに寄り添うことができるのかと衝撃を覚えた。こうした理想的な探究学習の在り方は、受験を見据えた詰め込み的な教育へのプレッシャーがなく、クラス人数も少ないが故に教員が生徒ひとりひとりに向き合う余裕のある、定時制高校ならではの強みを活かしたものだ。定時制高校から始まる「これからの教育の未来」を語る宮崎東の先生方の語り口はとても心強いものであった。
後半の2日間は児湯郡新富町の地域商社である「こゆ財団」のアテンドのもと、児湯郡内で研修を行った。3日目は「こゆ財団」出身の福島梓さんの案内で、隣町の高鍋町にある高鍋高校を訪問した。高鍋高校では一通り学校見学をした後、3年生代表の生徒による探究活動の発表と哲学対話が行われた。探究活動の発表は「日本の留学者数が少ない要因はなにか」というテーマでの英語発表で、高度な統計手法を用いたハイレベルなものであり、研修参加者からの質疑応答もそれに応えるように手加減なしの本格的なものとなっていた。哲学対話は「英語をつかわずに海外旅行をしたいか」という問いをめぐるもので、各々が考えるコミュニケーションの理想や異国の地に赴くことに感じる意義といった論点から、参加者間での価値観の違いが際立つような対話となった。

高鍋で会場を片付けながら、参加してくれた生徒たちと個人的に交わした会話がとくに記憶に残っている。全体で発表していた子とは別の子に、どのような探究活動をしているのか聞いてみたときのことだ。彼女は宮崎県の平和教育について探究したという。聞くところ、宮崎には特攻隊基地が存在していて、彼女の家のすぐそばにも関連史跡があるそうなのだが、それにも関わらず、宮崎県内の平和教育ですら有名な鹿児島の特攻隊基地についてしか扱わないことに納得のいかなさを覚え、学校の平和教育の枠組みから忘れ去られてしまっていた歴史の再発見をテーマにした、とのことだった。「こういうの変に見られるかもしれないですけど」と言いつつも、オタク的な「好き」の感情を爆発させながら自分の探究対象への思いを溢れんばかりに語っている姿はとても生き生きとしていて、ひときわ印象に残っている。宮崎東と同じように、既存の教育の枠組みを自らの関心や発見によって打ち破っていくような研究も受け容れることができる点に、探究学習の可能性を垣間見た出来事だった。
最終日の4日目は、こゆ財団の中山隆さん、鈴木伸吾さんの案内で新富町を訪れ、こゆ財団の方々との哲学対話に加えて、こゆ財団の活動の紹介や視察が行われた。哲学対話では、〈コミュニティー形成としての哲学対話〉というテーマで導入が行われ、つづけて「好かれる先生と嫌われる先生がいるのはなんで?」という問いをめぐって対話が行われた。この問いは大人に混じって参加していた中学生が出した問いで、教師と生徒の非対称な人間関係や、学校特有の息苦しさなど、世代を超えて通じる共通体験に基づいた活発な対話となった。また対話後に振り返りを行う時間があったため、既存のコミュティー内での哲学対話の効用や、良い問いの選び方、対話での沈黙の捉え方など、対話を通して生じたメタ的な疑問をその場で話し合うこともでき、実りの多い時間だった。

新富町では、地元の方々の声を聞き、実際に町内を巡ってその現場の空気感を肌で感じる中で、昨今は「地方創生」というスローガンのもとで推進されているような、地域づくりの実際に触れることができた。視察を通して地域の特産品や観光名所、美しい新造の公共施設といった、当地ならではの様々な魅力を味わわせてもらった一方で、その背後から伝わってきたのは、こゆ財団の方々いわく他の市町村と比べて特色に乏しい「何もないまち」である新富町を、どうにか魅力的にしなければならないという強い使命感だ。こゆ財団の方々が語っていた試行錯誤や悩みの数々は、移住や都市への流出による人口の増減、盛んに競われる観光客数やふるさと納税額、ブランド化した地域産業の知名度といったかたちで地方社会の「価値」が隈なく可視化され、評価されてしまう現代において、自らの地域コミュニティーを存続させていくにはどうすればよいのか、という切迫した問題意識の中で行われた葛藤や格闘の痕跡であったように思う。とはいえ、こゆ財団が実際に行っている様々なプロジェクトから伺えたのは、そうした現状の価値尺度の中で競おうとするのではなく、既存の枠組みにはない新たな価値を創造的に見出そうとする、ベンチャー的とも言えるような挑戦の姿勢だった。こゆ財団の方々からは、そうしたエネルギーが常に迸っているように感じられた。
私は今回の研修を通して、新たな社会的・教育的コミュニティーの開拓の最前線に立つ人々の前で、哲学に携わるものとして、いったい何が言えるのだろうか、とずっと考えていた。今回の研修で哲学対話のファシリテーター経験があり、また哲学を専門とする学生は私だけだったので、哲学や哲学対話について話すことを求められる機会がしばしばあったからだ。ただ、その時は、地に足のついた彼らの語りの前で、私が哲学について語り出すことはあまりに軽薄に思えて、自分の考えを言葉にすることはできなかった。今もまだうまく答えられる気はしていない。
ただ、この報告で遅ればせながら言葉にしようと試みたのは、「教育」や「地方創生」といった、社会に与えられた枠組みの内側にとどまりながらも、そうした共通の尺度にうまく沿うことができなかったり、見過ごされてしまったりするひとやものを再発見し、肯定しようと試みている人々との出会いである。私はそれにとても勇気づけられたし、その中で奮闘することの葛藤や喜びを語る人々はとても眩しかった。私が哲学にもとめているような自由な思考と発見の空間が、そこではもうすでに成立しつつあるように見えた。だから、それについて実体のない言葉を重ねることしかできない自分に、私は引け目を感じていたのかもしれない。とはいえ、研修先で会った方々は、哲学や哲学対話になんらか通ずるものを感じてくれていたのだろうから、そうした思いを受け止めつつ、私達が彼らとともに開いた対話の場が、自分や自分のいる場所を自らのちからで見つめ直していくような思考の場として、彼らの営みに少しでも共鳴できていたことを願う。

報告:倉科俊佑(東京大学文学部人文学科 哲学専修課程4年)