【報告】ワークショップ「精神疾患研究の科学論――生物学的アプローチの検討」
2011年9月3日、東京大学駒場キャンパス18号館ホールで、ワークショップ「精神疾患研究の科学論――生物学的アプローチの検討」が開催された。
近年、精神疾患に関する遺伝子研究・分子レベルでの研究や脳イメージング技術を利用した研究によって、様々な知見が蓄積されてきた。このような「生物学的アプローチ」による精神疾患研究は、精神疾患をどこまで解明することができるのか。これが今回のワークショップの主なテーマである。
【講演】
まず、加藤忠史氏(理化学研究所・脳科学総合研究センター精神疾患動態研究チームリーダー)が「精神疾患克服へのロードマップ」と題する講演を行った。精神疾患の原因が心理や社会に求められがちな日本では、反精神医学的な動きが高まる一方で、生物学的アプローチによる精神疾患の原因解明はもはや諦められたかのように見える。そのような状況を打開するべく、加藤氏は精神科医療の未来をポジティブに展望する。
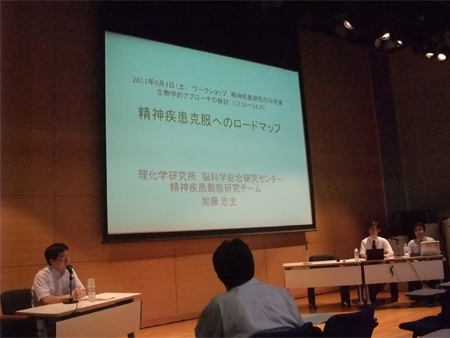
現在まで、精神疾患の場合には、面接のみで診断し「検査法」が存在しないという状況が続いている。この状況に対して精神科医療に未来をもたらすには、症状だけで疾患を分類するのではなく脳の病変で分類するやり方が必要だ。そのための道筋を、加藤氏は以下のように示した。(1)大規模ゲノム研究により精神疾患のまれな原因遺伝子変異を見つける、(2)その遺伝子変異をもつモデル動物を作る、(3)そのモデル動物が、精神疾患と類似の症状を示し、同じ薬が効くかどうかを確認する、(4)このモデル動物で、脳の病変を明らかにする、(5)その脳病変を、患者死後脳で確認する、(6)脳病理所見に基づいて病気を定義し直し、疾患概念を確立する、(7)特徴的な脳病変を診断できる方法を動物実験と臨床研究により開発する、(8)モデル動物を用いて、根本的治療法、予防法を開発する。この「精神疾患克服へのロードマップ」は、死後脳研究の少ない現状を克服するために「ブレインバンク」を作る必要があるなど、壮大な構想である。

二人目のスピーカーの糸川昌成氏(東京都医学総合研究所・「統合失調症・うつ病の原因究明と治療法」プロジェクトリーダー)
は「精神疾患の生物学的研究の現状と未来――明らかになったことと未解明なこと」という題で講演を行った。糸川氏も、まず、精神疾患の原因解明が難航する理由を考察したが、「対象の均一化」にまつわる危うさと「価値判断」が症候の判定に含まれるという加藤氏とは別の理由を取り上げた。
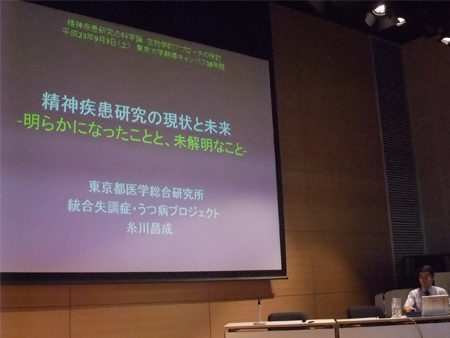
糸川氏によれば、欧米ではこうした危うさを反省することなく、「数」で精神疾患研究を乗り切ろうとし、何万人もの被験者を動員して膨大な全ゲノム情報を解析するといった国家プロジェクト級のビッグサイエンスが主流になってきたが、対象の均一性が得られない以上、数を増やしても原因解明にはつながらない。加藤氏のロードマップがこの種のビッグサイエンス路線の新展開であったのに対して、糸川氏は、むしろ、個別の症例を丁寧に観察することでプロトタイプを発見し、それを一般症例まで敷衍する手法が有効だと提案する。そして、そうした手法によって比較的均一な対象の単離に成功した思われる自験例が紹介され、AGE(終末糖化産物)の蓄積が統合失調症のリスクを高めるという説を展開した。

最後に、UTCP事業推進者である石原孝二氏が「DSM-5ドラフトの背景―精神疾患研究の科学哲学」という題で講演した。加藤、糸川両氏が、生物学的アプローチの実践者として研究の現状と将来について語ったのに対し、石原氏は精神疾患研究における科学性を哲学的に問うた。DSM-III以降、病因に関しては非理論的な立場に立ち、症状のみで診断できる診断基準を与える記述的アプローチがDSMの基本スタイルとして確立している。このアプローチに対しては、診断基準がどれだけ精神疾患を反映しているのかという「妥当性」には疑問が呈されてきた。現在進められている、DSM-5の改訂作業においては、「妥当性」の問題の解決が目指されているが、この方向性の根底には、より病因・病理生理学に基づいた診断への転換を志向する大きな流れがある。石原氏は、このようにDSM-IIIからDSM-5への道のりをまとめつつ、「妥当性」を向上させることが病因に基づいた診断基準を作ることに実際なるのかという点にはなお議論の余地があることなどを指摘した。

質疑応答では、石原氏の講演を受けて精神疾患研究の科学性が話題になった。それに対して、加藤氏は、特に精神疾患に関して科学性を疑うのは、むしろ、科学的に解明不可能な「心」のファンタジーを精神疾患に読み込むある種の偏見に基づくのではないかという見方を示し、精神疾患も脳の病変によって解明できるという立場を鮮明にした。他方、糸川氏は、「心」のファンタジーに一定の共感を示し、例えば主体性や自我境界が障害される場所を特定することで、精神疾患研究も神経科学者と同じように心の機能の解明に寄与できるという期待につなげた。
【感想】
この質疑応答の議論に見られるように、「精神疾患研究の科学論」には、「心」の存在論的身分や「心」の解明のための方法論という哲学の根本問題が含まれている。そうした意味で、哲学的な興味を刺激するワークショップだった。
哲学的に、ということで言えば、この日の議論の中でも明らかにしていくべきことは多いと感じた。例えば、精神疾患の原因解明が遅れているという事実は、精神疾患の原因を「社会」に求める傾向につながり、精神疾患の科学を妨げているという認識がこの日はしばしば表明された。たしかに、精神疾患は一種の「社会的構成物」にすぎないという見方は多く、これが反精神医学的機運に結び付いているのはたしかだが、しかし、そもそも「社会的に構成される」ということの意味や動機が哲学的には重要である。I・ハッキングが論じるように、「社会的構成物」という概念は非常に曖昧に使われており解明を要するものだが、それは、「科学性」の意味がはっきりせず、信頼性や妥当性の概念を明瞭化する必要性とおそらくは一体である。精神疾患の科学「論」は同時に反精神医学「論」でもある。こうした課題にこそ、哲学が引き受けるべきものがあると私には感じられた。
池田喬(PD研究員)






