【報告】UTCPシンポジウム「絵画の生成論」
2009年11月15日、UTCP新中期プログラム「イメージ研究の再構築」主催によるシンポジウム「絵画の生成論」が開催され、爽やかな秋晴れのなか駒場キャンパス数理科学研究棟地階大講堂に100名を超える聴衆が集った。

【趣旨説明を行う三浦教授】
第一部
まず同プログラム事業推進担当者の三浦篤教授から趣旨説明が行われた。つづいて日仏の5人の美術研究者による発表の最初を飾ったのは、ハーヴァード大学教授アンリ・ゼルネール氏による「アングル作《『アエネイス』を読むウェルギリウス》」である。冒頭で氏は、美術作品とは、作者のみがその完成を決定付けることができるものというよりもむしろ、常に変化し続ける、いわば「永遠に完結しないもの」であると述べられ、「絵画の生成」をめぐる議論にとって根幹的といえる視点を提示された。
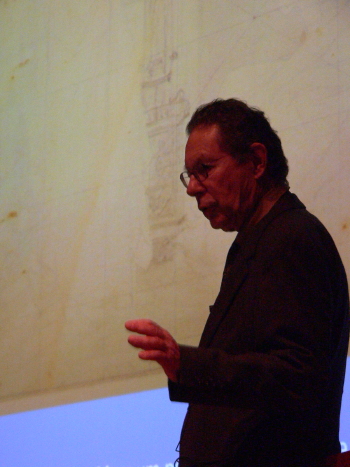
その上で氏は、極めて複雑な生成過程を内包するアングルの作品《『アエネイス』を読むウェルギリウス》を取り上げる。これは当時新古典主義の画家の間で非常に流行していた主題であり、アングル自身タイヤッソンによる油彩やジロデによる版画を参照している。アングルが初めてこの主題を取り上げたのは1811年だったが、現在トゥールーズのオーギュスタン美術館に所蔵されている同作は、アングルの弟子たち、また画家本人の手によってたびたび加筆されており、当初の画面がいかなるものであったのかは謎に包まれている。ゼルネール氏は、『J.A. アングル作品集』(1851年)に掲載された図版と記述から当初の構図に最も近似していると考えられるシモン・プラディエによる版画(1832年)を主軸に据えてトゥールーズの油彩や現在ブリュッセル王立美術館所蔵の別ヴァージョン(1814年)、各地の美術館に遺されているデッサンの数々、あるいはプラディエの版画の試し刷りといった資料を比較検討し、画家最晩年の1865年に制作された最終ヴァージョンへと至るこの主題の変遷過程を辿られた。
その綿密な考証から浮かび上がってくるのは、油彩、版画という異なる媒体を通じて、衣襞の表現や眼・手といった細部、さらには全体の構成をめぐってアングルがさまざまに試行/思考する様である。注目すべきは、50年以上にわたって繰り返されたこれら無数のヴァリアントが、オリジナル作品を直接参照することなく描かれているということだ。第一ヴァージョンの所有者が当初作品を貸し出さなかったり、のちに大幅な加筆によってその構成が変更されたりしたためである。このことを指摘した上でゼルネール氏は、プラディエの版画の上に油彩で着彩されたこの最終ヴァージョンは、アングル自らがもはや存在しなくなったオリジナル作品を「仮想的に」複製した作品なのである、と結論付けられた。
19世紀中葉に誕生した精細な複製技術と油彩をめぐる議論にとって刺戟的な問題を提起するアングルの作品群を考察し、さらにはオリジナル作品の「仮想的」な存在の仕方という視点を提起された氏の発表は、「絵画の生成論」を再考しようとする本シンポジウムの冒頭を飾るにこの上なくふさわしいものであった。
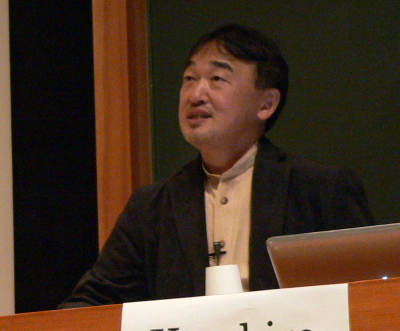
続いて佐藤康宏氏による発表「18世紀京都の画家たち——複製技術時代の絵画」が行われた。その演題が示すように、ここでもやはり絵画の生成における複製技術、より具体的には木版画との関連性が問題とされた。
佐藤氏はまず、18世紀京都画壇が直面したのは、ある種のダブル・バインドであったと規定する。その背後には木版という複製技術によって和漢古今の膨大なイメージが参照可能になったという歴史的事情がある。とりわけ重要な役割を果たしたのは、大岡春卜[しゅんぼく]が著した大著『画功潜覧[がこうせんらん]』(1740年)であった。狩野派が秘蔵してきた絵手本の図様など、様々な既存のイメージを木版画にして出版した本書をはじめとする画譜の登場によって、これらを手本として絵画制作を行うことが広く画家の間で一般的となる。この結果、一方では模倣による絵画制作に対する批判が強まり、他方では絵画は版画といった「低俗」なジャンルには不可能な表現形式をこそ実現すべきであるという意識が生まれたのである。
このような状況のもとで出現したのが、いわゆる指頭[しとう]画あるいは酔作であったと佐藤氏は指摘する。池大雅[いけのたいが]に代表される指頭画は、大勢の観衆の見守る中、筆を使わず指で直接墨をとり一気に画布に描きあげるという制作手法である。あえて筆による精巧な描写を拒み、指の動きの不自由さを引き受けるこの手法は、そのパフォーマンス・アートとしての要素にも明らかなように、画家の身体性の直接的な発現を意図したものである。大雅や与謝蕪村が行った酔作、すなわち酒に酔った状態で制作するという行為もまた、画家の身体性を極度に前景化させることによって、複製版画には表現不可能な個性を絵画にもたらし、作品に一回的な性格を与えようとするものであるといえる。しかしながら同時に、こうした制作手法では、作品としての完成度が低くなることは不可避的である。そこで試みられたのが、大雅の《漁楽図》や蕪村の《夜色楼台図》に見られるような、筆勢の強調と形態のデフォルメであり、大岡春卜の《欄間図式》を基にした若冲の《貝甲図》における、画中のモティーフをある種抽象的な記号ともいえるレヴェルまで変容させるという表現であった。これらの作例では、既存の版画イメージに拠りつつなおかつ画家個人の個性あるいは造物主としての創造性を作品に付与する方途が探求されているのである。
18世紀の京都を舞台に繰り広げられた、木版画の普及がもたらした絵画制作における葛藤の克服の痕跡を辿られた氏の発表は、版画/絵画、複製/オリジナルという西洋美術における概念の枠組みと議論とが、日本美術にも接続しうるものであることを明示し、本シンポジウムの議論に大きな広がりをもたらした。
最後に特筆しておきたいのが、氏があくまでスライド映写によって聴衆にイメージを供されたことである。それは、デジタル技術という新たな複製技術の時代に突入している我々に対する、氏のもうひとつの問題提起であり警句であったように思う。
(以上、報告:安永麻里絵)
第二部
セゴレーヌ・ル・メン「クールベ──芸術生成の諸問題」
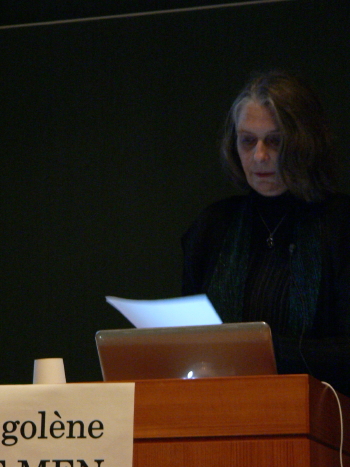
第一部に引き続いて、複製技術によって蓄積されたイメージのアーカイヴに作品の源泉を求めるという分析手法が、こんどはクールベのタブロー《傷ついた男》(1855年)へと適用される。いわゆる「民衆版画 imagerie populaire 」がクールベに着想を与えていたことは、すでにマイヤー・シャピロやリンダ・ノックリンの研究によって知られているが、その成果をふまえつつ、この発表においてル・メン氏は、《傷ついた男》の由来を、民衆版画の主題として流布しており、またクールベの友人マックス・ピション作の民衆歌謡のなかでも言及されている「ピュラモスとティスベー」物語に見いだしていく。オウィディウスの『変身物語』に含まれるエピソードであり、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』へも影響を与えた「ピュラモスとティスベー」は、次のような筋書きを持っている。愛し合っていた二人の若者、ピュラモスとティスベーは、両親に交際を禁じられていた。しかしある夜、密かに墓地で逢おうとする。先に到着したティスベーは、そこでライオンに出会い、外套を落として逃げる。遅れて来たピュラモスは、この外套を見て、恋人がライオンに殺されたものと思い込み、自殺する。しばらくして戻ってきたティスベーもまた、ピュラモスが死んでいるのを見つけ、自殺してしまう。こうした悲恋の運命を、クールベは、みずからの実人生と重ねていたと考えられるのである。1973年の調査によって、《傷ついた男》のカンヴァスには、もともと、睦み合う若い男女の姿が描かれていたことが明らかにされた。クールベは、その幸福な場面を塗りつぶし、破滅した自画像へと変えてしまったのである。このことは、伴侶ヴィルジニー・ビネとの関係が破局したという事実と、おそらく符合している。クールベの作品群における《傷ついた男》の位置づけと、「ピュラモスとティスベー」の伝承過程とを詳しく考え合わせた本発表は、この「二重写本 palimpseste」のごとき自画像には、クールベの「エロスとタナトスが重ねられている」と同時に、錯綜したイメージの系譜が縮約されていることを教えてくれた。
三浦篤「エドゥアール・マネと〈タブロー〉の脱構築──断片化と筆触」
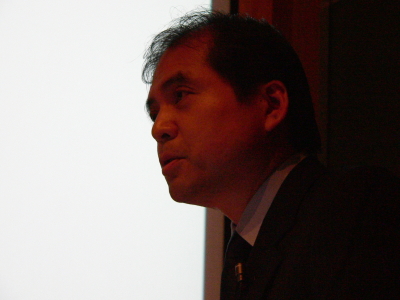
三浦氏の発表は、絵画の生成論を考えることで、一枚のタブローがもつ歴史的意義をドラスティックに変えてしまう可能性を示した。再検討されたのは、「オペラ座の仮面舞踏会」を主題としたマネの二つのタブローである。一方で、ワシントンのナショナル・ギャラリーが所蔵する《オペラ座の仮面舞踏会》は後期マネの代表作として知られているが、他方、本発表において注目されるのは、日本のブリヂストン美術館が所蔵する一見マイナーなヴァージョンである。緻密な描き込みによって仕上げられた前者に比べ、奔放な筆致でスケッチ風に描かれた後者は、これまでの通説では、前者のための下描きでしかないと見なされてきた。しかしながら、三浦氏の仮説では、そのように見なすべきではない。マネは、絵画の正統的コンポジションを「脱構築」する手法を、二つ持っていた──すなわち、「画面の枠取りに基づく対象の断片化」、そして「現実再現と自律性のはざまで揺れ動く筆触」である。実のところ、ワシントン・ヴァージョンは前者の、ブリヂストン・ヴァージョンは後者の手法を用いていたと見なせるのである。(1)一方で、マネはしばしば、対象の全体をきちんと収めずに、半端にカットするような画面の枠取りをしてきた。このことは、完成したはずのタブローをバラバラに切り分けるという挙措にまで極端化する。そもそもマネは、美術館の整備や複製技術の普及によってアーカイヴ化されたイメージ群を自在に引用し、それらをしばしば脈絡を欠いた、暴力的ともいえる仕方で再構成するという手法に積極的だった。三浦氏によれば、マネは、「あらゆるイメージが相対化され、同質化することにひときわ敏感であった」のである。断片化への熱意は、19世紀後半におけるアウラを喪失したイメージたちの繁殖によって触発されていた。(2)他方で、マネはまた、印象派の実験に先行/と並行して、「絵の表面を「仕上げる」ことを金科玉条とする美的基準を相対化すること、すなわち筆触やマチエールの自立的な表現」をも試していた。そこでマネの特異性をなすのは、印象派ほど色彩分割をラディカルに推し進めることなしに、もっぱら「筆触そのものを際立たせる」という狙いである。三浦氏は、この狙いに関わる作品系列を跡づけた上で、問題のブリヂストン・ヴァージョンをその一例として解釈して見せた。「一見すると乱暴で異様な塗りが、絵としてぎりぎりの体を成していて、印象派の筆触分割とは似て非なるマネ独特の感覚と技術が、逸脱すれすれの水準で駆使されている」──そこに「戦慄を覚える」という三浦氏の再評価は、生成論的アプローチによって開かれる批評の可能性をヴィヴィッドに示している。
近藤学「アンリ・マティスの油彩における作品生成過程(1913–16)」

最後の近藤研究員は、1913–16年におけるマティス作品の層状構造をテーマとした。その導きとなるのが、大作《川辺の浴女たち》のもつ謎めいた履歴である。きわめて平坦で硬質な様式で仕上げられたこの作品の表面下には、実のところ、もっと柔らかく牧歌的な様式をもつ前段階が潜在している。その痕跡は、ところどころ、そのまま露呈していたり、塗りつぶされた色面にレリーフ状の起伏として残っていたりする。近藤氏は、このように見え隠れする層を、制作途中で記録された写真と赤外線分析にもとづいて復元した上で、その原型が、《コンポジション第二番》(1909年)──有名な《ダンス》・《音楽》と三連画(トリプティーク)をなすはずだった三枚目の水彩エスキス──、およびその発展形と目される油彩《浴女たち》(1909年)であることを指摘する。そしてこの時期、他の作品においても──《金魚鉢とパレット》(1914年)など──、異なった様式をひとつのカンヴァスに重ねていることが強調される。その理由は、いったい何なのか。1913年夏から、マティスは危機の時代に入ったと言われてきた。これまで避けてきたキュビスムの手法を取り入れ始めたのである。その顕著な作例が《白とピンクの頭部》(1914年)であるが、X線調査によると、幾何的な構成によるその完成面は、実のところ、柔らかい線で描かれた層の上に重ねられている。他方、注目されるのは、1914年から、同じ主題について、キュビスム風のヴァージョンと「マティス風」のヴァージョンを描き分けるという試み──前出の《金魚鉢とパレット》、ほかに《ピアノのレッスン》(1916年)など──がなされたことである。近藤氏は、こうした事実をポジティヴに解釈する。すなわち、この時期のマティスは、キュビスムに感染して迷走し、危機に陥ったというよりも、異なった様式をすすんで相対化し、それらの差異を重ね合わせ、併置して肯定するようになったのである。そう考えることで、1916年末からの「ニース時代」における伝統的様式への回帰についても再評価が可能となる。これまでニース時代は、第一次世界大戦が多くの画家にもたらした保守化の一例として解釈されてきた。氏によれば、この解釈には一定の妥当性があるものの、個々の事例に即して再検討する余地がある。マティスの場合は、上記の諸作品を通じて様式の相対性を自覚するという経験を経てはじめて、伝統的様式を──キュビスムに対するのと同様に──採用することができるようになったのではないかと考えられるのである。こうした氏の見解は、マティスの画布を、様式の複数性が登記される場として、つまり美術史というアーカイヴそのものを(部分的に)畳み込んだメタ・カンヴァスとして評価するものであったと言えよう。
(以上、報告:千葉雅也)
第三部

続く第3部では、来場者からの質疑への応答と、登壇者の間での討論が行われた。個別の発表者、個別の論点への質問からも、5名の発表すべてに関わるテーマが引き出され、さらなる議論へと発展していくという、非常に実り豊かな展開となった。そこで浮彫りとなったのが、「絵画の生成」という共通テーマが導出する、新たなテマティックの数々である。すなわち絵画のコンポジション、筆触や塗り重ね、画家の身体の痕跡といったものが問題となる場としての「表層」、「複製」等々だ。
「指頭画」に注目する佐藤氏の発表は、5名の中では唯一、日本絵画に関するものであった。しかし「指頭画」におけるパフォーマンス性は、18世紀フランスの画家シャルダンの制作プロセスにも見出しうるとゼルネール氏は指摘する。この画家は同一のモティーフを繰り返し描いているが、その度に異なる形態が摂られており、そこには一種のパフォーマンス性が現れ出ている。同一のものが反復される中での「即興」が、作品のオリジナリティを担保するという点で、シャルダンと同時代の日本絵画の試みとは通底するのではないかと言うのである。またル・メン氏は、佐藤氏が取り上げた例における「間メディア性」に興味を惹かれたと発言。これを受けて佐藤氏は、メディウムの横断と同時に、芸術ジャンル(ハイアートと民衆絵画)の横断も生起していたと分析する。
ル・メン氏が言及するクールベ作《傷ついた男(自画像)》の「クロース・アップ」と、三浦氏が指摘したマネにおける「断片化」、さらにはゼルネール氏が取り上げたアングルの連作における「全体と部分」というテーマは、すべて「断片性」の問題に帰すことができる。それでは、それぞれの画家たちはこの「断片」という契機を、どのように取り扱ったのだろうか?会場から提起されたこの問いは、個々の発表を繋ぎつつ、さらなる分析の段階へと進展させるものであった。マネの「切断」には二種類あり――すなわち、眼前の現実の「フレーミング」と、描かれた現実を再構築する手段としての「画布の分割・裁断」である――、この両者は峻別する必要性がある。ゼルネール氏によるこの指摘には、三浦氏も首肯する。また、とある自作品を「大きな断片」と表現したアングルにおいても、「断片」は非常に興味深い問いであり、ジェリコーら同時代の他の画家に敷衍することも可能である。さて、描画主題の周辺を裁断する作業は一見共通に見えても、クールベとマネとの間には依然として断絶があるとル・メン氏は言う。後者の裁断が「枠取り」のためであるのに対して、前者は「一点集中」の効果を生むものであった。二人の画家の間の差異は、断片を再構成する「コラージュ」の作業においても存在している。このように19世紀の画家たちが「断片」や「切断」のテマティックの下に語られるのに対して、20世紀のマティスは画布を「継ぎ足す」ことはあっても、切断することは決してなかった。それは絵画のコンポジションを、一種の有機体として捉えていたためである、と近藤氏は指摘する。部分への分解や切断が不可能な「有機的な総体」としての絵画という意識によって、20世紀は前世紀と隔てられる。ここからは、「断片」と「総体」、「有機性」といった概念が、19世紀と20世紀の認識を分かつモメントたりうるのではないかという、より大局的な、そして非常にチャレンジングな問いが導出される。
芸術ジャンルを越境した多様なイメージの「借用」と「アッサンブラージュ」も、各々の発表に通底するテーマであった。クールベは民衆版画を、観者にはっきりと判る形で引用している。対照的にアングルは、このような大衆的なイメージを一度完全に消化した上で、それと気取られぬように領有してみせる。江戸時代の日本においては、先行するイメージの「複製」や「模倣」は、異なる文脈において享受されていた。例えば鈴木春信には、師である西川祐信の模写と言いうるような作品も存在するが、当時の観者たちはその「複製」としての性質を踏まえた上で、いかにオリジナルが改変されているかを楽しんでいた。他方でマネは、ルネサンス期の巨匠の作品から同時代の大衆文化まで、様々な絵画的「典拠」を互いに完全に等価なものとして扱い、それらを組合せることで《草上の昼食》や《オランピア》といった作品を描いた。これらの作品が発表時にスキャンダルを惹起したのは、その背後に存在している「先行するイメージの借用」を当時の観衆が気取ることができなかったためであり、この一種の暴力性において、春信の例とは対照を成していると三浦氏は結論づける。
この先行するイメージをいかに隠蔽ないし可視化するかという問いに対し、マティスは「痕跡」を留めるという方策を採った。すなわち絵画の生成変化の過程を、あたかも生物の「成長記録」のように、消え残った描線として残すのである。ここからは、「絵画は何時完成するのか」という問いが派生する。17世紀以降の西欧では、「デッサン(dessin)」もまた一種の完成作として、蒐集や展示の対象となっていく。1867年の個展では、クールベ自らが「習作études」という一角を設け、種々のタブローと等価なものとして、自身のデッサンを展示した。ゼルネール氏の看破するところに依れば、マネにおいては描画行為そのものが演劇的であった。筆触そのものが作品たりえるという観念、完遂されつつも次のプロセスへ向けて開かれている絵画というモメントをマネは打ち立てたのであり、そこにこの画家の画期性がある。
このような応答と対話の過程で、個々のディスカッサントの間に潜在していた共通のテーマが浮上し、当初は相互に独立していた5つの発表が、有機的な連関を伴った布置を描き出すという大団円を迎えることができた。本プログラムの趣旨に賛同し、専門分野の枠を超えて示唆に富んだ発表をして頂いたセゴレーヌ・ル・メン氏、アンリ・ゼルネール氏、佐藤康宏氏、それからディスカッションに積極的に参画してくださった来場者の方々に、感謝の意を表したい。

(以上、報告:小澤京子)
関連記事






