【報告】Neil Levy Seminar Series
2009年7月13日から22日にかけて、メルボルン大学応用哲学・公共倫理センター(Centre for Applied Philosophy and Public Ethics; CAPPE)のニール・リーヴィ(Neil Levy)氏を迎えて、一般講演を含め全6回にわたる連続講演が開催された。

ここでは、若手研究員による各講演会の報告に先立ち、リーヴィ氏の研究業績を紹介するとともに、今回の連続講演の経緯と全体に関する所感をごく簡単に記しておきたい。
リーヴィ氏は、サルトルやフーコーといったフランス哲学者の研究に出自をもちつつ、心の哲学や行為論に関する業績を含め、規範倫理学やメタ倫理学、応用倫理学といった諸分野において矢継ぎ早に目覚ましい業績を挙げている、新進気鋭の分析哲学者である(文末の著作リストを参照)。また、脳神経倫理学の分野においては若手ながら主導的な地位を占めており、当該分野において初めて単著での著作を出版するとともに、雑誌Neuroethics (http://www.springer.com/philosophy/ethics/journal/12152) を2008年に刊行し、その編集長を務められている。
われわれUTCP「脳科学と倫理」プログラムでは、2008年度の夏学期大学院ゼミにおいてリーヴィ氏の著作『脳神経倫理学:21世紀への哲学的挑戦(Neuroethics: Philosophical Challenges for the 21st Century)』をテキストとして選出した経緯もあり、氏のUTCPへの招聘を実現すべく昨年以来調整を重ねてきた。今回、念願がかなって連続講演を開催する運びとなった次第である。開催に当たっては、プログラムに所属するPD・RA研究者を中心に、各講演に対して特定質問者を1~2名ずつ立て、事前に講演原稿の検討と質問内容の準備を進めてきた。各講演では、最初にリーヴィ氏より約1時間の講演をおこなってもらい、その後に各自15分の特定質問、続いてリーヴィ氏からの返答を受け、総合討論へ移行するという形式をとった。講演の詳細に関しては各々の報告を参照されたい。
事前準備を入念に行ってきたためもあり、各講演では特定質問者からのものを含めさまざまな観点から本質的な質問が多数提起された。リーヴィ氏はそのほぼすべてに対して即座に綿密な応答を与えて下さった。今回の連続講演は、とりわけわれわれ若手研究者にとって、世界の第一線で活躍する哲学者と英語で長時間の議論を交える貴重な機会となった。この場を借りてリーヴィ氏に厚く謝意を表したい。
小口峰樹(UTCP若手研究員)
【リーヴィ氏著作リスト】
Levy, N. 2007. Neuroethics: Philosophical Challenges for the 21st Century, Cambridge: Cambridge University Press.
Levy, N. 2004. What Makes us Moral? Crossing the Boundaries of Biology, Oxford: Oneworld.
Levy, N. 2002. Moral Relativism: A Short Introduction, Oxford: Oneworld.
Levy, N. 2002. Sartre, Oxford: Oneworld.
Levy, N. 2002. Being Up-To-Date: Foucault, Sartre and Postmodernity, New York: Peter Lang.

Seminar 1: Does the Extended Mind Hypothesis Really Matter?
2009年7月13日 於東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム2
報告:小口峰樹(UTCP若手研究員)
本講演は「『拡張された心』仮説は本当に重要か(Does the Extended Mind Hypothesis Really Matter?)」と題され、心の哲学においてクラークとチャルマーズが提唱した「拡張された心」仮説(以下EMHと略)が脳神経倫理学の諸議論に対してどのような影響を与えるかが議論された。
EMHは「心の座はどこにあるのか」という伝統的な形而上学的問いに対するひとつの解答を与えるもの(あるいは伝統的な解答に対する視座の転換を促すもの)である。心の座を脳に認める心脳同一説は、心的状態をまさに脳状態にほかならないものとみなしてきた。これに対し、EMHによれば、心は脳をその座とするだけではなく、その外部に拡がる環境をもその座としうる。この「心の拡張」という発想は、「機能主義」の自然な帰結として理解することができる。機能主義によれば、心的状態は、それがどのようなマテリアルによって実現されているかではなく、システムとしてどのような機能を果たしているかによって定義される。それゆえ、そのシステムの一部(あるいは全部)がたとえ神経組織とは別のマテリアル(たとえば複雑な計算を行うときに使う紙と鉛筆)によって担われていたとしても、そのマテリアルは心的状態の担い手として認められるのである。すなわち、何がある行為者の心の座とみなされるかは、行為者の身体がもつ物理的な境界によって決定されるのではなく、行為者が従事しているタスクに対してそれがどのように関与するかによって決定される。心は頭蓋骨の内部に閉じられているのではなく、身体の境界さえも越えて環境のなかへと拡張されうる(そして実際にされている)のである。
リーヴィは本講演において、EMHに対する二つの主要な批判を退けた上で、EMHが脳神経倫理学のなかで行われているさまざまな議論に対してどういった含意をもつのかを展開する。
第一の批判は脳外部のマテリアルが担う内容に関するものである。アダムスとアイザワは「心は原初的かつ非派生的にその内容を獲得するが、脳の外部のマテリアルが担うことができるのは派生的な内容だけである。後者は行為者の原初的な意図や規約に依存することによってしかその内容を獲得することができない」と主張し、EMHは派生的内容を心的内容とする誤りを犯していると批判する。これに対してリーヴィは、たとえ原初的/派生的という区別を認めたとしても、心が全面的に原初的な内容によって占められていると考えることはできないと反論する。われわれが心的なものであると疑いなく認めるもののなかには、その内容が何らかの規約に依存するかたちで成立しているもの(たとえばベン図のイメージを利用して思考する場合など)がある。それゆえ、内容の原初性/派生性という区別は心的なものの区別と一致しているとは認められないのである。
第二の批判はEMHの認知科学の枠組みとしての有用性に関するものである。一部の哲学者や認知科学者は「科学の対象はある個別化可能な因果的規則性をもったものでなければならない。しかし、拡張されたシステムの因果プロセスは種々雑多であり、もし『心の科学』が成立すべきものであるならば、EMHはそのための枠組みとしては有効性を欠いている」と主張する。しかし、リーヴィによれば、個別化可能な因果的規則性の成立が科学的探究の対象となる基準であるという見方を採用するならば、心に関して現在行われている探究の多くが科学として認められないという不合理な帰結を招く。なぜなら、現在の認知科学が対象にしているものを眺めるならば、そこに見出されるのはさまざまな階層を含む統一性のない雑多な諸現象だからである。もし現在の認知科学を真正な科学として認めるならば、捨てられるべきは個別化可能な因果的規則性という基準の方であろう。
リーヴィによれば、われわれがいったんEMHを受け入れるならば、脳神経倫理学の射程とそれに特徴的な諸問題は変化を被るだろう。リーヴィは一例として精神薬理学によるエンハンスメントをとりあげ、その倫理的是非に関する代表的な諸議論が脳の物理的境界を心の境界と同一視する内在主義的直観によって制約されていると論ずる。EMHが正しいとすれば、ある技術的な介入が、脳を直接狙うものであるか、それとも環境内に拡張された認知の座を狙うものであるかは、倫理的に重要な違いを生むものとして理解されるべきではない。問題となるべきは認知を変化させる過程ではなくその結果である。EMHは、脳内に対する介入を実際以上に重く受け止めること(あるいは行為者の周辺環境に対する介入を実際以上に軽く受け止めること)を防止し、われわれを正しい倫理的評価へと導く有効な指針として機能しうるのである。
リーヴィの講演に続いて、小口峰樹(UTCP)および礒部太一(情報学環)から特定質問が提起された。
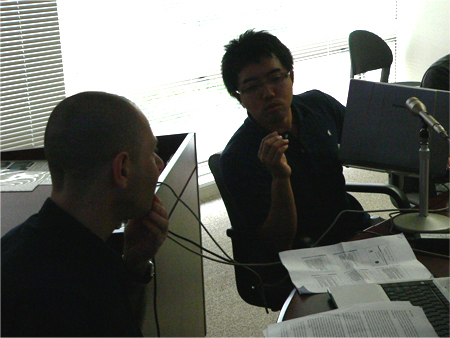
小口は以下の二つの質問を行った。第一に、エンハンスメントに関してしばしば提起される「不自然さの問題」は、リーヴィが講演のなかで示唆したように内在主義的直観に全面的に依拠しているのではなく、拡張された認知システムに対してその自律性や真正性の喪失というかたちで改めて問題となるのではないか。第二に、EMHは認知に関する内在主義的直観をそのまま温存しており、EMHを徹底しようとするならば、そうした直観を離れた認知に関する何らかの有望な理論からこそわれわれは出発すべきではないか。
リーヴィは、第一の問いに対して、人間においては自然性それ自体のなかに可塑性が刻み込まれているがゆえに、不自然さの感覚が告げ知らせるものを倫理的に重要なものとして受け取る必要はないと応答した。また、第二の問いに対しては、どんな科学であれ、その出発点においてはわれわれのもつ素朴な直観に依拠した指示の固定を通じてその対象を選出せねばならず、その過程はEMHに依拠した心の科学においても例外ではないと反論した。

礒部は、脳機能を拡張する技術であるブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)を題材として取りあげ、その技術の概説ならびに閉じ込め症候群(LIS)に対するその応用の紹介を行った上で、EMHの観点から見たBMIの倫理的・社会的影響がどういったものか、とりわけLIS患者のアイデンティティに対して与える影響がどういったものかという問いを提起した。
この問いに対してリーヴィは、「特徴づけ」という意味でのアイデンティティ(「あなたは誰か」という問いに対する答えとしてのアイデンティティ)を他の意味でのアイデンティティ(人格の数的同一性)から区別した上で、「特徴づけ」という意味での人格的同一性にとっては技術的環境よりも社会的環境の方が重要であり、それゆえBMIによる認知的拡張が人格的同一性に対して与える影響は当人の社会的位置づけに由来する影響に比べてわずかであろうと応答した。
その後の質疑応答では、特定質問者からの再応答も含め、多様な論点からの質問が提起された。リーヴィ自身が冒頭で述べたように、リーヴィの哲学の特徴のひとつは、行為者に対する環境の影響という視点から議論を展開するというそのスタイルにあり、その意味で、本講演はリーヴィの発想の源泉を告げ知らせるものとして、初回の講演にふさわしいものであったと言えよう。
Seminar 2: Does Evolution Explain Morality, or Explain It Away?
2009年7月14日 於東京大学駒場キャンパスコラボレーションルーム2
報告:筒井晴香(UTCP共同研究員)
連続講演会第二回目は進化論と道徳をテーマに行われた。他者との助け合いのような、人間の道徳行動は、進化の過程で選択されてきたものとして説明可能である。動物の利他的行動に関する進化生物学的研究や、数理的モデルを用いたゲーム理論的研究によって、このことは広く知られている。しかし、進化の過程で選択された行動とは、究極的には利己的目的を持った行動のはずである。道徳の進化的基盤が明らかにされれば、道徳的行動は究極的には利己的行動に等しいということになり、道徳の道徳たる所以が失われてしまうのではないだろうか。リーヴィは本講演で、このような「進化的説明による道徳の消去(ないし矮小化)」の問題に対する有効な回答を与えている。

より詳しく述べると、進化的説明による道徳の消去ないし矮小化の問題は、リーヴィによって以下の二点にまとめられている。第一の点は上で述べた究極的利己性の問題。第二の点は道徳的性質の存在論に関わる問題である。道徳的性質が進化によって形作られたものだとしよう。すると、もし進化の過程が別様であったならば、それに従って道徳的性質も全く異なったものになっていただろうといえる。すると道徳的性質は堅固な存在論的基盤を持ちえないのではないか。
リーヴィは上の二つの問題に対し、それぞれ以下のような答えを与える。第一の点について、彼は行動の説明を近位の説明(行為者の理由や動機づけに関わる)と遠位の説明(進化的に確立された機能に関わる)の2種類に分ける。進化的説明は遠位の説明であるのに対し、道徳性が関わるのは近位の説明である。従って進化的説明は道徳性に訴えた説明に取って代わるものではない。第二の点について、リーヴィは道徳構築主義(moral constructivism)の立場を取る。これは道徳的性質を、人々の態度によって構築されるものとして捉える立場である。例えば「罪深い」ということを、それに対して人々が(人目を避けたり叱責したりといった)ある一連の態度を取ることとして捉えるのである。構築主義を取れば、道徳的性質は我々の感情や行動に関する性質に等しいため、存在論的問題は生じない。
リーヴィによれば、構築主義は次のような含意を持つ。それは、道徳的性質を「この現実世界の我々の態度」に固定化する(rigidify)ということである。この点は有名な「双子地球」の思考実験を援用することで説明されるが、要するに「この現実世界における我々の態度こそが真の道徳的性質を決定する。他の可能世界において我々の『罪深さ』や『誇らしさ』等によく似た性質が見られたとしても、それは道徳的性質ではない」ということが構築主義から帰結するのである。

リーヴィの講演の後、UTCPメンバーの筒井晴香・吉田敬が特定質問を行った。筒井は以下の2点に関する質問を行った。まず、双子地球の思考実験においては種の「本質(essence)」が鍵となるが、リーヴィの道徳版双子地球の思考実験において道徳の本質はどうなっているのか。第二に、リーヴィの議論における道徳普遍主義的含意と、道徳相対主義からの可能な反論について。リーヴィからは、道徳の本質は集団の福利に貢献する機能的性質に存し、その機能的性質を実現する仕方は多様でありうる(従ってこのレベルでは道徳多元主義・相対主義が認められる)という回答を得た。吉田は講演の内容を踏まえ、近年注目の高まる「神経経済学(neuroeconomics)」の知見を紹介した。神経科学の手法を用いて、人間の経済行動を解明する神経経済学は、動物行動に関する進化的研究からは分からない、人間特有の道徳的行動の基盤を明らかにしつつある。例えば、一回限りの取引相手を助けたり懲らしめたりといった、見返りを求めない振る舞いに対し光が当てられている。リーヴィは講演において示された進化的説明の単純さを認めつつ、一回限りのやり取りに関する説明は進化的観点からも可能である旨を論じた。また吉田が引用したFehrらの「強い互恵性(strong reciprocity)」のアイデアに対し、近位/遠位の説明の区別に基づいて反論を述べた。

次回では、本講演でリーヴィが示した道徳構築主義のアイデアが、サイコパス(精神病質者)の道徳的責任という、きわめて現実的なテーマに応用される。進化論を受け入れた道徳は、犯罪と精神病質という喫緊の社会問題に対し、いかなる観点を提供するのだろうか。
Seminar 3: Psychopathy, Responsibility and the Moral/Conventional Distinction
2009年7月16日 於東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム2
報告: 朴嵩哲(UTCP若手研究員)、関谷翔(UTCP共同研究員)
はじめに連続講演会第3回目のリーヴィの議論をまとめ、さらに私たちの質問と、それに対するリーヴィの応答を見てみよう。

【リーヴィの議論】
彼は、サイコパスが犯罪を犯したとしても、道徳的責任を問えないということを立証しようとする。ここでサイコパスとは何か簡単に説明しておこう。精神医学者の間で見解の不一致があるが、以下のように、サイコパスの特徴にかんするほぼどんなリストにも含まれる特徴がある。
・過去の行為について本物の良心の呵責や罪悪感を感じない。
・被害者に同情を感じない
・衝動的で責任感が無く、長期的なプランを実行できない
・常習的犯罪とは思慮分別が無い点で異なる。
最近10年ほどでサイコパスの神経科学的特徴づけも進みつつある。Blairらによると、サイコパスの行動は扁桃体の機能不全によって生じている。扁桃体は感情負荷的表象(affect-laden representation)の処理に関わっているので、道徳的社会化にとって不可欠であるといわれている。
このように特徴付けられるサイコパスに道徳的責任を問えないとリーヴィは主張する。その議論をまとめると次のようになる。
1. 私たちの道徳的規範へのアクセスは、他者への危害によって喚起される感情的反応を利用して初めて可能になる(リーヴィは進化についての考察によってこの主張を補強している。
2. サイコパスはこうした感情的反応を持たない。
3. 1+2→サイコパスは(中心的)道徳的規範にアクセスできない。
4. 行為者への責任を帰属させるためには、認識論的必要条件が存在する。すなわち、関連する非道徳的事実について知っていることと、道徳的規範(何が道徳的に悪い行為か)について知っていることである。
5. 3+4→したがって、サイコパスは責任帰属のための認識論的必要条件を満たさない。
6. したがって、サイコパスには完全な道徳的責任を帰属させることができない。
以上がリーヴィの議論の骨子である。
【朴の質問―実行可能性をめぐる懸念―】
リーヴィに対するUTCP研究員の朴による一つ目の質問は次のような内容であった。
リーヴィの道徳的概念の保有と責任帰属の規準は、感情や(それに伴う)動機の形成能力である。この規準を「感情・動機規準」を呼ぶことにしよう。こうした規準を実行に移すことには懸念がある。
まず、感情・動機規準を受け入れるならば、ひょっとすると、サイコパス以外の犯罪者たちも、道徳的規範にアクセスできないために免責されてしまうという可能性がある。なぜなら、彼らが実際に犯罪を犯したという事実からすると、道徳的規範に従おうとする感情や動機を欠如していたという可能性を否定できないからである。そうだとすると、感情・動機規準によれば、こうした犯罪者はサイコパスと同様に道徳的概念をそもそも持っていないのだから、したがって免責されるべきではないのだろうか。
また、サイコパスと通常の犯罪者の違いは連続的であり、両者を明確に区別できないのかもしれない。そうだとすると、裁判において、被告がどの程度「サイコパス的」なのかを決定するために、脳画像などのデータを参照しながら決定しなければならなくなるだろう。このようなプロセスは多大な時間と専門家の助けを必要とするだろう。結局、リーヴィの規準は、現在において実行が困難であるように思われる。

【リーヴィの応答】
この問いに対するリーヴィの答はこうだ。
彼は、彼の規準は実行することが非常に難しいことにまったく同意する。しかし、哲学者は実行可能性のことは、ひとまず棚上げにしてさまざまな可能性について論じるべきだと主張する。可能な政策の提案と政策の選択については、認知的分業体制をとり、政策の選択は人々に任せるべきだという。
もう一つの懸念、すなわち、全ての犯罪者がサイコパスと同様に道徳的概念を持たないので免責されるかもしれないということに対して、リーヴィはサイコパスと通常の犯罪者は明確に区別できるとして反論する。第一に、ブレアの実験によると、通常の犯罪者は、道徳的規範と慣習的規範の区別をさせる課題において正常にふるまうが、サイコパスはそうではない(すべてが道徳的規範であると答える)。第二に、通常の犯罪者は衝動的に暴力に訴えるのに対して、サイコパスはためらいもなく、道具的に暴力を使用する。
ただし彼は、流通しているサイコパス・チェックリストはとても粗い尺度なので、サイコパスでないと診断された人が実際には道徳的規範を理解していないという可能性があるという。また、道徳的規範の把握そのものが段階的なものであるかもしれない。そうだとすると、責任概念も段階的なものになるが、そのような段階的な責任理論で利用できるものはまだないという。
【朴の質問―「責任」概念の明確化】
朴による二つ目の質問は「責任」概念にかかわる。
リーヴィが「サイコパスには責任を問えない」というとき、彼はいったい何を意味しているのだろうか?
責任は罰の概念と密接に関わっている。通常、私たちが誰かに責任があると判断するとき、その人に対して罰を与える。また、責任がないと判断するなら、罰を与えない。したがって、リーヴィは「サイコパスには責任が無いのだから、罰を与えてはいけない」と述べていると考えるのが自然であろう。
しかし、「罰」は複雑な概念である。次に、「罰」概念を明確にし、上の解釈に若干の修正を加えたい。
罰は少なくとも二通りの目的で課される。一つは苦痛を与えることで、罪を償わせるという目的であり、もう一つは道徳的規範の再教育という目的である。大人の犯罪者に対する罰は、「償い」という側面が重要になるが、若者の同様のふるまい対しては、「再教育」という側面が重要になる。この違いは、大人と若者の道徳的規範の理解の程度を反映していると考えられる。そうだとすると、「道徳的規範を十分に理解していない」という点でサイコパスは大人よりも若者に類似しているため、彼らは若者と同様の扱いを受けるべきだ、ということになるだろう。したがって、リーヴィの主張は次のように理解するべきだろう。すなわち、サイコパスは道徳的責任を持たないのだから、彼らに「償い」の目的で罰を与えてはならず、ただ「再教育」の目的でのみ罰を与えるべきなのである。
【リーヴィの応答】
リーヴィは責任と罰が連動するという通常の考えに同意する。つまり、「サイコパスには責任が問えないのだから、彼らにはいかなる罰も与えてはいけない」と彼は考える。彼は、朴の「再教育は罰の一つである」という理解に反論し「再教育は罰ではない」と主張した上で、サイコパスの扱いについてより明確な提案をする。
彼は、犯罪者に苦痛を与える処置を行うことを正当化するしかたを、「過去指向的」なしかたと「未来指向的」なしかたに区別する。朴の用語と対応を付けるなら、「償い」は過去指向的であり、過去の行為によって正当化される、苦痛を伴う処置である。また、「再教育」は未来指向的であり、未来においてより良い帰結(つまり再犯の防止)をもたらすということによって正当化される処置である。ここで、「再教育」は未来指向的に与えられる苦痛を伴う処置の一つにすぎない。場合によっては、無能力化や刑務所における隔離といった処置も、未来指向的なしかたで正当化される。
「再教育」を含めた未来指向的な処置は、罰では決してない。これは単なる用語法の問題ではない。それは以下のような理由による。
「誰かが自身の行為によって罰を受ける」ということが適切であるのは、苦痛を伴う処置が、その行為が罰に値するという事実によって、正当化される場合である。したがって、罰は、「過去指向的に与えられる苦痛を伴う処置」として理解されるべきである。
もし、サイコパスのように、その人に責任がなければ、その人に苦痛を伴う処置を与えることは、その人の過去の行為だけから正当化することはできない。この場合、苦痛を伴う処置は、未来指向的にのみ正当化される。この場合の苦痛を伴う処置は、いかなる意味でも罰ではない。なぜなら、(未来指向的正当化が功利計算によってもたらされるなら)私たちは、サイコパスとそれ以外の人を平等に、功利を考慮する対象とするからである。もし行為者に責任があれば、私たちはその人の功利を考慮に入れないのである。サイコパスは感染症の患者と同様に扱うべきである。彼らには彼らを含めた社会全体の利益の観点から、必要以上の苦痛を与えてはいけないのである。
【朴と関谷の質問(反論)―マインドリーディングに関して】
リーヴィによると、道徳的概念を持つためには、単に道徳的規範と慣習的規範の区別ができるということだけでは不十分だという。道徳的規範を理解するためにはその規範を、「他者の危害」という観点で理解しなければならず、したがって他者の痛みや恐れや悲しみを理解しなければならないのである。
この点に私たちは同意する。しかし、「他者の痛みや恐れや悲しみを理解」することは少なくとも二通りの仕方で実現できると主張したい。
この点をはっきりさせるために、(分析哲学における)マインドリーディング論争について簡単に紹介しておきたい。
私たちは他者のふるまいを、心的状態を読み取ることによって説明したり予測したりすることができる。ここで私たちが行っている他者の心的状態の読み取りを「マインドリーディング」と呼ぶ。マインドリーディングのメカニズムについて、主に二通りの説がある。一つは理論説で、もう一つはシミュレーション説である。
理論説によれば、マインドリーディングは他者の心に「ついて」の高階の信念を利用した推論である。たとえば相手の悲しみを理解しようとするときに、「目の前で女性が涙を流している」ことが分かっていれば、「涙を流している人は悲しんでいる」という素朴心理学の一般法則をあてはめて、「彼女は悲しんでいる」と推論できる。ここで、自分が悲しくなる必要はまったくない。
しかし、シミュレーション説によれば、上の場合では実際に自分も悲しくなる(よりもっともらしい言い方をするなら、自分自身の悲しみを生み出すメカニズムを利用する)ことによって、その女性の悲しみを理解するのだという。いわば自分を使って相手の心をシミュレーションするというわけである。
シミュレーション説論者のゴールドマンによると、他者の基本的感情(fear, disgust, anger)の読み取りは、シミュレーションによって読み取られているということを示す多くの証拠があるという。おそらく、サイコパスはそのようなシミュレーションメカニズムを欠損しているのだと思われる。
しかし、原理的には、理論説の言うように、理論にもとづく感情の理解も可能であるだろう。このような方法によって、「他者の危害」を理解することができるなら、サイコパスを教育して道徳的規範を理解させたり、そうすることでさらに、彼らに対して責任を帰属させたりすることもできるようになるだろう。
道徳的規範を身につけるためには、2つのステップが必要である。第一のステップは、他者の危害とはどのようなことかを理解することである。ここは理論説のいうプロセスで実行できるかもしれない。第二のステップは、(第一のステップにもとづき)他者に危害を与えないように強く動機付けられることである。このステップが道徳的規範の理解そのもののために必要かどうかは(動機内在主義をめぐる議論が未決着であることが示すとおり)議論の余地がある。しかし、社会の維持のために「規範に従う」というこのステップが必要なことは明らかであろう。シミュレーション的な「他者の危害」の理解は、二つのステップを同時に実現することができる。なぜなら、たとえば他者の恐怖をシミュレーションを通じて理解するときには、自分でも恐怖を感じるため、それを避けるように振舞うことによって、自然と他者に危害を与えないようになるからである。したがって、マインドリーディングに関するシミュレーション説は、道徳的行動の進化を明快に説明する。しかし、進化論的考察は、現在の私たちのありかたを説明するものにすぎず、未来においてどうすべきかに答えるものではないだろう。重要なのは、道徳的規範へとアクセスする、現に利用されている方法とは別の方法がありうるということである。

【リーヴィの応答】
彼は、サイコパスは現に感情に対する理論的なアクセスも欠いているとして私たちに反論する。
サイコパスは、誤信念課題において正常な応答をするが、感情帰属の課題では著しい能力の欠損を示す。実際、理論的に理解できそうな場面でも、まったく相手の感情を理解していなように思われるので、理論的な感情帰属能力を欠損しているように見える(彼は、クレックリーの逸話をその証拠の一つとして挙げている)。
サイコパスに「こういう行為はしてはいけない」という形で私たちが「道徳的に悪い」と呼ぶ典型的な例を教え込むことによって、道徳的規範を理論的に教えることもできないように思われる。なぜなら、彼らは道徳的規範を道徳的たらしめている本質を理解できないだろうからである。彼らは、ある行為が「悪い」結果を及ぼすとはどういうことかを理解できないのである。
【進化論的説明、義務論、帰結主義:関谷の質問とそれに対するリーヴィの回答】
リーヴィによれば、感情は2つの瞬間に道徳に関わっている。1つは道徳の中心的規範(core moral norms)を獲得するときであり、もう1つは道徳的動機を履行するときである。進化生物学(特にゲーム理論を組み込んだ集団遺伝学)は、なぜ利他行動が進化の過程で現れたかを互恵的利他性や血縁淘汰によって説明したが、これは道徳を説明したわけではない。
動機内在主義をめぐる議論を避けるため、リーヴィは進化論的説明を持ち出してきているが、この種の進化論的説明では現状を無批判に最善の(最も適応度の高い)状態と見なしがちである。なぜ道徳が適応的であるのかについては検討を要する。
リーヴィは、道徳に関するすべてが進化的にどのように誕生してきたかについて説明しようとしているわけではなく、道徳の中心的規範についてのみの説明であるとして、これら2つの反論を斥ける。利他性から道徳のすべてがどのように生まれてきたかについてはまだまだ分からないことが多いが、道徳の中心的規範が利他性から生まれてきたと考えるのが最もらしいとリーヴィは言う。同様に、道徳の内容についての議論ではないので、道徳が適応的であるかについてはリーヴィ自身、懐疑的である。
また、リーヴィの議論は帰結主義と義務論との関係をめぐる問題を孕んでいるように思える。道徳とは何かと考えたときに、帰結主義や義務論はその問いに解答を与えそうな有力な候補であるが、リーヴィの議論では、道徳の中心的規範として他者危害原則が想定されることにより、暗に義務論を正しいとしてしまっており、帰結主義の立場に立ったときの議論がなされていない。つまり、サイコパスが帰結主義的原則に違反した場合には道徳的責任があるのかという問題について検討されていない。サイコパスの道徳的責任について論じる前に、そもそも道徳とは何なのかという問いに答えなくてはならないように思われる。
リーヴィは義務論が正しいとして、帰結主義に対して論点先取に陥っている可能性を認めながらも、例えばトロッコ問題において太った人の背中を押して、彼を死に追いやるという行動を悪い行動たらしめているのはまさに危害であり、同時にそれは道徳の中心的規範であると主張する。さらに、サイコパスは一見、帰結主義的に見えるかもしれないが、それは健常者の捉える帰結主義と同じではないのではないかと述べ、リーヴィは、サイコパスには(義務論が正しくても帰結主義が正しくても)道徳的責任はないと結論した。
Seminar 4: Resisting Weakness of the Will
2009年7月17日 於東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム4
報告: 西堤優(UTCP共同研究員)
この講演会のなかで、リーヴィ氏は、まず「意志薄弱 (akrasia)」と「意志の弱さ (weakness of the will)」の違いを強調し、R. Holton氏に倣って、前者を行為者の最善の判断に反した行為、後者を行為者の決意に反する行為として明確に区別した。

日常生活のなかで私たちは、自分が一度決めたことを実行するために、誘惑に駆られても、それに屈しまいと自己を制御しようとする。しかし、誘惑が強ければ強いほど、そして誘惑に耐える時間が長ければ長いほど、その誘惑に耐えるための自己制御は困難になっていく。私たちは自己制御に失敗した場合、つまり、意志の弱さが露呈した場合、決意に反して行為してしまう。リーヴィ氏は、意志の弱さに関連したこの自己制御に注目し、認知心理学が提案する二つのシステムから意志の弱さを説明している。
認知心理学が提案する二つのシステムとは、互いに作用するが独立している「システム1」と「システム2」である。システム1は、脳の辺縁系依存的で衝動的なシステムであるが、対照的にシステム2は、前頭葉依存的で、熟慮的なシステムである。私たちが誘惑を感じたとしても、それに耐えて決意したことを実行できるのは、システム2が欲求のままに実行しようとするシステム1を制御できているからである。しかし、システム2において自己減耗(Ego depletion)という状態が引き起こされると、もはやシステム2はシステム1を制御することができなくなってしまう。つまり、誘惑に負けて、決意に反した行為が引き起こされてしまうのである。
このように認知心理学的概念で意志の弱さを記述することによって、リーヴィ氏が最も強調する点は、認知心理学的概念は、素朴心理学的概念である意志の弱さとは必ずしも一致しないということである。その経験科学的な証拠として、リーヴィ氏は、自己減耗が集中力を要する課題によって引き起こされたケースや、またそのようにして自己減耗が引き起こされた人が実際に意志の弱さを露呈するケースをあげている。従来の素朴心理学的概念に対して、経験科学的な証拠をもとになされたリーヴィ氏の新たな提案は、意志の弱さがより広い現象の現れの一つであることを明らかにした点で、大きな意義があるように思われる。
しかし、二つのシステムに注目すると、意志の弱さはシステム2の自己減耗によってのみ引き起こされるものではないのではなかろうかという疑問が湧いてくる。たとえば、システム2の機能不全によりもともと自己制御の喪失状態である人や、欲求に駆られたシステム1がシステム2を圧倒し、システム1主導で引き起こされる意志の弱さもあるのではなかろうか。今後、私たちの素朴心理学的な意志の弱さの概念が、あらゆる経験科学の証拠によって裏打ちされることに期待したい次第である。


Lecture: Social Engineering: A Defense
2009年7月21日 於東京大学駒場キャンパス18号館コラボレーションルーム1
中尾麻伊香(UTCP若手研究員)
この講演は一般向けということもあり、リーヴィの研究分野である哲学や心理学の知見を「社会」にどのように応用させるのかということが主題となった。タイトルに用いられている“Social Engineering”という用語は、しばしばネガティブなもの―社会的な目的を達成するための他人に対する非道徳的介入―とみなされるが、リーヴィは、Social Engineeringは必ずしも非道徳的なものとみなされる必要はなく、行為者の意志決定を補助するものとみなしうるとして、その可能性を拓こうとする。

テーマとなったのは「幸福」である。Dan Haybronによれば、「幸福」はながいあいだ哲学者の最大の関心事であったが、近代以降の哲学者はほとんどそれについて語らなくなった。その理由は、自分にとって何が幸福であるかを最もよく判断できるのは各個人であるとみなされるようになったからであるという。ところが近年の心理学では、ひとびとは彼ら自身で妥当な判断ができるとは限らないという知見が得られている。
幸福を求めるひとびとが幸福になれないのは何故なのか?リーヴィはまず、「快楽的順応(hedonic adaptation)」という現象を説明する。健常者は、もし自分が身体障害者になったとしたら、極めて大きな不幸を感じるだろうと考える。しかし実際には、身体障害者は一旦不幸になった後にしばらくすると障害を被る前の「平常状態」を取り戻すことが多い。一方、宝くじの当選者には逆の現象が起こる。この快楽的順応の影響力について自覚がないということは、ひとびとは自分の将来の感情状態について予測するのが不得手であるということを意味する。
リーヴィはこのほかにもさまざまな例を挙げ、ひとびとが適切な未来予測をできないことを示す。そして、感情的未来予測を向上させることで、ひとびとはよりよい判断ができるようになるという。そのためには、ある種のパターナリズムを伴う、たとえば選択肢を制限するといったような、直接的な手段が望ましいというのがリーヴィの結論である。たとえば性転換手術によって自分は著しく幸福になると信じているひとびとがいるが、ひとびとのそうした信念は間違っていることを示すいくつもの理由がある。そのとき、性転換手術を禁止するのではなく、手術を受けるためのハードルを高く設定することで、ひとびとをよりよい選択へと導くことができると考えるのである。このようにリーヴィは、専門家の判断で情報をコントロールする(選択肢から認知的な歪みをもたらす要素を取り除く)ことによって、ひとびとの幸福を実現し、よりよい社会を形成することを提案する。

質疑応答においては活発な議論が交わされた。私自身は、専門家とは具体的にはどのような人を指すのか、そしてひとびとが情報を読み解くためにもつべきとされる「リテラシー」をどのように考えるのかという質問を行った。リーヴィの回答によれば、専門家とはそれぞれの分野のエキスパートで、その数は多く、それぞれが特定のタスクを持つ。また、リテラシーは、どの専門家を信じればいいのかを見分けるために必要となるため、リーヴィの提案する専門家システムとは矛盾しないと返答した。ほかにも、科学的には正しいが社会的によくない結果を招くと思われる知見(例えば、ある人種の特定の遺伝子が特定の病気や障害と関連づいていることが明らかになった場合など)を、どのように公開していくのか、バランスをどうとるかといった問題などが議論された。リーヴィの主張は自由を最も尊重すべき価値と考える立場との間になお緊張関係を残しているように思われるが、刺激的なテーマのもとに議論は盛り上がり、有意義な会となった。

Seminar 5: Cognitive Enhancement and Intuitive Dualism
2009年7月22日 於東京大学駒場キャンパス18号館コラボレーションルーム4
中澤栄輔(UTCP若手研究員)
この回がリーヴィ氏連続講演会の最終回である。「認知的エンハンスメントと直観的二元論」というのが講演のタイトルだ。(このブログ記事をここまでお読みくださっている方には必要ないかもしれないが)いちおう、「認知的エンハンスメント」とはなにか、そして「直観的二元論」とはなにか、ということについて若干説明をしながら講演要旨を記そう。

医療を本来の治療という目的を越えて人間の能力の増強のために用いることを「エンハンスメント」という。認知的エンハンスメントは、身体的エンハンスメントや道徳的エンハンスメントと区別され、人間の知的能力にかんするエンハンスメントである。たとえば、リタリンなどの薬物を使用することで注意力が高まり、知的な作業を効率よく行うことができる。そのようにして、わたしたちが通常の状態で持っている認知的能力を拡張させる医療的介入を認知的エンハンスメントという。
こうした認知的エンハンスメントには道徳的問題がつきまとう。「はたして薬をつかって頭をよくすることは善いことなのか」。たぶん、こうした疑問に「いや、善いことではない」と答えたくなる人は多いのではないか。エリオットはプロザックを服用することで疎外感を克服しようとするエンハンスメントについて次のように述べている。
もしプロザックによってあなたの性格が変更されるとしたら、たとえそれが良い意味での変更であったとしても、憂慮されるであろう。それは端的に、「あなたの」性格とは言えなくなってしまうからだ。こうしたタイプの性格の変更は本来性(オーセンティシティ)の倫理に抵触すると思われる。(Elliott, C. 1998. The Tyranny of Happiness: Ethics and Cosmetic Psychopharmacology. In Erik Parens (ed) Enhancing Human Traits: Ethical and Social Implications. Washington, D.C.: Georgetown University Press, pp. 177-188.)
このようにエリオットは認知的エンハンスメントを本来性という観点から道徳的に問題視している。伝統的に、本来性という概念は「善く生きる」うえで人間にアプリオリに備わっている性質と考えられている。いわば、理性的人間の真実の生き方を規定する価値である。
リーヴィの今回の講演はこういった本来性概念の批判的考察に主眼が置かれていた。彼の批判は二段構えだ。第一の主張は、わたしたちの道徳的判断は理性の働きによるというよりも感情の働きによる、というものである。すなわち、認知的エンハンスメントにまつわるネガティブな道徳的評価は、わたしたちの理性の働きをとおして得られたもの、というよりもむしろ感情の働きの結果というわけだ。さらに、第二の主張は、認知的エンハンスメントにたいするそうした否定的な感情はわたしたちが暗黙のうちに前提している「直観的な二元論」の枠組みを脅かすからだ、とリーヴィは主張する。
リーヴィによると、心と物が別々の実体であるというデカルト由来の心身二元論は深くわたしたちの日常的直観に結びついている。だとすると、認知エンハンスメントのように身体(脳)に介入して心(認知機能)を増進することは、そうした日常的直観に支えられているカテゴリーを侵犯することになる。このカテゴリーを侵すことで惹起されるマイナスの感情が引き金になって、わたしたちは認知的エンハンスメントに反対したくなる、と、そのようにリーヴィは考えている。
リーヴィの仮説「認知的エンハンスメントにたいするそうした否定的な感情はわたしたちが暗黙のうちに前提している直観的な二元論の枠組みを脅かす」を確かめるためには次のことが言えなくてはならない。
1. わたしたちの多くが直観的に二元論を前提にしている。
2. 直観的なカテゴリーを脅かすことはネガティブな道徳的評価をひきおこす。
1について、リーヴィはベーリングが2002年におこなった死後の世界にかんする信念の社会調査によって確証されていると論じる。しかしながら、2にかんしては、リーヴィも述べているように、いまだ経験的データは得られていない。

特定質問者である、中澤栄輔(UTCP)はこの「2. 直観的なカテゴリーを脅かすことはネガティブな道徳的評価をひきおこす」という仮説にかんして調査を行った。ただし、この調査は非常にラフなものであり、参考程度にとどめるべきである。とはいえ、結果として、直観的なカテゴリーを脅かすことはネガティブな道徳的評価を引き起こすということが(若干)確証された。
もちろん、リーヴィの仮説はさらにより精密に経験の裁きを受けなければならない。また、哲学的問題を経験的データによって確証していこうという実験哲学の発想自体もさらに反省的に捉えなおされるべきである。そういった点でリーヴィも経験的手法にある一定の留保をしている。しかしながら、経験的データを援用して伝統的な本来性という概念を解体しようというリーヴィの試みは、認知的エンハンスメントを巡る論争に新境地をひらくものであり、十分に刺激的で意義深い。







