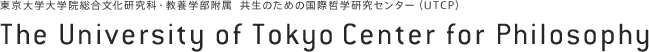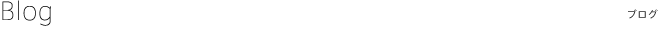【報告】UTCP Series Second View 第4回「医療刑務所における摂食障害の治療」報告書②
この報告では、2025年5月24日(土)13:00〜15:30に開催されたUTCP Series Second View 第4回「医療刑務所における摂食障害の治療」の内容を紹介する。この講演会では、北九州医療刑務所から、心療内科医の瀧井正人先生、看護師の守田裕子先生、刑務官の髙野美幸先生をお招きし、それぞれのご専門の立場から矯正医療における摂食障害の患者の処遇と治療についてお話しいただいた。
ブログは三部構成になっており、この第二部では、法務事務官の髙野美幸先生と法務技官看護師の守田裕子先生のご講演、参加者からの質疑に対する先生方の回答の一部を紹介したい。
髙野美幸先生ご講演——刑務官から見た摂食障害の患者の処遇と治療
髙野先生は、瀧井先生が所長として着任されて以来、摂食障害を患う受刑者の担当として、また医療部との連携係として業務にあたられてきた。
先生によれば、北九州医療刑務所に移送されてくる摂食障害患者の多くが、常習累犯窃盗という罪を犯していること、そして「なぜ治療が必要なのか」を理解できない者が多く感じるという。そのような受刑者と、日々どのように接されているのだろうか。以下では、北九州医療刑務所に移送されてくる摂食障害患者の傾向、刑務官としての「命を守る」という役割の重要性、医師、看護師、刑務官の「三位一体」の連携についてのお話をまとめたい。
刑務官として接してきた摂食障害患者の性格や特徴として、次の四点を挙げた。まず、「他者との比較」を行う傾向である。他の摂食障害患者と自分を比較し、劣っていると訴える。これは、わずかでも自分の体重が相手より増えただけで、劣等感を抱き、激しい不安に駆られるといった形で現れる。二点目に、「固執とわがまま」な傾向である。患者たちは、何かに固執し、わがままで頑固な一面があるという。具体的には、食事の時間やメニュー、食べ方など、些細なことにも強いこだわりを見せ、それが満たされないと激しい抵抗を示すことがあるそうだ。三点目に、「ネガティブ思考」があるという。患者たちは他人の評価を常に気にし、ネガティブな思考に陥りがちだそうだ。周囲の何気ない一言を、自分への批判や拒絶だと過剰に解釈し、自尊心が深く傷つけられているような振る舞いを見せるという。四点目に、「他責思考」である。つまり、問題の原因を自分ではなく、周囲の環境や他者のせいにするということだ。自分の病気や置かれている状況を、刑務所の環境や刑務官の対応のせいにし、責任を転嫁することで、自らの行動と向き合うことを回避しようとする傾向がみられるという。
髙野先生は、摂食障害を持つ受刑者はこのような特徴を持つがゆえに、対人関係を築くことが難しく、病気や人間関係から逃げて、「やせること」に必死にしがみついているように感じると語られた。このような行動は、患者たちが自らの心の痛みに直接向き合うことから逃避し、コントロールできる唯一の対象である「体重」を巡る戦いに終始していることを示している。
続いて、刑務官としての「命を守る」という役割の重要性についてお話しされた。瀧井先生が着任されるまで、ごく稀なケースではあるが、体重が著しく減少し、適切な治療がなされないまま亡くなる受刑者もいたという。髙野先生のように、患者の生活を昼夜問わず管理する刑務官の不安は非常に大きかったそうだ。しかし、瀧井先生の治療が始まってからは、摂食障害患者が亡くなることは一人もなくなり、心身の回復が見られるようになったという。回復、というのは具体的には、体重が増えたという物理的な変化もそうであるが、それだけでなく、患者の表情が豊かになり、他者とコミュニケーションを取ろうとする姿勢が見られるようになったことからも感じ取れるそうだ。
北九州医療刑務所では、医師、看護師、刑務官の「三位一体」の連携が治療体制の強みであるという。摂食障害という病気を理解することから始め、カンファレンスで密に情報共有を行い、治療方針をすり合わせることで、円滑な治療を実現しているという。この定期的な情報共有は、それぞれの専門職が患者の全体像を把握し、一貫した対応を可能にする上で不可欠であると語られた。
髙野先生によれば、刑務官は、受刑者の規律秩序を維持する「厳しい指導者」であると同時に、心身の健康を保持するための「良き理解者」でなければならない。精神疾患を持つ受刑者、特に摂食障害を持つ受刑者への対応は非常に難しいが、それでも、患者が感情をぶつけてきた際に感情で返さず、それを受け止め、励まし、諭すという姿勢を貫いているとおっしゃった。
最後に、先生は一般刑務所でも摂食障害患者が増加している現状に触れ、今後、矯正施設全体が摂食障害の受刑者に対応できるよう、情報共有や働きかけを続けていきたいという抱負を述べられた。この課題に取り組むためには、医療刑務所で培われたノウハウを、より広範な矯正施設で共有し、専門的な知見を持つ人材を育成していく必要があると結んだ。
守田裕子先生ご講演——看護師から見た摂食障害の患者の治療
最後に登壇されたのは、看護師の守田裕子先生である。瀧井先生のご講演にもあったように、北九州医療刑務所で行われている摂食障害治療プログラムは、「行動療法」「心を育てる治療」「チーム医療」の3つの柱で成り立っている。守田先生は、看護師の立場から、プログラムの具体的な内容について説明してくださった。
まず「行動療法」についてである。行動療法には、「行動制限」「物理的対策」「食事療法」などが含まれる。
「行動制限」として、入所時に、作業、入浴、運動、読書、水道水の使用などが制限されるそうだ。しかし、体重増加や生活態度の改善に伴い、段階的に解除されていく。これは、患者の「痩せるための行動」を含む様々な「回避」を物理的に遮断し、体重増加を促すことは勿論、自分自身の心と向き合うことを促し、自分の問題に前向きに取り組めるようになることを目的としている。
「物理的対策」とは、居室の水道水が出ないようにする「水禁」スイッチや、ポータブルトイレの排泄物チェックなど、嘔吐や食べ物の隠匿を見逃さないための様々な工夫のことである。これらの対策は、患者の病的な行動パターンを物理的に断ち切るために不可欠である。一般の病院では実現が難しいが、矯正施設なら可能となる北九州医療刑務所の強みである、と守田先生は述べた。
そして「食事療法」である。瀧井先生が提唱する「食べる実力」に応じて、受刑者には、1/8から3/4まで分割された食事が配食される。これは、患者が一度に多くの量を摂取することへの恐怖を和らげ、少しずつ食べられる量を増やしていくことを目的としている。また、経口摂取が困難な場合は、経鼻経管栄養(鼻注)が実施される。これは命に関わる状態の患者を救うための最終手段である。治療への抵抗が強い患者にも強制的に栄養を投与されるもので、患者の身体的回復を最優先するための治療である。
続いて、「心を育てる治療」についての説明があった。看護師は、瀧井先生の診察以外でも、日常業務を通して広い意味でのカウンセリングを行っているという。
特に印象的だったのは、「読書療法」に関する説明である。読書療法で使用される本は「医務本」と呼ばれ、瀧井先生によって選定された約160冊がある。ファッション誌・グルメ本や自己啓発本は望ましくないとして除かれ、頭ではなく心で読むためのシンプルな絵本や童話が中心となっている。患者が自分の病気と向き合う前に、人間としての基本的な感情や感受性を取り戻すことを目的としている。
読書療法は「段階的読書」というプロセスで進められる。具体的には、受刑者の入所初期は、絵本から始まり、徐々に物語、文庫本、小説へとステップアップしていく。患者の精神年齢や状態に合わせて、このようなステップを踏むことにしているそうだ。守田先生によれば、絵本を通じて幼少期の満たされなかった感情に触れたり、物語の主人公の心情に共感したりすることで、失われた自己の再構築を促す目的があるそうだ。瀧井先生による診察の際に、患者が「医務本」の感想を語ることもあるそうだ。
守田先生もまた、チーム医療の重要性を強調された。診察前に行われるカンファレンスでは、看護師や刑務官が患者の生活状況や問題行動の有無を瀧井先生に報告し、治療方針が綿密に話し合われる。また、診察後には、瀧井先生から看護師や刑務官に感想が求められ、患者に対するそれぞれの視点や気づきが共有されることで、より質の高い治療へと繋がっていることが語られた。この「三位一体」の連携は、患者のわずかな変化も見逃さず、迅速に対応することを可能にしている。
守田先生は、摂食障害と窃盗が深く結びついているという認識のもと、再犯防止に繋がるよう、患者と向き合っていると述べられた。そして、矯正施設の特質を活かした協力的な連携が、北九州医療刑務所の治療の強みであると締めくくられた。
質疑応答
講演会に先立ち、事前に参加者の方々からお寄せいただいた質問について、講演後に、登壇者の先生方にお答えいただいた。
Q1:出所後の生活と再犯予防について、データがあればお示しいただけますか?
瀧井先生:
摂食障害の症状など出所後の患者の状況を直接的に調査することは、法律的・倫理的な問題から困難である。しかし、矯正施設に再入所したことは確実に把握できる。当所の治療プログラムを受けた患者の再入所は、それ以前の患者と比べて有意に減少している。患者の話からは、摂食障害の状態が悪いと窃盗をする回数も増え、捕まることも多くなるそうで、再入所が少なくなったということは、摂食障害の状態も改善しているのだろうと思われる。
髙野先生:
刑務官は、出所者と関わることは基本的に禁止されており、出所者がどこで何をしているのかを把握することはできない。ただし、再犯して再びどこかの施設に収容された場合は、データベースで確認することが可能である。
Q2:絵本を使う意図や目的、そして摂食障害と倫理観の崩壊について、お考えや事例をお聞かせください。
瀧井先生:
(絵本について)守田先生の講演でも紹介されたように、絵本を用いるのは患者さんの「心を育てる」ことが目的である。摂食障害を抱える人たちは、表面的な知識は豊富でも、本当の意味での精神年齢は低い場合がある。そのため、幼児が読むようなシンプルな絵本を通じて、自分自身の内面と向き合う機会を与えることが重要だと考えている。
(倫理観について)摂食障害が遷延化すると、患者は「嘘」をつくことが常態化し、内面的な変化が引き起こされる。このため、もともと持っていた倫理観や道徳観が希薄になっていく。また、摂食障害の背景に虐待や不適切な養育がある場合、社会で生きていく「実力」が育っていないケースも多い。摂食障害を長く続けることによる害と、もともと育っていない部分とを分けて考える必要がある。
Q3:先生ご自身の治療に対する意識は、刑務所内とそうでない場合で違いがありますか?
瀧井先生:
基本的な考え方である「回避の遮断」は変わらない。しかし、医療刑務所に来る患者は、一般の医療機関に来る患者よりも重篤度が高い。そのため、刑務所の強固な物理的構造を利用して「回避の遮断」をより強力に行っている。一般の医療機関の病棟では、患者が治療を回避するために逃亡したり自傷行為をするのではないかといった不安などから、治療者が厳しい対応をためらうことがある。しかし、刑務所では刑務官の管理があるため、そうした不安を抱えずに治療に専念できるという利点がある。
Q4:患者の治療動機を高めるアプローチや、刑期終了後の医療資源への繋がりについて教えてください。
瀧井先生:
(治療動機について)「嘘にまみれて自分を誤魔化している」状態では、治療動機は生まれようがない。そのため、まずは患者に現実と向き合ってもらうことが不可欠である。嘘や不適切な行動を厳しく正し、できないのであれば「お手伝いします」という姿勢で、回避できない環境を作り出す。また、経鼻経管栄養(鼻注)のように、物理的に身体を拘束する治療は、患者が一旦立ち止まり、「自分が今まで何をしてきたか」を考えさせる機会となることもある。
(医療資源への繋がりについて)出所後の医療資源は不足しており、円滑な接続は難しい現状にある。帰住先近くの医療機関にお願いすることもあるが、患者が受診を継続しないケースも少なくない。家族の力が支えとなる場合もあるため、家族と面会して患者の状況を理解してもらう機会を設けることもある。
髙野先生:
医療刑務所には、摂食障害だけでなく、統合失調症などの精神疾患患者も移送されてくる。特に摂食障害の場合はBMIが著しく低い者、精神疾患の場合は一般刑務所での処遇が困難な者が対象となる。出所が近づくと、帰住先の社会福祉士などと連携し、そのまま地域に戻る、病院に措置入院する、あるいは保護移送(帰住先近くの刑務所に移送)するなど、個々の状況に合わせて出所方法を判断している。
Q5:一般社会での患者への「寄り添い方」について、医療刑務所での実践から得られるヒントはありますか?
守田先生:
刑務所にいる摂食障害患者は、社会で見られる患者とはかなり異なるようである。そのため、一般社会で有効な「寄り添い方」とは異なるかもしれない。しかし、厳しさの中に「真剣に向き合う」という姿勢が伝わることで、患者は変わることができる。患者の反応から自分たちのやりがいを感じる瞬間は多く、その真摯な姿勢が患者にも伝わっていると信じて接している。
Q6:保護施設で疲弊している職員の方へのアドバイスをお願いします。
瀧井先生:
患者は、食事や服薬の拒否、故意の嘔吐といった行動を通じて、周囲との関係を保とうとしていることがある。患者の思い通りにさせてしまうと、その行動を追認してしまうことになる。患者の要求をすべて受け入れるのではなく、時には「あなたの思い通りにはならない」という姿勢を見せることが、患者自身に人間関係のあり方を考えさせるきっかけになるかもしれないと思う。
Q7:(刑務所内での)受動的な環境から、(出所後に)自らの選択を求められる環境への変化に対応する対策について教えてください。
瀧井先生:
医療刑務所は、保護的・受動的な環境ではなく、むしろ患者が自らの力で生きていけるよう促す方向性で治療を行っている。また、患者の家族を施設に呼び、患者の病状や現状を理解してもらうことで、出所後の支えとなるよう促すことも重要なアプローチの一つである。
ここまでで講演会当日の内容を報告しました。続く第三部では企画者による感想を報告します。(報告:山田理絵)