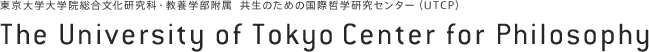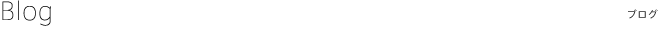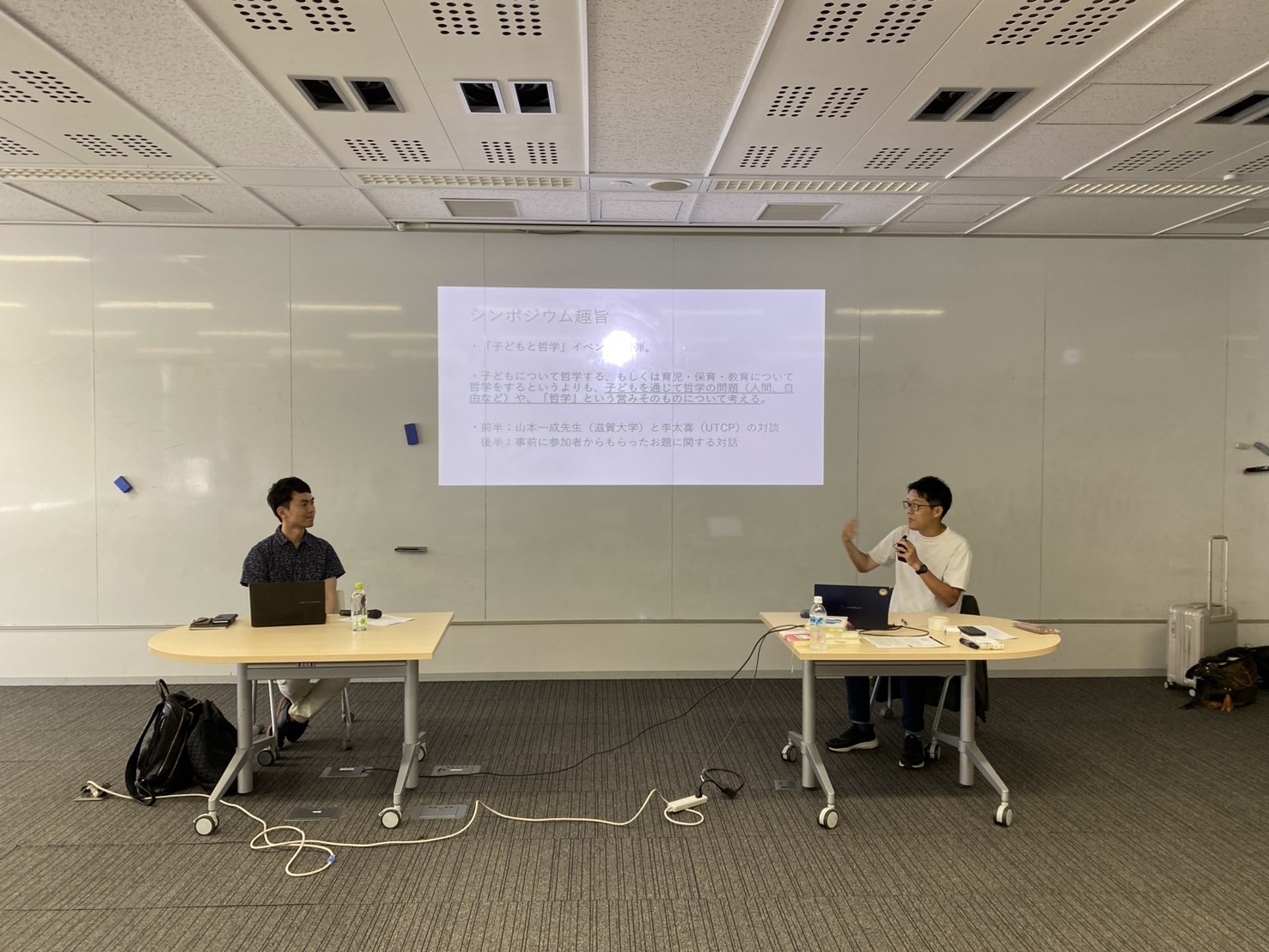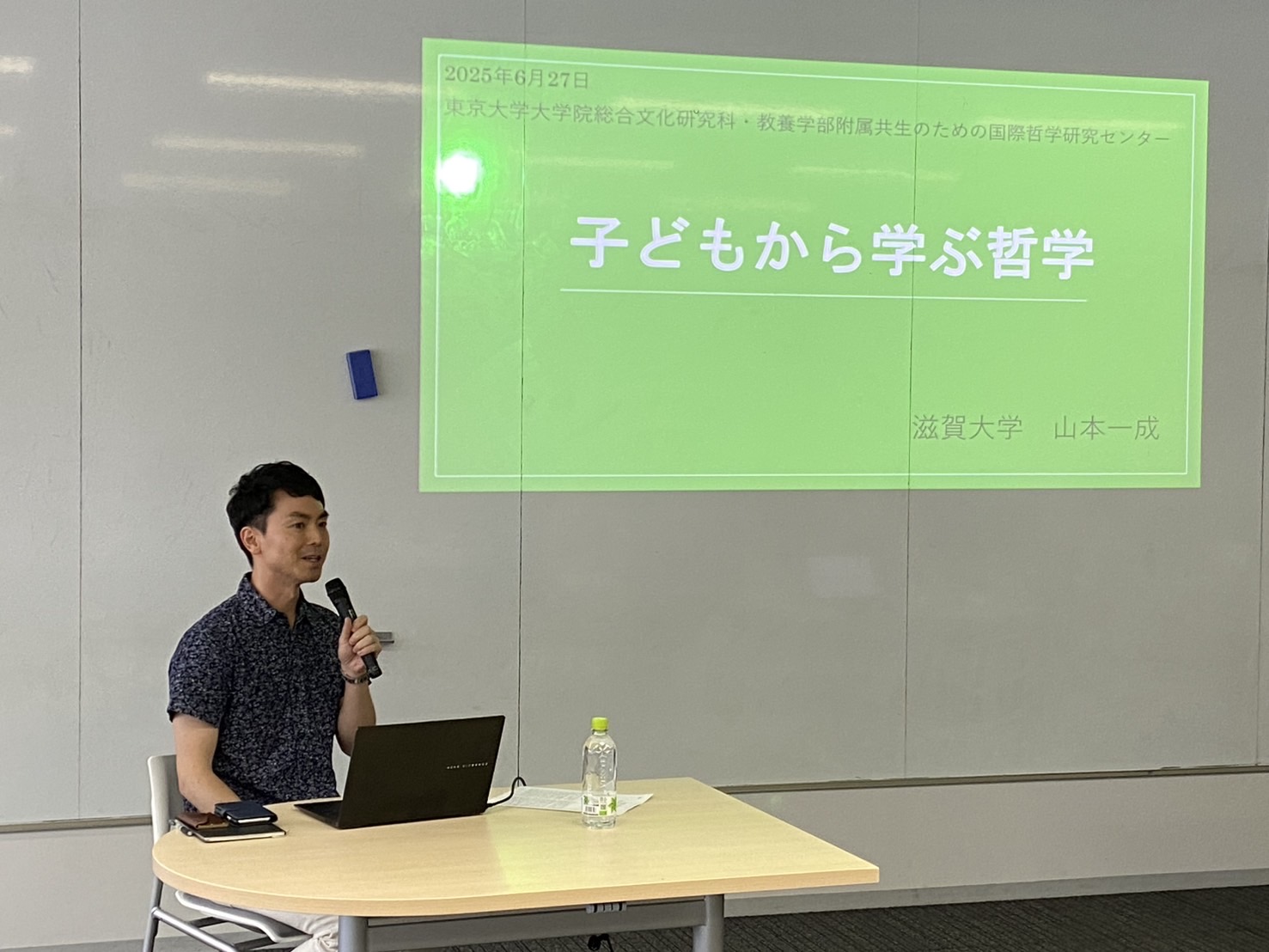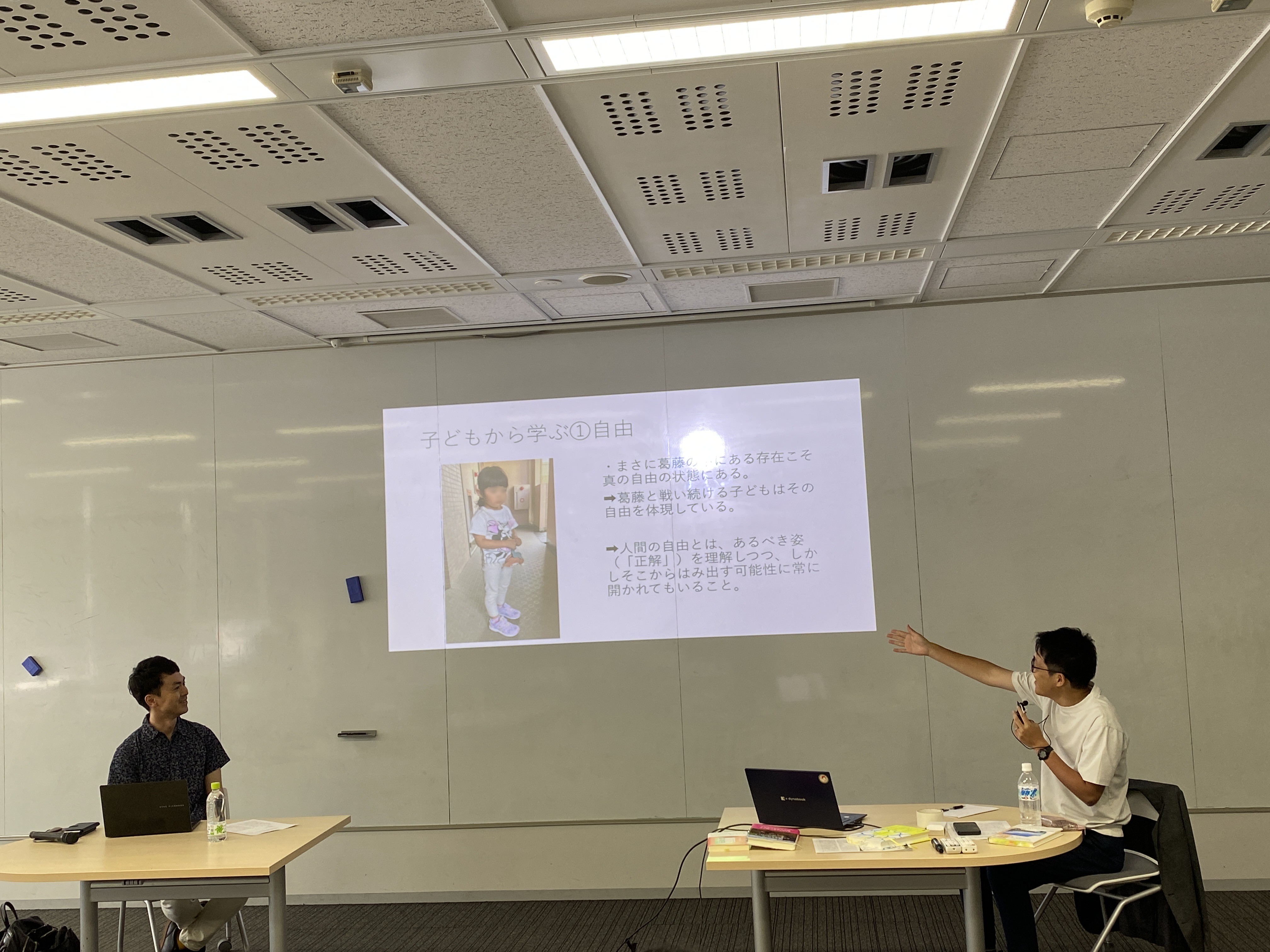【報告】ワークショップ「子どもから学ぶ哲学」
2025年6月28日、ワークショップ「子どもから学ぶ哲学」が駒場キャンパスにて開催された。3月に行ったワークショップ「子供を育てるってなんだろう」につづく、「子どもと哲学」をテーマにしたイベントの第二弾となる。
前回のイベントでは久保健太さんとともに、「子どもや育児について哲学的に考える」ことを試みた。一方、第2弾となる今回は「子どもや育児から哲学を学ぶ」ことをテーマとした。つまり、必ずしも子どもそのものを対象とするわけではない専門的な研究に関して、子ども達とのかかわりがどんなことを教えてくれるのかを考えることにした。
登壇者は、滋賀大学の山本一成先生で決まった(以下、親しみを込めて山本先生のことを「一成さん」と記す)。一成さんの著書『生きているものどうしの想像力:アニミズムがひらく生命の保育・教育』は、一成さんと娘さんとの印象的なエピソードから始まる。ドリップコーヒーを淹れている最中、渦を巻くお湯の中でプクプク浮かぶコーヒー豆をみて、娘さんが「動いてるね、人間だねぇ」と呟く。一成さんの本は、この言葉を出発点にして、サステナビリティ教育やアニミズム、生態想像力などの話題をつなげながら、「人間」ないし「人間と自然の境」を捉え直していく。
こんな著書を書かれた一成さんが、今回のイベントにうってつけなのはよくわかるだろう。一方で一成さんからは、私(李)が育児を通じて、私の研究する「自由意志」についてどのようなことを考えるかを話して欲しい、というリクエストを受けた。こうして、育児にまつわるエピソードを取り上げながら、一成さんと私で対談をするという企画の骨子ができた。
それを受け、イベントの一つの趣向として、参加される聴衆の方々にもエピソードを寄せていただき、それについてぶっつけ本番でみんなで考えるという試みをしてみることにした。果たしてエピソードが集まるか不安はあったが、それは杞憂であったことが後に分かる。
当日、会場に集まったのは10人程の聴衆だった。学生の方や、学童で勤められている方、お子様連れのお母さんも数名来てくれた。
前半は一成さんと私の対談という形で、交互にそれぞれが持ちよったエピソードを披露しつつ、それと自分の研究の繋がりについて話した。
一成さんはまず、自身の教育学という専門が、「人間とは何か」という問いと根底でつながるものだと述べられた。そして著書にもあったコーヒー豆の話をし、それがアニミズムの感覚につながること、そしてこの子どものアニミズムを真剣に受け止めることで、新しい人間の見方に開かれる可能性があると話された。
また、他にも子どもと凧揚げをした際に、子どもが「凧が飛びたがっている」と述べたエピソードを取り上げて、凧に命を見出し、凧をケアしようとするこの子供の想像力は、実は自然に対して人格を認めようとする近年の社会的・法的な話題と通じ合うことを指摘された。
私からは、いやいや期の子どもが全くお風呂に入りたがらず、一方で親は何とか子供を風呂に引きずり込もうとする、という「あるある」の話を提供し、そこから自分の自由意志研究の一つアイデアを取り出せるという話をした。
自由という観点から見た時、この綱引きの状況では、子どもも大人に、ともに自由であると言うことはできない。なぜなら「様々な選択の可能性がある」こととして自由を考えるならば、子どもも大人も一つの選択肢に固執してしまっているからである。このように、自分のやるべきことや、やりたいことが固定化してしまうことが自由の否定につながるのならば、むしろ何をすべきか、答えを見つけようとしたり、作り出そうと葛藤する姿が、真の自由を体現したものだと言えることになる。
ならば、一つの選択肢を正解と見なすことが習慣化し、内面化してしまっている大人ではなく、自分のやりたいことと、周りに求められていることの間で悩み、答えを出そうとする子供の姿の方がよほど自由だとは言えないか。こうした自由の理解は、しかし哲学の側でも実は見過ごされてきたものなのである。
イベントの後半は、参加者の方が寄せてくれたエピソードを取り上げ、そこにいた人達全員でそれについて深めう時間となった。一時間以上、たっぷりとそれぞれのエピソードを取り上げることができた。
印象的なエピソードを幾つか紹介したい。一つは、オセロ風のゲームで、白黒の数で負けた子が、「盤面を裏から見たら私の勝ちだね!」と勝ち負けを逆転させるというもの。勝ち負けさえ逆転させてしまう子供の発想力がおもしろい、という話になった。そんな話に喚起されて、子どものおむつが取れなくて保育園でプールに入れず水遊びをしており、それに対して親が焦ったり、かわいそうだと子供の気持ちを先取りしていたら、当の子ども自身は「特別な遊びができている」とポジティブにその事態を捉えているという話が出た。子供たちの考え方が、親の考えを超えた、囚われない自由さを備えることが改めて参加者で共有されたと思う。
もう一つは、子どもから「人間には心があるよね。じゃあ建物は?虫は?お花は?」と尋ねられ、心は命のことか?それとも感情のことか?心はどこにあるのか?と戸惑ったというエピソード。他にも、石も生きていると考える子供の話も飛び出した。こうした子供の疑問は、まさに一成さんが研究されているアニミズムや想像力へと直接つながるものである。命とは何か、心とは何か、子どもそれぞれに、それぞれの考え方があることが明らかになり、そこから話は、石にも心を認める文化が存在することや、哲学における心の理論を拡張する可能性などへとひろがった。
最後に、子どもが哲学について多くを教えてくれることから、翻って哲学とはどんな営みだと言えるのかについて、私なりの考えを述べた。
哲学が得意とするのは、普遍的な条件や基準、根拠などについて考えることで、世界の物事を統一的に秩序付ける論理を作り出すことである。その意味で、哲学は、世界の複雑さを「単純化」する運動だと言える。
そこから見た時、子供は、この単純化に抗う存在として位置づけられないか。画一的な整理からはみ出し、複雑さを取り戻す力として。ただし一方で、彼らは彼らなりの物事の整理もつようとする。ここには、複雑さのなかで新しい秩序を生み出そうとする創造の運動もまたある。
実はこのような複雑性への抵抗は、哲学内部にも存在する(脱構築、家族的類似性、etc…)。であれば哲学とは、正しくは「単純化と複雑化の往還」とみなすべきだろう。この点を踏まえれば、子どもたちはまさに哲学の実践者だと言えるのではないか。
今回、私は司会だけでなく登壇者でもあったため、気負うところがあったのも事実である。しかしこのイベントは、単純に子どもとのエピソードを思い出す良いきっかけとなったし、同時に子供と哲学の関係を考えたいという私の動機の整理にもつながった。それは、「子供と大人が共有できる楽しさは、まだまだ語られ足りていない」というものである。
このイベントが、子どもとともにいることが持つ新たな楽しみに、少しでも光を投げかけるものとなったなら幸いである。(報告:李太喜)