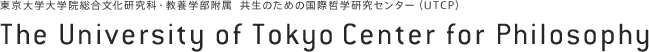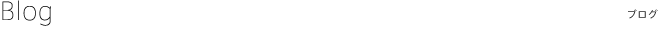【報告】ワークショップ「哲学的懐疑論と現代社会の懐疑論」
2025年3月15日、駒場キャンパスでは「哲学的懐疑論と社会的懐疑論」と題したワークショップが開催された。前半は名古屋学院大学の横路佳幸先生による講演、後半には参加者全員を巻き込んだ哲学対話を実施した。
題名から分かるように、このイベントは地球温暖化やワクチン、歴史上の出来事(例:南京大虐殺)に関する懐疑論など、現在のアクチュアルな話題である懐疑論と、哲学が伝統的に問うてきた哲学的懐疑論の接続を試みたものである。
実はこの企画は、私自身の個人的な経験に端を発する。哲学の入門的な授業で認識論における外界の懐疑(目の前の机など、この世に存在するとされているものは本当に存在すると言えるのか)について取り上げた際、「科学に関する懐疑論とそれはどう違うのか。科学に対する懐疑論も正しいことになるのか。」というコメントをもらうことがあった。
その場ではなんとなくお茶を濁して切り抜けたが、たしかに現代社会における懐疑論は、その根拠の正当性を疑うという点で哲学的懐疑論との共通点を持っており、また、科学的常識さえ疑うラディカルさに近さがあると言える気もする。こんなモヤモヤが、私の頭の中に残っていたのである。
横路先生は私の大学院生時代の友人で(なので、以下では親しみを込めて「横路さん」と書く)、最近は疎遠だったが、懐疑論に関する翻訳書『哲学がわかる 懐疑論──パラドクスから生き方へ』(プリチャード著、岩波書店)を出版されていることは知っていた。この本は、特に近年のSNSなどを通じた様々な懐疑論や陰謀論の拡大と、哲学的な懐疑論の関係を論じる、目下私の興味に適った本であったため、是非そのような点に関して訳者の考えを聞かせてほしいとお願いしたのである。
講演が決まり、哲学的に固い内容も含むのでどれくらいの人が来るだろうかと不安もあったが、実際は20名以上の方が参加する盛況なイベントとなった(嬉しいことに、そのうちの多くが高校生を含む若い学生であった。UTCPのイベントになかなか大学生は参加してくれないのである)。
前半に行われた横路さんの講演は、その多くの人にとって大変刺激的なものになっただろう。そしておそらく、講演の内容に一番驚いたは外ならぬ私である。
横路さんはまず、哲学的/社会的、双方の懐疑論の例を挙げつつ、懐疑が可謬性(間違っているかもしれない可能性があること)に由来することを指摘したうえで、講演の目標を「ほとんどありそうにない可能性から懐疑論を展開する哲学者から見て、社会的懐疑論者をバカにすることはできるのか」について結論を出すことに置く、とした。
さて懐疑論は、(他にも理由があるが)知識が可謬的であることを問題視し、可謬的な知識は正当な根拠に支えられているとは言えないと主張する。この点で哲学的懐疑論も、社会的懐疑論も変わるところはない。しかし現代の哲学では、可謬的であったとしてもそれを知識と呼んでよいとする「(知識の)可謬主義」という立場が採られるようになった。この立場に立てば、疑う余地がある(可謬的である)としても、疑うべきではないもの(誤りの可能性の低いもの)と、疑うべきもの(誤りの可能性の高いもの)を区別することができる。つまり哲学の側には、懐疑論からの批判に耐えうる理論があることが確認される。
問題(?)はここからである。以上から、哲学的に見れば社会的懐疑論は否定される、という結論を導くのがよくある筋書きだろう(実際、翻訳書の著者プリチャードはそういった議論をしている)。しかしここから横路さんは、仮に可謬主義の立場を採ったとしても、人間の認識能力の限界からして、私たちが現在持っていると考える知識の多くは疑うべきもの、つまり誤りの可能性の高いものであると主張し、懐疑論の第2段階へと進むのである。
横路さんがそう主張する理由は、私たちの判断や推論に無意識に入り込むバイアスにある。私たちが知識を作り上げる過程はバイアスにまみれており、それは陰謀論者も、陰謀論を否定する専門家の側も変わらないことは、多くの心理学の実験が実証するところである。この点から見れば、私たちは社会的懐疑論者をバカにすることなどできないことになる(!)。
横路さんはもちろん慎重に、この懐疑論が否定論を意味しないことを強調する。懐疑論から導かれるのは、「Pが正しいともPが間違っているとも信じない」という態度であり、「Pが間違っていると信じる」否定論ではないからである。しかし少なくとも、「Pが正しい」とも信じられない以上、私たちは(少なくとも両論のある)多くの知識について判断の保留を取るべきだということになる。
ここから、私たちが科学否定論や陰謀論と向き合う際の正しい態度が論じられる。詳細は省くが、最終的に奨励されるのは、不合理な相手とは近づかないという選択肢である。そして自らは、(少なくとも両論がある時には)肯定論にも否定論にも偏らず、慎重に探索をし続ける由緒正しきピュロン派の姿勢を持ち続けるべきである。こう横路さんは結論付ける。
以上の横路さんの話は、予定調和的に社会的懐疑論を切り捨てるものではなく、むしろ様々な領域における研究成果を活用し、私たちが持つ知識のあり方に疑いを投げかける、極めて挑戦的なものである。おそらく多くの「良識派」や「哲学者」は、この結論に賛同しないだろう。しかし私には、横路さんのこうした議論こそ、勇気ある、誠実な哲学の実践だと感じられた。
イベントの後半では、哲学対話が行われた。横路さんの刺激的な話は「陰謀論にはまる人たちは、単に懐疑するにとどまらず、なぜ否定したがるのか」や、「なぜ人は何かを正しいと信じたがるのか」など、多くの問いを喚起した。その中で哲学対話のテーマに選ばれたのは、「判断保留しているときにどうやって意志決定をすればいいのか」という、まさに講演内容の問題関心を引き継ぐ問いであった。
私がファシリテーターを務めたグループには横路さんも交じり、活発に意見を交換した。そんななかで一人の高校生が、「そもそも私は物事を決められなくて、優柔不断で。」という話をしてくれた。それを聞いて横路さんが、「ああ、私が講演で言いたかった態度は「優柔不断」という言葉がぴったり来ますね」と、彼女の言葉を受け止めた。哲学対話の営みと、哲学研究の営みの交差するところを見つけて嬉しく感じた。
このイベントは私(李)がUTCPに来て企画した二つ目のイベントということもあり、当日の運営が円滑に進むかなど、悩ましいことだらけであった。しかし、当日の進行は、横路先生の喋りの達者さや、参加してくれた方の前のめりな姿勢のおかげでつつがなく進められたと思う。ここに、関わった全ての方への感謝を申し上げます。(報告:李太喜)