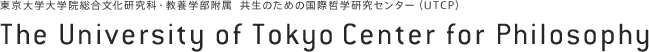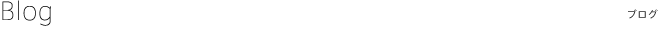【報告】 ハビエル・ペレス・ハラ氏講演会「Beyond Nature and Nurture: Perspectives on Human Multidimensionality」
2025年6月13日に、ハビエル・ペレス・ハラ Javier Pérez-Jara氏をお招きし、「Beyond Nature and Nurture: Perspectives on Human Multidimensionality」というタイトルで講演をしていただいた。
ハラ氏は、2025年6月にイニゴ・オンガイÍñigo Ongay氏と編集した著書 Beyond Nature and Nurture: Perspectives on Human Multidimensionality を刊行した。この著書は、いわゆる「氏か育ちか(nature vs. nurture)」に関する論文を集めたものだ。氏か育ちかという単純な二項対立を乗り越え、多次元的かつ学際的なアプローチがいかに人間行動の真の理解に不可欠であるかを詳細に論じるものである。この編著には、本センターのセンター長である梶谷真司先生が “Naturalism of Mother’s Milk and Its Historical Change in Japan: Modernization of Nature as Normative Concept” という論文を寄稿している。
この報告では以下に、ハラ氏の講演内容を紹介する。

---------
人間行動の理解は、古くから人類が問い続けてきた根源的なテーマである。特に、「氏か育ちか(nature vs. nurture)」という二項対立は、長きにわたりこの議論の中心に位置してきた。しかし、この伝統的な枠組みは、人間の複雑で多面的な存在を捉えるにはあまりにも単純であるという認識が、近年、学術界で急速に広まっている。『自然と育成を超えて:人間の多次元性に関する視点』は、心理学、生物学、哲学、社会学といった異なる学問分野の学者たちが協力し、それぞれの専門知識を結集することで、学術的な孤立を打破しようとした。すなわち、統合的な視点を提供し、人間の行動が遺伝的要因、環境的要因、そしてその相互作用によっていかに複雑に形成されるかを明らかにしている。
「人間とは何か?」という問いは、古代ギリシャのスフィンクスの謎にも象徴されるように、古くから哲学的な探求の中心に据えられてきた。しかし、物理学や化学とは異なり、人間という存在については、文化や歴史を通じて普遍的なコンセンサスが存在しない。イスラム教、共産主義、キリスト教、古代エジプト、道教、神道、儒教など、それぞれの文化や思想体系が異なる人間観を提示している。この多様性は、人間が生物学的、物理的、歴史的、宗教的、社会学的側面を併せ持つ、本質的に複雑で多次元的、かつ動的な存在であることに起因する。
このような複雑性ゆえに、ある特定の分野の専門家が、自身の専門分野からの視点を過度に強調し、他の側面を軽視したり無視したりする傾向が見られる。例えば、生物学者が人間の行動を遺伝子や神経伝達物質だけで説明しようと試み、社会学者が社会構造や文化規範のみに焦点を当てる、といったことが起こりうる。このような還元主義的なアプローチは、部分的には正確な洞察を提供するかもしれないが、全体像を見誤らせ、結果として対立を生み出す原因となる。
この還元主義的な見方は、単に学術的な論争にとどまらない。政治、法律、倫理といった社会の根幹をなすシステムは、しばしば人間に対する特定の、時には限定的な定義やアプローチに基づいている。人間の本質に関する不完全な理解は、社会の規範、政策、そして個人の生活に直接的かつ強力な影響を及ぼす可能性がある。したがって、人間存在の多次元性を深く認識し、その複雑性を受け入れることは、学術的な課題であるだけでなく、より公正で効果的な社会システムを構築するための喫緊の課題だと言えるのだ。
複雑な現代社会の問題に対処するために、学際的アプローチの必要性が広く認識されている。しかし、現実のアカデミアでは、学際性が口では奨励される一方で、残念ながら制度的な壁があることも事実だ。多くの大学や研究機関では、特定の専門分野に特化した業績が重視されがちで、複数の分野にまたがる研究は評価されにくい傾向がある。このため、学際的な共同作業へのインセンティブが阻害されているのだ。
この学際性のパラドックスの危険性を、仏教の伝統に由来する「盲人と象」の寓話が鮮やかに示している。この寓話では、目の見えない男たちが象の異なる部分に触れ、それぞれ「象は蛇のようだ」「柱のようだ」「扇のようだ」「壁のようだ」と主張する。彼ら一人ひとりの記述は、彼らが触れた部分においては正確であるが、部分的な真実を「象全体」に普遍化しようとするとき、全体像を見誤るというものだ。この寓話は、生物学、歴史学、社会学といった各学問分野が、人間行動や社会現象の特定の側面について深い洞察を提供する一方で、いずれか一つの分野の視点のみを絶対視し、それを複雑な現象全体に普遍的に適用しようとすると、全体像を見誤る危険性があることを教えてくれる。

「氏か育ちか」の議論自体も、古代ギリシャや中国に遡る古い歴史を持つ。古代ギリシャでは「ピュシス(自然)」と「ノモス(社会的に構築されたもの)」について議論され、また中国では、孟子と荀子が人間の本性を論じた。これらの古代の議論からは、人間が、その存在の基盤において、自然と文化、生得的なものと学習されたものの間の複雑な相互作用の中に位置づけられてきたことがわかる。この、長い歴史を持つ問いに対して、現代の科学は新たな光を当てる。
現代科学は、「氏か育ちか」という単純な対立を、より洗練された相互作用のモデルへと転換させるための具体的なメカニズムを明らかにする。例えば、脳の可塑性についての研究がある。このテーマの研究では、人間の脳は動物界で最も柔軟性が高く、出生後も社会的な環境の中で重要な発達を続けることが指摘されている。経験や学習によって脳は変化し続け、これが文化的な適応の基盤となるのだ。
また、エピジェネティクスは、遺伝子が固定された決定要因ではなく、環境要因や個人の生い立ちによってその発現(オン・オフ)が動的に制御されることを示している。例えば、遺伝的素因があっても、不利な環境がなければ発現しない場合がある。さらに、ニッチ構築という概念では、生物が環境に適応するだけでなく、積極的に自らの環境を改変する。この変容された環境が、今度は人間の行動や進化にフィードバックループとして作用し、文化、人工物、自然が複雑に絡み合う。また、ボールドウィン効果、妊娠中の母体ホルモンレベル、乳児の腸内フローラに関する議論も、「氏か育ちか」についての議論を新たなフェーズに進める研究テーマ、概念と言える。これらのメカニズムは、人間行動が遺伝子、脳、生理機能が社会文化的な環境と動的に相互作用する中で形成される、多次元的な現象であることを示しているのである。
現代の文化社会学は、文化が相対的に独立した因果的力を持つことを強調する。文化は経済や生物学の単なる派生物ではなく、下方因果関係を通じて社会構造、環境、さらには人間の生物学そのものに影響を与えることができる。例えば、人間の文化的慣行(産業生産、消費パターン)は、大気や海洋の化学組成を変化させ、地球規模のバイオームを変容させている。気候変動はその典型例であり、文化が物理的、化学的、生物学的な影響を引き起こす複雑な因果関係を示している。
さらに、文化は人間の生物学そのものをも改変する力を持つ。殺人の発生率、自殺パターン、男性の平均余命といった行動特性は、生物学的な違いだけでなく、文化的な規範や価値観に深く根ざしている場合が多くある。これは、生物学的還元主義が経験的に誤りであることを示唆している。垂直的な因果関係では、文化的な要因が社会構造を変化させ、それが生物学的特徴を再形成する。文化は根本的な生物学的限界を覆せはしないが、かつて不変と考えられていた人間の特徴に深く影響を与えるものとなるのだ。

あらゆる社会現象は、本質的に多次元的である。例えばうつ病は、生化学的なアンバランスを伴う一方で、環境毒素、生物学的な問題、社会的な要因など、多様な原因によって引き起こされる。結果は似ていても、根底にある原因は多様であり、しばしば収束し、一部の要因が他の要因よりも大きな重みを持つ。重要なリスクは、複雑な現象に対して単一原因または一次元的な説明を採用する誘惑である。これは、特に政治家にとって魅力的であるが、経験的に誤りである。暴力、うつ病、自殺といった問題は、物理的、化学的、環境的、社会的、文化的といった多岐にわたる要因が複雑に絡み合い、それぞれの要因が異なる重みで作用することで発生する。問題の真の根源を見誤らせ、効果のない対策を導き出すことにつながるため、複合的な視点が必要である。
-----------------
このようにハラ氏は、ご講演を通じて、人間行動と社会現象の理解において、従来の単純な「氏か育ちか」という二項対立がいかに不十分であるかを明らかにし、多次元的で学際的なアプローチの重要性を強調した。
講演後の質疑応答では、学術界における学際的研究のあり方が主要な議論点となった。学際的アプローチは必要不可欠であるものの、現在の学術制度が専門分野ごとの業績を重視するため、キャリア形成において不利になるという現状が指摘されたのである。専門家が自己の領域に閉じこもりがちであるという課題に対し、異なる分野の知見を積極的に取り入れ、深い専門性と幅広い理解を両立させるための協働の重要性が強調された。
また、人間行動を単純な生物学的決定論や文化単一論に還元するのではなく、脳の可塑性やエピジェネティクスといった科学的メカニズム、さらには文化の因果的力や創発といった概念を通じ、多層的なアプローチで理解することの重要性が説かれた。自殺やうつ病といった複雑な社会現象は、環境、食生活、文化、社会といった複数の要因が非対称かつ動的に影響し合って生じるため、単一の原因に還元せず、多次元的に分析し、主要な変数を特定する必要があるという認識が示された。
最後に、専門家が専門用語を避け、複雑な概念を一般にも分かりやすく伝える能力を向上させることの重要性が議論された。これにより、学術的な洞察と公共の議論との間のギャップを埋め、氏か育ちかの議論における偏見を克服し、文化の相対的自律性を認識した上で社会問題の改善へと繋がれば良いだろう。
講演や質疑応答を通じて、ハラ氏が特に強調したポイントは、複雑で動的かつ多次元的な現実を、単一の原因や単純な二項対立に還元すべきではないということと、認識論的に複雑性を理解するためには、多角的な視点と学際的なアプローチが不可欠であり、異なる学問分野間の対話を促進することが極めて重要であるということだ。一見すると、純粋に科学的な事柄に見えるようなものでも、その根源には文化的な規範、経済的慣行、法的枠組みが絡んでおり、すべての知識領域の洞察を統合することが求められるということである。またそのために、様々な領域の専門家の「真の意味での」対話が求められることが改めて確認された。
ハラ氏が編集した書籍 Beyond Nature and Nurture:Perspectives on Human Multidimensionality は、まさにこの多次元的アプローチの具体的な実践例であり、その成果は、現代社会が直面する多岐にわたる課題への対処において、新たな洞察と解決策を提供してくれるだろう。

(文責:山田理絵)