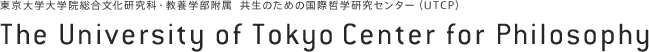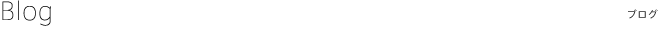【報告】2024年度キックオフシンポジウム「共生の揺らぎ Polyphony of Lives」(第1部)
2024年度キックオフシンポジウムの前半では、一般社団法人シブヤフォントの古戸勉さんにご登壇いただいた。古戸さんは、ご自身のこれまでの経験を振り返りながら、障害を持つ人に対する偏った見方が社会に浸透している背景、障害を持つ人と健常な人が「共に生きられない」「共に生きにくい」社会になっている背景などについてお話ししていただいた。
はじめに古戸さんが「障害にはどんなものがあるか?」と会場の参加者に問いかけると、会場から「身体障害」、「精神障害」、「自閉症」、「発達障害」、「精神障害」…など、いくつかのレスポンスがあった。このようにさまざまな「障害」の名称があるが、障害を持たない人は、これらの「障害」の名称や特徴として挙げられる内容を知って、<障害についての知識を持っている>という認識のもとで語ることがある。また、テレビやネットで、障害や障害をもった人についてのニュースが流れる時、そのコメントに「障害を持っているのにすごい」とか「やはり障害があったのだな」というものがあるのを目にすることがある。しかし、障害をもった人の個別の具体的なストリーや、日常生活についてあなたはどれくらい知っていますかと、冒頭で古戸さんは投げかけたのだった。
たとえば「自閉症」や「発達障害」などの言葉は医学用語である。われわれの多くは「自閉症は〜」、「発達障害の人は〜」などと語ったり、そのようにメディアや人々が語るのを日常的に見聞きしたりするが、このようなカテゴリーのみから実際に障害を持った人々のことを捉えるのは大きな問題がある。もちろん、「自閉症」や「発達障害」に固有の障害特性はあるかもしれないが、あくまでそれは全体的な傾向であり、そのように診断された人は一人として同じ人はおらず、育ち方、現在の環境、体型や好みがひとりひとり異なった個人なのである。
古戸さんは、これまで障害を持った人に直接関わる仕事をする中で、実際にそのような仕事をしている人と、そうでない人との間に「障害者」に関する知識や情報量の差が圧倒的にあると感じてきたという。
ではなぜこのような差が生まれてしまうのか?古戸さんは、日本社会の仕組みとして「障害者のことが分からなくて当然の社会」になっていると指摘した。その上で、マスメディアの報道と教育について次のように指摘した。
まず、日本の教育システムの中で、特に高校への進学を境目に障害を持つ人と持たない人が「分けられる」ようになっていくというというのである。
例えば知的障害を持つ人のほぼ100%、それ以外の障害を持つ人の多くが特別支援学校の高等部に進学することとなり(ちなみに特別支援学校の高等部は高卒にはならない)、いわゆる一般の高校に進学する生徒たちと教育上分離されることとなるのだ。障害を持つ人からすれば、中学校まで障害を持たない人と共に学校生活を送ってきたとしても、高校進学後はさまざまな障害を持った人とのみ関わるようになる。そして、特別支援学校卒業後に、障害者支援事業所で仕事をしたり、グループホームに生活の基盤を置いたりすれば、そこで関わる人たちの多くが障害を持つ人という環境になる。
それに対して障害を持たず、普通高校などに進学した人は、学校生活では障害を持つ人と接点を持つことはほぼなくなる。ボランティアや実習などで、障害者施設などを訪問する場合もあるだろうが、それはほんのわずかな時間・期間に過ぎない。このように教育システムの中でいつの間にか障害を持つ人と持たない人が分離され、お互いに日常的に関わることが極めて少なくなっていく、と古戸さんは強調した。
また古戸さんは、障害を持たない人や、日常的に障害を持つ人と関わらない人が偏った「障害者理解」に陥りがちなのは、マスメディアの影響もあると指摘した。古戸さんによれば、ニュースで障害者が取り上げられるときそのストリーは美談か悲劇のどちらかの場合が多いという。例えば美談であれば「〜〜障害を持った人が賞を取りました!」とか「いま障害者施設の〜〜という取り組みが注目されています」などと報道される。悲劇の場合の典型的なストーリーとしては、高齢の親と障害を持った子が長い間二人で生活していてそのうちに、親の健康問題などで生活が立ち行かなくなる、といったものがあるだろう。
しかし、美談として語られる個人の生活や団体の活動、あるいは悲劇のストーリーも、障害を持つ人の生活のほんの一部分を切り取ったものに過ぎない。それ以前には、ひとりひとりの淡々とした日々の生活があるが、マスメディアではそうした部分はほとんどフォーカスされていない、と古戸さんは語った。
「インクルーシブ」という言葉がしばしば語られるようになった。しかし、古戸さんによれば、障害を持つ人とそうでない人が、教育のシステムやその後に続く就労のシステムの過程で、制度的に「分けられて」いる日本社会では、障害を持つ人が障害者支援事業所に閉じこもらざるを得ない現実が生み出されているという。(報告:山田理絵)