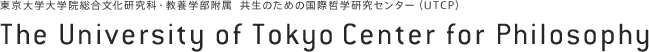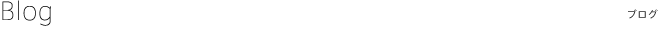【報告】筒井史緒 standART byond①~〈「幸福知」のためアート・ワークショップ・シリーズ〉は、なんのためにスタートしたのか。
2024年5月14日土曜日、新緑の樹々がきらきらと日差しと戯れ、光る風がときおり頬を撫でては吹きすぎてゆく初夏の午後。駒場キャンパスの一角で、UTCPの新しいワークショップシリーズ、standART beyondの第一回が開催された。
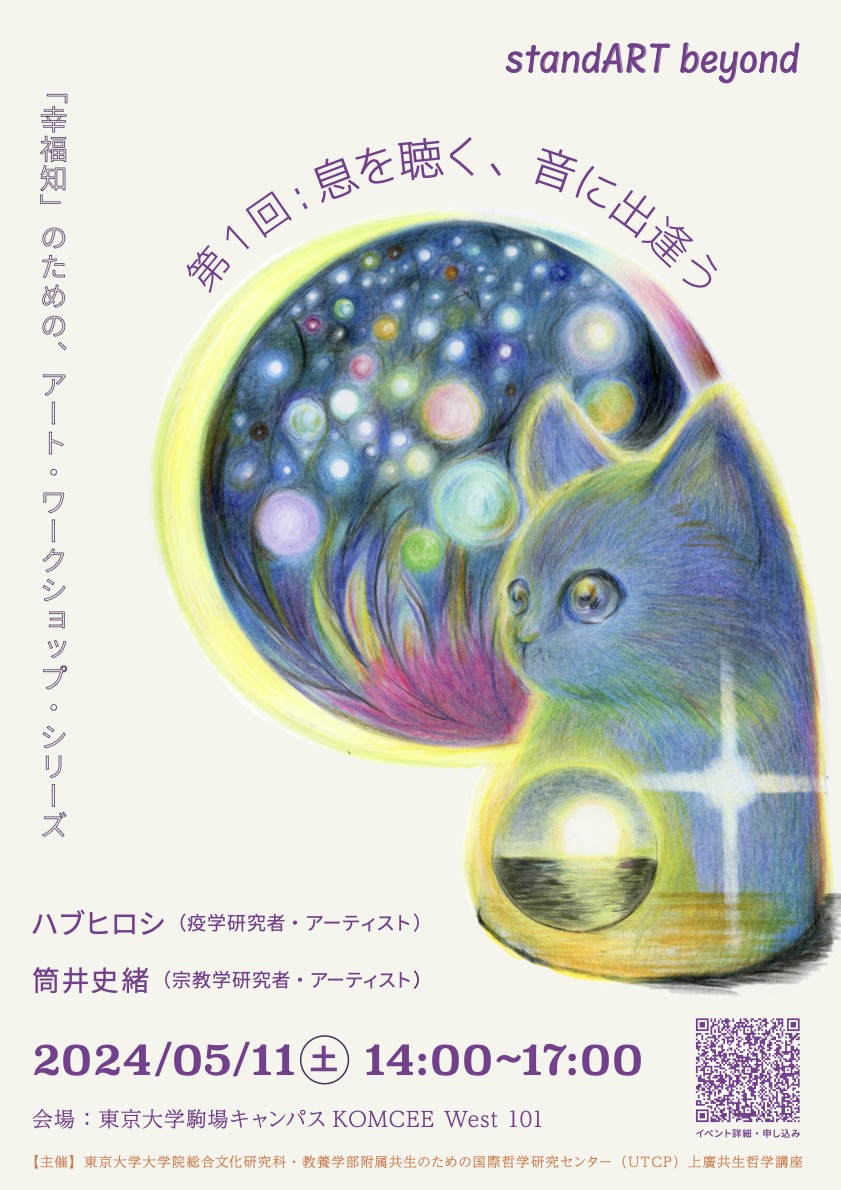
Vol.1のポスター。原画イラストを担当した。
このシリーズには、〈「幸福知」のためのアート・ワークショップ・シリーズ〉というサブタイトルがついている。Vol.1の内容報告は次回に譲って、この記事ではまず、このシリーズ全体の意図を説明しておきたいと思う。
シリーズ立ち上げの大前提として、いま「知の枠組み」を変革してゆく必要がある、という問題意識がある。
「知」というのは、そもそも人類が、世界や宇宙を理解し、人間存在を理解し、どうしたらより危機を避けて快適に(つまり幸福に)生きることができるか、を追求するために発達させてきたものだが、それがいま自家中毒を起こしつつあるのではないかと思う。
知の進展はある意味で、半分は成功してきた。いまやサイエンスは宇宙の起源や終末を語り、人間の遺伝子や脳を解析し、人間の知能を近い将来超えるのではというほどのデータ処理能力をもったAIすら生み出した。また、あくなき快適さの追求によって、すくなくともグローバル・ノースにおいては、今生きるために必要なモノはそれなりに充足している。
そういう意味では、知の営みはひとまずの成功を見てはいる。
しかし「知の追求」が、逆に人間から生き生きした喜びや生命力を奪ってきたという面も、看過できないものになっている。それはとりわけ、現代日本において深刻であるように見える。
たとえば近年顕著な、「他者に勝つ」「経済的利益を増大する」ことを至上とする社会的な価値観のなかで、知はそのための道具として使われるようになった。たったひとつの正解、たったひとつの目的のために、子どもたちは「なぜそうなのか」を問う隙も権利も与えられることなく、ただあらかじめ社会によって設定された基準をどれくらいのレベルでクリアできるかだけを「優秀」の基準として訓練され、大人たちはいかに効率よく結果を出すかによって日々おのれの存在価値を判定される。
そこには、「かけがえのないわたし」もいないし、「愛しあい尊敬しあいともにはぐくみあう他者」もいない(現在のスタンダードな価値観からゆくと、他者は自分に優越感を与えるか屈辱感を与えるかの二択だ)。あたたかな気持ちで安心して暮らせる、「それぞれの存在が生き生きと共生しながら幸せに生きる社会」もない。
あたたかみ、生きている手触り、やさしい世界。生きていて本当に良かったと感じられること。そうした、データにはのりにくいが、人間にとって必要不可欠なことが欠けていることが、現代の日本の閉塞感の一因であると思う。
こうした閉塞感を打破するひとつの試みとして、このワークショップ・シリーズは構想されている。
といっても、このシリーズ自体は、あらかじめこちらが準備した「幸福のための新しい知のスタンダード(standard)」を提供する場所ではない。そうではなく、わたしたちも、これまでの知の枠組みの内側にいることを意識しながら、それを超える(beyond)新たな、そしてはおそらくはとてつもなく古い、ほんとうによく生きるための知のスタンダードを、さまざまな体験を参加者とともに重ねながら、多面的な彫像のように少しずつ彫り出していこう。そんな、こころみのプロセスとしての場所である。
そのこころみのためのツールとして、アート(ART)を選んだ。
アートといっても、わたしが意図しているのは、ただ絵を描けばよいとか歌を歌えばよいとかいう、フォーマットとしてのアートではない。
自分の存在のコアにじかに触れながら、いまここ、この瞬間に、世界と会話し、自分にしか感知できない世界のかたちを、全身全霊で生き、それを自分の存在全体を通して表現する、そうした営みはすべてアートである。
息をしているだけだろうが、立っているだけであろうが、笑っているだけであろうが、遊んでいるだけであろうが。
逆に言えば、その切実さ、正直さ、誠実さ、解放のない営みは、フォーマット的にはアートといわれるものであっても、わたし自身はアートとは呼ばない。
つまり、プロセスとしてのアート、ありかたとしてのアートを、わたしはアートと呼んでいる。それは言葉を変えれば、自分自身でいること=アートである、ということでもある。
なぜ「ありかたとしてのアート」を、ツールとして選んだのか。それは、「知」がいつのまにか、「論理知」のみを指すようになったために、知はそのほんとうの広大さを失ってしまった、というのが、わたしの基本的な発想の底にあるからだ。
「論理知」は強力だが、それは言葉にならない、生命を浸す質のような、混沌とした豊穣なものをとらえることはできない。しかし、そうした生命の豊穣をありのまま受容することなくして、人間が本質を生きることはできない。
人間もまた、生命の一部だからだ。
たとえば、西洋近代が、肥大した自己意識を「わたし」ととらえ、その自己意識とそれ以外のあいだにはっきりとした分離線を引いたとき、自己と他者、自己と世界はべつべつの存在になった。そしてその世界から分かたれた「わたし」は、ロジックを絶対の道具として、世界を説明し支配しようと欲望する。
これとは逆に、たとえば「プリミティブ」「ネイティブ」「アニミスティック」と称されるような世界観や、仏教などの宗教的哲学においては、人も、他の生物も、あるいは無生物ですらも、大いなる生命の流れのうちに支えられ、そこから生まれ、それに育まれ、そこへとまた融けてかたちを失ってゆくようなものであった。それがかつての「知」のすがただった。
そこに、人間の理性の絶対性はない。
こうした、理性にとってはわけのわからないものでしかない生命の感覚を、そのまま受け取ることができるのが、「直観知」なのだ。
そして、古今東西、究極的な本質や幸福やよりよい世界について語る知恵は、まぎれもなくこうした直観知からの直接的なインスピレーションを受けることによって生まれてきた。なぜかわからないけれど、説明しろと言われてもできないけれど、そして言葉にすると矛盾だらけだけれど、どこかでかならずそうだとしか感じられない感覚によって。
それは、まさに「ありかたとしてのアート」を体験しているときに人が使っている領域の感覚なのである。
このシリーズでは、その「直観知」をもういちど、「知」の必要不可欠な領域として取り戻そうとしている。「直観知」を取り戻し、「論理知」と統合してゆくことで、知はより本来の力を取り戻すだろう。人を、社会を、世界を、ひいては宇宙を、ほんとうによりよく営んでゆくための、知恵の源泉として。
わたしはけして、論理知に価値がないと言っているのではない。それどころか、それはおそらくとても重要なものだ。しかし、証明やデータや論理的説明や再現性「だけ」を正しく、信頼できる唯一のものと思い込むことによって、人間は知のバランスを崩す。
「知に生命を取り戻す」。それが、知がほんとうに、わたしの、人類の、社会の、そして地球のウェルビーイングのために働くものとなるために、必要なことなのではないか。
そして、このようなよりホリスティックな知を名指すものとして、「幸福知」という言葉をつくった。
standART beyond。
新しいスタンダードを、これまでの彼方へ、論理の向こう側へ、かけがえのない生命の営みを取り戻しながら、つかみなおしてゆくこころみ。
「幸福知」のためのアート・ワークショップ・シリーズ。
生命の豊かさを知に迎え入れ、自分も、他者も、社会も、世界も「幸福に」生きるための、やわらかな喜びと遊びの場所。
手探りで、たくさんの人と、育ててゆけたらと願っている。
(報告:筒井史緒)