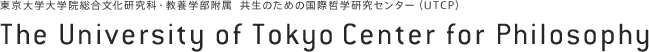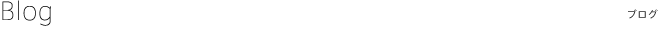【報告】筒井史緒 standART byond 報告②~Vol.1 「息を聴く、音に出逢う」開催報告
2024年5月14日土曜日。
〈「幸福知」のためのアート・ワークショップ・シリーズ〉standART beyondの、第一回となるワークショップが開催された。
ゲストに、疫学研究者でアーティストであるハブヒロシを迎えたVol.1。テーマは「息を聴く、音に出逢う」。
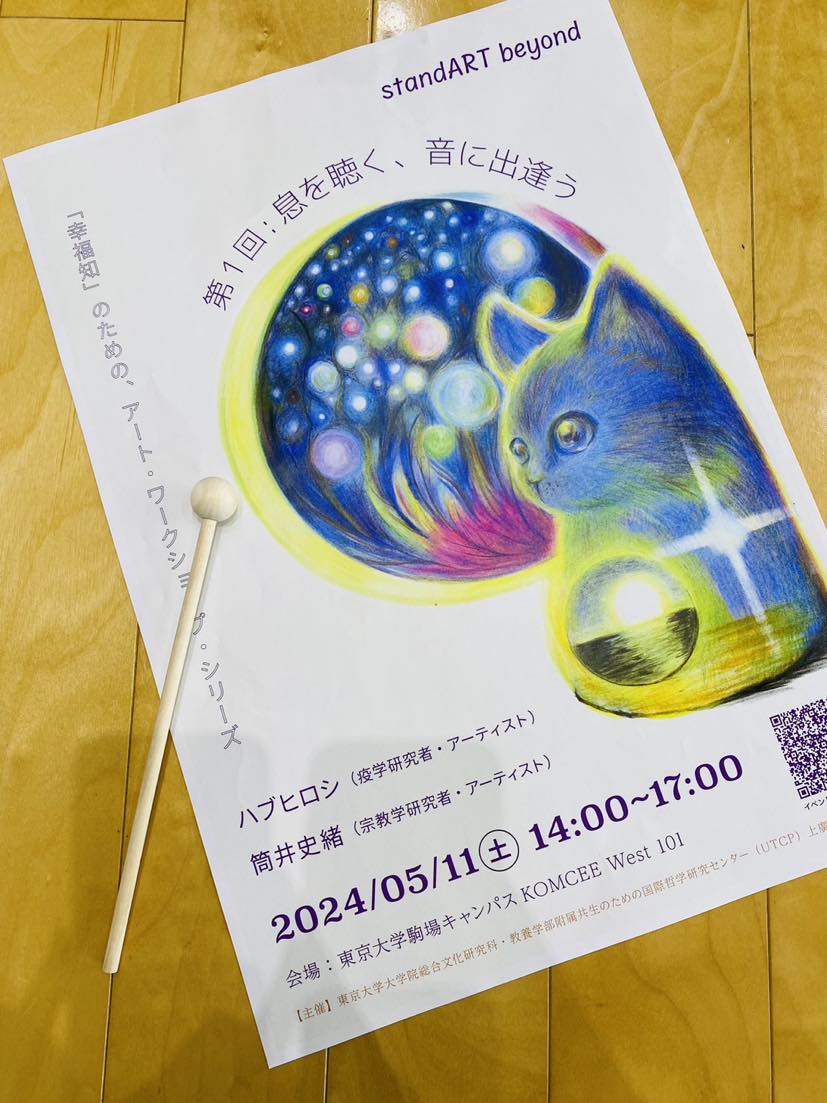
ホストであるわたくし筒井も、宗教学研究者で、かつアーティストである。そもそもハブくんとの出会いは、学者としてではなく、音楽の場でアーティストとして知り合ったのが最初だった。
学問の研究テーマも、ともに、大きな意味で「本当のウェルビーイングとは何か」「人間が幸福に生きるためには何が必要か」を探求する、という点で、共鳴しあっている。また、その探求の手段として、「アート」を手掛かりに、より豊穣で、生命に根差したありかたをアカデミアに取り戻す試みを行っている、という点でも、共通したヴィジョンをもっている。
ハブくんもわたしも、〈学者×アーティスト〉としてやろうとしているのは、ロジックやデータや再現性を重視する〈アカデミア〉と、わりきれないもの、説明のつかないもの、混沌としたもの、いまここのかえのきかない体験をそのままことほぐ〈アート〉との、両方に足をつっこみ、これらを融合・統合してゆこうという試みだ。【standART beyond】のスタートとして、この両輪をもつハブくんがゲスト登壇してくれたことは、シリーズを象徴するようなことでもあった。
ワークショップは、だいたい三部構成で行われた。
第一部では、わたしとハブくんがそれぞれ、ワークショップの意図や自身のバックグラウンドを話しながら、まずは丹田呼吸の体験(ハブくんは丹田呼吸の指導者でもある)。

丹田呼吸は、まず身体にフォーカスし、身体を感じるという意図で行った。
現代の、とりわけ都会の生活では、身体の感覚を離れ、頭メインで生活しがちだ。しかし本来、人間にとって頭脳とは全体のごく一部の機能でしかない。近年の脳科学では、「わたし」という意識も、脳のあとづけで構成されたフィクションでしかないことが明らかになってきている。
わたしは「幸福」について考えるときによく、「いきものとしての人間」に戻ることが必要だ、と考えているのだが、呼吸はまさに生命の営みの基盤であり源泉だ。さらに「ハラ」は古来、「肚落ち」という言葉にあるように、頭とは違う、より深い理解や納得の体感をつかさどる中心とも考えられてきた。
できるだけ頭をオフにして、いきものとしての自己の感覚を鮮やかに感じてみようという意図で、丹田呼吸からのスタートとなった。

ハブくんの合図で全員が丹田呼吸を行う。しっかりやるとなかなかハードだ。
呼吸だけでこれほど身体が熱くなるのか、と驚く。参加の皆さんからは、丹田がはじめて分かった、膝が痛かった、うまくできなかった、など、さまざまな感想が出る。
ここで、そうか、主催する側の意図と、参加者の体験は、まったく別のものになる可能性に満ちているのだと、あたりまえのことに改めて気づかされた。どうしても、熱を込めて企画などすると、「こういう体験をしてもらいたい」という熱い想いが生まれる。それはそれで、別になくす必要もない想いなのだろうが、そもそも、企画の意図が「かけがえがないわたし」を手探りで体験してもらうことである以上、その体験の内容をこちら側が規定するのは、企画の意図にむしろ反しているのだ。
ここから、ワークショップの内容や進捗に関して、より意識して手を放すようにこころがけはじめた。
少し休憩をはさみ、第二部。参加者それぞれがマレット(太鼓や木琴のバチのようなもの)をもち、4人ほどのグループに分かれて、東大駒場キャンパスをめぐり、好きな音を見つけてこようというワーク。
今回の参加者の面々は、小学生や高校生もいて、老若男女さまざま。バックグラウンドも、ほんとうに皆いろいろだ。それでも、「幸福知」といういまひとつ抽象的なテーマにもかかわらず、「面白そう」とピンときて来てくれた方々だけあって、オープンになんでも体験して楽しもうという好奇心と、真摯に生きることについて考えたいという純粋さは、皆さんに共通だったように思う。
そんな多様な、そして多くは初対面の、年齢も肩書も性格もバラバラな人々が、子どものように初夏のキャンパスをかけまわり、あれやこれやとなんでも叩いてみて、音と遊びに身と心を任せた、自由な午後のひととき。
ちなみに主催の梶谷・筒井・ハブも、部屋で皆さんを待ちながら、室内で好き放題、音を出したり歌ったり踊ったりしながら、お祭り状態で留守番していた。
なんと楽しかったことだろう。
帰ってきた参加者は、それぞれかけがえのない体験をお土産としてもちかえってきてくれた。部屋を出る前とぜんぜん違う表情。そして、それぞれのチームがとても仲良くなっていた。大人も子供もただただ嬉しそうで愛らしい。
少し休憩をはさみ、第三部はシェアタイム。ハブくんが、哲学対話が未体験なのでやってみたい、ということで、急遽、簡易的に体験版をこころみる。

参加者の皆さんの体験は、やはり多様でバラバラなものだった。
マレットをもつだけで、世界が音の可能性の海へと一変してみえる面白さ。初対面の人と音を分かち合う楽しさ。呼吸はむずかしくて集中できなかった子が、外で自由に遊ぶとなると率先して大人をひっぱること。なんで日本の最高学府でこれをやるのだろうかと考えてしまったこと…
わたしが個人的に印象に残っているのは、「今日は、進行のためのパワーポイントがなくて、本当に良かった」という感想だ。
当日の朝に集合した時、最初ハブくんは「さくっとパワポ作っていいですか」と言っていた。もちろん、と言ったのだが、そのときにわたしは何気なく「すごいねえ、わたしはパワポ使えないんだ」とつけくわえたのだ。いまどきそんな大学教員がいるのだろうかという発言だが、いるのだからしかたない。しかし、なにげなくわたしが言ったその一言に、なぜか彼は感銘を受けてくれ、結局そのままパワーポイントを作らずに臨んだのだった。
梶谷さんという存在もそうなのだが、わたしが素敵だなあと思う人やものの多くは、即興的だ。即興とは、「準備をしない適当なモノ」ではぜんぜんなく、むしろ、その場その場に真剣に存在し、場を感じ、場に対応する、という、世界と自己の出会いを真摯に受け取り、真摯に応答する態度だ。だから、「こうしておけば文句は出ないだろう」「こうしておけばなんとかなるだろう」という準備ができないぶん、リスクは高いといえば高い。
しかし、丹田呼吸の感想での気づきからもつながっているのだが、体験の場を提供する側が、体験の質をあらかじめ規定することも、あれこれと準備しすぎることも、けっきょく、なにかがその場で生まれてくる、その可能性と力をそぐことになっているのだと思う。
参加者が体験する力を信頼する。場と瞬間がもつ創造の可能性を信頼する。
アートがまさにそういうもので、仮にもアートを手掛かりとするシリーズであるからには、主催する側が、人も場も信頼することがとても大事なのだ。
起こってくることをみる、起こってくることに応答する、そうやって生まれてくる瞬間を目撃する、そしてまたその新しい何かに新しく応答する。その繰り返し、その粒と粒のつらなり。

参加した人が口々に「楽しかった!」と嬉しそうにしていたこと、主催したわたしたちもとてつもなく楽しかったこと。それが、この企画のいちばんの成果だったように思う。
前回のブログに書いたように、このワークショップ・シリーズは、「こころみのプロセス」である。これからの人類にとって、いちばん幸せな知のかたちを探ってゆく、こころみのプロセス。そのような意味で、わたし自身も、開催前よりもひとつ深い気づきを得て、プロセスをひとひら紡ぐことができた。
正しさよりもたいせつな何かを、人が、社会が、なくさないように。
固定した結論を出すことが大事なのではなく、探りつづけ、見つづけること。その営みを真摯に楽しむ中にこそ、言語化できない感覚での答えのようなものが、わたしたちひとりひとりのなかに明るさと確信と解像度を増してゆくはずだと感じている。
その端緒として、ものすごく、楽しい一日だった。
あの場にいてくれた皆さま、ほんとうにありがとうございました。
(報告:筒井史緒)