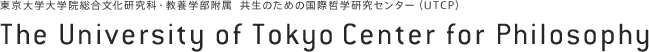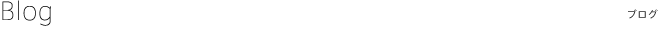【報告】「表象と表現〜俳優・若林佑真さんをお招きして〜」
2024年5月25日(土)、トランスジェンダー男性であることをカミングアウトして活動されている俳優の若林佑真さんをお招きし、駒場キャンパス18号館(Zoomでのリアルタイム配信あり)で対談イベントを実施した。ホストは、デザイナーのライラ・カセムさんと、この報告をまとめている山田である。
若林さんは大阪出身で大学まで関西で過ごし、大学卒業後に俳優の仕事をするにあたって拠点を東京に移された。今年は俳優の活動をはじめて10年の節目になるという。はじめに、高校から大学までの生活、トランスジェンダーであると気づいたきっかけ、そして、俳優の仕事を始めた経緯について教えていただいた。
若林さんは生まれた時に割り当てられた性別は女性で、性自認は男性である。ご自身がトランスジェンダーであることに気づいたのは高校生の時で、大学に入ってから周囲にカミングアウトを始めたという。
若林さんが大学生だった時期、関西ではトランスジェンダー外来が1軒しかなかったそうだ。予約をとっても診察まで1年待ちという状況で、若林さんは見た目と性自認とのギャップに苦しんだという。その後、病院で診断書をもらい、ホルモン注射を打ち始めて、大学ではトランスジェンダーとしての人生を歩み始めていった。
もともと若林さんは、中高とキリスト教の学校に通っており、大学は、同志社大学の神学部に進学された。彼曰く、中高の聖書の授業は、人が目を背けがちなことにしっかり向き合う授業だったそうで、ご自身がトランスジェンダーだと気づいたのも、聖書の授業だったという。聖書について勉強するなかで、キリスト教の「弱者と共にある」という考え方を学んだ一方で、聖書の記述を根拠に同性愛を否定するような考え方もあることを知った。その二つに矛盾を感じた若林さんは、聖書で本当に同性愛が否定されているのだろうかと考え、性的マイノリティと聖書との関係を研究をするために神学部に進むことを決めたそうだ。
若林さん個人の結論は、キリスト教の大事な部分は「弱者と共にある」ということなのではないかと考えたという。したがって、自身がトランスジェンダーであることも、キリスト教を学び神学部を卒業したことも等しく誇りを持てることだと語った。
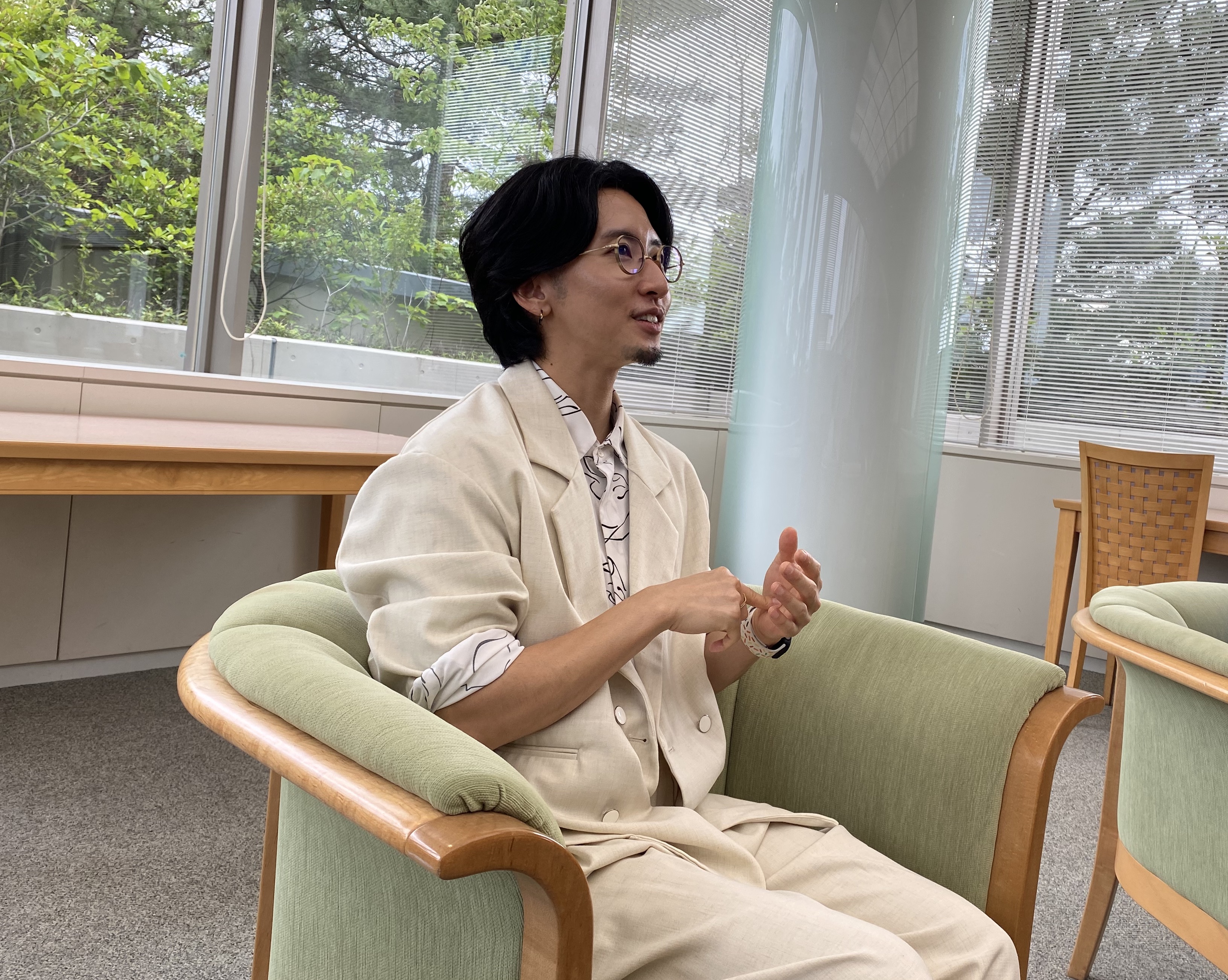
大学でキリスト教の勉強を進める傍ら、ある時期から就活を考えなくてはならなくなった。しかし、トランスジェンダーとしての人生を歩み始めた若林さんにとって、この就活が壁となって立ちはだかることとなった。
当時は、現在と比較して、トランスジェンダーを含めた性的マイノリティの方を前向きに、オープンに採用しようという企業も少なく、若林さんは女性の服装で、女性として就活をせざるを得なかった。こうして若林さんは「就活につまづいた」というが、奇しくもこのつまづきが俳優を目指すきっかけになったそうだ。
ある日、大学に、タレントの杉本彩さんが講演にいらしたという。杉本さんはタレント活動と並行して、動物愛護にも力を入れて活動されている方で、講演ではそうしたお話もあったそうだ。講演の後、保護犬を引き取ったというある学生が、<私が保護犬を1匹引き取っても保護犬をめぐる状況は大きく変わらないのではないか>という趣旨の質問を杉本さんに投げかけたところ、それに対して杉本さんは<ひとりひとりの小さな行動が、やがて大きな力になる>と返されたそうだ。このやりとりを聞いた若林さんは、「自分がトランスジェンダーであることにもなにか意味があるのではないか」、そして、「自分もメッセンジャーになりたい」と思ったそうだ。
若林さんの行動力はすごい。早速、自分の宣材写真を撮って、杉本彩さんの事務所に送ったそうだ。残念ながら事務所には入れなかったというが、これを皮切りに、約50社の芸能関係の事務所に手書きの履歴書を送ったという。大学3年生の時に、東京の俳優事務所に採用されたことが、俳優としてのキャリアのスタートになった。その後大学卒業までの1年間で、毎週夜行バスで大阪から東京まで通って演技のレッスンを受けたそうだ。こうして卒業後に上京し、俳優として活動をはじめて今年で10年を迎える。
トランスジェンダーであり俳優であるということは、「正直大変です!めちゃくちゃ大変です!」とおっしゃった若林さん。お話をうかがっていると、これまで彼がトランスジェンダー俳優として大変さを感じてきた要因は、やはりトランスジェンダー(特にトランスジェンダー男性)が芸能業界において圧倒的にマイノリティであるということに集約されるように思う。
マイノリティであるということは、トランスジェンダーの役が少ないということと、トランスジェンダー俳優が少ないということの両方のことを含んでいる。
若林さんによれば、世界的に見てもトランスジェンダーの男性が出てくる映画は圧倒的に少ないという。また、日本においてはトランスジェンダー役があったとしても、多くの場合シスジェンダー(生まれた時に割り当てられた性別と、自分の性自認が一致する人)の俳優が演じることがほとんどだという。この一因として、興行収入や視聴率を重視する映画・ドラマにおいて、収入や視聴率を稼ぐことができるトランスジェンダー俳優がほとんどいないからということが挙げられる。
しかしそもそも、<収入や視聴率を稼ぐことができるトランスジェンダー俳優がほとんどいない>というのは、単にトランスジェンダーであって影響力がある人が少ないということだけを意味しているのではない。そうではなくて、こうした現状の背景にトランスジェンダー俳優が育ちにくい仕事の環境があることを意味していると若林さんは指摘した。トランスジェンダーの役が少なかったり、トランスジェンダーであることをカミングアウトして俳優を行う環境が整っていなければ、当然、トランスジェンダー俳優が役をもらう機会が限定されてくる。
また、数少ないトランスジェンダー役があったとしても、現在はシスジェンダーの役者に割り当てられてしまう。そうすると、役者さんたちが現場経験を積んだり、社会的に認知されたりする機会も当然限られてくる。こうして、トランスジェンダーの俳優が育ちにくい環境が再生産されているというのである。
トランスジェンダー役が登場する作品が少ないというのは、トランスジェンダーに対してまだまだ社会意識が希薄であることを反映しているのだろう。
若林さんは2022年に「チェイサーゲーム」という民放のドラマに出演し、トランスジェンダー男性の当事者役を演じられた。若林さんによれば、トランスジェンダー男性当事者が、その当事者役を民法のドラマで演じるというのは初めてのことだったそうだ。これは若林さんやトランスジェンダー当事者にとって、きわめて重要な1ページだと思われる。その反面、SNSでは「原作にないトランスジェンダーの話題を入れないで」、「なんでも社会問題を入ればいいってもんじゃない」などネガティブなコメントも目立ったという。このような「トランスジェンダーの日常に興味がない」ことを表明するようなコメントを見た時、若林さんは率直に悲しく感じたと語った。

トランスジェンダーの表象の仕方においても課題は色々とある。若林さんによれば、トランスジェンダーを描いた作品は、その人が不幸な人生を送るというストーリーが圧倒的に多いという。特に、亡くなるという結末を迎えることが少なくないそうだ。
若林さんは、こうしたストーリーについて、個々の作品のストーリーに対する評価と、一般にトランスジェンダーが登場する映画に死の描写を入れることについての是非は、分けて考える必要があると前置きした上で、次のように述べた。トランスジェンダー当事者たちが感じる苦しみを「死」という描写を通じて描き出すことによって、社会にある種のメッセージが伝えられる可能性もある。しかし、それでもなお、トランスジェンダー役が描かれる映画は、不幸な結末になることが多すぎるのは、やはり表象の仕方が偏っていると言わざるを得ないだろう。若林さんは、現実には幸せに生活を送っているトランスジェンダー当事者の方々も沢山いることに言及しながら、「もっといろんな日常生活が描かれる作品が増えて欲しいなと思う」と語った。
こうした表象の現実がある一方で、10年にわたり俳優を続け、民放ドラマでトランスジェンダー男性役に当事者としてはじめて出演した若林さんは、確実に日本のトランスジェンダー俳優のパイオニアであるという認識も広まっていると思われる。
あるとき、トランスジェンダー当事者であって、俳優になりたいと思っている人からメッセージが届き、<自分はトランスジェンダーだから、俳優になれないと思っていたけど若林さんを見て「目指していいんだ」と思えた>と綴られていたそうだ。こうした声を受けて、大変なこともあるが、俳優の「やりがい」を見出していると語った。
また、表象のあり方や関わる人々の意識に変化も生じているという。
たとえば、メディアによって作られた性的マイノリティのイメージによって現実の性的マイノリティの人が苦しめられてきたことを意識して、現在はそれを変えていこうという流れがある。その事例が、当事者が当事者役を演じることであったり、後に紹介するように、若林さんのような方が「監修」として、映画の構成にかかわることであったりする。
加えて、性的マイノリティの表象について真剣に向き合う、当事者ではない役者たちがいることも見過ごせない。若林さんによれば、トランスジェンダーを当事者が演じるべきかどうか、非当事者である自分が演じて良いか、いかにして性的マイノリティの人が活躍できる業界作りができるのかを真剣に考えている俳優さんもいるとのことだ。(残念ながらそうではない人もいて、近年、海外で差別的な発言をして炎上した役者さんもいるようだが。)
若林さんは、色々な人がいるということを知ってほしい、と繰り返し、メディアが持つ影響力が大きいからこそ、間違った表象や偏った表象を少しでも減らしていくことが大事だと強調した。

若林さんは俳優としての活動に加え、当事者としてトランスジェンダーに関わる表現を扱う作品の監修にも入られてきた。
若林さんが、脚本の監修に入る時、たとえばどのようなセリフや場面に違和感を感じ、それをどのように修正してきたのだろうか?先に紹介した「チェイサーゲーム」の1コマでは、トランスジェンダー役の渡邊凛が、インターン先の会社の社員の前で、自身がトランスジェンダーであることをカミングアウトするシーンがある。この場面のセリフについて若林さんは次のような修正をしたそうだ。
元々のカミングアウトのセリフは「僕は生まれてからずっと男でした。僕は男なので男として生きたいと思っています。」といったものであった。それを若林さんは、「自分が生まれた時に割り当てられた性別に違和感があります。だから今ありたい姿で生きています」と変更するように働きかけたという。
ではなぜ、元々のセリフは変更すべきだったのか。それは、元々のセリフは、<トランスジェンダー=反対の性を生きたいという人>というステレオタイプを強化してしまう可能性があるからだという。トランスジェンダーの中には、生まれた時割り当てられた性別とは反対の性を生きたいと思う人が一定数いる。しかし、トランスジェンダーの人々はもっと多様であり、反対の性を生きたい人ばかりではないと、若林さんは述べた。
医学的には、トランスジェンダーは「性同一性障害」と呼ばれていた時期があり、この概念では<生まれた時に割り当てられた性とは反対の性を生きたい>という側面が強調されていた。それに対して、昨今は「性別違和」や「性別不合」とも呼ばれるようになり、自分が生まれた時に割り当てられた性別では生きられないこと、それ自体に焦点が当てられる言い方に変わってきた、ということである。
このようなトランスジェンダー当事者の多様なあり方、そして概念の変化が生じてきた時代に、「僕は生まれてからずっと男でした。僕は男なので男として生きたいと思っています。」というセリフは、<トランスジェンダー=反対の性を生きたいという人>という偏見を強化する方向に働く懸念があるため、若林さんは変更した方が良いと指摘したのである。
最近では、若林さんは2024年3月に公開された映画『52ヘルツのクジラたち』に出演者、監修として参加されている。その映画についての話題も、参加者とのやりとりを含めて多くが語られたが、ここではその一部を紹介したい。
トランスジェンダー男性役が登場するこの映画で、若林さんはトランスジェンダー表現に関してさまざまな段階で監修に入られたというが、なかでも脚本の監修は1年ほど関わった大きな作業であったという。時に、自分が感じた脚本への違和感が、性的マジョリティである人々に伝わらないこともあり、難しさを感じたと語った。
伝わらない...とはどういうことだろうか。作中に出てきた場面ではないが、例え話として、若林さんが日常生活で「伝わらない」と感じる場面として次の事例を挙げられた。
若林さんが初対面であった人に、必要があって「トランスジェンダーだ」とカミングアウトする時、「わたし/ぼく、そういうの偏見ないんで」とただちに返されることがあるという。こうした反応について、若林さんは「すごく違和感がある」と語った。なぜかというと、「偏見を持たれるアイデンティティをあなたは持ってますね」と言外に伝えているようであるからだ。こうした反応に接すると傷つき、悲しい気持ちになるという。
しかし、こうした違和感を性的マジョリティである人に伝えると、「どこが悪いのかわからない」という反応が返ってくることもあるそうだ。発言した人は、まったく悪意なく、むしろポジティブな意味で言っていると考えているので、自分の発言が相手に対する偏見を表していることに、たとえ指摘されたとしても理解できないことがあるそうだ。
このような性的マジョリティの、性的マイノリティに対する、無意識的で差別的な反応は、他の社会的マイノリティの方々に対する社会的マジョリティの態度にも共通するところがある。たとえば身体障害や精神障害を持った人も、その障害が可視化された時、似たようなニュアンスの言葉をぶつけられることがあるだろう。これについては会場の参加者からも、色々な経験談・事例があがった。ちなみに車いすユーザーであるライラさんは、そのような言葉に接する時、「あ!大丈夫、私もあなたに偏見ないんで!」と返すという。(ユーモアの効果的な使い方!)

若林さんのお話は、映画の脚本のなかの実例ではないが、若林さんのいう「伝わらない」とは、こういった性的マイノリティの当事者の方々の感覚が、言葉を尽くしたとしても、マジョリティになかなか理解されないことがあるということだ。また、こうしたことを若林さんが指摘し続けることによって、<この人は気にしすぎ、考えすぎ、細かい>というレッテルを貼られてしまうことにもなりかねない。
これに対してライラさんは、特権を持っている人たちは、自分が持っている特権に気づかないからこそ「悪意がない」偏見や差別的な発言をしてしまうのではないかと述べた。したがって「自分の特権ってなんだろう?」と、マジョリティに投げかけて、自分の特権をまず認知する・考えてもらうと、すり合わせがしやすくなるのではないかと論じた。また、インクルーシブな現場を作る上で、当事者と全体をまとめる人などとの間に第三者が入ること、現場に第三者がいることが大事なのではないかと問いかけた。
後半では、会場やオンラインの参加者の方々の質疑応答も含むかたちでトークが続いていった。
会場からは「社会的マイノリティに理解のない人になりたくない」という思い「わからなければいけないというプレッシャーや圧があるのではないか」というコメントもあった。こうした圧やプレッシャーのひとつの帰結として「わたし/ぼく、そういうことに偏見とかないんで」という、言われた方にもやもや、不快感を与えるような差別的発言があるのかもしれない。
では、トランスジェンダーを含む性的マイノリティの人々に対して、当事者ではない人がどのように接すればいいのかという話題が出た。若林さんは当事者として、「分からないから教えて」と言える人、ひと対ひと、としてのやりとりをフラットにできる人がいいと思うと語った。
また、社会の中である程度生きて年を重ねていくと、過去の状況を反映した偏見や刷り込みが自分に染み付いていることもあるかもしれない。どうしたらこうした刷り込みを相対化したり、偏見を若い世代に再生産しないようにできるか、という質問もあった。若林さんは、こういった講演会で当事者の話を聞いたり本を読んだりして色々な情報を取り入れて、自分自身の知識をアップデートしていくのが良いのではないか、それに伴って認知や言動も変わってくるのではないかと、若林さんは述べた。

この講演会に参加してくださった方の多くが、おそらくあっという間の二時間だと感じられたのではないか。若林さんの明るく気さくなお人柄で、会場は、対談が始まってすぐに暖かな雰囲気となった。また、トランスジェンダーをめぐる表象について、ご自身の過去のエピソードも沢山含めつつ、分かりやすく丁寧に、そして時にユーモアたっぷりに伝えてくださった若林さんのお話に、会場は大きな笑いに包まれることもあった。
加えて、ライラ・カセムさんとのやりとりも大変興味深かった。自虐とユーモアとの違い、ユーモアの効果的な使い方などについてのお二人の議論は、示唆に富んでいた。
この度はご登壇いただきありがとうございました!いつかまたUTCPにお越しいただける日を楽しみにしています!
(報告:山田理絵)