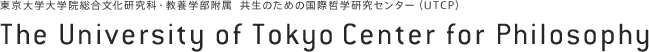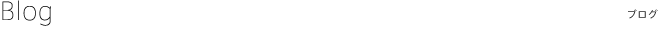梶谷真司 邂逅の記録130 大牟田から世界を変える――ポニポニの小さくて大きな挑戦
2024年3月6日から8日に、福岡県の大牟田市へ行ってきた。大牟田未来共創センター(ポニポニ)の活動を見るためである。
代表の原口悠さんとは、RISTEX(社会技術研究開発センター)のプロジェクト(2016~2018)に関わっていた時に、当時採択されていたプロジェクト間の交流ワークショップで知り合っていた。
その彼からコロナ禍の最中、2021年9月に連絡をいただいた。ワークショップのことはあまり覚えていなかったが、原口さんは、異様にハイテンションで愛想がよく、強烈なインパクトがある人だったので、すぐに思い出せた。届いたメールは、その時の印象とは打って変わって、とても落ち着いた丁寧な文面で内容的にもきわめて真面目。自分も地域おこしで対話の場を重視しており、哲学対話に興味をもっているので、話をしたいとのことだった。
さっそくポニポニのホームページや、メールに貼ってあったリンク先の記事を読んでみた(https://poniponi.or.jp/)とくに「私たちが考えていること」には目を見張った(https://poniponi.or.jp/thoughts/)。地域おこしのNPOのホームページには、普通、多くの人に読んでもらえるよう、柔らかくて親しみやすい文章が書いてあるものだが、ポニポニのHPは(名前が妙にくだけているのと対照的に)、思想的・理念的で難解な文章が連なっている――「大牟田で暮らし、働く一人ひとりの存在が肯定され、社会的な理由で孤立することなく、多様な選択肢の中でそれぞれの力が発揮され、わくわくする持続的なまちとなることを目指しています。」「誰もが潜在能力を持ち、それは人とのつながりによってはじめて発露するものである」「不安定化する社会構造により、セルフ・アイデンティティが不確かな社会状況において(存在論的不安)、私たちは「エゴ・アイデンティティやI(わたし)≒存在」が肯定され、「温まる」機会や仕組みを地域において保障することが重要になる」などなど。
一見、ただ抽象的な一般論を述べているようでいて、よく読むときわめて周到に言葉を選んで書いている。しかも、その途中に突然「わくわく」や「温まる」といった日常語が登場するのが面白い。そのすべてが意図的に仕組まれている感じがする。
そんな特異な文体にも驚いたが、活動報告を読んでみると、私が哲学対話を通して考え、やりたいと思っている「共創(inclusion)」に近いことを考えていて、しかも実際の活動としてすでに具体的な形にしているように見える。こんなことができるのかと感動すら覚えた。
*超高齢社会「以後」の地域経営モデル
https://digital-is-green.jp/branding/human-centered/001.html
https://digital-is-green.jp/branding/human-centered/002.html
https://digital-is-green.jp/branding/human-centered/003.html
彼らと何かができるなら、こんなありがたいことはないと思った。コロナ禍で移動できない時期に来た原口さんからの連絡は、オンラインのトークイベントへのお誘いであった。「湯リイカ」という、世の中にあるいろんな問題について考える「問いと対話」の企画である。私と原口さんと、もう一人ポニポニのメンバーで芸術工学博士でもある山内泰さんの3人で、「哲学対話の場で何が起きているのか」というテーマで話をした(収録:2021年10月26日/2022年3月6日公開)。実際にはZoomで話しているだけなのだが、ご覧いただけば分かるように、銭湯でお風呂につかりながらまったり放談する設定になっているのが面白い(https://dialogue-eureka.jp/furotomo/kajitani-shinji/)。彼ら自身が大牟田で対話の場を作っており、しかもHPにあるように高度に概念的な話もできる人たちであり、哲学対話についても、他で話すのとは一味違ったものになった。
その後、一度大牟田に行きたいと思っていたら、今度はコロナ明けの2022年12月2日~4日、ポニポニ初の対面イベント「にんげんフェスティバル」を開催するとのことで、対談企画の一つに私を呼んでくださった(https://poniponi.or.jp/festival/identities/)。このイベントは、プログラムを見たら分かるとおり、かなり尖った企画である。ゲストの顔ぶれを見ると、東京(もしくはせめて福岡)でやるのかと思うような面々である。それをあえて大牟田のような地方都市で、しかも3日間にわたって。
私は真ん中の3日、地域創生Coデザイン研究所(NTT西日本の100%子会社)の社員でポニポニのメンバーでもある松浦克太さんと対談することになった。テーマは「差異に基づくコミュニティ~哲学対話で起きていること」。当時、哲学対話をコミュニティ論から考えるようになっていたので、その話をさせていただいた。
https://poniponi.or.jp/festival/identities/program/eureka-day2-talk3

本当は、私自身3日間大牟田にいて、いろんな講演・対談を聞きたかったが、都合がつかず、当日現地入りして対談をして、夜は原口さんたちと夕食を取ったあと福岡まで帰り、翌日に東京に戻った。
このような事情で、フェスティバルの時は、私もすぐに帰らないといけなかったし、ポニポニの人もイベントで忙しかったのであまり話せなかった。そこで今回は、ゆっくり話をして彼らの活動を見たかったので、こちらから依頼して伺うことにした。
3月6日、大牟田に到着してオフィスを訪れた。原口さん、山内さんが出迎えてくれた。そこにはポニポニの他のメンバーも4~5人いた。中に入ると、「どうぞどうぞ」と言われ、私も何となくみんなと一緒に座る。ホワイトボードにぎっしり文字が書かれているので、ミーティング中だと分かるのだが、そのわりにはとても打ち解けた感じで、楽しくおしゃべりしているようで、かといってけっしてケジメのないだらけた感じはなく、笑っていても、基本的には真剣な雰囲気である。その日の私は、とくに何をするでもなく、オフィスで彼らと一緒に過ごし、夜は懇親会でメンバーの人たちとおしゃべりをして、ポニポニや大牟田での活動についていろいろと伺った。

翌7日の午前中は、10時すぎにオフィスに行くと、ちょうど大牟田市立宅峰中学の地域学校協働活動推進員の江㟢文寿さんがポニポニのこれまでについて話を聞きに来ていた(宅峰中学はポニポニが総合的な学習の時間の支援で関わっていた学校)。そこに私も加わる形で時折質問して、センターの設立とその後の経緯、その間のメンバーの思いなどを聞いた。
すると、学校にせよ地域コミュニティにせよ、紆余曲折はあっても、基本的には上に書いたような理念に沿ってやってきたことが分かった。しかもそれは、ポニポニの内部でも実践されていた。まず出勤・退勤の時間がまったく管理されていない。メンバーはいつ来てもいつ帰ってもいい。仕事も、誰かから指示されない。自分でやりたい企画を立て、自分で必要な協力を求め、自分で進めていく。まったくの自主性に任されていながら、孤立はしない。HPの理念どおり、お互いがそれぞれの能力を信じ、つながりの中で発揮されることを期待している。この自由さはけっして気楽なものではないが、メンバーがいい緊張感の中で楽しんでいるように見えた(部外者だから表面しか見えてないかもしれないが)。
さて午後は、市営住宅プロジェクトの現場を見せていただいた。
*ポニポニの山内さんとNTT社会情報研究所の林瑞恵さんへのインタビュー
https://furue.ilab.ntt.co.jp/book/202403/contents2.html
その現場となったのは、老朽化した市営の歴木(くぬぎ)住宅である。そこに住んでいた約50世帯の人たち(2023年3月の時点)が、市の施策によって、高泉に新たに建てられたマンション型の市営住宅に移り住むことになった。こうした住み替えは、行政や部外者から見れば、きれいで便利な家への引っ越しと見なされるが、引っ越す人たちには、リロケーションダメージと呼ばれる負荷がかかることが多い。これは住む場所が変わることによって生じる身体的・精神的なダメージで、実際に病気になったり、鬱などの精神的な症状が出たり、場合によっては命を落としてしまう。
このような事態を回避するのに、ポニポニが大切にしたのが対話の場である。当時原口さんたちは、すでに「わくわく人生サロン」という対話のプログラムを始めていた。これは65歳以上の人のための場で、「一人ひとりに注目し、対話的な関係によってそれぞれの潜在的な力(自由)を引き出していくこと」を目指している(https://poniponi.or.jp/project/wakuwaku)。原口さんたちはそこで、「安心できる場において対話を行うと、人は役割から外れ、温まり、他者や社会への関心に開かれ、自然と動き出していく」ことに気づいたという。
市民住宅の住み替えにおいても、同様の手法を用い、現地で住まいについての住民の思いや、各自が大切にしているものなどについて話をする場をもった。ここで興味深いのは、まずこうした対話の場を地域の福祉事業所の職員や、工業高等専門学校の教員や学生たちと一緒に作っていること、つまり最初から具体的なインクルージョン(共創)をしていることである。もう一つは、ここで積み重ねてきた自分たちの暮らしについて思いをはせること、大切な思い出だけでなく、大切なものについて語ることは、周りの人々や物との関わりの中でどのようなアイデンティティを形成してきたかを浮き彫りにするということである。
こうした対話を意識的に行うことが、住み替えの具体的な方策につながっていく。たとえば、新しいマンションは、収納スペースがあって、古い家具は処分してしまうのが普通だが、それはアイデンティティの喪失にもつながりかねない。しかし家具のサイズが合わないので、もっていくことができない。そこで、ずっと使っていた家具を高専の先生や学生たちと一緒にリメイクして、引っ越しの時にもっていくということにつながった。

また、古い住宅から新しいマンションへの引っ越しは、設備の面でも住空間の面でもまったく異なり、山内さんがおっしゃるように「50年分未来へ行く」ことを考えれば、そのストレスは測りがたい。そこで引っ越し先のマンションにあらかじめ慣れるために、住み慣れた歴木住宅の空き部屋にモデルルームを再現した。高泉に行って実物を見るのではなく、あくまで長年住み慣れたところで、自分たちの生活と連続的に捉えたもらうためである。
さらに住民の暮らしに根差すアイデンティティを守るのに、ポニポニの人たちは「住みこなし」という概念を使う。歴木の人たちの家には、広めの庭があり、多くの家では、そこに自分たちで部屋を増築して家を拡張していた。また区域の空き地に畑を作って野菜を育てていて、そこが住民たちの交流の場になっていた。こうして自分たちの住まいと周辺の土地に、住民たちが自ら関わり、自分たちに合うように変えていくことを、ポニポニでは「住みこなす」と表現し、こうした主体的な発露の余地を「関わりしろ」と呼んでいる。
そこで考えたのは、引っ越した先の高泉で、こうした「住みこなし」「関わりしろ」を何らかの仕方で生み出すかであった。そして住民の意向を反映する形で高泉の敷地内に畑を作ったり、玄関先を飾りつける人が出てきたときに、それを積極的にサポートしたりした。まさに理念の通り、それぞれの人が持つ潜在能力が人とのつながりによって引き出されていったと言える。
同様のことは、最終日の8日の午前中に見学させていただいたVRプロジェクトにも言える。これは、自宅や施設で外出が難しい高齢者がヴァーチャルリアリティの映像を見ることで、擬似的に外の世界を体験してもらうというものである。東京大学科学技術研究センターの登嶋健太さんが介護施設で働くなかで発案した 「VR 旅行」の、いわば大牟田バージョンを作る試みである。ここでもポニポニと地域創生Coデザイン研究所、NTT社会情報研究所が協力し、大牟田市生涯学習課、高齢者施設「延寿苑」、地元の大学生など、いろんな人たちが関わっている。
何より面白いのが、技術者が制作した「素晴らしい映像」を見てもらうのではなく、地元の元気な高齢者たちが撮影している点である。その中には90歳を超えたおばあさんもいる。プロジェクトメンバーがグループに分かれて、おじいさん、おばあさんたちに撮影しに行きたい場所を考えてもらい、360度カメラの使い方も講習で身につけてもらい、自らカメラを手に取りたいものを撮ってもらう。その編集を若い人たちが行う。
私が延寿苑を訪ねたのは、プロジェクトメンバーが集まり、出来上がった各グループのVR動画をお互いに見る日であった。おばあさん、おじいさんたちは、そこでVRゴーグルの使い方を学び、午後から施設へ行って彼女たち自身が利用者に説明をして見てもらう準備をしていた。

撮影をした高齢者は、年齢が近いから外出できない高齢者が何を見たいか分かる――駅で新幹線を見送る、お寺でお参り、境内にいる猫に餌をやる、住職の話をする、屋台でから揚げを買う、紙風船で遊ぶ、お祭りで屋台のある通りを歩く、等々。自分たちが案内人となって、ヴァーチャルな世界を紹介する。同じような世代だからこそ、昔とすっかり変わってしまった町の情景について、思い出話とともに語り合うことができる。映像を見た人たちが自分で見たいと言って、外出への意欲をもつようになる。あるいは、今度はこんなところに行ってきてほしいと言って、撮影してきた人たちはさらにやる気になる。そうやってまさに一人一人の存在が肯定されることで各自の能力が発揮され、わくわくする持続的なまちとなる――ポニポニの目指すところが具現化されている。
私がこのようなポニポニの活動でとくに注目するのは、協働する関係の作り方である。私自身、東大の産学連携等で感じてきたことだが、何か目的を決めて、いろんな組織から人が参加しても、みんな組織の一員としてしか発言も行動もできない。そこで自分の意見を言ったり、自分で判断して行動したりする余地はない。みんなそれぞれの立場に固定され、組織の責任を負って義務感から参加するだけになりやすい。そこには楽しみも主体性もない。だから基本的にはうまくいっていない(と私は思う。やっている人たちは、うまくいっていると思っているみたいだが、私に言わせれば、それ以外にやり方が分からないだけで、“仕事”だからそれでかまわない、そういうものだと思っているのだろう)。
けれども上で紹介したポニポニの活動では、特定の目的を決めずに個人的な人間関係を先に作っている。楽しいから一緒にいる。とくに責任や義務があるわけではない。会って話しているうちに「これをやってみよう!」というアイデアが出てくる。すると、それぞれの人が属している組織やコミュニティに持ち帰って、他の人たちを説得したり、組織に合うようにアレンジしたりする。もともと“仕事”としてやらされているわけではなく、やりたいという気持ちが根底にあるので、誰もがそれぞれのモティベーションに応じて動き、何とか実現できるようにできる範囲で協力し合う。だから「私ばっかりやって、あいつはやっていない」とか「負担が一部の人に偏っていて不公平だ」という不満も少ないようだ。もちろん特定の人が他の人よりたくさんやっていて大変だということはある。しかしそれを「不公平」とは思っていないのだろう。
これはたんに「うまいやり方」なのではない。「社会システムの変革」で解決する、既存のシステムの中に新しいシステムを組み込むというポニポニの理念、方針の現れである(https://poniponi.or.jp/thoughts/:他の理念も含めて読んでいただきたい)。
彼らの活動は今のところ目覚ましい成果を上げているように見える。それが継続していくのかどうかは、ポニポニ自身の可能性だけでなく、日本の社会の可能性を測る試金石である。なぜなら彼らがHPの「わたしたちが考えていること」で書いているように、「大牟田へのコミットメント=社会全体や世界へのコミットメント」だからである。彼らは大牟田での活動を通して、近代の世界、日本全体に共通する社会システムを見出し、それを変革することでより良い世界を実現しようとする。壮大な挑戦だが、彼らが行う具体的なプロジェクトの一つ一つは、たとえ小さくても、そこへ向かう一歩なのである。