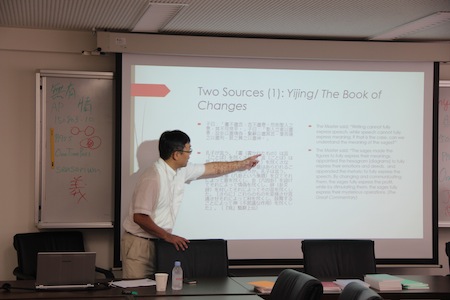【報告】2015年度東京大学-ハワイ大学比較哲学夏季インスティテュート(5)
引き続き、2015年8月に行われたハワイ大学と東京大学の比較哲学インスティテュートについての報告です。今回は、6日目(8月10日)と7日目(8月11日)の講義の様子について、佐藤麻貴さんと佐藤空さんに執筆してもらいました。
*****************************
8月10日午前中は駒澤大学の藤井淳先生による、空海の言語世界についての講義だった。真言受容の背景における空有論争、儒教(名教)からの影響の二点の視座から、空海にとっての言語とは何だったのか、空海の生きた時代背景、空海の書いたテキスト、書などから講義をいただいた。
空有論争は、空海の時代において特に論争されていた問題であり、その背景には三論宗と法相宗の対立がある。すなわち、三論宗は中観の立場をとって、意識が存在しないと理解したのに対し、法相宗は唯識の立場をとり、意識が存在すると主張していた。法相宗からは奈良時代に、道鏡、行基、玄昉などが輩出され、法相宗の方が主流であった時代背景において、空海は、三論宗の立場から入唐したとされている。帰国後、空海は、彼が持ち帰った胎蔵界曼荼羅こそ、両者の対立を超克するものとし、胎蔵界曼荼羅には、大日如来による四宗(法相宗、三論宗、天台宗、華厳宗)の統合が示されているとした。
空海における言語とは、言語こそが真実を伝えることができるツールであるとの認識に基づいているようだ。それは、『声字実相』という言葉からも推測することができる。声字は音と文字を指すのに対し、実相は現実界を指している。空海の思想にふれると、彼がインド哲学から深い影響を受けていたのが理解できる。すなわち、インド哲学においては、言語は実体のある客体(Atman, Mahatman)であるのに対し、仏教においては、言語は本来的には概念(Anatman,Ninatman:アートマンの存在の否定)でしかない。また、インド哲学においては声常住論であり、声が永劫を象徴し、その故に儀式等を重視するのに対し、仏教においては声無常論であり、声は一時のものでしかなく、精神面をより重視する。こうしたことから、空海の密教には、インド哲学との親和性が見られるとのことであった。空海の言語世界とは、言葉が世界のすべてを象徴しており、文字と実体との接続があるという立場に基づき、世界の全ての諸現象や実物を、一つの梵字に集約することができるといった思想であったとして、講義は締め括られた。
午後は、ハワイ大学石田先生の三回目の講義だった。前回に引き続き、言葉→聴覚からの認識→視覚からの認識という、言葉の二段階変化について振り返った。そこで、道元が理論と実践を重視したのに対し、空海は言葉と儀式を重視したとして、簡易に紹介し、「自然が我々に語りかけてくるのだとしたら、それはどのようにして可能なのか、どのようにしたら我々は自然と会話をすることができるのだろうか」という問いを投げかけられた。「以心伝心」という言葉は、空海が禅思想から学び、日本に紹介したことを挙げながら、それに対し、道元は「一句の正伝あれば山伝水伝あり」という言葉を残していることが紹介された。
もし、正しい思想、考え方というものが、道元のように直線的に弟子へ伝えられていくというものなのだとしたら、空海の声や字から、正しい思想、あるいは倫理やモラルというものは導くことができるのだろうか。もしできるのであれば、それは如何ようにして可能なのだろうか。また、どうして、我々には倫理が必要とされているのだろうか。この世界とは、道徳的に良いものだと言えるのだろうか。倫理とは根源的に「良いこと(good)」を要請する。自然の摂理として、複数の存在が相互影響しあいながら、また自らが変化しながら相互に関係しあうこと。こうした自然の働き自体を根源的に「良い」ものだと考えられることができるのではないだろうか。空海は、道元とは異なる、そうした相互影響に基づき、変化しつつある事物に内包されている「良い」ものを、倫理的だとしているのだとしたら、それは道元が示唆する倫理とは異なるアプローチであるといえるだろう。色々な問いを投げかけられていく上で進められていく授業は、我々学生に主体的に考えさせてくれる余地を与えてくれる。空海と道元の示唆する倫理の差異について、また自然の持つ根源的な働きを善とすべきなのかについて、様々なことを考えさせてくれる講義だった。
文責:佐藤麻貴(東京大学大学院博士課程)
***
東洋文化研究所での最後の講義となった8月11日は、午前中に中島隆博先生(UTCP)が、そして午後はピーター・ハーショック先生(ハワイ大学イースト・ウェスト・センター長)がそれぞれ講義された。
午前中の中島先生の講義のタイトルは、“Does Word Exhaust Meaning or not?” 「言尽意不尽意論争」(意味は言葉によって尽くされるか否か?)というものであった。講義のトピックは、中国の六朝時代においてなされた言葉と意味の関係性をめぐる、「言尽意不尽意論争」と呼ばれた一大論争に関してである。そこでは、「言は意を尽くすことができる」という立場と「言は意を尽くすことができない」という立場にわかれ、論争がおこなわれていた。またこれと同時に、「意は言を尽くすことができるか」という議論もなされていた。講義においては、「言は意を尽くすことができる」という立場と「言は意を尽くすことができない」という立場の中間的な立場「忘れられた言(葉)によって意を尽くす」を取った王弼(Wang Bi)や、荀燦(Xun Can)の議論に焦点を当て、議論がすすめられた。
午後のハーショック先生の講義のタイトルは、“Empty Words: Buddhism, Language and Liberation”(空虚な言葉:仏教、言語、解放)というものであった。前半においては、まず、およそ紀元前400年の仏教的伝統の出現から、紀元後700年までの南アジアにおける言語に関する仏教思想の展開についての議論がなされた。最初期の仏教のテクストと教えで表わされているように、仏教にとって、言語に関する関心が起こった理由は主として倫理的、実利的なものであった。すなわち、言語の使用に伴うカルマ的含意と、これらの含意がいかにして、葛藤、苦痛、災難からの解放を実感する仏教の救済の要領に生産的な影響あるいは悪影響を与えうるかという関心であったのである。南アジアの他の哲学的伝統との継続的な相互作用の中で、仏教の焦点は言語と知識の関係、特に概念化することと、真理を経験し表現することの両方に関して言語の条件づけの効果がどのように作用するのかということに関する形而上学的、認識論的関心に移って行った。これらを念頭に置いた上で、講義の後半では、阿毘達磨、中観派、唯識派といった大乗仏教の伝統が、言語が意識と現実の間を媒体するものであるということを特に強調しつつ、いかにしてこれらの問題に関わって行ったのかということに関して議論が深められたのであった。
文責:佐藤空(UTCP)