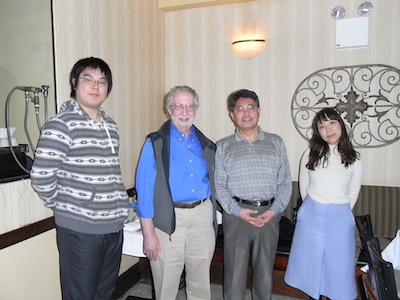【報告】ニューヨーク市立大学(CUNY)道徳心理のワークショップ
ニューヨーク市立大学のローゼンソール教授は、「意識の高階思考説」で名高い心の哲学者だ。ある心の状態が意識的であるのは、たんにその心の状態をもつだけではなく、それについて考えてもいること、つまり高階思考を持っていることにほかならない、というわけである。このローゼンソール教授が長年、心の哲学者や科学者を招いて開催してきた研究会としてCognitive Science Speakers Seriesがある。今回、2015年3月13日に、私たち(信原、片岡、飯塚)は、この歴史ある研究会に招いていただいて、いずれも道徳心理に関わるテーマで発表を行った。聴衆はローゼンソール教授とその学生をはじめ、10名あまりであったが、熱心に発表に耳を傾け、多くの刺激的な質問を行ってくれた。以下、各自の発表の模様を発表者自身により簡単にお伝えする。
信原幸弘 “In defense of motivational internalism”
道徳判断には必ず動機が伴わなければならないのだろうか。それとも、動機なしにも、道徳判断は可能だろうか。本当のことを言うべきだと判断する人は、本当のことを言おうという動機を必ず持つのだろうか。それとも、本当のことを言おうという気はさらさらないが、それでもそう言うべきだと判断することはありうるのだろうか。道徳判断をめぐっては、動機が必ず伴うという「動機内在主義」と、必ずしもそうではないという「動機外在主義」が激しい論争を繰り広げてきた。私は、この発表では、内在主義の擁護を試みた。
本当のことを言うべきだと判断したなら、そうしようという動機を持つのは、当然のことに思える。そう判断しながら、動機をまったく持たなければ、本気でそう判断しているのかが疑わしいだろう。しかし、外在主義者は本気で道徳判断を行いながら、少しも動機を持たない人たち、すなわち「無道徳者(amoralist)」とよぶべき人たちがいると主張する。無道徳者たちは、本当のことを言うべきだと心の底から思っても、そうしようという気にはならないのである。
無道徳者の問題は道徳判断の本性に関わる深刻な問題であるが、私は道徳判断を行為遂行の脈絡で行われる実践的判断と、道徳的善悪に関する信念形成の脈絡で行われる理論的判断に分け、理論的な道徳判断には必ずしも動機は伴わないが、実践的な判断には必ず伴うと論じた。この区別によれば、無道徳者は理論的な道徳判断を行うことはできるが、実践的なそれを行うことはできないということになる。
私の発表に対して、無道徳者が存在するのかどうかがやはり問題となった。ソシオパス(社会病質者)は無道徳者ではないかという考えが出され、彼らの道徳判断は口先のものにすぎないのかどうかといったことが聴衆の間で議論となった。私としては、そのような問題が生じるからこそ、道徳判断を理論的なものと実践的なものに分ける必要があると再び訴えて、答えとした。
片岡雅知 “Courage and its psychology”
「徳への転回」 [The virtue turn] が哲学を席巻している。すでに人口に膾炙した徳倫理学に加え、徳認識論も大きな流行をみせている。しかし既存の研究は徳一般の考察に傾き、個々の徳の特殊性は見過ごされてきた。また、心理学も近年徳への関心を高めているが、両分野はほとんど没交渉である。今回私は「勇気」を題材に、個々の徳の特殊性と心理学への着目が哲学的な徳の一般理論にどう影響しうるかを示した。
哲学者Linda Zagzebskiは、徳とは関連する目的をおおむね実現するものだと論じた。だとすれば、有徳な行為はその目的をおおむね達成すると考えられる。だがこれは私たちの日常的な徳理解に沿っているだろうか? この問いが重要なのは、理論的で人工的な原理を立てず生きられた倫理的思考にフィットするという点が徳倫理の大きな美点だからだ。
ここで、「勇気」の心理学的研究を見てみよう。Cynthia PuryとAutumn Henselは、リスクを恐れずよい行為を試みたが成功した人と失敗した人を実験参加者に提示し、その行為がどのくらい勇敢であったか判断を求めた。すると興味深いことに、行為が失敗しても勇敢さはかなり高めに判断される。つまり私たちは、「勇敢な行為は失敗していてもいい」と考えているのであり、これは「有徳な行為はその目的をおおむね達成する」という上の一般的説明への反例となりうる。もちろん別の実験解釈も可能ではあるが、類似の研究が徳の一般理論を覆しうることは明らかである。よりよい徳理解のためには、理論と実証研究のさらに積極的な対話が求められる。
心理学と哲学の新たな接点を提示した点で本発表は好意的に受け入れられたが、質疑ではいくつかの概念や前提のさらなる明確化が求められた。とりわけ、「おおむね成功」の「おおむね」(=信頼性)についてどのような理論を想定しているかという質問は、ここに議論の多くがかかっている重要な論点であり、一般論に走り十分な回答を用意できなかったことが悔やまれる。さらに議論を洗練させていきたい。
飯塚理恵 “In defense of character virtue against recent psychological criticism”
今回のニューヨーク市立大学(CUNY)のWSは、私を含め3人の研究者がそれぞれ道徳心理学に関する発表を行った。このWSには、WSをオーガナイズして下さったRosenthal先生を始め、CUNYの哲学の院生が多く集まり、活発な議論がなされた。
私の発表は、性格が存在するのかを巡る近年の論争に関するものだった。私達は日常的に、性格に関する様々な語を用いて自身や他者の行動を説明したり予測したりしている。たとえば、すぐ忘れ物をする学生を「彼女は慌てん坊だ」などと言い、よく議論を放棄する祖父に対して「彼は横暴なので、私の言う事を聞かないだろう」などと言うだろう。その際、性格は様々な状況を通じて、一貫したものだと想定される。しかし、状況主義者と呼ばれる哲学者達は、私達の行動が状況を通じて一貫しないことを示す様々な心理学の実験結果に基づき、性格が私達の心の理解のために不適切なものだと主張してきた。一方、倫理学者の中には、私達の目指す「善い人生」とは、賞賛すべき善い性格、すなわち「徳」を培うことであると考える者達がいる(徳倫理学)。徳は善い性格であり、そこでは性格が存在することが含意されているので、性格が存在しないと主張する状況主義と徳倫理学者達は対立している。
状況主義者の「性格(徳)は経験的に不適切だ」という主張が、本当は何を批判しているのかを明らかにすることは難しい。徳は私達みんなの行動を説明したり、予測したりする必要はないが、例えば、ある行為が気前の善い、有徳な行為であるためには、人に善く見られたいからではなく、「相手にはそれが必要だったのだ」とか、「相手がそれを私に求めたから」といった、その徳に相応しい理由を元に行為がなされねばならないと徳倫理家は考えている。もし、私達が倫理的にふさわしい理由に基づいて行為したり、性格を形成したりすることができないということが科学によって示されれば、徳倫理にとって困ったことになる。しかし、状況主義者はここまで強いことを示してはいないし、心理学的に重要な動機付けに関する諸研究は、それが可能だという前提の元でしか成立しないと主張した。
また、状況主義が、結局私達が有徳になることが困難なあり方をしていることを示したと理解するならば、今後このような論争は、科学技術的介入を用いて私達自身をより徳を獲得し易い存在に変えるべきだろうか、というエンハンスメントを巡る論争へと発展するだろうと提案した。
WSの後にはRosenthal先生と学生達で引き続き活発な議論を行うことができた。先生は徳倫理に広く共感し、徳倫理批判への応酬にも強い興味を抱き、激励して下さった。このような機会をいただいたことに深く感謝している。