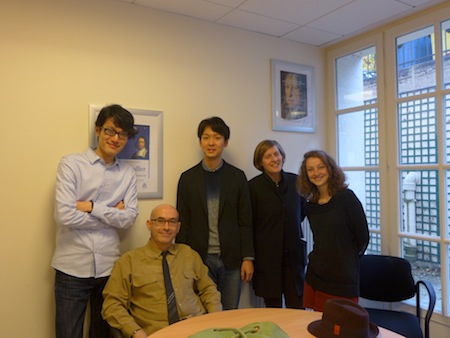【報告】UTCP+ENS共同セミナー"Posthumain, Postanimal, Postmachine"
2014年11月20日に、パリ高等師範学校(ENS)との学術交流プログラムの一環として、ENSのサルトル教室にて、UTCPと久しく連携されているドミニク・レステル教授の指導研究生らとともに「ポスト・ヒューマン」の問題をめぐる共同セミナーが行われた。
20日当日、レステル教授がセミナーに先立って提起した討議の中心テーマは、「トランス・ユマニスム(trans-humanisme)」——テクノロジーの飛躍とともにその生存様態、生存環境を急速かつラディカルに変容させている今日の不安定な「人間」の位相を捉えること、そしてそれに対応する「人文」(ユマニスム)の在り方を考えること——であった。教授はまず、「トランス・ユマニスム」が今まさに進行している現象そのものであり、その速度に思想や哲学は大きく遅れている点を強調された。教授によれば、現状においては、技術的な可能性の飛躍とその現実化のリズムの方がむしろ私たちの思考や想像力の範囲を押し広げている。遺伝子工学やAI、拡張現実といった技術革新がもたらす環境的、法的、経済的な変化に対して、これまでに人文諸科学において蓄積された知のうちの何が動員可能であるかは今のところ未確定であり、さらには人文的知がそうした現実に「抵抗」するのか、「共生」するのか、「協働」するのか、という根本的問いも未決のままである、このように教授はまずセミナーの基調となる問題提起をされた。
続いてこの問題提起を受け、ENSとUTCPから各二名の研究生がそれぞれ研究報告を行い、提出された事例や観点について全員で時間の許す限りの討議を行った。ごく簡単に、各発表を振り返っておきたい。
■Hisato Kuriwaki (UTCP) , « Sexualité et Postsexualité. Perniola lisant Sartre »
まず、栗脇永翔は「セクシュアリティ」という観点から「ポスト・ヒューマン」の主題に取り組むことを試みた。仮に「ポスト・セクシュアリティ」というものがあるとすれば、という出発点からペルニオーラの『無機的なもののセックス・アピール』と、その中で言及される『存在と無』におけるサルトルの性理論を比較検討することで「セクシュアリティ」と「ポスト・セクシュアリティ」の境界を問い、前者に対し後者を完全に後に来るものとしてではなく、むしろその傍らにある「パラ・セクシュアリティ」として理解するパースペクティヴを提示した。(*この箇所のみ、文責は栗脇)

■Anna Katharina Laboissière (ENS) , « Un homme-animal-machine. Le chamane comme figure liminaire du posthumain »
アナ=カタリナ・ラボイジエールは、「テクノ・シャーマニズム」という観点から、60~80年代のいわゆるサブカルチャーに見られる異世界の表象がテクノロジーの発展とともに今日どのように再び取り上げられ、また現実化されているかを紹介した。問題となる「テクノ・シャーマニズム」が具体的にどのような形を取って現れるのかが今ひとつ不明確だという指摘があったものの、「閾的な形象」を求める人々の潜在的動向が、資本化されやすいサイボーグ的なものから、資本化を逃れるシャーマン的なものへと今日移行しているという発表者の分析は、問題となる文化現象の政治的射程を示唆する重要なものだった。
■Sotaro Ohike (UTCP) , « L'animalité contre l'état naturel humain. De la méthode de Bataille »
続いて大池惣太郎が、ジョン・ハーシーのルポルタージュをめぐって書かれたバタイユの「ヒロシマ」論を題材に、バタイユにおける「動物性」とその思考の「方法」の問題に関する発表を行った。バタイユは「ヒロシマ」の表象の中に人間的無関心と動物的無関心という二重のアパシーを分離不可能な形で読み取っているが、そこにおいて「動物性」は、人間/動物を分節する説明的概念としてではなく、他者の生を自己のうちに不可能として二重化する固有の思考の軌跡として現れる。発表者はそれを、一元的な関係論へと向かう思考の自動性に抗するバタイユ固有の「方法」として提示した。
■Ségolène Guimard (ENS) , « Des limites de l'habiter humain. Obsolescence de la distinction érème/ écoumène »
最後にセゴレーヌ・ギマールは、バシュラールの「居住不可能なもの」の定義から出発して、現在それを覆すように「非居住閾(エレーム)」/「居住閾(エクメーヌ)」という区別が次第に無効化している事実を、宇宙空間に至る居住可能性の拡張、生命を非本来的な生態環境へと送り込む様々な実験の事例などとともに論じた。エレーム/エクメーヌの分節の変化は、「人間的に住まうこと」をめぐる私たちの「経験の地平」の変容でもあるが、発表者はそこに、ある種の実験的希望と、一層徹底した生の再回収への危惧が同時に含まれていることを指摘し、発表を締めくくった。
以上のように、共同セミナーで報告された主題は多岐にわたるものだったが、決して散漫な研究発表の寄せ集めとなることなく、むしろ「トランス・ユマニスム」の問題性を多様な観点から討議することに繋がった。それには、この共同セミナーが学会のような時間制限を設けずに行われ、それぞれの報告に十分な質疑応答の時間が確保されたことが大きく寄与していると思われる。適度な緊張感と誰でも自由に発言できる開かれた雰囲気のなか、参加者たちは時間を気にせず問題を深めることができ、結果、活発で充実した共同討議の機会となった。また大きな告知がされなかったにも関わらず、当日少なからぬ出席者に足を運んでいただき、議論にさらなる活気と興味を注いでいただいたことも、各位への深い感謝と共に報告しておきたい。

続いて、滞在中のプログラムの一つとして共同セミナーの翌日から二日間参加したレステル教授のゼミの様子についても簡単に報告を行う。初日のゼミは「トランス・ユマニスム」の先端的事象を、とくにアートと政治の現場から紹介するものであり、二日目は、ニーチェの再読を通じてポスト・ヒューマンの時代における「哲学者」の役割、および「哲学的に思考すること」のステータスを再考する内容であった。
豊富な事例の参照とともに行われた両日の講義は、この報告で仔細に紹介するにはあまりある濃密な内容だったが、そのなかで特に印象深かった教授の言葉に、« Pour penser, il faut pratiquer »(「考えるためには実践しなければならない」)というものがあった。現実の変化を実際にその身で経験し、自分自身を変化させることを通じて思考しなければならないということだが、この言葉は、現在進行中の出来事が私たちの思考よりはるかに先に進んでいるという観点において発されたものであり、大変重たい命題であると感じさせられた。
同時に、この言葉は報告者を別の疑問の前に引き据えるものでもあった。「考えるためには実践しなければならない」という命題は、実践を通じた変化へ積極的に身をさらすことを私たちに命じている。だが、現実の変化とともに私たち自身が変化するとき、「変化」そのものを解釈し、思考するモメントはどこで可能なのだろうか。果たしてこの命題とともに、私たちは起きている事態に対し、「抵抗」や「共生」や「協働」といった言葉が意味を持ち得るほどの距離感とスタンスを維持できるだろうか。そもそも、私に「変化」が生じた後にそのことを思考するのは誰なのか。彼が「思考する」ことを選ぶという保証はあるのだろうか。
こうした疑問の中で想起されたのは、共同セミナーの最後にコメンテーターとして小林康夫先生が発された「無重力の世界に哲学は可能か」という問いであった。小林先生がこの問いを通じて指摘されていたのは、「哲学」が一見普遍性と結ばれた思考の営為であるかのようでありながら、実は「重力」という私たちの物理的、生態学的前提に深く規定された営みである、ということであった。この指摘の射程をここで詳らかにすることは到底できないが、少なくともそこには、ある種の磁場、ないし引力が思考の条件として必要であることが示唆されているように思われる。レステル教授が指摘されるように、現実の出来事の速度に私たちの思考は確かに大きく遅れている。だが、その時差は思考に不可欠なものかもしれず、それどころか固有の磁場が生み出す遅れや隔たりこそ、あるいは思考と呼ばれるものかもしれない、そうした疑問を、滞在を通じて考えさせられることになった。
また同時に、レステル先生の言葉が、「実践」や「変化」を単にオプティミスティックに称揚している訳ではないという点も強調しておかねばならない。そのことを感じさせる印象深い一コマとして、初日のゼミの次のような場面を紹介しておきたい。教授が倫理的に言ってかなりきわどい遺伝子工学を用いたアートの実験例を――それに対するスタンスや判断を一貫して示すことなく――紹介したことに対して、授業の最後に一人の学生がやや苛立たしげに、そうした極端な事例を論じる際に「倫理的」観点が一切問題にされないのはなぜですか、と質問した。教授はそれに対して、その質問の正当性は理解するが、この問題に関して「倫理的」であることが何を意味するのかを自分は知らない、と応答された(後日ゼミ生たちに聞いたところによると、教授はこうした反応を予想し、おそらくは挑発的な意図も持ちながら、極端な事例を列挙されていたのではないかということだった)。
このやり取りは興味深いものだったので、翌日の授業の前に、報告者自身教授に質問を行った。昨日のゼミでも「倫理的」観点のことが問題になったが、「トランス・ユマニスム」の問題系は、現象に対して何らかの批評の足場を持つことを禁じるものなのだろうか、という報告者の質問に対し、教授は次のように答えられた。大規模産業化された畜産、動物実験、暴力的な遺伝子操作などは、言うまでもなく許されるべきではない。自分はそれに反対である。しかし、それは現に起きており、これからさらにいっそう起きていくだろう。たとえば遺伝子産業は原子力産業に比べ設備投資が低コストであるため、世界中に遺伝子操作可能な合法・非合法のさまざまな拠点がすでに無数に存在しており、それを規制するには非現実的なほど膨大なコストがかかる。設備投資と規制の関係を現実に支配しているのはそうした経済原理であり、既存の人間主義的言説はそれを抑止する役に立っていない。機能していない「倫理的」言説を反復するのは安易であるばかりか無責任である。だからこそ、新しい事態に対応した有効な思考を探さなければならない、「考えるためには実践しなければならない」。こうした応答に、ゼミ生たちの矢継ぎ早な質問も加わり、その日は結局、予定された授業時間のほぼ半分が「トランス・ユマニスム」と人文的知の関わりをめぐる議論に費やされることになった。
こうしたプログラム全体を通じて浮かび上がったのは、「トランス・ユマニスム」が思考の営みを固有の重力の場から引き離すクリティカルな問題系であるということである。「考えるためには実践しなければならない」という命題は、そこで一つのダブル・バインド――変化に身をさらさない限り現実を思考することはできない、しかし変化と一致するときそこに思考はない――に曝されているように思われる。レステル教授の学生たちへの応答は、そうしたダブル・バインドのうちで粘り強く思考することの重要性を、まさに実践的に示していた。最後に、二日間を通じて、重要な問題に対し時間を気にせず議論を尽くそうとされる教授の態度、また臆せず積極的に疑問をぶつける活発なゼミ生たちの姿勢にたいへん感銘を受けたことも申し述べておきたい。
そのほかにも書き残したことは多く、本出張は短いながらも多くの学びのある貴重な学術交流の機会となった。このプログラムは、小林先生とレステル先生の多年にわたる緊密な連携と友情の結果として実現されたものである。滞在を通じ、単に組織として連携するだけでなく、個人のレベルで、世界の様々な研究者と持続的な交流を維持することの重要さをあらためて実感させられた。温かく、実りの多い交流の場を準備してくださったレステル先生はじめゼミ生の皆さんに、この場を借りてあらためて感謝を捧げるとともに、このような素晴らしい経験の機会を与えられたことに心より感謝申し上げ、今後の研究の糧としていきたい。
(文責:大池惣太郎)