【報告】P4Eワークショップ:「学校」をめぐる哲学対話(2)
ワークショップ2日目となる8日は、教育関係者だけではなく、様々な参加者が60名ほど集い、「学校」をテーマに3時間の哲学対話を行った。
まず、ウォーミングアップとして、5人1組のグループを作り、「質問ゲーム」を行った。「あなたにとって、学校とは何ですか?」という問いから始まり、グループの中の一人がこれに答え、他のメンバーはその答えに対して次々に質問を重ねていく。このゲームを通じて、参加者ひとりひとりが、自身の学校経験(生徒として学校に通った経験、子どもを学校に通わせた親としての経験、職場として学校に通う教師としての経験など)を次第に思い起こし、それと向き合い始めたように感じられた。「学校」という言葉を聞いたとき、最初に浮かんでくるのは、懐かしさであれ、あるいは嫌悪感であれ、単純な一色の感情だ。しかし、何度も繰り返し問うことを通じて、記憶を呼び覚まし、それについて考えていくうちに、学校という言葉のもつ意味も、それに伴う自身の感情も、多彩なものに変わっていく。

つづいて、「わたしは教師です」「わたしは子どもです」という方々の2つのグループと、「わたしはそのどちらでもありません」という方々の3つのグループ、計5つのグループにわかれて、「学校」をめぐる哲学対話を行った。教師のグループでは、「成績評価をつけない学校は可能か」という問いのもとで、教師が生徒を評価することと学校教育との関係について、対話を深めたそうだ。子どものグループでは、「学校はへんなにおいがする」「でも職員室はいいにおい(お菓子のにおいがするから)」といった、いま彼らが学校の中で感じているさまざまな事柄から対話をはじめ、「どうして先生のことを好きになるのは、きもちわるい感じがするのだろう」という問いについて、探究を深めたらしい。私がファシリテーターを担当したグループは、学校にまつわる様々なマイナスのイメージ(理不尽である、規律が厳しい、多様性を認めない、など)から対話を始めたが、次第に「それでも学校には抜け道があった」「学校という場所は、生徒を見守りつつ放っておいてくれて、それがありがたかった」というような、暖かなイメージに変わっていったのが印象的であった。
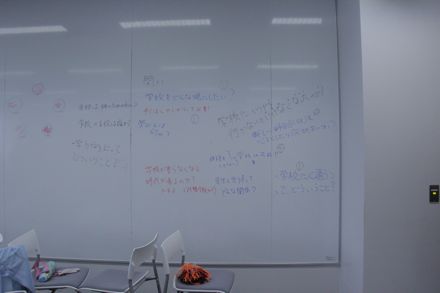
最後に、参加者全員が円になって座り、全員での対話を行った。ここでは、学校ではどうしても「抑圧」されているように感じる、という問題が話題となった。この感覚は、おそらく多くの参加者が共有しつつも、しかしその「抑圧」の正体については、誰しも捉えかねている印象があった。また、その「抑圧」の正体についての考え方が、自分が学校にどのような立場で関わっているのか(教師、生徒、保護者、卒業生など)によって、まったく異なっているようにも思われた。時間の制約により、この問題について十分に考えることはできなかったが、参加者それぞれがこの問題を「おみやげ」として持ち帰って下さったことと思う。

「学校」について哲学するのは難しい。それは、「学校」が制度的・政治的な問題であるからでも、哲学的な問題でないからでもなく、決して自分の子ども時代と切り離しては考えられない問題だからだ。どれほど客観的に、あるいは抽象的に「学校」について考えようとしても、その問題はかならず、「この私はどこから来たのか」「私はなぜ、いま、このようなありかたをしているのか」という問いと、強く結びついてしまう。今回の哲学対話では、こうした難しさから逃げるのではなく、それと付き合いながら、学校について考えることができたように感じた。
2日間のワークショップを通じて、学校と哲学の関係についてじっくりと考えてきたが、両者がどのような関係を結びうるのか、また、学校の中で哲学対話を行うことにどのような意味があるのかということは、いまだよくわからない。ただ、印象的であったのは、2日とも帰り際に(あるいはアンケートで)、「このイベントに出て、元気になりました」という感想が多く寄せられたことだ。(哲学対話のイベントでは、楽しかった、いろいろ考えられた、という感想は多く頂戴するが、元気になった、と言われることはさほど多くない。)なぜ、学校の中で/学校について哲学すると元気になるのか、ということは、案外、次の探究の手がかりになるかもしれない。
(神戸和佳子)






