【報告】2013年『開放時代』東京会議ワークショップ「中国の〈いま〉と人文学―『開放時代』との対話を通じて」
2013年6月15日、「中国の〈いま〉と人文学―『開放時代』との対話を通じて」と題するワークショップが、東京大学・駒場で開催された。このワークショップは、科研費プロジェクト「現代中国思想史構築のための中国知識界言説研究」が中心になって、広州の『開放時代』雑誌、UTCPと共催したもので、『開放時代』からゲストスピーカー3名、コメンテーターに池上善彦氏(元『現代思想』編集長)、羽根次郎氏(愛知大学)を招き、東京大学の村田雄二郎教授の司会で進められた。
最初の報告は、『開放時代』の学術審査委員である陳少明氏(中山大学教授)の「問題としての中国知識人」である。陳氏によれば、中国の「知識人問題」の根源は、革命イデオロギーではなく、社会における知識(人)の需給関係に求められる。中国の近代において、欧米や日本に留学した新式知識人が伝統社会に対する革命の主唱者となったが、その後労農を主体として成功した革命は、決して知識の需要増につながらなかった。このため、共和国成立以後も、知識人は革命で成立した新社会の不満分子、敵対者と見なされた(反右派・文革)。さらに1989年の六四(天安門)事件も、根底には改革開放路線のなかでの同様の矛盾、すなわち高等教育の急速な拡張と近代化の遅延からくる知識の需給ミスマッチがあった。しかし現在、近代化の進展と大学の大衆化に伴って、ミスマッチは次第に解消されつつあり、イデオロギー上の「知識人問題」も消失する趨勢にあると結論付けられた。

続いて呉重慶氏(『開放時代』名誉編集長)から、『開放時代』の年度フォーラムや特集号が、「中国社会主義のマクロヒストリー」という一貫した問題意識に貫かれているという報告があった。現代中国の知識界は、共和国60年史の前半30年(毛沢東時代)と、後半の30年(改革開放)の歴史評価をめぐって、「新左派」と自由主義者が鋭く対立する状況にある。近年の『開放時代』のアジェンダ設定には、この両時期をつなぐ脈絡を探り、思想界の左右の対立を調停したいという願いが込められているのだという。
呉銘氏(『開放時代』現編集長)の「中国知識界における新メディアの活用」と題する報告は、比較的検閲の緩やかなネットメディアが、政治的に敏感なテーマの重要な研究手段になっていることを、いくつかの『開放時代』掲載論文を例に説明するものであった。ただ呉銘氏によれば、娯楽性の強い「マイクロブログ(微博)」がネットメディアのなかで優位を占めつつあり、そこでの討論は互いを罵りあう「情緒化」の傾向が著しい。また多くのネットユーザーは情報の洪水のなかで有益な情報に出合えず、名の知られた一部の知識人が「スター化」しているという。呉銘氏はこうした現状に警鐘を鳴らし、知識人がネットに対して冷静に向き合うだけのリテラシーの必要性を訴えていた。
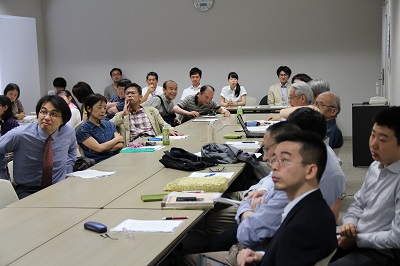
以上の報告に対して、コメンテーターの2人、池上氏と羽根氏はとくに呉重慶氏の議論に触発された点が多かったようである。羽根氏は共和国前半の30年の再評価のもつ意義について、まず国民革命時期(中華民国)の「国民」、共産革命時期(毛沢東時代)の「人民」、改革開放時期の「公民」という主体変遷の見取り図を示し、それをもとに、80年代以降の「公民」概念が中華ナショナリズムに結びつく傾向に対して、「人民」が含意する第三世界や日本との連帯可能性に着目しようとの提案した。また池上氏は、「マクロヒストリー」を日中に共通の思想課題とするための操作として、日本では戦後55年体制が確立されるまでの10年間の混乱期がカギであるとのコメントを行った。すなわち、この時期の工場でのサークル運動や山村工作隊の武装闘争路線といった「隠蔽された歴史」のなかに、戦後をアメリカ追随ではなく、アジア人民との連帯へと転化する可能性が(少なくとも思想的には)あったという議論を展開した。ただ池上氏も留保を付したように、こうした試みの失敗は、日本共産党の路線転換だけの問題ではなく、土地改革などを成功させたアメリカが「解放軍=占領軍」として受け入れられたという側面が確かにある。そしてこのことは、池上氏のように「歴史の皮肉」といって片づく問題ではなく、日本人民の(少なくとも無意識裡の)主体的な選択だったのではという疑問がないでもない。

その後、多数の来場者との間で積極的な討論が交わされた。中国知識人のアイデンティティには世代的な差異があり「知識人問題」の一言では括れないのではないか、大学の大衆化・ネット世論の情緒化の2つの現象の関係をどう見るか、またどう評価するか、共和国60年はそもそも首尾一貫したものと捉えるべきなのか、思想対立の調停より地道な実証的歴史研究こそいま必要なのではないか、といった疑問が出された。他にも、時事的な話題として、『開放時代』は「重慶モデル」をどう考えるのかという問いかけもあった。総じて今回のワークショップは、中国が専門でない場合も含めて、中国知識界に対する鋭い思考を啓発するものであったといえよう。
(文責:杉谷)






