【出張報告】「国際精神分析・哲学学会(ISPP/SIPP)」第三回大会(於ブラジル・サンパウロ)(2)
先には、大会プログラムの一つの軸であった講演にもっぱらスポットライトをあてたので、ここでは、もう一つの軸をなしていた若手研究者による発表について記して報告を補うことにしたい。

昼食に利用したサンパウロ大学構内のレストラン
会期中のどの日も、朝夕の講演に挟まれた午後早くの時間に、2つに分かれた会場で、大学院生やポスドク研究者、大学講師など(サンパウロ大学からの参加者のなかには大学生もいた)4、5名が各人20分を持ち時間として発表するセッションが組まれた。その40を超える数の発表の内容が多岐にわたったことについては、フロイトやラカン、クライン、ウィニコットといった分析家たちだけでなく、マルクス、ニーチェ、アドルノ、レヴィナス、メルロ=ポンティ、ドゥルーズ、ファノン、フーコー、デリダ、フェディダといった名前をタイトルから拾い上げるだけである程度伝えることができるかと思う。また、会場の雰囲気も手伝ってか、発表後のディスカッションで若い研究者がいっそう積極的に発言していたこと、そして、大会が一日、二日と進行し、発表者がお互いをよりよく知るにつれてますますそうであったことは、そこでの議論から得られた専門的な知識や研究上の刺激とは別に、学術的な集まりのいろいろなあり方とその意義を学ぶ機会になったという意味で一つの収穫であった。


UTCPの中期教育プログラム「精神分析のエステティクス」に所属するPD研究員の佐藤朋子、藤岡俊博、共同研究員の澤田哲生による発表については、この報告に続く、各自による要旨の紹介を参照されたい(名前は発表順.また佐藤は、先に報告したSafatle氏の講演にディスカッサントとして参加した)。なお、藤岡と澤田の発表の全文は、先月末に刊行されたUTCPブックレット『精神分析と人文学 問題としての「欲望」』で日本語で読むことができるので、そちらもご一読願えれば幸いである。


ブラジルを含む南米では精神分析が社会に広がり、庶民の生活に根付いている、という話をときおり耳にすることがある。日程上の制限もあって、今回、街に出てそれを実地に確かめることはできなかったが、大会参加者の様子や、朝サンパウロ大学に向かうためのタクシーをホテルのカフェテリアで待つあいだに偶然に言葉を交わした紳士が(あるラカン派の団体のコロックに参加する予定で宿をそこにとったという)分析家だったというちょっとした出来事などから、いくらかはかいま見ることができたように思う——そして、David-Ménard氏がさしたる驚きもなしにその紳士と会話を続けたというエピソードを添えるならば、これはパリの状況についての間接的な報告にもなりうるだろうか。

一日を終え、ホテルに帰るためにバスを待つコロックの参加者たち
最後になりましたが、São Paulo大学のVladimir Safatle先生、Sílvio Carneiroさん、Richard Theisen Simanke先生、Josiane Bocchiさんには、ヴィザ申請のための書類の用意をはじめとする渡航のためのいろいろの準備、サンパウロの滞在——サンパウロ大学のご援助をとりつけて用意してくださったホテルはとても快適でした——、帰国後のUTCPブックレットの作成に際してのやりとり、と、文字どおり、なにからなにまで大変にお世話になりました。心からのお礼と、活気ある大会に参加できましたことについての喜びの言葉とをここに記します。
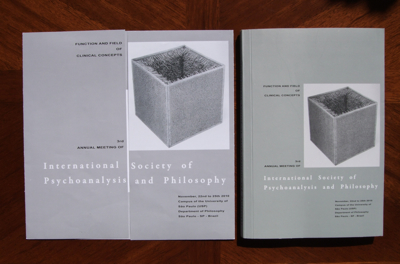
コロックのプログラムとプロシーディング
===
11月22日発表
佐藤朋子「アーカイヴの思考 ジャック・デリダと〈抑圧されたもの〉の回帰の後期フロイト理論 Une pensée de l’archive. Jacques Derrida et la dernière théorie freudienne du retour du refoulé」
要旨
〈抑圧されたもの〉の回帰、つまり、意識から一度追いやられたものが何らかの形のもとで再び現われるという考えは、症状形成や夢、失錯行為を考察する際にフロイトがとる視座の要石をつねになしているものの、それを精密な形で呈示するためのメタ心理学的定式はいくつかの契機を経ながら変化している。W.イェンゼンの小説『グラディーヴァ』をめぐる1906年の論考や1915年の論文「抑圧」などでの模索、1920年の『快原理の彼岸』における反復のプロブレマティクの一環としての再定式に向けた準備ののち、1922年の「夢解釈の理論と実践についての見解」では、抑圧された印象の非拘束性に由来する力が「上昇欲動(der Auftrieb)」の語のもとで概念化される。以降の理論は、その概念を中軸にした再編成に応じて後期理論として区別されえ、またその特徴と射程は、1934-38年のモーセ論にみられるように、抑圧されたかつての印象が新たな印象の到来をきっかけに活性化し回帰するというメカニスムの明確化において際立っている。
デリダは1995年の著作『アーカイヴの病』で、初期のフロイトの仕事のうちに、アーカイヴとアルケオロジーのあいだの絶えざる緊張と同時に、その緊張がしばしば帰着するところとしてのアルケオロジー的競り上げとある生き生きとした起源への立ち戻りの運動を指摘している。また、アーカイヴ化は、フロイトにとって、過去の登記だけでなく約束と将来の運動を作り出す緊張をも条件にしていると述べる。「アーカイヴ」の観念とともにデリダがここで導入しようとしている思想史的観点は、先に整理したメタ心理学の発展と突き合わせることを通じて先鋭化されうるのであって、つまり、そのことを通じて錬成される仮説によれば、後期のフロイトにとって、「生物学的アーカイヴ」の謎は、デリダがかいま見ているよりも根本的であり、起源の探究にも先立ち切迫する問いを課すものだということになる。
(発表後の時間ではとくに「死の欲動」の位置づけに関して質問があり、それに対して発表者は、その問いの重要性を認めたうえで、フロイトのいわゆる生物学的言説を再読するなかで今後それに取り組みうるだろうという見通しを述べた。)
11月23日発表
藤岡俊博「エマニュエル・レヴィナスと「雰囲気」の問題」Emmanuel Levinas et le problème de l’“atmosphère”」
要旨
エマニュエル・レヴィナスは、同時代の他の哲学者たちと比べて、精神分析に対してつねに微妙な距離を保ち続けた稀有な哲学者である。彼はフロイトに対する批判的態度を終生隠すことがなかった一方で、特に後期著作では、「外傷」や「強迫」(さらには「精神病」)のように、哲学よりも精神分析に類縁性のある概念を頻繁に用いているのである。
本発表では、レヴィナスの哲学と精神医学との関係を考察するための一助として、「雰囲気(atmosphère)」という概念に焦点を当てて、レヴィナスと精神病理学との思想的関連を調査した。まず、ミンコフスキーやテレンバッハらのテクストを通して、人間を取り囲む環境としての雰囲気のうちに、身体的かつ心的に人間を保護する側面が認められていることを確認したうえで、良好な雰囲気とともに形成される「親密さ」が、世界に対する人間の内部/外部の関係を可能にする「家」とも密接に結びついていることを、バシュラール、ボルノウ、シュミッツらの議論を通じて示した。これらの研究において、機能不全に陥った雰囲気は主体の内部にまで侵入し、精神的な変調をもたらすことが主張されていたが、興味深いことに、レヴィナスの思想において雰囲気はつねにこの「否定的」な側面を担わされている。本発表では、特に『存在するとは別の仕方で』(1974)の分析を通じて、雰囲気の侵襲によって内面性の崩壊へと至る主体性の様態が、精神病理学が提示する精神病の議論と構造的な類似を持っていることを指摘した。本発表の枠内では、レヴィナスにおけるこのようなメランコリー的主体、同著作に特有の奇妙な一人称的エクリチュールの問題に立ち入ることはできなかったが、暫定的な結論として、レヴィナスが非常に早い段階から雰囲気の主題に関心を抱いていたことを、彼がリトアニア語で発表した唯一の論文と目されている「仏独両文化における精神性の理解」(1933)の読解によって示した。高地/低地の対立に貫かれたトーマス・マンの小説『魔の山』(1924)に潜む雰囲気の問題を抽出したレヴィナスは、生物学的生と死との逆説的な混淆のうちにある「形而上学的雰囲気」を見出し、そこにドイツに固有の「精神性」の観念を認めている。このように、最晩年に至るまで「精神」という語の意味を問い続けたレヴィナスにとって、雰囲気の主題はつねにその関心を捕えて離さなかったものであった。
11月25日発表
澤田哲生「身体的なものから生き生きとした身体へ―メルロ=ポンティの1954-55年講義ノートにおけるドーラ症例の分析をめぐる考察 Du somatique au corps vivant : Réflexions sur l’analyse du cas Dora par Merleau-Ponty dans les Notes de Cours 1954-1955」
要旨
この講義のなかで、メルロ=ポンティは、フロイトが治療にあたったドーラの症例を詳細に分析している。彼は、とりわけ、ドーラの身体面の諸症状(咳の発作、失声、カタル)と、父親の付属物(肺病、咳、K夫人)へ同一化を行使する現象に注目している。身体面の諸症状は、フロイトによると、抑圧された欲望を患者の生活に不意に回帰させる機能を備えている。メルロ=ポンティは、回帰してくるものは、患者の生活のなかで抑圧された「心的な部分」だけでなく、「身体」を伴った「記憶」であると主張する。患者が、抑圧以前に他者に対して取っていた身体上の距離感、態度、位置も、同じく回帰していると、彼は主張するのである。かたや、同一化の現象は、メルロ=ポンティにとって、「間主観性」という概念を考察し直す契機となっている。父親の所有物とドーラの関係(同一化)の背後には、父親への恋着の感情という別の種類の対人関係が含意されている。現象学的な意味における対人関係が、自我と他者の「対化」を重要視するのに対して、同一化のなかでは、自我でも他者でもない「第三者」が、既存の対人関係にすでに挿入されている、とメルロ=ポンティは指摘する。
結論として、精神分析が提供する症例の分析は、現象学の諸概念を考察し直し、発展させる上で、重要な役割を備えているという指摘を行った。メルロ=ポンティを論じた発表者が同じ枠で他に二人いたため、発表後の質疑応答で意見交換を行った。会場からは、それぞれの発表者が提示した、間主観性理論に関する質問とコメントが出された。






