【報告】松本健さん講演会「グローバル時代における大学間の国際関係について―アメリカへの留学の変化から出発して」
2010年7月22日、松本健(財団法人グルー・バンクロフト基金,常務理事)さんをお迎えし、「グローバル時代における大学間の国際関係について―アメリカへの留学の変化から出発して」と題する講演会が開催された。
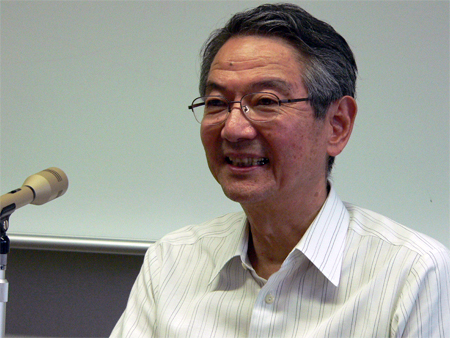
以下、講演後の質疑応答の議論も含めて、本講演の一部を報告したいと思う。
松本さんがまず提示したのは、日本人学生の米国大学への留学生数(学部・大学院合計)減少の事実であった。統計が存在する1954年以降、1997年の47,073名をピークとして漸減して、2009年には29,264名にまで減少している。これは、ピーク時の40%減ということになる。
グローバル時代における日本の大学は、今後ますます諸外国大学との学術交流、そしてなりより競争に加わることを余儀なくされるだろう。日本の大学は、国際的な存在感、競争力が否応なく求められているのである。このような現状において、上記の事実はなにを意味するのだろうか。
松本さんは、この現象の理由として、日本において留学経験が評価されないこと、学生の海外への関心低下、日本の教育環境における海外留学に対する消極性や制度的不備、学生のハングリー精神の減退などを挙げられた。

日本社会においては、学生時代の留学経験は決して有利とはいえない現状がある。たとえば学部での1-2年の留学は、必然的に就職活動の時期に影響を与えることになる。学年が進行しない「休学」扱いで留学した場合、在籍期間が長期化する。かりに「休学」しなかったとしても、留学によって、近年その早期化が問題となっている就職活動(大学3年のうちに就職活動を開始することが多くなっている)に出遅れる可能性が多分にあり、明らかに不利といわざるを得ない。日本の企業の多くが新卒採用を極端に重視していることを鑑みれば、これは日本の雇用事情における極端な年齢主義が大きな壁となっていると考えられる。
また、企業の採用担当者には、留学を経験した学生は日本の企業風土と合わないと、考えられてしまう傾向もあるとのことであった。たとえば、意見をはっきり主張するなどの行為は、調和を乱す行為として敬遠されるという。日本企業の強固な閉鎖性の問題である。

質疑応答の時間では、日本人学生の米国大学への留学生数減少を、学生の海外への関心低下やハングリー精神の減退によって説明することの是非が議論となった。ピークを迎える1997年からの10年程度で、学生の海外への関心低下やハングリー精神の減退が急速に進んだと考えるのは難しい。とくにハングリー精神の減退については、1990年代以前にも多く聞かれた話題でもある。けれども、留学をはじめとして何らかの行動を起こすのは、最終的には個人の勇気と努力が不可欠であることも確かである。
さらに、上記と関連して、日本の教育環境における海外留学に対する消極性や制度的不備についても議論となった。たしかに留学は個々人の勇気と努力が不可欠であることに間違いはないが、けれどもそれを頼みにするのではなく、教育機関とくに大学において制度的に組み込む必要性もあるのではないか、との考えも出された。
留学生数のデータの詳細についても関心が寄せられた。学位取得を目的で正規に米国大学へ留学する学生と日本の大学(院)に在籍しながら休学などして米国大学へ留学する学生では、それぞれに対する制度的な支援の仕方や、その後の就職事情、ライフプランも異なってくる。そのため、戦略的に海外大学への留学を奨励するのであれば、データの詳細な分析が必要との見解も出された。また、留学を希望する学生に対して、留学後の進路などを含めた事前・事後のケアの必要性の論点も出された。
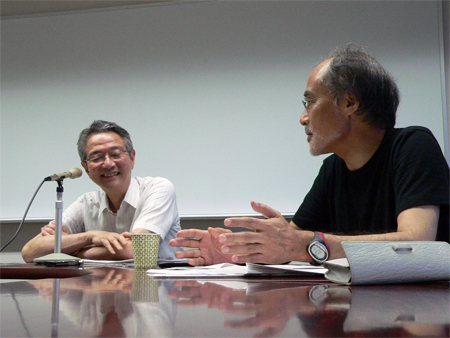
本報告では留学生数減少の論点に絞らせていただいたが、講演では、このほかに、日本および米国大学の組織・制度の違いや、両国における文系・理系の教育研究環境の違いについても、松本氏ご自身の経験を交えながら踏み込んで解説していただいた。
岩崎正太(UTCP・RA研究員)






