【報告】Bernhard Waldenfels 連続講演会
2009年11月18日、および11月20日にベルンハルト・ヴァルデンフェルス氏(ボッフム大学元教授)の連続講演会が行われました。
【第1回目】Phenomenology of Attention
講演要旨
「注意」は西洋哲学の中心的主題の一つではない。しかし、ヴァルデンフェルス氏は「注意」に重要な役割を見出し、この扱いを不当だと考える。本稿では応答的現象学の観点から、注意に重要な役割を帰属させるための諸前提となる注意の現象学的特徴が記述される。

第一節では「注意とは何か」という問いを生じさせる「原事実」が提示された。次節以降の記述は、この「原事実としての注意」に対する応答にほかならない。
まず、注意は受動的側面(パトス)と能動的側面(応答)を持つ「二重かつ媒介的な出来事」である。それゆえ、その能動的側面を捨象する基礎づけ主義と、受動的側面を捨象する構築主義はともに一面的である。また、この二重性に対応して、注意の主体は受動者と応答者に分裂している(第二節)。またパトスと応答という二つの運動は、ある種の時間的ズレ(diastase)によって隔てられている。ただし、両者は異なる出来事ではなく、私たちはパトスの原初的先行性と応答の原初的後続性に同時に直面する(第三節)。
次に、注意の能動的側面、とりわけ、その創造性が詳しく検討される。何かに向くことは何かから背くことを意味する。その意味で、注意とは選択である。しかし、それは先行的に与えられたものから何かを抽出すること(実在論的解釈)でもなければ、あらかじめ注意されたものとして特徴づけられた心的状態が存在する(主観主義的解釈)のでもない(第四節)。注意は、特定の与えられ方や行動の仕方によって成立する。これらは経験の組織化を通じて創造される。この創造は応答を通じて生じる。(第五節)。私たちを触発するものはあらかじめ意味を担うのでも、あらかじめ規則に従うのでもなく、意味や規則は応答のなかで創造されるのである。前意味的・前規則的なものを明らかにするためは応答的エポケー(注意的エポケーはそのなかに含まれる)が必要である(第六節)。

注意の反復は世界と習慣の形成をもたらす。このことは、(1)注意に一次的・革新的形式と二次的・通常形式があること、(2)実践、技術、媒体という中間領域が注意を規定していること、(3)注意が組み込まれている仕方を明らかにするにはphenomenotecniqueによる補完が必要だということを含意する(第七節)。また、注意のパトス的部分と応答的部分が完全な均衡を保つことは滅多にない。それらの配分に応じて、注意は様々な形式を取る(第八節)。

最後に、注意の社会的側面への言及がなされる。何かに注意することは、何かに注意させられることとして、他者の介入によって生じることもある。しかし、他者の注意を喚起すること自体が喚起された喚起である(第九節)。このように社会的なものである以上、注意を倫理的衝動から切り離すことはできない。注意を用いた感覚の働きには、他者の要求を尊敬し、それに応えることへの倫理的衝動(感覚のエトス)が深く携わっている(第十節)。
宮原克典(東京大学大学院総合文化研究科)
【第2回目】The Emergence of the Voice
「声の出現 The Emergence of the Voice, ドイツ語原題Das Lautwerden der Stimme」と題された駒場での第二回の講演が開催された。
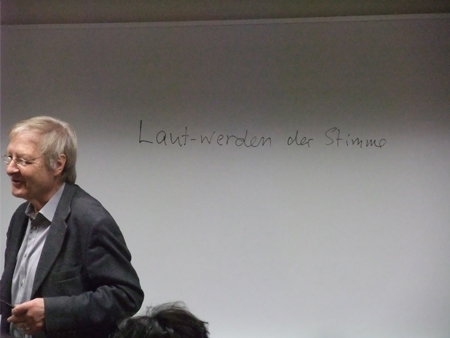
主題は、表題にも示されているように、声である。講演後、ヴァルデンフェルス氏が述べていたところによると、講演の意図は、何よりもデリダの『声と現象』以来、哲学的には貶められてきた声の復権を試みることにあった。もちろん、よく知られているように、ヴァルデンフェルス氏は、ドイツでのデリダ受容を先導し(1997年に出版されたデリダについての論集„Einsätze des Denkens“は、氏とハンス=ディーター・ゴンデックによって編まれている)、親交も深かった人物である。現象学者として世界的に著名なヴァルデンフェルス氏ではあるが、その哲学は現象学的なアプローチを基盤としながら、アリストテレス以来の西洋哲学の伝統だけではなく、同時代の思考をも積極的に引き受け、いまなお新たに展開されているのであり、今回の講演はそのような展開の開陳だったわけである。
声の復権という試みにおいて、ヴァルデンフェルス氏が思考においてまず奪回しようと努めていたのもまた、何よりもその出来事という性格であった。声は聞かれる対象であり、聞く行為の客体である。しかし、そのような関係のうちに声を位置付けることはできない。むしろ、声は、それ以前に出来事として生起する。そのとき考えられているのは、まさに出来事のうちで音は意味を受胎するということである。おそらく、声は、誰かによって聞かれるのではなく、主体や客体なしに「聞こえる、聞こえてくる」という出来事のうちで捉えられるのだ(ヴァルデンフェルス氏は、日本語や中国語の表現が声の出来事性により近いことに触れていた)。

ヴァルデンフェルス氏の考察は、この声の出来事性を正確に捉えるために、声という現象の諸相を辿っていくことになった。氏が強調していたのは、出来事性から派生することではあるが、声という現象が、伝統的な哲学的な二項対立には位置付けられないことである。なかでも、そのようなことから引き出されるひとつの帰結として、声の本質がエコーに結び付けられていることは興味深かった。声は聞かれるそのときにすでに反響なのである。おそらく、この洞察から引き出しうることは大きい。たとえば、異言[Glossolalie]は、声のエコー性の純粋な現れではないだろうか。いずれにせよ、声の現象学的考察は、発生状態の言語――ここでの言語は極めて広い意味で取る必要がある――の新たな考察への通路を開いてくれるように思われた。
この講演は、以下の論文をベースにしている。ご関心のある方はご覧いただきたい。
Bernhard Bardenfels, Das Lautwerden der Stimme, in: Stimme. Annäherung an ein Phänomen, hrsg. von Doris Kolesch und Sibylle Krämer, Frankfurt am Main 2006, S. 191-210.
森田團(UTCP若手研究員)






