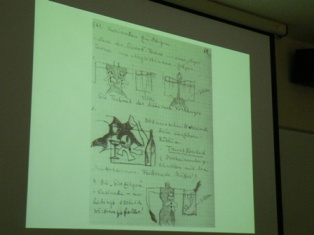【報告】UTCPセミナー+ワークショップ——フランソワ・アルベラ教授(ローザンヌ大学)
2010年1月13日、スイスのローザンヌ大学文学部映画史映画美学科教授フランソワ・アルベラ氏による講演会が、翌14日にはワークショップが行われた。いずれも1920年代ソヴィエトにおけるアヴァンギャルド芸術を、映画を軸としながら領域横断的に検討する内容である。
レクチャー「エイゼンシュテインの「ガラスの家」:フィルムを超えた映画 ――ひとつのプロジェクト」
アルベラ氏は20世紀初頭のソヴィエト映画研究の大家であり、今回はセルゲイ・エイゼンシュテインによる未完に終わった映画『グラス・ハウス』のプロジェクトについて詳細な考察を行った。
【左から浦雅春教授(司会)、近藤学(UTCP/当日通訳)、アルベラ教授】
アルベラ氏は冒頭で、サルトルやヘーゲルらによって議論された「無」という哲学の概念、あるいは映画には常に未完の可能性が付きまとうという映画作家エプスタンの言葉に触れながら、映画がプロジェクトに終わることによって逆説的に作品そのものを超えることもありうることを指摘した。アルベラ氏の考えでは、『グラス・ハウス』のプロジェクトは、プロジェクトが作品を超える最も際立ったケースであるという。
『グラス・ハウス』に関わる資料は1970年代後半から幾度か発表がなされているが、アルベラ氏はエイゼンシュテインの草稿のコピーを入手し、S. M. Eisenstein, Glass House: du projet de film au film comme projet (Presses du Réel, 2009) にまとめている。この著作は『グラス・ハウス』に関する現時点での決定版といえるものである。
アルベラ氏の調査によれば、『グラス・ハウス』の内容は次のようなものであった。キャバレーやコメディ、「警察もの」(犯罪、ギャング)などのシチュエーションが高層建築の中で展開する。高層建築はガラスで覆われているために、これらの状況はすみずみまで丸見えになっているが、それと同時に、ガラスの一部分が反射や煙の充満によって不透明になっているために、一定の距離をもって眺められる。エイゼンシュテインによって描かれた数々の興味深いスケッチを丹念に読み解きながら、アルベラ氏は映画の重要なモチーフのひとつが可視化と異化の共存にあると指摘する。
【アルベラ教授】
さらに、『グラス・ハウス』のストーリーは次のように展開する。「キリスト=詩人」が登場し、グラス・ハウスの中の人びとの放蕩を改めさせようとするものの失敗に終わり、挫折して自殺を余儀なくされる。次に登場した「機械人間」が人びとを扇動して反乱を起こさせ、ガラスの家を破壊へと導く。そしてその廃墟にはコミュニズム建設のモデルであるコミューンの村が建設される。
この作品は社会主義ソヴィエトからの資本主義批判であり、ガラスの高層建築がその象徴となっているのは明らかである。アルベラ氏は水晶宮からシェーアバルト、ミース、ル・コルビュジェにいたる多様な流れのなかでガラス建築が元来ユートピアを志向していたことを指摘し、『グラス・ハウス』が資本主義によって夢見られるユートピアそのもの諷刺となっていると論じる。
さらにアルベラ氏はストーリーのみならず、グラス・ハウスの構造そのものにも着目する。グラス・ハウスは建物の中を見せる舞台装置でありイメージの枠であるが、透明であるために、同時に装置やフレームの限界を廃棄するものでもあるという。アルベラ氏はガラス建築の透明性に映画という制度を超える可能性を見出すのである。
最後にアルベラ氏はグラス・ハウスと問題を共有している同時代のソヴィエトの造形芸術の事例を紹介している。ひとつは、マレーヴィチのスプレマティズム絵画である。グラス・ハウスの持つ固定されたパースペクティヴの破壊に伴う形象の崩壊は、マレーヴィチによる無対象絵画と共通点を見出すことができるという。さらに、ロトチェンコとステパーノワによる写真を用いたブックデザイン『ソ連における映画』をとりあげ、映画の物質性および装置としての映画が強調されていることを指摘した。
今回発表されたアルベラ氏の研究は、資料の発掘とその分析という歴史的、実証的な作業をベースとしながらも、映画のみならず諸芸術に関する博学な知識に裏付けられた想像力を大いに発揮し、グラス・ハウスというイメージが持つ広がりと可能性を明るみにしようとするものであった。エイゼンシュテインのプロジェクト、ひいては映画というジャンルそのものが持つ総合的なイメージを解き明かすには、アルベラ氏のような強靭な知性と対象に対する情熱が要求されるのかもしれない。
今回の講演では、美術、映画、ロシア文化等様ざまな分野の研究者たちが本学のみならず他機関からも集ったため、きわめて多数の参加者を得ることができた。司会の浦雅春氏、通訳の近藤学氏そしてUTCPスタッフの方々に謝意を表したい。
ワークショップ「1920年代と30年代におけるソヴィエトアヴァンギャルドの諸相」
つづいて14日にはワークショップが行われた。このワークショップは1920年代および30年代のソヴィエト文化を、映画のみならず、文学、造形芸術、建築、演劇の分野にわたって検討することにより、ソヴィエト芸術のジャンル越境的な様相を明らかにすることを目的としていた。
【手前からアルベラ教授、石橋今日美氏(当日通訳・東京工科大学)、土田環氏(司会・早稲田大学)】
ワークショップは東京大学大学院博士課程の河村彩氏の報告から始められた。河村氏は、労農通信員運動と五カ年計画という社会的背景に触れながら、1920年代後半から1930年代にわたる文学、映画、写真における一連のドキュメンタリー運動をソヴィエトにおけるアーカイヴ・モメントという枠組みとして提示することを試みた。文学理論家のセルゲイ・トレチャコフと「ファクトの文学」運動、映画監督のジガ・ヴェルトフ、写真家のアレクサンドル・ロトチェンコ、作家のマクシム・ゴーリキーのジャーナリズムの仕事の事例を提示することによって、アーカイヴという概念が当時のソヴィエト芸術に共通するひとつの重要な原理となっていたという見解を提示した。
【河村彩氏】
続いて日本学術振興会特別研究員の本田晃子氏が報告を行った。本田氏は先日のアルベラ氏の講演の主題でもあったエイゼンシュテインの『グラス・ハウス』で見出された問題と、同時代の建築家たちによって計画されたガラス建築における数々の試みとの交差を明らかにした。本田氏は構成主義建築家ヴェスニン兄弟のガラス建築が持っていた演劇性、ル・コルビュジェの高層住宅プランに見られるアメリカ型都市生活の象徴としての摩天楼批判、イワン・レオニドフのプロジェクトに見られる内外空間の分離の克服などの事例を分析した。
【本田晃子氏】
アルベラ氏は、ソヴィエト文化の研究者はヨーロッパでも決して多くはないという現状を考えると、日本で同じ研究を志す者に出会えたことは幸福であると述べてから、二人の発表者に対するコメントを行った。河村氏の発表に対しては、文学、映画、写真という三つのジャンルの「インターセクション」を指摘した上、写真を用いてディスクールが形成される際に事実の歪曲が生じるという問題点、コンセプトとしてのアーカイヴには、過去を志向するものと未来に備えるものの二種類があるのではないかという指摘を行った。本田氏に対しては、セットとしての舞台美術という点において建築と映画は必然的に深い結びつきを持つことを指摘した。さらにクレショフの映画『ジャーナリスト』は、実現されなかったにもかかわらずすぐれた装置や小道具のデザインが行われたことに触れ、映画そのものではなくマケットにも可能性が見出せることを主張した。
引き続き、アルベラ氏による報告が行われた。アルベラ氏はマテリアル、テーマ、ファクトというキーワードによって、1920年代のソヴィエト芸術に現われた様ざまな志向を整理してみせた。アルベラ氏によれば、当時のソヴィエトの造形芸術および文学に関する理論には、マテリアルそのものを重視する側と、作品全体の調和を得るためにテーマを重視する側とに分かれていたという。さらに、ファクトを主張する批評家たちによって、文学にこれまで芸術とみなされてこなかったものが導入され始めたことを指摘した。この芸術内における反芸術を目指す傾向は映画にも見られ、即興撮影などによる「荒々しい」マテリアルの導入が、映画の「表象そのものに孔をうがつ」作用を果たしたと主張した。アルベラ氏の報告からは、先日の講演と同様に、装置として映画をとらえ、それを超える契機を様ざまな事例に見出そうとする志向がうかがわれた。
その後、議論の場は会場にも開かれ、当時のソヴィエト芸術を理解する上で欠かせないリアリズム(社会主義リアリズム)の問題と映画との関わりについて質疑応答が行われた。
映画のみならず、ソヴィエトの芸術文化全般に広く精通したアルベラ氏の意見は、二人の若手研究者にとっても非常に有益なものであったと思われる。本ワークショップの参加人数は他機関の研究者も含めてかなりの数にのぼり、真に開かれた知の現場が実現した。司会の土田環氏、通訳の石橋今日美氏、UTCPのスタッフの方々には深くお礼を申し上げる次第である。
(報告:河村彩)