【報告】国際ワークショップ「人文学と公共性」
2009年9月28日、若手研究者らが中心となって、UTCPと延世大学は国際ワークショップ「人文学と公共性」を開催した。政治、形式、歴史、国家制度という異なる視座から人文学のあり方を問うことで、人文学がいかなる公共空間を創出するのかが浮き彫りとなった。
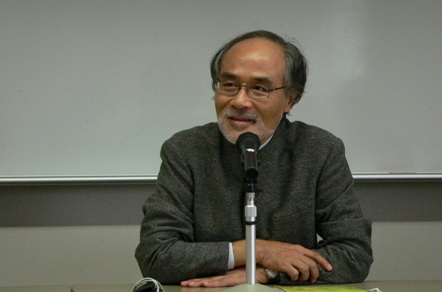
セッション1「人文学と政治」
二つの報告はともに、ハンナ・アレントをキーパーソンとして取り上げつつ、今日の政治状況に対して彼女の理論がもつ射程を明らかにするものであった。

朴晋佑「コンパッションの政治のために」
報告は、アレントにおける「コンパッション(共感)」の概念を手掛かりとして、「スペクタクル社会」とも呼ばれる現代社会のなかで、いかにして「コンパッション」の政治が可能となるかを探るものであった。まず朴氏は、19世紀にとりわけ注目を集めていた「同情(sympathy)」の概念に触れ、それが、他者の苦痛を想像のうちで再現する観客の存在を前提とした演劇的な概念であることを明らかにした。そして氏は、アレントにおける「憐憫(pity)」や「コンパッション」にも他者の苦痛を眺めるという演劇的契機があることを述べたうえで、アレントの議論に即しつつ、「憐憫の政治」の危険性について指摘した。朴氏によれば、人々の苦痛をスペクタクル化する現在のメディア状況は、「コンパッション」を単なる「憐憫」にし、さらには他者の苦痛に対する「共感疲労」さえもたらしてしまう危険がある。朴氏の展望は、メディアやイメージがひき起こす大衆の情緒的な反応が現代政治にとって不可避であることを前提したうえで、そのなかから新たな「コンパッションの民主主義」を作り上げようとするところにあった。

大竹弘二(南山大学)「秘密、嘘、現実喪失――ハンナ・アレントと政治の機密」
大竹は、「秘密」についてのアレントの考察が、今日の社会における権力構造の解明に寄与するものであることを示した。現代政治が秘密主義的な性格を帯びつつあることは、カール・J・フリードリヒを始めとして少なからぬ政治学者に指摘されていたが、アレントはこうした現代の秘密政治の問題を、「嘘」とりわけ「自己欺瞞」についての理論のなかで展開している。だがそこから明らかになるのは、彼女にとって現代の危機は、むしろ秘密の喪失にあるということである。つまり、今日のプロパガンダ政治は、政治的行為の隠された基盤である「事実の真理」(あるいは「過去」)を揺るがし、任意に差し替え可能なものにしてしまうというのである。それは、全体主義体制下の人間についてのアレントの分析に見られるように、行為の「始まり」としての実存(すなわち「過去」の積み重ねのうえにある「いまここ」の「私」)の危機であり、それが容易に交換可能な一つの偶然に還元されてしまうことを意味する。アレントのこの診断は、まさに今日のポスト・フォーディズム社会における脱アイデンティティ化の権力を予示していたと言える。
大竹の報告は、朴氏の報告と同じく、コンパッションの政治の可能性をも念頭に置いている。人が自らのかけがえのない単独性に固執することなく、別のようにありえた自分との交換可能性を意識するときには、苦しんでいる他者の立場への共感もが生じうるからである。それはいわば、「情動の政治」のポジティヴな可能性にも繋がっているのである。朴氏が指摘するように、今日のスペクタル社会のなかで、政治における情動の役割はますます大きなものとなっている。そこからいかにして「コンパッション」に基づく「連帯」を生み出していくか、これはもはやアレントの理論を超えた我々自身の課題なのかもしれない。
(以上文責、大竹弘二)
セッション2「人文学と形式」

So Younghyun「学術的エクリチュールの境界」
Soさんは1960年代以降の韓国で、実証的な文学研究とジャーナリズム的傾向をもつ文学批評との境界設定が議論の対象となり、それが大学制度の確立と相関関係にあったことを指摘する。制度的土台が完備されていなかった解放以前は、文学研究と批評は未分化な状態であり、文学に対するメタ作業は「批評」の名において、文学研究者が行っていたが、解放と戦争を経た50年代に大学内で国文学研究の領域が確立される過程で「実証主義的傾向」が選択され、結果的に、南北分断状況を克服することが切実な問題として存在していたにも関わらず、文学研究はそうした問題に対峙するための主体の現実的実践性よりも、対象の客観的実態をとらえる方向へと動いていった。このような流れの中で、脚注と参考文献を備えた実証的な論文スタイルのエクリチュール形式が支配的なものとなっていき、批評的エクリチュールとの境界設定が問題となっていったのである。
韓国の文学研究史をこのように振り返った後、Soさんは、グローバル資本主義の一元化傾向が強まり、文学研究と批評の主体も資本の論理によって再編成されている現在において、また、インターネットに代表されるニューメディア時代の全面化が進む現在において、文学研究も批評もそれぞれ違うかたちで危機を迎えていると指摘する。資本が文学の価値に判決を下し、インターネットが創作者と読者の直接的な出会いを実現させている点で、批評が存在意義を失いつつあるのに対し、「大学院中心大学」や「学振」などの国家システムによって文学研究の方は巨大な規律化の流れにのみこまれ、ますます論文スタイルのエクリチュールが研究者に強いられつつある。その結果、存立の危機におかれた批評が論文スタイルのエクリチュールの性向を強く帯びるようになってきているというのが韓国の文学研究の現状である。こうした現状を打破するためには、論文スタイルのエクリチュールの有用性を考察しなおす必要がある。つまり、主体と世界のあいだの客観的な距離を前提とし、世界に対する認識可能性を信頼しつつ、そのような認識が特定の形式のなかで具現可能であると信じる考え方(これが論文スタイルのエクリチュールの根底にある)を根本的に見直す必要があるだろう。Soさんの発表は、支配的となっている論文スタイルのエクリチュールが学問的有効性を失いつつあるばかりか、学問の活性化を不可能にする強制力すらもつようになっていることへの批判的意識から生まれたものだといえるだろう。

桑田光平「ロラン・バルトと問いとしてのエクリチュール」
桑田は、ロラン・バルトがデビュー作『エクリチュールの零度』で定義した「エクリチュール」概念、すなわち、作家が自らの時代や社会と関係を結ぶために主体的に選択した「形式」という考え方に立ち返り、そこから、バルト自身のエクリチュールの変遷をたどることで、彼がどのように自らの時代や社会と関係を結んできたのかを概観した。50年代、60年代、70年代とそれぞれ自らが置かれた制度的立場や社会・経済状況の変化などに応じて異なるエクリチュールを選択したバルトだが、そうした形式=エクリチュールの相違にもかかわらず、彼は絶えず社会とひとつの関係を保持しようとした。すなわち、ブルジョワ的価値観に基づいた世論、コンセンサス、ドクサ(社会通念)への抵抗という関係である。バルトはしばしば自らの理論的・政治的ポジションを変える「転位」の人だと言われるが、しかし、それは単に彼の個人的な嗜好によるものではなく、自らの時代・社会に対してもっとも有効的に関係を結ぶための戦略的な選択だったといえる。たとえば記号論に接近した60年代のエクリチュールは一見すると社会批判とは何ら関係のない疑似科学的で体系的なものに見えるが、しかしそれは、記号論という新しい学を社会批判のための道具として洗練させるために必要だったのである。どうすれば「ドクサ」と最も有効的に戦えるのかを考えていたバルトは、極めて柔軟に、その時その時の状況に適したエクリチュールを選択していたのである。以上の考察から、桑田はバルトのエクリチュールの変遷が示しているのは、最終的に依拠すべき「エクリチュール」というものは実体として存在しないということだと結論した。
さらに桑田は、バルトにとってのエクリチュールとは社会と批判的関係を結ぶための「場所」の創造行為だと言い換えた。レイモン・ピカールが文献学に基づかないバルトのラシーヌ解釈に対して憤慨したのは、単にバルト個人がテマティックな読解を行ったからではなく、大学以外の複数の「場所」でラシーヌを読むことができるようになったからではないだろうか。だが、バルトのエクリチュールの変容ないし複数性が示しているように、「場所」は絶対的なものではなく、絶えず新たに創造されなくてはならない。つまり、たえず新しいエクリチュールが産出されなくてはならないだろう。さもなくば、「場所」=「エクリチュール」は固定化し、ルーチン化し、社会や制度に取り込まれて形骸化し、本来持ち得ていた批判性を失ってしまうことになる。したがって、バルトにとっての、あるいは現在の人文学者にとっての「エクリチュール」は、バルトがカミュのエクリチュールに見出していたように、アトピック(非‐場所的)なもの、既存のものではないもの、ここにはないものを目指すものでなくてはならないだろう。紀要論文や学会発表の形式が明確に定められており、その形式にのっとらないものにはアカデミックな価値を賦与しない現在の大学において、バルトが言うエクリチュールを実践することは難しいといえるが、それでも大学は、少なくとも、新しいエクリチュールの創出について、つまり、新しい場所の創出につい思考するための最良の「場所」のひとつだということは言えるだろう。単に論文スタイルのエクリチュールを批判したり、ディシプリン(専門教育)を批判したりするのではなく、そうした制度的強制のなかでしか、「エクリチュール」というものは生まれえないというのが桑田の発表の要点だったといえる。
(以上文責:桑田光平)
セッション3「人文学と植民地主義」
このセッションでは、人文学の危機、あるいは〈人文学の危機〉という表象を、歴史的な視座から考えようとする二つの報告が行われた。

李炳翰(Lee Byunghan)「大衆知性時代の人文学:どこから、いかに、なすべきか?」
李は2008年の韓国で生起した「ろうそく抗争」を、「近代的知識人の社会的消滅」と「それに代わる新しい知性の出現」を象徴的に表現した、「デジタル市民革命」と位置づける。新しいメディアとしてのインターネットは、活字印刷を技術的な基盤とする近代的な知のあり方を、劇的に変化させてきた。サイバー空間に蝟集する、自ら名乗ることのない人々は、それと知らないまま、近代が抑圧した知の諸形態を呼び戻し、ある面では、「1960年代の急進主義者」の夢想を実現してしまっている。人文学/人文学者は、こうした状況と、どう向き合うべきなのか。
李氏が提案するのは、「文体の革命」と「大学の脱構築」というプログラムである。高度に制度化された学術的な文体は、それ自体が、読者を限定し、揺動する思考を馴致する役割を果たしている。であるならば、文の公共性を回復するためにも、〈いま・ここ〉のオーディエンスと共振可能な思考の文体を編み直す必要がある。また、大学が国家とのみ結びつこうとする事態を相対化するためには、大学を地域社会の資産へと再配置する方策を模索するべきだろう。それこそが、「地球的に思考し、地域的に実践せよ」という「グローバル時代の実践倫理」を誠実に生きようとすることに他ならない。

五味渕典嗣「《文学》の生存戦略――日本語文学の「昭和10年代」」
五味渕は、過去の日本語の文脈で、〈人文学の危機〉ならぬ〈文学の危機〉に直面してしまった者たちの経験を、批判的に検証する。主な話柄となったのは、1934-1935年の「行動主義文学論争」である。この論争は、言葉の上での応酬とは別のレベルで、フランスにおける反ファシズム運動への注目と関心を埋め込んでいた。当時の心ある文学者・文化人たちは、自由主義を旗幟に掲げた、広汎な連携を模索していたのである。
では、文学・文化言説の生産者たちは、なぜ有効な協働をなしえなかったのか。決定的だったのは、自らを「純文学」者と規定する書き手たちの、あからさまな危機意識の発露である。自分たちの生産する言説の市場が、総体として縮小に向かう中で、生存の場をいかに確保するか。この問題意識は、「大衆文学」の書き手を、競争相手として周縁化するだけでなく、国家による統制を容認し、その内側で後退戦を戦うという選択を動機づけていくだろう。1930年代後半以後に展開された、「純文学」者による良心的抵抗は、同時に、排除の論理に貫かれてもいたのである。
フロアからの指摘にもあった通り、このセッションでは、「植民地」という言葉は口にされなかった。しかし、二つの報告は、ポスト・コロニアル思想の衝撃を受け止めたのちに、いかに「抵抗」を思考するかという問題設定を共有していたと言える。現在の知の構造変動を深いレベルで肯定し、非=場所としてのサイバー空間を、固有名を持った地域に綴じ合わせようとする李の議論は、技術決定論に陥る危うさをはらみながらも――類似の指摘はフロアからもなされていた――そこに、「資本主義に取って代わる対案的秩序の種」があることを見逃してはならない、という発想を貫いていた。また、自らも知的・文化的な権力装置にとってのインサイダーであるという自覚を踏まえた五味渕の論は、国家との交渉による内在的な抵抗は、例えば三木清の実践が抱えた危うさと紙一重であることに注意を促すものだった。
生存の危機の自覚に駆動された思考は、論者にとっての〈いま・ここ〉から出発し、そこに防衛線を設定していく、近視眼的な後退戦に陥りがちな傾向がある。それを避けるためには、歴史的なパースペクティヴが不可欠であろう。かつて鶴見俊輔は、「前代の走者が迷い、つまづいたその地点こそ、後代の走者にとっての最も実りある思索の出発点となり得る」と書いた。対抗的実践にとって重要なことは、過去の単純な反復を、いかに切断していくか、ということである。そして、現在生起しつつある事態の中に、わずかであれ潜在する未来への希望を、注意深く鍛え上げていくことである。
(以上文責:五味渕典嗣)
セッション4「人文学と国家制度」

KIM Hang(高麗大学)「国家と人文学、何も返さない贈与:HK(Humanities Korea)のケースから」
研究者(とりわけ若手)の不安定な雇用状態にみられるように、人文学の危機は生計型パラダイムで論じることが重要である。教育研究の内実、制度、歴史などの観点ではなく、研究者の「生活」実態に即して人文学の現状を分析し、人文学と国家の関係変換のための試金石を模索する必要がある。韓国では一方で、産業界による大学への影響力が拡大し、新自由主義的論理でもって批判的思考を圧迫している。他方、1998年の経済危機以後、社会批判的な人文社会系の言説はさまざまな形で大学制度外で分化し、教育研究機関が自主的に設立されてきた。ただ、産業界も現場の人文学活動もともに、人生の意義を究明する知に従事するがあまり、批判的な「毒」を失っているとKIMは診断する。彼は人文学を「言語と歴史の総体の記録」とシンプルに規定し、法的責任とは異なる仕方で、国家と人文学の批判的関係を問い続けるべきだと結論づけた。
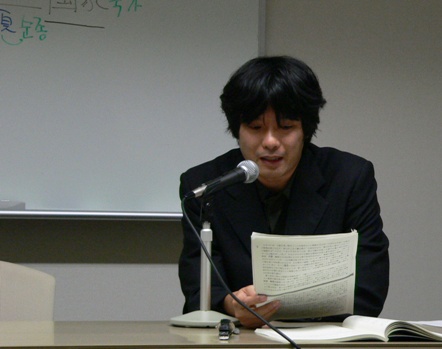
西山雄二(UTCP)「国家と人文学――「新しい教養」の行方」
日本の大学における人文学の現在の状況は、1991年の大学設置基準の大綱化に大きく起因する。文部行政のみならず、産業界からの要請によって、ポストフォーディズム社会に役立つ「新しい教養」が求められるようになった。従来の専門教育と教養教育が効率的に一元化されて構想される「新しい教養」は、自己責任を遵守する独創的で柔軟な主体性の形成を目的とする。「新しい教養」は近年の国民教育の復活の流れとも深く関係しており、それゆえ、大学における人文学の営みは新自由主義と新国家主義の狭間に置かれているといえる。発表ではこうした「新しい教養」を大学とその外部の関係、大学内部の変化から分析し、その将来的な展望を人文学の視座から模索し、①「型」の習得するためのテクストの読解、②真理探究におけるフィクションへの権利の確保、③自己形成ではなく他者の教養との共鳴としての教養、といった論点を提示した。
最後のセッションだけあって、質疑応答は白熱し、「評価をどう考えるべきか」「国家との関係において大学とは左翼的なものであるのか」「フィクションの権利の危険性をどう考えるのか」といった質問が相次いだ。なかでも、「日本でも韓国でも一部の大学のみが国家から資金援助されて、残りの大多数の大学や学生は貧しい状態で喘いでいる。この格差を私たちはどう考えるのか」という問いが印象的だった。大学論に必要なことは、大学が多種多様な現実で構成されていることを自覚し、モノローグ的な「私の大学論」の誘惑に陥らないことである。大学に関係する者はまず自分の限定的な立場を自覚することで、大学を批判的な公共空間として創造することができるだろう。

(文責:西山雄二)






