【報告】アラン・M・リュー連続講演会 「今日の技術の問い」
2009年6月5日と7月3日の二日間にわたって、リヨン第3大学のアラン=マルク・リュー(Alain-Marc Rieu)さんによる連続講演会「今日の技術の問い(The Question of Technology Today)」が開かれた。

リューさんの専門は哲学、ヨーロッパ思想、科学技術社会論であり、とりわけ「知識社会」という概念を用いて近代化や産業社会の構造を研究している。リューさんは東アジアとりわけ日本にかんして造詣が深く、フランスの高等師範学校(Ecole Normale Supérieure)の東アジア研究所のリサーチフェローもしているほか、過去にも駒場に1年間滞在するなど、かなりの日本通だ。今回のリューさんの来日は中央大学の中川恭明先生の招聘により実現したものであるが、UTCPでも連続講演会を開催していただいた。
UTCPでは現在、先端教育プログラムのひとつとして「技術哲学セミナー」を行っている。今回のリューさんの連続講演会はこの「技術哲学セミナー」の一環として行われた。
技術哲学は1980年ころからアメリカの哲学者を中心に論じられてきた。Paul Durbin、 Carl Mitcham、 Larry Hickman、 Don Ihde、 Langdon Winner、 Andrew Feenbergといった技術哲学の代表的研究者を挙げることができる。こうした20世紀末の技術哲学の状況に大きな影響を与えたのが、社会構成主義である。技術とは本質的に社会とのかかわりにおいて為される人間の営みであるという技術観の導入は、技術哲学の「社会的転回」と言うこともできるだろう。しかしながら、技術哲学が社会的転回を経て、さらにどこに向かっているのかは依然として不透明な状況にある。すなわち、哲学的反省はいまだ成熟していないとも言えよう。わたしたちの日常生活はさまざまな技術に囲まれおり、わたしたちは近年の急速な技術の発展の恩恵を受けて暮しているにもかかわらず、科学哲学に比べても、またそのほかの哲学に比べても、「技術哲学」はそれほど注意を払われていない領域にとどまっている。
こうした状況を踏まえて、わたしたちは技術哲学を新しい仕方で展開する必要を痛切に感じている。わたしたちの主要な関心は「現在の科学技術のあり方と社会のあり方にそくした技術哲学の構築」である。このようなわたしたちの技術哲学へのアプローチをリューさんも共有している。6月5日の連続講義第1回目の冒頭でリューさんは「現在の技術哲学の問いとは、科学や技術が社会の展開のなかでどのような位置づけを持っているのか、ということだ」と述べた。
リューさんによると、技術を論じる際には常に2つのアプローチを念頭に置かないといけない。哲学的アプローチと経済学的アプローチである。リューさんの基本的スタンスはこの2つのアプローチは本質的に相補的なものであり、そのどちらかが欠けても議論は不完全なのだ。
技術にかんする哲学的アプローチにはすでに長い伝統がある。それは毀誉褒貶の歴史だ。たとえば、アリストテレスによれば、人間の魂の活動のなかでもより低次のはたらきにポイエーシス(制作)があり、そのポイエーシスにかかわる知識のあり方がテクネー(技術)である。テクネーはエピステーメー(真理や神といった必然的な存在者の認識にかかわる)より、いわば「劣った知識」とみなされた。その一方で、たとえばハイデガーは技術をわたしたちの世界が今このようなしかたで存在することの根本にかかわるものだと考えた。そうしたハイデガーの技術観は技術を誇大視し、技術によって私たちの世界が決められていると考える、技術決定論である(こうしたことに関しては村田純一『技術の哲学』岩波書店、2009年を参考にしていただきたい)。
また、技術にかんする経済学的アプローチとは、科学技術政策を含め、あらゆる技術のあり方は経済的あるいは社会的状況に依存する、という技術にかんする社会構成主義を基本とする。こうした社会構成主義は1990年代に非常に盛んになった。
リューさんによると、繰り返しになるが、こうした哲学的アプローチと経済学的アプローチの両方が技術論には必要である。わたしたちは、技術哲学が社会構成主義を経てさらにどこに向かっているのか、という今後の技術哲学の展開に非常な関心を払っているが、リューさんのアイデアはその問いに回答への道筋を提示するものである。具体的なその道筋は第2回目の講義で明らかにされるが、それはもちろん単にハイデガーなどの技術哲学を復活させて、経済学的アプローチと哲学的アプローチのバランスを保とうというものではない。哲学的アプローチをもう一度組み立てることで、経済学的アプローチをそのなかに包摂していこうという、かなり大胆な試みなのである。
(以上、中澤栄輔)
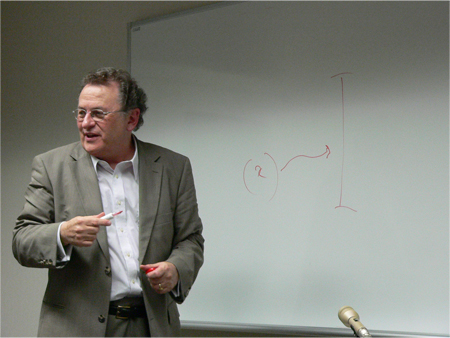
連続講演会第2回目は「技術の形而上学から技術の人類学へ」という副題が付され、技術開発や技術革新に関して現在支配的である経済学的な観点からの説明に対して、われわれはどのように対抗的・批判的な枠組みを確保しうるのかという問いが議論された。

リュー氏はこの問いに対して、ある文化圏における技術発展の形而上学的条件に関する考古学的分析を行うことから出発する。リュー氏が「形而上学」と言うとき、そこではフーコーにおける「エピステーメー(episteme)」あるいはレヴィ=ストロースにおける「ミソロジー(mythology)」が念頭に置かれている。すなわち、技術の形而上学とは、技術を、何らかの手法や装置としてではなく、ある種の「知識」――ある固有の編成様式を備えた言説や表象の集合――として捉えた上で、特定の文化圏における技術=知識の発展をその歴史的条件にまで遡って特徴づける分析的方法論である。
その一例として西欧における技術的発展に対して考古学的分析を施すことで、リュー氏はその固有の発展様式を可能とした「形而上学的階層」として次の四つの層を析出する。第一の層は「身体化された暗黙的知識としての技術」、第二の層は「自然から峻別された人為としての技術」、第三の層は「自然の模倣としての技術」、第四の層は「応用科学としての技術」である。リュー氏によれば、これらの形而上学的階層は、合理的に再構成された歴史記述において見出されるものであるともに、現在の西欧における技術=知識を可能性の条件というレベルにおいて編成しているものでもある。すなわち、これらの階層は西欧における技術の発展過程を説明するとともに、その現在まで続く固有の編成様式を特徴づけるものなのである。
次に、以上の考古学的分析を踏まえ、リュー氏は二十世紀のフランスにおいて出現した「技術の人類学」という学問動向の分析を行う。リュー氏によれば、技術の人類学という学問動向には、技術の考古学において析出された形而上学的前提が明確に表現されている。そのなかでリュー氏が着目するのが、ベルトラン・ジル(Bertrand Gille)の「技術システム」およびジルベール・シモンドン(Gilbert Simondon)の「技術の内的論理」という概念である。これらはともに、西欧において、技術が政治的・社会的な統御を失い、それ自身の論理に従って自律的に運動しはじめるそのメカニズムを捉えるものである。
リュー氏がこうした新たな分析枠組みを模索するのは、技術の標準化による技術発展の画一化という現状を相対化し、特定の文化や社会の在り方に即した技術発展の様式を構想するためである。リュー氏の技術哲学は、人文学が社会に対して抵抗の一手段を提供する可能性を示唆するものとして、技術に対する理論的考察を展開するうえで大いに参照されるべきものであろう。
発表後の質疑応答においては、主に使用された概念や論理の流れについて活発な議論が展開された。
(以上、小口峰樹)







