【報告】「共生と文化領域―東洋におけるフランス哲学」
2009年3月30日、台北の台湾中央研究院にて国際シンポジウム「共生と文化領域――東洋におけるフランス哲学」が開催された。
その主旨は、28-29日に台湾大学で行われた国際シンポジウム「東西哲学の伝統における「共生哲学」構築の試み」を引きつぐものである。先立つ台湾大学での討議は、「共生」という(日本語の)概念がもつ歴史的経緯など、この概念をあらためて厳密化することから始まったが、日本語・中国語・英語・サンスクリット語が飛び交うなかで、それらの翻訳空間のただなかで思考するという試みこそが、「共生哲学」の構築現場そのものであったと言えるだろう。

続く中央研究院での一日もまた、共生哲学のいわば「現場性」を体感させてくれるものであった。そのテーマは、「東洋」において「フランス哲学」がいかに「受容」されてきたのかといったスタティックな問いではない。もっとダイナミックに、フランス哲学から得られたインスピレーションを、東洋の「文化領域」をめぐる考察のなかに、いかに織り込みなおすのか(とくに、第二セッションでの「中国哲学」のアクチュアリティをめぐる問題提起)。そして、東洋に住まいながら、かといって東洋的世界観といったものをナイーブに差し挟むことなく、いかに、ひたすらダイレクトに、フランス哲学のオルタナティヴな読みを切り開くのか。この日、すこぶるマルチリンガルな状況のなかで、我々は皆、高い集中力をもって「共に考え=生きる」ことを追求した。
中央研究院は、大学教育とは一線を画して、最高水準の研究活動に専念するための組織である。繁華街に隣接する台湾大学とは異なり、市街からしばらく車を走らせたところに孤立しているため、日本で言えば、筑波の大学都市のような立地を思わせる。国家機密に関わる研究も行われているとのことで、厳しい警備がなされていた。(以上、文責:千葉雅也)
第一セッション 司会:黄冠閔
午前の第一セッションでは、中央研究院の黄冠閔氏の司会のもとで、大橋完太郎(東京大学)とナヴェ・フルマー(UTCP)が発表を行った。
大橋完太郎
Toward a New Media-aesthetic Theory: an Interpretation of the Encyclopedic Ideal of Diderot

大橋の発表は、フーコーの『言葉と物』に示された古典主義の百科全書概念には収まらないダランベールとディドロそれぞれの「百科全書」理念を詳述し、ツリーとマップ、あるいは動くタブローといった知識の布置の概念や表象と実在の関係とが再考に付された。この発表では、『百科全書』に内在する知の共存原理であり様態でもある「編集知」の概略を明らかにし、「百科全書」という理念がドゥルーズ&ガタリのリゾーム的な知と共鳴する部分を浮き彫りにしようと試みた。続く質疑の中では、知をマッピングする「権力」の問題、あるいは、異なる理念を調停する具体的な策略、あるいは、それらをより包括的な視座に置く指摘として、知と主体とが構成する「隔たり」の論理的・倫理的な位相が問題とされた。
Naveh Frumer
Sovereignty and Potentiality: Butler and Derrida on Agamben

続いてナヴェ・フルマーは、アガンベンが著書『ホモ・サケル』内で展開した「剥き出しの生」という例外的生権力の概念を、デリダとバトラーの思考をもとに批判的に吟味することを試みた。フルマーは、アガンベンの歴史的実在に対する扱いと、主権に対する哲学的考察が撞着することを指摘し、アガンベンの試みを歴史的潜在性に関する抽象概念として取り上げるべきであると主張した。アガンベンの理論には、デリダが言うところの「ダブル・バインド」、すなわち理論的な潜在性といった形のもとで歴史を否定する「脱−政治化」作用がリスクとして機能しているのであって、そのリスクを批判することから政治哲学的であり同時に政治的でもある思考の賭け金が準備されるという指摘がなされた。哲学的であることと政治的であることの妥協しがたい対立と調停の可能性をめぐって、次の発表者である何氏との間に緊密な議論の応酬があったことが印象深い。
第二セッション 司会:中島隆博
午前の第二セッションは、中島隆博(UTCP)の司会のもとで、Fabian Heubel氏(中央研究院文哲所)と楊凱麟氏(中山大学哲学所)の発表が行われた。
Fabian Heubel(何乏筆)
Des enjeux d'une critique « transculturelle » à partir de l'œuvre du dernier Foucault

この発表では、文化的に異なる西洋という領域から形成された知の様態から、どのようにして近代中国といった領域に対して有効な視点を供与できるかという点に関しての浩瀚な考察が行われた。Heubel氏はニーチェの系譜学的な方法の中に民族中心主義を乗り越える視点を見出し、それがフーコー的な方法へと引き継がれた経緯を詳細に追いかけ、フランソワ・ジュリアンやジョエル・トラヴァールといった論者が今日中国思想に見出すに至った「外の思考」の可能性を吟味・指摘する。氏は西洋語の内在的な条件として既に外部への超出の契機が存在していたことを指摘し、近代の「中国語」の哲学の中にも、そうした超出の可能性の条件を見出せるのではないかと結論づけた。
楊凱麟
Géophilosophie transgressante et nomadologie sur place: pour une étude de la philosophie française à la langue chinoise

楊凱麟氏の発表は、ドゥルーズ、ドゥルーズ&ガタリ、そうしてフーコーの思考的営為を内在的な母語を異化する理論として読み解こうという野心的な試みだったと言える。ドゥルーズの「脱領域化」の議論をヴァナキュラーな言語によって行われるべき哲学の理論的骨子として読み替えていくことを通じて、中国語で哲学するという「哲学的エートス」の意義を積極的に打ち立てることを提言していた。
両者の発表はともに、台湾における「中国語によるフランス哲学」のアクチュアルな状況を示しているのみならず、それが新しい中国語による哲学の展開を予感させるものであった。こうした論点は、たとえば哲学の「翻訳」という比較哲学的な観点一つをとってみても司会の中島氏がこれまで提示してきた様々な論点と呼応するものであり、三者の間にはまるで休憩や疲労をいとうことがないかのような意見の交換がその後も続けられていた。
(以上、文責:大橋完太郎)
第三セッション 司会:龔卓軍
午後の第三セッションでは、龔卓軍氏(台南藝術大学)の司会のもと、千葉雅也(UTCP)および星野太(東京大学)がそれぞれ発表を行った。
星野太
On the Differend: Lyotard, Habermas, Rancière

本発表において星野は、リオタールにおける「争異(differend)」を政治哲学的な概念として練り直すという目的のもと、リオタールの著作『争異』(1983)をめぐる以下の二点について考察した。すなわち、リオタールによるハーバーマス批判、およびランシエールによるリオタール批判である。まず前者について言えば、『ポストモダンの条件』(1979)に顕著に見て取れるように、リオタールはハーバーマスの討議理論を厳しく批判している。しかしその一方でリオタールの「争異」は、異なる「文(phrase)」同士の共約不可性のみをいたずらに強調するのではなく、文同士の「新たな連結」の可能性を重視していることがわかる。また後者については、ランシエールによる痛烈なリオタール批判の背後に隠れた両者の連続性を指摘することで、「争異」(リオタール)と「不和」(ランシエール)を貫く美学的=政治的性格を浮き彫りにすることができる。本発表は、以上のようなリオタール、ハーバーマス、ランシエールという三者間の「争異」を整理することによって、リオタールの「争異」概念そのものがもつ可能性を再考することを試みた。
千葉雅也
The Limit of Stupidity: Animal Otherness Suspended between Deleuze and Derrida
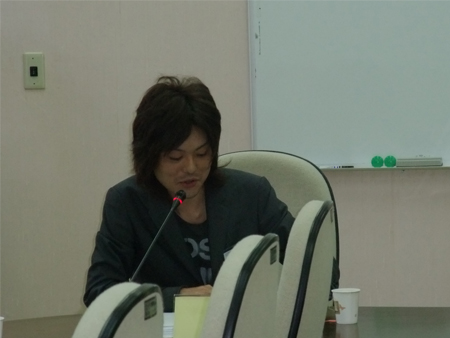
本発表において千葉は、デリダによるドゥルーズ読解を経由しつつ、ドゥルーズにおける「愚かさ(bêtise)」という概念の可能性を浮き彫りにしてみせた。『差異と反復』(1968)において提示されたドゥルーズの「愚かさ」という概念は、デリダが指摘したようにある種の人間中心主義を孕んだ概念であり、そこでは動物性ないし「動物の愚かさ」が排除されている。しかし70-80年代におけるドゥルーズ=ガタリの著作は、「ダニ」をはじめとする動物の限定された世界をむしろ肯定的に論じている。さらに言えば、『差異と反復』で提示されたような「人間の愚かさ」をめぐる議論が、ハイデガーの議論と同じく人間の「(準)全体性」を強化してしまうのに対し、『千のプラトー』で展開されるような「動物の愚かさ」をめぐる議論は世界の多様性そのものを開示する。結論として千葉は、こうした「動物の愚かさ」がもつ政治哲学的な射程に言及した。すなわちそれによれば、ドゥルーズにおいて思考の可能性であり不可能性でもある「愚かさ」は、共生の可能性でもあり不可能性でもあるのである。
質疑応答の場においては、司会の龔卓軍氏および会場から様々な質問が投げかけられた。星野の発表については、とりわけ『争異』においても言及されていたアウシュヴィッツの強制収容所をめぐる問題、およびそれをめぐるランシエールのリオタール批判が主要な争点となった。千葉の発表に対しては、ドゥルーズのテクストの内在的解釈をめぐるものから「動物性」のステータスを問うものまで、幅広い問題が提起された。本セッションにおける二人の発表は、リオタール、およびドゥルーズという20世紀のフランス哲学の読解を軸としつつ、それをより広い政治哲学の問題へと展開するものであったと言える。
(以上、文責:星野太)
第四セッション 司会:揚凱麟
最後のセッションでは、揚凱麟氏の司会のもと、揚婉儀氏(東海大学哲学系)と張國賢氏(南華大学哲学系)が発表を行った。
揚婉儀
Une philosophie pour l'Humain: Sage raisonnement fondé sur la pensée d'Emmanuel Lévinas
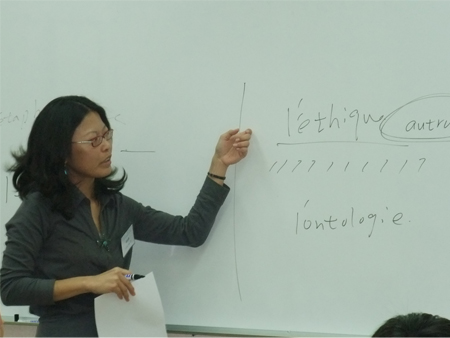
レヴィナスの哲学によれば、「人間」の「実存」は、他者の「顔」への対峙によって、緊迫した「倫理」を問われている。他者との「共生」において「実存」することの倫理は、「私」ひとりの「存在論」よりも根本的に、「人間」の「人間性」を支えている。このようにレヴィナス哲学のエッセンスを示してくれた揚婉儀氏に対し、司会の揚凱麟氏は、ドゥルーズ+ガタリ『千のプラトー』(1980)における「顔貌性」(visagéité)の概念を使いながら、「顔」が政治的な表象となり、暴力的に作動する危険性について言及した。これに対して揚婉儀氏は、レヴィナスにおける「顔」とは、特異的なものとしての他者の現れであり、「顔貌性」の暴力には決して回収されず、それに抵抗しつづける顔であると強調した。これを受けて千葉は、「動物」や「鉱物」など「非人間的なもの」の「顔」について考える可能性を問うた。しかし揚婉儀氏によれば、レヴィナスの倫理は、あくまで「人間性」のそれである以上、非人間的なものは主題化されないという。おそらく、この論点において、レヴィナス哲学とドゥルーズ&ガタリの哲学は、大きく対立しているのだろう。この討議によって、「人間的顔」の倫理から出発しつつ、さらに「非人間的顔」――そのようなものがあるとすれば――の倫理について考えてみるためのヒントが得られた。
張國賢
S/M et la pensée du temps chez Deleuze

張國賢氏は、ドゥルーズの『ザッハー=マゾッホ紹介』(1967)を「時間」の哲学へとつないでみせた。張氏によれば、これらの性倒錯において働いている「死の欲動」を、ドゥルーズは、「空虚な時間の形式」として再定義する。ドゥルーズによれば、「私」は、「出来事」の時間によって横断され、「ひび割れた」ものであり、たえず他なるものへの「生成変化」をつづけている。精神分析は、「欲望」というものを「欠如」を埋めるための営みと見なすが、ドゥルーズそしてガタリの場合は、そうではない。私に穿たれるのは、埋められるべき「欠如」ではなく、出来事のたえざる到来という「ひび」なのである。このように張氏は、ドゥルーズ哲学における精神分析批判のコンテクストを明示してくれたが、時間の都合上、「サディズム」と「マゾヒズム」の差異をめぐる解釈には踏み込まなかった。張氏の読みはひじょうにクリアなものだったが、千葉は、欠如の論理を核とするラカン主義が(1960年代後半の)ドゥルーズへと及ぼした影響は無視できないと指摘した。しかし張氏は、ドゥルーズの精神分析批判を、ガタリとの共同作業を含めて、大きなパースペクティヴでとらえようとしている。
打ち上げの席で、揚凱麟氏から、台湾そして中国語圏でのドゥルーズ研究についてお話を伺った。ドゥルーズの著作は、フーコーと並んでよく読まれてはいるが、翻訳はあまり進んでいないとのことである。台湾では、翻訳の仕事が、研究者のキャリアとして重視されないという事情があるらしい。『哲学とは何か』などはすでに訳されているが、主著『差異と反復』を中国語にするのは難しいだろうとのことである。

(以上、文責:千葉雅也)






