【報告】ワークショップ「人文学にとって現場とは何か?」@研究空間スユ+ノモ(ソウル)
2009年2月15日、ソウルの研究空間スユ+ノモにてワークショップ「人文学にとって現場とは何か」が開催された。〈スユ+ノモ〉のみなさんの入念な準備と配慮のおかげで、実に楽しく素晴らしい内容の会となった。
午前は板張りの広い空間で伝統的な木の机で、午後はセミナー室で椅子に座って議論をおこなった。午前の部の部屋は大変居心地がよく、空間配置によって話しやすい雰囲気が醸成された。部屋の隅にはお茶とお菓子、ミカンが並べられ、基本的に飲食しながらの議論となる。
「研究空間スユ+ノモ」によるブログ報告(韓国語) ⇒ こちら

I. 歓待の倫理
本セッションは、UTCPのメンバーである我々五人の、二日間におよぶ韓国での研究交流活動の開始点となるものであった。座布団に座りながら、60名近くの参加者とともに、会は終始和やかにそして活発に進められた。〈スユ+ノモ〉関係者の話によれば、参加者のうち少なくとも半数は〈スユ+ノモ〉を利用していない方々であったという。また、〈スユ+ノモ〉での通常ゼミで、私たちのワークショップへの参加聴講へと振り替えてくれたものもあった。午後になっても参加者の数はほとんど減らなかった。日本から無名の研究者が来て行うワークショップがそれだけの数の人に訴えかけたことは単純にうれしかった。
本ワークショップは「人文学にとって現場とは何か?」と題されてはいるものの、これは厳密な意味での統一的テーマではなかったので、第一セッションでこの問題が主題的に論じられたわけではない。「歓待とは何でないか?」という私の発表タイトルを受けて、李洙榮(イ・スヨン)氏も歓待をテーマとして取り上げてくださった。二人が別様に、私はドゥルーズから基本的着想を得ながらクロソウスキーに即して、李さんはデリダの脱構築から一歩前に進むべくフーコーに依拠しながら、歓待を論じた。とはいえ、このセッションは、確かに、「人文学の現場」と呼んでもよいであろう何かを感じさせる機会だったように思う。
國分功一郎(高崎経済大学)
「歓待は何でないか?―クロソウスキーとドゥルーズから考える」

國分は、クロソウスキーの『歓待の掟』を読みながら、歓待(hospitalité)と寛容(tolérance)を区別する必要性について話した。どちらも、「他者を受け入れる」というスローガンのもとに取り上げられる語である。しかし、歓待が、他者の受容を通じて、未だ現実化されていない本質を現実化し、変容をもたらす出来事を名指すのに対し、寛容は、他者の存在に我慢(tolérer)しつつ、自らをなんとしてでも維持するための原理のことである。したがって、「他者を受け入れる」というスローガンに惑わされてはならず(というのも、寛容論者も「他者を受け入れている」と主張するから)、変容というモーメントに目を向けねばならない。
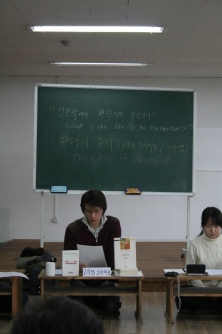

ここから導き出される結論は、歓待が法権利的なものの外にあるということである。というのも、変容を命ずることはできない以上、歓待は、それを履行しなければ罰せされるような法にすることはできないし、また、人権のように、当然のこととして要求できる権利として明文化することもできないからだ。だが、だとしても、法権利的な水準での議論を無視することは非現実的である。私は、したがって、上の結論に付する形で、カントが『永遠平和のために』において、三つの確定条項の最後に、訪問権(Besuchrecht)としての歓待(Hospitalität)の必要性を掲げていたことに言及して発表を閉じた。
李洙榮(イ・スヨン)(スユ+ノモ)
「後期フーコーの倫理学を中心にした他者の問題―知と主体のコミューン的形成の問題」

李氏は、デリダの歓待論を枕にして話を始められた。デリダは「条件付きの歓待」と「無条件の歓待」とを区別した。歓待は歓待である限り無条件の歓待でなければならない。たとえば、「あなたが快く迎えてくれたから、私もあなたを迎える」のであれば、それは歓待とは言えない(日本的に言えば、それは「接待」だろう)。だが、実際に行われる歓待は条件付きでしかありえない。だが、ここに妥協を見るべきではない。李氏の発表の要点は、デリダの問題提起を具体的な政治空間の文脈へと延長して次のように問うところにある——ならば、実際に行われ得る歓待は、いかなる政治的な条件のもとで行われるのか?
そしてその政治的条件は、「いかなる手続きと権力装置のもとで形成されたのか」? ここから李氏は、後期フーコーの「統治性」の概念に依拠しつつ、歓待が前提としている主体と他者の編成の歴史的変化を問うことになる。かつて真理は、真理に到達するためには自己をどのように変容させればよいか、そのためにはどのような修練(askesis)が必要かという問いの水準に位置づけられていた。真理は、主体を変容させることで初めて獲得できるものだったのだ。しかし、いわゆる「デカルト的契機」以降、真理は、認識の水準へとその位置をずらされることになる。真理はただ認識されるべきものになった。その結果、「自己への配慮」(epimeleia heautou)と呼ばれた自己のテクノロジーは、真理にとって不可欠なものではなくなり、個人主義的な一種のエゴイズムとしてみなされる(というか、忘れられる)ことになる。結論において李氏は、「自己への配慮」が師の存在を必要とする共同的な実践であったことに注意を促し、そこから、〈スユ+ノモ〉の共同体的学習を、現代における「自己への配慮」の一つの創造的実践として定義した。

討論において私は、歓待の論理とスピノザ哲学の関係、歓待の議論において権利の問題(カントの言う訪問権)に言及することの妥当性、他者に対して開かれることの危険やその失敗の可能性の問題などについて興味深い質問を次々に受け、質問者に導かれるようにして、スピノザにおける変容の条件としての「共通性」の問題、ドゥルーズが言うスピノザ的な動物の分類学の可能性、法権利の彼岸、クロソウスキーに大きな影響を与えたシャルル・フーリエの情念論などについて話をした。話をする中で自然と李氏との討論が始まり、質問のために手を挙げてくださった方々全員に発言していただくことのないまま、タイムリミットが来てセッションは閉じた。


セッション中にも発言したのだが、私は、李氏が格闘している問題は日本でも共有されていると思った。それは一言で言えば、「脱構築以後」の問題ということになるかもしれない。デリダ本人がどう言っていようとも、脱構築には、我々を思考停止に陥らせるところが効果としてあった。たとえば、政治権力、政治制度、法…なんでもいいが、そういったものはすべて脱構築可能であり、また脱構築の結果として得られるのは——李氏の言葉で言えば——「根源的な成立不可能性」である。脱構築は、この成立不可能性をあげつらって終わる論者を大量生産した——デリダ自身はそうした態度に終始批判的であったのだが。しかし、問題は——再び李氏の言葉を引用すれば——「不安定な根拠をもつ近代の政治形式がいかに構成されたのか」を問うことであり、また、その「成立不可能性」にも関わらず、脱構築可能な政治的構築物が機能しているのはなぜか、いかにしてか、を問うことであるはずだ。なぜなら、我々はまさしくその政治的構築物の中で生きているからである。

言うまでもなく、ここで重要なのは、デリダを非難することではなく、デリダの遺産を受け継いで、脱構築以後の歩みを我々自身が創造していくことに他ならない。李氏は近年刊行されたフーコーの講義録をもとに、後期フーコーの思考をその歩みの創造の足がかりとされた。私自身は、解明がいっこうに進んでいないドゥルーズの思想をその足がかりにしたいと思っている。この課題は緊急のものだが、取り組みはまだ始まったばかりである(私自身、その作業をうまく進められていないことに忸怩たる思いでいるので、そのことをここに記させていただきたい。また、李氏の言う、「自己への配慮」の実践としての〈スユ+ノモ〉のあり方についても、フーコー研究の更なる進展や、〈スユ+ノモ〉の今後の動向を通じて判断していかねばならないだろう)。

私は、この緊急の課題が、示し合わせたわけでもないのにこのセッションにおいて共有されていたことに、ある種の「人文学の現場」を感ぜずにはいられなかった。それは抽象的な現場である。だが、この抽象的な現場が人文学には欠かせない(他の学問分野でもそうだろうが)。それ故、その現場に到達することは一定の修練を必要とするし、現場に居続けることも非常な努力を要請する(これは自戒をこめて記す)。それは、どこかに行けば見つかるような現場ではない。そして、おそらくそのような現場においてこそ、真の思考の交流が行われる。他の思考が自らの思考を触発し、どちらがどちらの思考であるのかがわからなくなり、思考が変容し、進展していくという出来事が起きる。それを歓待と呼んでも、決して、この語の拡大適用ではないはずだ。「人文学の現場」は歓待の場である。
(以上、文責:國分功一郎)
II. 人文学の場所

西山雄二(UTCP)
「人文学にとって大学とは何か―ジャック・デリダ『条件なき大学』をめぐって」
西山はまず、日本の国立大学をめぐる改革(一般教育科目と専門教育科目の区分の廃止、独立行政法人化)を自由と責任という観点から紹介し、大学と社会の関係の問いを提示した。1990年代、一橋大学学長だった阿部謹也は俗社会のなかにとどまりながらも大学は聖なる雰囲気を保持するべきだとし、他方、『知の技法』三部作を刊行した小林康夫は知識の枠組みそのものの行為遂行的な変容とともに大学の知を社会に対して開こうとした。だが、とりわけ独法化以後、内実のないエクセレンス(卓越性)概念によって、大学は社会‐経済的な論理に浸透され、そうした大学と社会、内部と外部という視座から問いを立てることができなくなる。

グローバル化時代において、大学および人文学の役割や責任とは何か。人間が内在的な仕方で人間の営みを無条件的に探究することは、人間が人間を信じる力を絶やさないことであり、そこに人文学の使命はある。新自由主義的趨勢が人々の生存競争を加速させるなかで、大学の責任とは合法的な争いへの信を残しておく端緒となることである。小林康夫が知識から行為へ、認識から実践へと大学の問いを移行させたのだとすれば、西山はさらに、研究教育への信という地平において大学の困難さを思考しようとする。
高秉權(コ・ビョングォン)(スユ+ノモ)
「人文学にとって現場とは何か」

高秉權(コ・ビョングォン)は、彼が実践している「現場人文学」をとりあげつつ、知は生を救うことができるか、また、そうした救済の力を研究教育者がどの程度信じているのか、と問う。刑務所在所者との〈平和人文学〉、野宿者との〈聖フランシス大学〉、脱性売買女性との〈人文学アカデミー〉、障害者との〈黄原人文学講座〉などをおこなっている高にとって、人文学とは社会的弱者がその貧困状態から脱するために必要なもの、つまり、自分が生きていることを実感するように促す知的実践である。
高は、2006年に『希望の人文学』という題で韓国語訳が出版されたEarl Shorris, Riches for the Poor: The Clemente Course in the Humanities(W W Norton & Co Inc, 2000)を引用して、「政治的な生が貧困から抜け出させてくれる道だとするなら、人文学は省察的思考と政治的生に入門する入り口である」と言う。貧しい人々が私的な孤立から脱し、「公的な領域における行動する生」を生きることができるとき、貧困が克服されうるのであり、人文学はその契機をもたらす。ただし「現場人文学」は決して貧しき者たちを「立派な市民」へと作りかえる矯正やリハビリのプログラムではなく、むしろ彼/彼女らの「人となり」をその社会的な文脈において問題化する。重要なのは、当の人文学者自身が「わたしたちの知は信頼しうるのか?わたしたちは人文学に希望をかけてもいいのか?」と問い続けることであり、彼/彼女らの生の変革がなければ人文学は救済の手段とはならない。

ニーチェはキリスト者を他と分けるものは、彼/女らの「信仰」でなく「行動」であると語った。救いとは実践による変化、実践上に現われた変化であるのみだ。イエスにとって重要なことは天国を感じるためにどのような生を生きるかであり、どのような信仰をもつのかではない。同様に、知に信頼を抱き人文学に希望をかけるということは、知への盲目的な信仰を意味せず、知を実践することである。高は生の変革と連帯にこそ人文学の真価があるとした。

その後、討議は結局2時間半以上に及び―高氏は「マラソン的」と形容した―、さまざまな議論がなされた。
「現場人文学において、責任の問題をどのように考えるべきか。説明責任と応答責任という二重の意味において。」「それぞれの現場において、参加者の学びが成立する適切な人数とはどのくらいだろうか。」「時代を巻き込む問いを生起させるのが現場の役目ではないか。」「日本と比べて、韓国では学問と権力との結びつきが強く、高さんが大学制度ではなく、その外部に人文学の現場を求めるのはそうした社会的背景も影響しているのではないか。」「デリダは『すべてを公的に言う権利』を提起したが、それと同時に、彼は検閲の問題を考察することで『何を言ってはいけないのか』という問いも考慮していた。」


森田氏が発した問いは高氏の発表だけでなく、「研究空間スユ+ノモ」の活動そのものに対する深い問いかけだった。「知を生の現場と接近させるという試みは理解できるが、しかしさらに、そうした知と生の関係を批判的に思考する知の営みが必要だろう。知と生を同一視するとそれは神話の状態に近くなるのではないか。知と生の関係そのものを革新していく視点をどのように確保すればよいのだろうか。」


私たちUTCPは「グローバルCOE」という、大学制度の「選択と集中」の結果編成された公的な研究拠点である。他方で、〈スユ+ノモ〉は若手研究者によって大学制度の外に創設された在野の私的な機関である。この二つの現場の出会いがいかなる出来事をもたらすのか、私たちにとって興味深い試みだった。全体として、緊張感に満ちた議論の質は高く、会場からの積極的な質疑も的を射たものが多かった。会場には、韓国国鉄の鉄道員で幾度もの不当解雇に対して裁判闘争をおこない、再雇用を勝ち取ってきたという方も耳を澄ましていたが、彼にとって人文学の現場はどのように映ったのだろうか。



研究教育は時代を巻き込む問いが生み出されるような現場を必要とする。現場の問いとはそれゆえ、問いを生起させることはいかにして可能か、という「問いの問い」である。出来事に参加する者が洗練された歓待の技法でもってこうした研究教育の力を信じなければならない。今回、私たちはそうした出来事をさらに信じる力を受けとった。
今回のワークショップを準備・運営された〈スユ+ノモ〉のみなさんには深く感謝する次第である。
(以上、文責:西山雄二)










