【UTCP Juventus】諫早庸一
UTCP若手研究者研究プロフィール紹介の第18回は、RA研究員の諫早庸一(中央ユーラシア史)が担当します。
私の関心は、文化接触にあります。人間が、自らとは異なる環境で培われたヒトやモノを如何に取り込んでいくのか。この問題を考えることで、人間の他者理解の様相や、「文化」と名指されるものの動態を明らかにしていきたいと思っています。
自身が、対象とする地域は中央ユーラシア(ひとまず「アジア」と呼ばれる地域全般を指すと考えてください)、時代は、モンゴルによって中央ユーラシアが政治的に統合される13世紀前半から、モンゴル帝国が瓦解し、中央ユーラシアの東西に明朝とティムール朝という2つの政治勢力が並立し、その体制を維持する15世紀までです。以下で何故この地域・時代を研究対象としているのかについて若干説明したいと思います。
モンゴルの支配のもと歴史上唯一、中央ユーラシアは政治的統合を経験します。「パクス・モンゴリカ」のもと、天文学や医学、農学や歴史叙述に至るまで、さまざまな文化要素やそれを担う人々が、空前の規模で東西を往来するようになります。従ってこの時代は、文化接触・異文化受容の問題を扱うのに格好の時代であるわけです。しかもその後、中央ユーラシアの統合は長く続かず、14世紀後半には、中央ユーラシアの東西にそれぞれ政治勢力が誕生し、それぞれに独自の文化を発展させていきます。「統合から分立への流れの中で、いったん混淆した文化が、その経験のもと、その後どのような展開を見せるのか」以上のような文化動態に関する問いを検討するのにも相応しい時代であるのです。さらに、自らの研究手法の問題もあります。先に述べますと、自身が研究の核に据えるのがペルシア語(具体的にはアラビア文字で書かれる近世ペルシア語)です。10世紀に中央アジアで生まれたこの言語は、モンゴルの支配領域において公用語的な地位を確立し、広く中央ユーラシアのリンガ・フランカとなりました。そして、その後は中央ユーラシアの西側を主な範囲として、「ペルシア語文化圏」とも表現され得る、独自の文化圏を発展させていきます。そのため、この言語で書かれた諸文献を丹念に読み解いていくことで、当時の中央ユーラシアの(モンゴル帝国崩壊以降はその西側の)文化の様相を知ることが出来るのです。以上のように、この地域・時代は、自身の問題関心に合致し、なおかつ取り組むべき言語が明確であり、それゆえに研究対象となりました。さらに、東の果てにおいてではありますが、自身もまた中央ユーラシアの文化の担い手であるということも、この問題を研究する理由の一つです。後に述べるように、自身が扱うトピックは我々に馴染み深いものです。それらの要素が遠く隔たったユーラシアの西側で如何に受け入れられ、その地に独自のものへと変容を遂げていったのか。自らの研究は、「我々」と「彼ら」の間にある文化的な距離を探る試みでもあるといえるかもしれません。
1. これまでの研究
以上のような問題関心のもとで、自身がまず注目したのが「とき」でした。近代に至り、単一の尺度で測られる時間が誕生し、それが世界を席巻する以前には、地域性や宗教性を帯びた多様な「とき」が存在していました。太陽に基づくものや月に基づくもの、或いはその両方に基づくものもあり、加えてその始点もそれぞれに異なっていたのです。中央ユーラシアにおいても、様々に存在していた「とき」が、モンゴルによる統合によって、相互に影響し合い、変容していきます。
「とき」の中でも、自身が注目したのが、我々にも馴染みの深い十二支です。ユーラシアの西方、イランの地でも現在に至るまで、十二支が用いられています。十二支が彼の地にもたらされたのが、モンゴル時代でした。当時のペルシア語文献に現れる十二支に注目することにより、イラン系定住民の人々が、為政者であったモンゴル系遊牧民の「とき」を、自らの「とき」に組み入れ、具体的にはイラン暦の年始を持つ十二支を徴税や祭祀の基準としていった過程を明らかにすることが出来ました。
以上の考察を含めた修士論文を、2006年に神戸大学人文学研究科に提出し、それが京都大学歴史学研究会発行の『史林』第91巻3号に掲載されました。
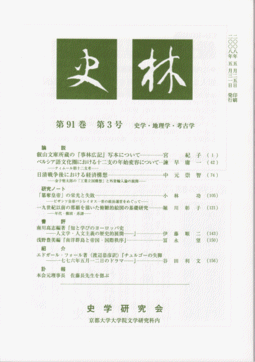
2. 今後の展望
今後も、ペルシア語史料に見られる我々に馴染み深い文化要素に注目して考察を続けていく方針に、変わりはありません。より具体的には以下の2つの要素に注目して研究を進めていこうと考えています。
α, 「中国暦」
これまでは、中国暦の1要素ともいえる十二支に注目してきましたが、その本体である中国暦もまたモンゴル時代以降、ペルシア語史料に記されるようになります。そしてそれは、中央ユーラシアの統合が失われたティムール朝期以降も記され続けるのです。
中華王朝にとって、天の意を汲む暦は権威の拠り所でした。権威と密接に関わっていた中国暦が、漢語文化圏の外側に在る「ペルシア語文化圏」でどのように継承されていったのか。政治的に分立した後も、東西の文化圏を代表する明朝とティムール朝との間には交渉があったことが知られています。明朝との交渉がペルシア語による中国暦の記述に何らかの影響を与えたのか。中国暦を通じて、文字と権威をめぐる問題について考えてみたいと思っています。
β, 「博士(bakhshi)」
中国語の「博士(bóshì)」に由来するバフシー(bakhshi)なる語がモンゴル時代以降にペルシア語史料に記されるようになります。この語は当初、仏僧を表す言葉としてペルシア語に取り入れられました(モンゴル期はイランにおいて仏教が隆盛した最後の時代です)。しかし、この語は興味深いことにその後、仏教徒・イスラム教徒を問わず、ウイグル文字を操る書記に付される語となり、遂には、アラビア文字を用いる従軍書記を意味する言葉へと変容していきます。
十二支の時と同じく、この言葉の変遷を同時代史料から追っていきたいと考えています。ただし、それを通じて読み解きたいと考えていることは、十二支を考察した際に見えてきたモンゴルとイランとの混淆ではなく、仏教とイスラム教、ウイグル文字とアラビア文字という、信仰とそれを表象する文字、そしてそれの「文化」との関わりの問題です。
以上が、これまでの研究と、これからの見通しです。UTCPのプログラムを通じて、自らの問題関心を発展させていければと思っています。







