【報告】新自由主義状況における出版メディアと人文学
1月26日、東京外国語大学の老舗研究会WINCにて、「新自由主義状況における出版メディアと人文学」と題された会が催された。編集者3名が登壇して発表をおこなうことで、編集者と書き手(とくに大学人)の対話の場をつくろうという斬新な企画である。
この日の提題者は小柳暁子(フリーランス編集者)、小林浩(月曜社編集者)、守田省吾(みすず書房編集者)の3名で、司会は岩崎稔(東京外国語大学)が務めた。出版人と大学人が個々別々に私的に交流するのではなく、こうした研究会の形で一堂に会して議論を交えることは大変貴重な機会である。人文学は出版社との関係なしに成立しない。大学人と出版人の対話は、つまり、人文学をいかに制度的に構想していけばよいのかというその根拠律に関わるものである。

まず、小柳氏と小林氏が、本の製作・流通・管理の過程を丹念に説明した。まず、①出版社が企画を立て、原稿を整理し、入稿し、装丁を依頼し、資材(用紙やスリップなど)を発注する。次に、②印刷所が刷版を仕上げて、印刷をおこなう。③製本所が製本し見本を納品する。④取次会社が配本部数を設定し、全国の書店に配送し、さらには代金の回収・支払を各出版社に代わっておこなう。⑤書籍は書店に入荷され、展示され、返品される。そして、⑥出版社は返品分を倉庫で管理し、注文があれば出荷し、逆に、過剰在庫分については新品にもかかわらず裁断して処分する(この上なく悲しい作業である)。二人が強調したのは、一冊の書籍が刊行されるまでにどれだけ多くの人間の労力がかけられているのか、ということだった。
小林氏はさらに、出版をめぐる過酷なゲームの規則を補足した。書店に営業に行き、新刊書籍を売り込むための時間は30秒しかない。書店員はきわめて多忙なので、営業部員は自社書籍の魅力を30秒で要約してアピールし、注文をとりつけなければならない。瞬間の一撃を要する、ほとんど剣道に近い技法である。また、書店に関していえば、現在、日本の総書店数は18,000軒ほどであるが、しかし、そのうちで人文系書籍を「誠実に」扱ってくれるのは約300軒にすぎないという。約300軒の流通箇所で人文書籍の販売を売り込まなければならないのだ。例えば、月曜社のある人文書籍の例で言えば、この300軒の書店に刊行1ヶ月前にFAXで営業をかけて、90軒からのべ400冊の配本依頼があり、取次会社の配本によって最終的に初回600冊が店頭に並んだという。人文系出版が、きわめて限定されたゲームの規則に沿った商業活動であることを再認識させられた。
3人目、守田氏からはその長年の経験からさらに含蓄のある話をうかがうことができた。
出版業は成長産業と言われていたが、1990年代半ばから急速に斜陽産業へと転じた。だが、経営を維持するために出版点数は加速度的に増え続ける傾向にあり、15年前と比べると、現在、年間出版点数は約2倍にもなる(雑誌を除いて年間約80,000点、1日約300冊の新刊出版)。だが、出版点数は増えても市場は明らかに小さくなっている。しかも、市場の実情はその大半がごくごく一部の書籍(『ハリー・ポッター』シリーズや『バカの壁』など)で占有されており、それ以外の約79,500点の書籍はさほど利益を産み出さないといういびつな構造をなしている。つまり、限られた市場の利益をめぐって、膨大な数の本が出版され、その大部分は瞬時に淘汰されていくわけである。出版点数が激増した分、出版人の労働時間は増大し、企画を十分に練る時間がとれなくなり、書籍の質が落ち、ロングセラーが生まれにくくなるという負のスパイラルが業界全体に蔓延している。
書店の状況はどうか。全国の総書店数18,000軒という数字は昔とさほど変化していないものの、その質の変化は決定的である。つまり、街の本屋が廃業に追いやられ、その代わりに、チェーン店や郊外型書店が乱立し続けているのだ。他方で、アマゾン・コムなどのネット書店も浸透している。この激変は読者をして、「書店から何かを学ぶ」という経験を貧しくさせている。かつて数多く存在した街の中小規模の本屋においては、個性的な店主や書店員の意向によって、魅力的な棚作りがなされていた。すなわち、私たちは書店の棚を見て、その書物群の視覚的連関から多くを学ぶわけであり、これはチェーン店やネット書店では経験できない書物の存在意義である。さまざまな書物の関係が織り成す世界が社会から著しく失われてしまったのだ。
では、さまざまな書物の関係それ自体はどのように激変したか。一方で、新書ラッシュはとどまることを知らず、消費欲望型の書籍の刊行は加速度的に進む。他方で、高額少部数発行の専門書の類は、一部の読者(研究者など)や大学図書館など狭い範囲で、ただ社会的公共財として密やかに流通する。守田氏は、「本の存在意義は消費欲望型でも文化財型でもなく、その中間に見い出される。実際、そうした宛て先をもつ本しかつくりたいとは思わない」と決定的な言葉を放つ。「本」とは「読者が自分のお金で真に買いたいもの」である。一方で、本は読者のつかの間の欲望を満たして忘れ去られる消費財ではなく、時代を超えて、時間的なずれをともなって、来るべき読者へと漂着しうる。他方で、本は特定の読者のあいだで交換されるものではなく、価値観の違いや世代や相違を超えて、空間的な拡がりともに、さまざまな読者に漂着しうる。消費欲望型か文化財型かという極端な二者択一においては、本の質を判断する決定的なものさしが失われる。不特定多数の見知らぬ読者の不在は出版の質を低下させる。出版(publication)が公共空間(public space)の可能性を刷新するための貴重な営みであるとすれば、いかに限定された社会的・経済的な状況とはいえ、読者への宛先は時間的・空間的に最大限に開かれていなければならないのである。
原理的に、なぜ本が売れなくなったのか。まず第一に、80年代に進行した大学大衆化がそれ以前の教養主義を消滅させ、人々の書籍への執着を減退させたこと。第二に、ある種の対立的構造の希薄化である。つまり、権力/反権力、アカデミズム/反アカデミズム(そのかつての好例は「丸山真男VS吉本隆明)、文化/カウンター・カルチャーといった対立構造の現場として出版は活気づくのだ。その対立構造は90年代に曖昧となり、希薄となってきたことが出版の現状に深い影響を与えているという。
そして、出版と大学の関係はどうか。かつて、読者、著者、大学人というカテゴリーは重なり合っていた。80年代以降、次第に、大学人が読者と著者と重複しなくなってきた。まず、学生の読書離れがある。次に、大学教員から「自由な」執筆活動の時間が奪われてきた。大学内の仕事が激増し煩雑化するなかで、教員の優先順位は教育、事務、研究、出版となってきた。かつては大学での教育や事務仕事の枠からはみ出した教員(実に少数派である)が、編集者との交流のなかで時間をかけて執筆活動をおこなっていた。出版と大学の関係の変化は、それゆえ、出版活動から読者と著者を奪うことになる。
こうした3名の発言は出版業界のみならず、人文学全体の深刻な状況を物語るものだった。また、一冊の本を誕生させる過程は多くの人々の過酷な物語によって支えられていることもよくわかった・・・立ちっ放しの激務のため、腰を悪くして30歳半ばで退職するケースが多い書店員。24時間輪転機を回し続けて、昼夜の別なく労働する印刷業者・・・等々。

全体討論の時間には、会場に来ていた多くの出版人(編集・営業)から生々しい発言が相次いだ。会場に来ていたのは50音順に、青木書店、朝日新聞社(月刊『論座』)、梓出版社、インスクリプト、慶應義塾大学出版会、日本経済評論社、春風社、平凡社、法政大学出版会、山川出版社、有志舎、吉川弘文館に勤務する方々である。その大半がWINC研究会の常連参加者ではなく、初参加者であった。
新自由主義の競争のなかで、小出版社は生き残ることはできない。逆説的だが、競争が激化すればするほど、「馴れ合い」とも呼べる個々の連帯が必要となるのではないか。
経済学の本をつくっても、書店では同じ経済でもビジネス書が優先される。書店の棚(ジャンル分け→特定の読者を計算)を見越した上での書籍製作が必要となる。またその結果、領域横断的な本、実験的な要素をもつ本(不特定の読者への呼びかけ)を世に問いにくくなる。
書物は二度生まれる。一度目は出版社が製作するとき、個体として誕生する。二度目は書店の海のなかに投げ込まれ、さまざまな人が関係する現場において関係性として再び誕生する。
書店の純利益は過酷なほどわずかなもの。書店側には1,000円の書籍に対して200円、雑誌ならば300円の収入しかない。そこから人件費、光熱費を差し引くと、純利益などほとんど残らない。書店経営はほとんど奇跡に近い状態で成立している。
学術出版を支える貴重な財源として、文科省や大学の助成金制度がある。しかし、この制度も競争入札が奨励され始め、出版の現場をさらに過酷なものにしている。果ては、助成金の適用条件が矮小化され、出版社(編集者)を通さずに、著者個人と印刷所との最小限の関係、つまり最小限の費用で書籍が刊行されるようになるのではないか。そうした最悪のシナリオは十分予想しうるし、しておかなければならない。
アメリカ中心のグローバル・スタンダードとは異なる仕方で出版業を活性化するために、人文系出版社数社は、中国、香港、台湾、韓国の出版人と共に、2005年以来「東アジア出版人会議」を組織している。東アジアの出版交流を人的交流、書物の交流、企画・出版の交流の三つの次元で検証し、具体的成果に向けてワークショップを毎年積み重ねている。その成果はネット上で多言語で発信されており、「東アジア読者共同体」の構築に向けた緩やかな、しかし確実な歩みが始まっている。
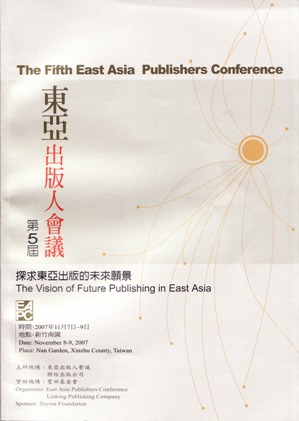
(2007年11月7-9日、台湾で開催された第5回「東アジア出版会議」の記録集。中国語、韓国語、日本語の多言語編集。第5回会議の成果については、月刊「論座」2008年2月号の特集「人文書の未来を求めて」を参照されたい。)
筆者は、研究者の世界の有名な警句「Publish or perish(論文を発表せよ、さもなくば滅びよ)」を引用しながら発言した。出版人および大学人にとって、むしろ、現状は「Publish and perish(出版せよ、そして、滅びよ)」に他ならない。出版人は激増する出版点数にひたすら耐えて激務をこなし、収益が激減するなかで、廃業に追い込まれる出版社が出てくる。また、大学人は過度の業績主義に煽られ、論文を過剰に生産し続ける。とりわけ不安定な身分の院生やポスト・ドクターは体を壊し、精神を病み、命を絶つものもいる。だから、限られた市場の利益をめぐって、それでも最大限の配分的正義を考慮しながら、「Publish and associate(出版せよ、かつ協同せよ)」を掲げて生き延びるしかないだろう。今回の研究会の題目は、「新自由主義状況における出版メディアと人文学(Humanities)」である。それはまさに、過度な競争を蔓延させる新自由主義状況において、最低限の人間性(Humanity)を保持するために、出版に何ができるのか、出版(publication)によっていかなる公共空間(public space)を残せばよいのか、という問いではないだろうか。
人文書出版をめぐるきわめて重い話が続いたが、しかし、会は決して業界の愚痴に終始するものではなかった。逆説的にも、厳しい状況のなかで、これほど人文学のことを想い、人文書をそれぞれの現場で支えている人々がいることを確認することができた。そして、大学人、つまり著者や翻訳者は彼/彼女らの責任に見合うような仕事の精度と人文学への誠実さが求められている。たしかに苦しい現状だが、しかし、余分な妄想をすべてそぎ落とし、もっとも乾いたニュアンスを込めてこの表現を使用させてもらうと、やはり人文学の研究や出版は、数多くの人間の協同によって継続される、「夢」のある仕事だ。これはこの研究会に参加した誰もが、一瞬、感じたことではないだろうか。
今回の斬新な企画を準備された東京外国語大学WINCの方々、参加者の皆さんに感謝したい。(文責:西山雄二)
付記:
今回の企画と関係するイベントとして、UTCPでは、2月23日(土)13:00-18:00に東京大学駒場キャンパスにて、シンポジウム「哲学と大学―人文科学の未来」を開催する。
また、2月27日(水)17:00-19:00には、トム・コーエン氏(ニューヨーク州立大学アルバニー校)を招聘し、アメリカにおける人文学の現状に関して講演をしていただく。コーエン氏は、ド・マンやデリダについての重要な論集(『物質的出来事:ポール・ド・マンと理論の死後の生』『ジャック・デリダと人文学:領域横断的読本』)を編集した論客である。最近では、「批判的気候変動に関する研究所」の研究ディレクターを務めている。この研究所は、地球の生物環境の変化と批判的思考を架橋しつつ、今世紀の「生」の在り処をを多角的に検討するというユニークなプロジェクトである。
詳細はイベント欄にて追って告知する。






