ヘーゲル『精神現象学』刊行200年
2007年は、現代哲学の古典であり、その出発点であるヘーゲル『精神現象学』の刊行200年にあたる。世界各地でシンポジウムが開催され、雑誌特集や論集が刊行されている。
2006年3月25-26日、東京で日本ヘーゲル学会が日独研究者からなるシンポジウムを開催した(その成果が下記の『理想』誌)。また、今年3月21-25日には、ベルリンでイェシュケやゲアハルトらの主催により、「意識の諸形態」の「発生学的思考」に関する国際的研究集会が開催された。9月10-12日には、オックスフォードで、イギリス・ヘーゲル学会によって国際的研究集会「ヘーゲルと『精神現象学』」が開催され、ジープやマラブーらが参加した。2006年にベルナール・ブルジョワによる新訳(イポリット以来4種類目の仏訳)が出たフランスでは、若手ヘーゲル研究者ジョゼフ・コーエンによって、ハーマッハーやバリバールらが参加する国際シンポジウムが12月13-15日にソルボンヌ大学で予定されている。
日本での出版物に関していえば、日本ヘーゲル学会による『ヘーゲル哲学研究』(Vol. 12、2006年)、『現代思想』(青土社、2007年7月臨時増刊)、『理想』(理想社、No. 679、2007年)で特集が組まれている。また、年末には論集『ヘーゲル「精神現象学」 現代思想の起点』(社会評論社)が刊行される予定だ。

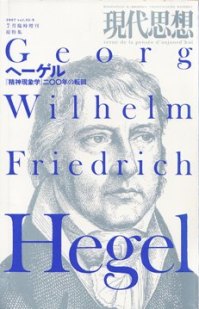
11月24日、廣松渉が創設した現代史研究会の第200回記念として、『精神現象学』200年のシンポジウムが組まれた。滝口清栄(法政大学)司会のもと、大河内泰樹(埼玉大学)、片山善博(東京農工大学)と私(西山雄二)が個別発表と討議をおこなった。
大河内氏は、現代哲学のコンテクストにおける『精神現象学』について発表した。まず、近年のヘーゲル評価に関して、ドイツではヘーゲルを「ゴシック建築のように保護するべきだ」との否定的な見方も出ている。他方で、アメリカでは、ムーアやラッセルらによってヘーゲル主義との決別から出発したはずの分析哲学が、クワインを経て、マクダウェルやブランダム以降、ヘーゲル評価に傾いている点は興味深い。また、ピッツバーグ新ヘーゲル学派とハーバーマスはともに、1)感覚的経験における所与性の神話の批判、2)心理主義や表象主義批判による脱超越論化の傾向、3)認識の客観性の相互主観的基礎付けの重視、4)語用論の採用、といった点で(限定的な仕方ではあるが)ヘーゲルを再評価している。大河内はさらに、ハーバーマスが語用論(討議倫理)のイデオロギー性に無自覚だったのではないかと指摘する。ヘーゲルは言語のもつ欺瞞性にむしろ意識的であり、一般的な言語使用とは異なる次元で、「告白」や「Ja」という行為遂行的な「許しの言葉」による共同主観性の可能性を示唆してもいるのだ。
片山氏は、1)カント、フィヒテ、ヘーゲルの主体概念をめぐって、超越論的主観性の枠組みの継承として、あるいは、相互主観性の立場として主体を理解するべきか、と問う。ヘーゲルの場合、自己知の超越論的主観性を突き詰めていくと、相互主観性を問題にせざるを得なくなる。2)また、片山氏は近著『差異と承認』(創風社)をもとに承認論の意義を強調した。古典的な承認論(フィヒテ、ヘーゲル)においては、「個の自由」と「他者との共同」の両立が問われた。現代の承認論においては、①正当な承認をめぐる議論(テイラーやホネットなど)、②承認の権力性そのものを問題視する議論(カルチュラル・スタディーズなど)、③規範の問い直しとしての承認論(バトラーなど)が展開されている。興味深いのは③で、バトラーの承認論では、自己の承認が他者の排除に加担していることを自らの核心に据え続けていくような自己意識の脱-静態的な構造が強調されている。

西山は、20世紀フランスにおけるヘーゲル『精神現象学』受容を概観した。19世紀を通じて不調だったフランスのヘーゲル受容だが、1)1920年代にジャン・ヴァールによって転機が訪れる。ヴァールは有限と無限との分裂に直面した「不幸な意識」を自己意識の弁証法的発展の動力源とした。キエルケゴール研究者のヴァールは、ヘーゲル哲学を否定性の実存的なパトスとともに汎悲劇主義的に解釈した。2)1930年代には、コジェーヴの『精神現象学』講義によって、ヘーゲルは無神論的な有限な人間主義として解釈され、実存主義とマルクス主義の紹介とともに、歴史の運動のなかで人間の自由を探求する新しいヘーゲル像が確立する。3)イポリットは、個別的な意識の現象学と絶対者におけるロゴスの存在論(『論理学』)との連関を問い、ヘーゲル哲学を駆動させる「不安」は人間的な実存の内に先在するのか、存在それ自体の内に先在するのか、と問う。彼はハイデガー存在論を踏まえつつ、『現象学』の最終的な宛先は人間ではなく、人間が存在のロゴスを受け入れるための開けであるとした。これは人間的な主体性を欠いた超越論的な場という着想をもたらし、1960年代のポスト・ヘーゲル主義(さらに言えば「構造主義」)の形成を招いた。『精神現象学』の受容と批判は20世紀フランス思想の重要な背骨をなしているのだ。
討議の時間ではなかでも、承認論と共感や共生との関係が議論された。社会的な承認と共生とは異なる「共感」は、ヘーゲル哲学においては愛に相当する。愛は承認論の原形をなすものの、他者の個別的な占有という点で、社会的な関係を説明するには不十分だとして退けられる。また、共生概念だが、そのホーリスティックな目的論によって、自己と他者、例えばマジョリティとマイノリティの政治的闘争があらかじめ緩和される恐れがある。他方で、ヘーゲルの承認論は相互主観性の確立に帰着するのではなく、共生の地平(普遍的な尺度)そのものの問い直しをつねに含んでいる。
『精神現象学』のアクチャリティーとして、西山から、来たるべき共同体の告知という点を指摘した。『精神現象学』では、「誕生の時代」、「質的飛躍の時代」における共同性(「我々である我、我である我々」)の構築が目指される。しかし、『精神現象学』において最終的な国家論は提示されず、ギリシア、ローマ、啓蒙期、フランス革命など、歴史的に途絶した止揚されるべき共同体の事例が挙げられるのみである。この意味で、『精神現象学』は共同体を告知しつつ、その実定的な解答を留保しているのであり、共同体の問いは開かれたまま私たちに委ねられているのではないだろうか。
最後に、大河内は、「自分は『論理学』の弁証法を専門にしているが」、と断りつつ、「しかし、弁証法という表現はあまり使用しないようにしている」と述べた。実は、ヘーゲル自身、弁証法という言葉をさほど使用していない。また、弁証法と言えば、各人が勝手に自分なりの意味づけをして、分かったつもりになってしまう。しかし、ヘーゲルのいう弁証法とは、つまり、絶対的な基礎づけがないという試練に思考を曝す原理である。それは例えば、観念論と唯物論の対立において、そのいずれにも最終的な根拠を認めることなく、この両義的な矛盾の運動に耐えながら思考し続けることだ。究極的な根拠を欠いたまま思考するという務めとともに、いまだなお、私たちはヘーゲルが切り開いた地平のなかにいる。 (文責:西山雄二)






