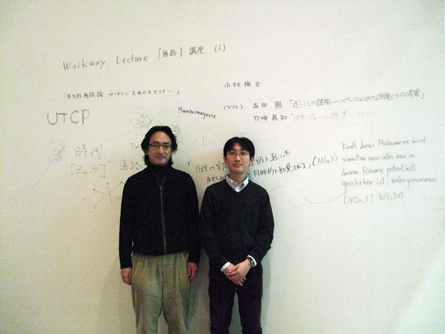【報告】共生的通路論――ベンヤミンをめぐるセミナー
とらえがたさ――芸術から土木へ
「とらえがたい」とは、意外に使うのが難しい形容詞だ。
筆者は、とある日本人思想家と対面した際、どこまでいっても核心をつかませないその人物のトークに、この形容詞を思い起こしたことがある。だが、実のところ、「つかませない」のと、「とらえがたい」とは違う。核心を掴ませまいとする人物は確かに「とらえがたい」。だが、そのような人物ならば、「とらえがたい」人物としてとらえることができる。「とらえがたい」と言いたくなる対象には、つまり、たとえオブジェクトレベルでそうであろうとも、メタレベルでの単純な包摂(とらえがたいものとしてとらえる)を許すものが少なくないのであって、その意味で、「とらえがたい」とは、使うのが難しい形容詞であるのだ。真にとらえがたいものは意外に少ない。
現在、東京都現代美術館で、「川俣正[通路]」展が開催されている(2008年2月9日~4月13日)。ベニヤ板の壁で囲われた通路が延々と続くこの展覧会(?)では、会期中に多数のトークショー、講座、ワークショップが計画されているのだが、先日、その一環として、UTCPワークサロン「共生的通路論――ベンヤミンをめぐるセミナー」が行われた。川俣正氏とUTCP拠点リーダー小林康夫先生の対談、竹峰義和氏と森田團氏によるベンヤミンについてのレクチャーで構成されたこの催しは、まさしく、真にとらえがたいものと出会う経験、そしてそれに肉薄する経験を得られた実に稀な機会であったと言うことができるだろう。
ベンヤミンについてのレクチャーの報告は、発表者の一人である森田氏に譲り、ここでは川俣氏の話について簡単な報告を試みたい。

川俣正とベンヤミンというのは、小林先生によって構想された、おそらくは突拍子もない組み合わせだが、その対談もまた、ベンヤミンから着想を得た「川俣さんにとって救済とはいかなる意味をもつのか?」という突拍子もない質問から開始された。
川俣氏からの答えは、「うーん…考えたことがないですね」。
言うまでもなく、川俣氏は、つかまれまいとしているのではない。川俣氏の口から出てくるのは、常に率直な答えだ。――救済とか、救うということは考えていないのだが、一緒に何かをすることによって、自分と人との感性を共有すること、シンパシーというものは目指しているかもしれない…。
「一緒に何かをすること」を受けて小林先生が言及されたのが、川俣氏がオランダのアルクマールで実施したプロジェクト『ワーキング・プログレス』(1996~1999)だ。これは、麻薬中毒患者やアルコール依存症の患者と共同作業で遊歩道を作るという「作品」である。
川俣氏の「作品」(といってよいのかどうか、実に判断に苦しむところなのだが)は、一般に、プロセス・アートとして知られている。いわゆる芸術作品が、霊感を得た作家がアトリエにこもって没頭する孤独な作業の結果の呈示であるとすれば、プロセス・アートは、その結果が呈示されるまでのプロセスそのものをアートに組み入れようとする傾向のことである。

もちろん、このような名称は、川俣氏の活動を考える上では百害あって一利なしだろう。川俣氏は、プロセスをアートに組み込むことを目指しているわけではないからである。こういうことをやってみるとどうなるかな…。どんなものができあがるのか見てみたいな…。そのような気持ちが活動の最初にあるのだと氏は言う。
だが、氏の活動がさしあたってはプロセス・アートと呼ばれる名称を受けいれるものであるとすれば、それはその活動がいつも、「一緒に何かをすることが好き」という気持ちに支えられているからだろう。アルクマールでのプロジェクトでは、モンドリアン・ファンデーションというオランダ国営のコンサルタント組織からの依頼を受け、患者たちといっしょに遊歩道を造るというプログラムが立てられた。初めは100メートルも出来るだろうかと思っていた遊歩道は、最終的に三年をかけて3キロまで延びた。
今回の[通路]展もこれに似た仕方で準備された。800人のボランティアが集まり、とりあえず1800個のベニヤ板のパネルを作る。そしてそれで美術館の中に通路を造っていく。彼らと話し合い、一緒に食事もする。一緒にするという活動が、とりあえずは「作品」と呼ばれるであろう川俣氏のアクティヴィティそのものである。だから、2月9日から東京都現代美術館で「展示」されている通路が作品なのではない。それを作る活動のすべて、そしてそこを通る人々、今回のワークショップ(そしておそらくはそれを報告するこの文章…)のすべてが、川俣正という固有名を付されるべきであると同時にそれを拒否もする反‐作品であるのだ。
アルクマールでのプロジェクトは、話だけ聞くと、セラピー・アートあるいはアート・セラピーとして括りたくなってしまう。小林先生も、「それはアートなのか? なぜアートなのか? なぜセラピーじゃないのか?」と問い、なんとかして、とらえがたい川俣氏の目的地を印付けようとするが、川俣氏はこれに対しても「こういうことをやっても、アートになるのかなぁと思ってやった」と答えたのだった。「『これがアートだ』と思ってやっているのではないんです」。

たとえば川俣氏は、横浜トリエンナーレ2005の総合ディレクターを引き受けた際にも、「自分の中ではこの一年間がトリエンナーレ。もう、始まっている」と述べていた。こんな喩えは氏に失礼だろうか。学校で文化祭が近づいてくると、クラスでは出し物について話し合いをして、クラスで準備をして、へとへとになりながら当日を迎える。展示であれ、舞台であれ、屋台であれ、もちろん当日が大切なのだが、しかし、やっている当人たちにしてみれば、話し合いから準備、そしてもちろん当日を含めて文化祭だ。楽しめるやつがいる、楽しめないやつがいる、ケンカがある、シンパシーもある、そうしたことをすべて含めて文化祭という名のアクティヴィティである。アートを取りまく伝統的な制度とは、文化祭の当日しか考えないようなものだ。
だから川俣氏はアーティストと呼ばれており、またその呼称を拒否もしないのだが、しかし、それよりも自分にはアクティヴィストという呼称の方がしっくりくる、と言う。「アート」というイデアは、多分、ずいぶんと遅れて川俣氏のアクティヴィティについていっているということだろう。
とはいえ、氏のアクティヴィティが「アート」という言葉を引き寄せるのは紛れもない事実である。氏の仕事は受注がほとんどであるという。或る意味で受身。だが、場当たり的でもない。明確な意図をもってすべてのアクティヴィティに統一性を与えようとはしないが、むしろ逆に、統一性を与えないように、という意図はもっている。一つ一つのアクティヴィティは確かに何らかのルールに沿って行われているのだが、そこから社会的なモラルのようなものは言いたくないし、そもそも、言えない。川俣氏自身が頑張って説明してくれたこのとらえがたさ。やはりそれが、アクティヴィスト川俣正をアーティストたらしめているのではないか。

何より不思議なのは、このとらえがたさが少しも否定的なものではなく、周囲にいる者を引きつけ、巻き込んでいく類のものだということである。何かを一緒にしたい、シンパシーを求めるというある種の“熱さ”を感じさせつつも、社会的使命のようなものは言わないし、言えないという“クール”な面も感じさせ、その「作品」からは何か手作業へのこだわりのようなものが感じられるけれども、氏自身は都会でサヴァイヴすることの方に関心を持つのだと言う。こうしたとらえがたい話を聞きながら、聞き手は、そのとらえがたさ故の疎外感など少しも感じることはない。むしろ、「それはいったいどういうことなのだろうか?」と氏と一緒に考えたくなる。「川俣正」という名の、アーティストというよりもアートに、参加したくなってくるのだ。
このとらえがたさのなかで、筆者はしかし、一つだけ、氏が明確に関心を示すキーワードを得ることができた。筆者自身も関心を有していたものだったのでよけいに印象づけられたその言葉とは、「土木」である。川俣氏は、「自分は土木的なものに関心がある」と明言した。
90年代以降、「建築」が強い知的関心を集めるという傾向がみられた(1991年から2000年まで行われたANY会議はその象徴だろう)。それは一つには、霊感を得た作家がアトリエにこもって没頭する孤独な作業の結果の呈示として考えられるいわゆる芸術作品がある種の行き詰まりを見せる中で、建築こそは「芸術的」な性質と「社会的」な性質をあわせもつものとして注目を集めたからであると思われる。建築はそれが置かれる場所から切り離せない。使われることを前提としている。その建設には複数の人間が関わらざるを得ない。したがって建築という営みは、考慮せねばならないディメンジョンの数が単純に多い。おそらくこうしたことが、建築の知的人気の秘密だったと思われる。
その傾向が非常に有益な成果をもたらしたことも事実である。だが、ここで注目したいのは、「建築」という思想潮流もまた、作家主義を少しも抜け出せなかったということである。いわゆる芸術作品が作家単位で語られたのと同様、建築を語ることは建築家を語ることと同義だった。そこには明確に作品があった。建築に対する知的好奇心がどれほど「場」や「環境」や「社会」や「生活」に目を向けようとも、それは作家主義の視点からしか、つまりは、建築家個人がコピーライトをもった作品からしか考えられなかった。

土木とは、そうした芸術や建築を下から支える技術であり、且つ、作家主義から極めて遠いところにある技術である。上下水、ガス、電気等々のライフライン、道路、橋、運河、トンネル等々の交通網。芸術家がアトリエにこもっていられるのも、建築が地上に建てられるのも、「技術の中の技術」と称される土木技術のお陰である。そしてそれは、技術者とその場との対話、地権者との交渉、社会の要請、環境への考慮、そうしたものすべての結果として実現される。土木がなければ共生はありえない。そして、土木技術は、作家主義を許すようななまやさしいものではない。
おそらく、いわゆる芸術から建築へと目を向けた知的好奇心は、近いうちに、土木に注目し始めるはずである。その時、土木への関心をいち早く表明していた川俣正氏が、「一緒に何かをする」という形でのアクティヴィティを重ねてきたことの意味を明らかにするための作業が始まるかもしれない。
(以上、國分功一郎)
UTCPワークサロン(in 川俣正[通路])「共生的通路論――ベンヤミンをめぐるセミナー」の後半は、ベンヤミンの検討に入った。まずは竹峰義和さんが「パサージュ――遊歩と移行のトポス」と題して、『パサージュ論』の成立経緯やその主要モティーフ、理論構成などを簡潔に説明した。発表の核となったのは、ベンヤミンの歴史認識を支える時間性の把握であったが、扱いにくい問題であるにもかかわらず、彼は極めて明快に問題を整理し、論じた。

『パサージュ論』の諸前提についての解説を受けつつ、私は「迷うことの諸相――パサージュの経験についての考察」と題して、より特定のテーマに絞って発表した。場所が川俣正氏の通路展の会場ということもあり、『パサージュ論』から出発して、通路なるもの、道なるものとは何かという一般的な問いを準備することを目指したのである。具体的には、ベンヤミンによる都市経験の分析の前提となっている「迷うこと」を、『パサージュ論』のいくつかのモティーフから浮き彫りにし、それこそがパサージュ体験の核心にあること、それどころか通路や道なるものの成立に本質的に関わっている可能性があることを示そうと試みた。

質疑応答は、一方でベンヤミンの時間概念、他方で迷うことの内実とその根源性のステイタスなどをめぐって行われた。川俣氏の作品に囲まれての発表と質疑応答であったが、緊張感と開放的雰囲気のバランスがうまく取れていたのか、非常に充実したものになったと思う。
とりわけアドルノについての単著もある竹峰さんからベンヤミンの時間概念についての話を聞けたのは収穫であった。幼年期や神話的太古という語によって示唆されている「かつて在ったもの」は、過去に実際に起こったことだけではなく、潜在的に起こったかもしれないことさえも含み、それらが孕む未来への可能性を知覚することがベンヤミンの歴史認識論の基盤であるという彼の主張は、ベンヤミンの時間概念や歴史哲学を考える際の出発点となる認識であろう。

ここから改めて明らかになったのは、ベンヤミンの時間概念をより精緻に分析していくことが、今後の課題となることである。そのためには幼年期や太古というある種の過去が持つ意味をまず問う必要が出てくるだろう。それらはもちろんたんなる過去ではなく、私たちの経験や生を根本的に制約している条件である。それゆえこの過去は「超越論的過去」(シェリング)とも呼びうる。おそらくこの超越論性と過去の内実、ならびに両者の関係こそが、ベンヤミンにおいて新たに問いに付されているのである。
(以上、森田團)