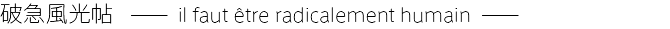★ 日日行行(415)
* だから、わたしにとっては、2021年は、「詩」という言葉がひとつの鍵となる年なのですが、そうしたらブルガリアのボヤン・マンチェフさんから昨日メールが来て、そこには「はじめに会ったときから、あなたは哲学者だけど、詩人だなあ、と思っていました」という言葉が送られてきて嬉しかったですね。
わたしの経験からも外国人の友人との出会いは、日本社会のレッテルを超えたところでの関係であるだけに、つねにより本質的にその人を見る、ということがあるように思います。この人が何であるか、それが決定的ですよね。わたしが誰であるか、(もちろん、わたし自身だってわからないわけですが)、それを見抜くということが、言語を超えて起こる。それがスリリングです。その友情が貴重です。いっしょに詩画集をつくるから、あなた詩を書いて!と言ってくれたのは、イレーヌ・ボワゾベールさんだったし。パリ在住の黒田アキさんは別にして(かれはパリジャンだから)、日本人は(詩集も出していない)わたしに詩を書いてね、とは頼みませんね。
そうそう、今週は、ニュージーランドに住む(これもブルガリア人)東大の昔の学生のデンニッツァ・ガブラコーヴァさんと遠隔で対話をしたのですが、彼女は、3年前に東京で会ったときに差し上げたわたしの『オペラ戦後文化論1」を精読してくださって、今度出版なさる彼女の本の序文に、そのなかの唐十郎についての論を引用してくださっています。昨日、その英語の序文が送られてきました。嬉しいなあ。そのように、わたしの拙文が若い人たちの研究の刺激になるなんて、これこそ物を書く人間として最大の喜びです。
そのように、情報ではなく、ひとつの思考、ひとつの言葉の営みが、地球という時空のあちこちを結んで、「友情」(「友情」ってそういうことなんですね)のリンクとなる。呼びかけ、応答、思考、詩、それが祝祭です。存在の祝祭。
(なぜか今朝は、青いノートには、宗教というものは、すべてある種の存在論だよねえ、というような「思考」を書きつけていましたが・・・「友情」とは、その拘束のなかでの「ヒ(火・日・灯・秘・)」の交換です。)