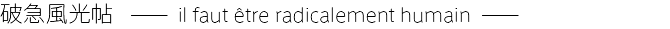★ 日日行行(342)
* 「人間というのは都市の中でしか生きることができない。そして都市は必ず歴史をもっている。こうした人間の現実のなかで希望とは何か。希望とは決して明るい未来が切り開かれることではなく、何かより幸福な生活が訪れることでもない。何が希望かと言えば、自分では読み解けない文字の中にいてそこで生きているのだということをわれわれが少しでも自覚すること。それしか希望はないのだと思います。」
と、毎度ながらこう語っているのはわたし自身。今日はひさしぶりに1歳半と5歳の孫と遊びましたが、基本的には判で押したような生活。書くべきこともないときの逃げの一手ですが、自分の昔の仕事を整理していて、こんなこと言っていましたか、となんだか、今の状況にもあてはまりそうだと思ったわけです。2003年の『ユリイカ』3月号、建築家のダニエル・リベスキンドの特集でした。わたしはかれのユダヤ博物館(ベルリン)も見に行ったりしているし、かれがヒロシマの賞をもらったときの授賞式にも列席しているのですが、このときは時間がなくて原稿が書けなかった。そうしたら、編集者がどうしても、と談話の原稿になったのでした。だからかえって自由に喋っているのかもしれませんが、「歴史」というのは読むことのできない文字の断片の回廊なんだ、みたいなことを言っていて、その最後に「希望」を語ろうとしているわけでした。もちろん、わたしにとっての「希望の哲学」の究極であるベンヤミンの「希望』論ともつながってくるのですが、自分のための希望ではなくて、他者のための希望ですね。いや、他者のための希望であるなどということは自分では決定できることではない。それでも、誰かに希望を届ける存在でありたいなあ、ということかしらね。
ともかく、自分自身が行動した結果の膨大な断片を整理していると、ときどきまったく忘れている自分自身の過去の思考にびっくりすることがあります。
(でも、いまや、この「読めない文字」がウィルスの遺伝子情報という見えない「文字」となってしまっているのかもしれませんね。それを「自覚する」ことで、いったいどのような「光」が差し込むのか・・・)