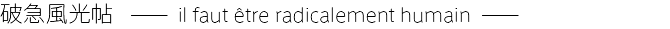★ 日日行行(261)
* 昨日の朝ですが、筑波大学で開かれた第3回European Association for Japanese Studiesの国際会議の冒頭、ドイツから来た考古学のMark Hudsonさんに続いて、基調講演をしました。
1月に出版した中島隆博さんとの共著『日本を解き放つ』を語るには、もっともふさわしい場所だったと思います。なにしろ発表者の多くは、日本在住あるいはこのためにいらした人も含めて、ヨーロッパ国籍の研究者たちですから。発表は原則、英語のようなのですが、わたしは、45分の短い時間でお話しするには、と、やはり日本語でやらせてもらうことにして、この本に収められたわたしの4本のエッセイを貫く「3点測量」、カラダ・コトバ・ココロのマクロパースペクティヴを駆け足で語らせてもらいました。
このような国際学会は、ある種の「知」の祝祭。そこでのKey Noteスピーチは、なによりもこの場そのものを「ことほぐ」ことをしなければならない、というわけで、冒頭では、武満徹さんの「November Steps」の一部を聞いてもらい、最後には、「いま」のわれわれの時代ということで、坂本龍一さんの2017年のアルバムasyncから、東日本大震災の「津波ピアノ」による曲「ZURE」の一部を響かせました。
67年と17年、この間がちょうど半世紀。それは、まさにわたしが生きた時代でもあったわけで、そのような個人的な感慨もどこかに秘めて、ヨーロッパの日本研究の方々に、空海・世阿弥・漱石と日本文化を展望するわたしなりの「大風呂敷」を広げさせてもらいました。
このEAJSの現在の会長は、スロヴェニアのアンドレイ・ベケッシュさん。わたしと同年代。かれとは20年前くらい前かなあ、1、2度、会ったことがあるのですが、今回、泊まったホテルのロビーで顔を合わせるなり、「あのとき、きみは、カーネーションの花を一輪ずつ女性たちに手渡していたんだ、それをよく覚えている」と。こちらはまったく記憶がないのですが・・・いずれにしても、会議とはまた別に、主催者の筑波大学の青木三郎さん(こちらも古い友人です)らとともに、二晩にわたって、おいしいワインをいただきながら、楽しく知的な会話を楽しみました。UTCPのときは、自分自身はつねに主催者側だったのですが、このように、ゲストの側に立つのもなかなかいいですね、Orgnisation への責任を免れているのでリラックスできて。
今日の帰路、雲は多いけど、秋の光が落ちてきます。この光を迎え容れる「からっぽ」が必要だなあ、と疾走するつくばエクスプレスの車窓を流れる田園風景を眺めながら、自分に言い聞かせておりました。il faut tenter de vivre (いざ、生きめやも)という感じがします、はい。