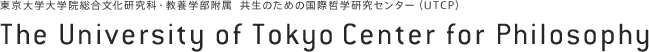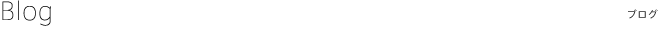【報告】東田直樹・綾屋紗月講演会「自閉症とアスペルガー症候群―コミュニケーションのかたち」
2010年7月18日(日)、来場者約180名、ほぼ満員の会場で、自閉症当事者の東田直樹さんとアスペルガー症候群当事者の綾屋紗月さんが講演した。二人とも特徴的なしかたで発表を行なった。以下でそれぞれの発表内容を紹介し、感想を述べたい。
〈東田講演〉
まず自閉症当事者である東田直樹さん(アットマーク国際高等学校3年生)が、直樹さんの母である東田美紀さんの手で腰のあたりをそっと触れられながらで発表を行なった。触れられていないと、自分の位置がはっきりしないのだという。
東田さんはパソコンの画面を見ながら読み上げていたが、彼は重度の自閉症者であり、うまく会話することができない。うまく話せない理由は、話そうとすると話したかったことを忘れてしまうことにあるという。また、彼がコミュニケーションのさいに補助として利用している「文字盤ポインティング」が彼にとって使いやすい理由を、自閉症者がよく利用する「絵カード」と比較しながら説明した。
また、東田さんの記憶や知覚のありかたは独特である。聴覚の特徴としては、人の声は他の音と混ざって区別が付きにくい。また、雨が降ると、まず音に驚き、「雨だね」と言われるまで、それが何の音でどこから聞こえてくるかが分からず、不安になるのだという。
記憶のありかたにも驚かされる。人の記憶は苦手で場所の記憶のほうが得意である。というのも、人は動いたり変わったりするが、場所はそうではないからである。また、記憶が線でつながらず、「昨日のことも1年前のことも同じ」である。つまり時間の遠近感覚がない。
さらに、東田さんは、よそ見をしていて話を聞いていないように見える時でもちゃんと聞いていること、要求を伝えるのが苦手なことを述べ、自閉症者の見かけや言動にとらわれないで接してほしいと訴えた。最後に、一番悲しいことは共感にもとづくコミュニケーションができないことなので、話せない人には話すことにかわる何らかの手段が必要である、と述べて発表を締めくくった。

〈綾屋講演〉
二人目の講演者である綾屋紗月さんは、手話による発表を、熊谷晋一郎さんによる通訳つきで行なった。綾屋さんは声を使って話すこともできるが、声をつぶして話す。また自分が大声になっても気づかない。こうしたことの理由を、発声の調整の際に利用する4種類のフィードバックの利用のしやすさ/しにくさの観点から分析した。
彼女によると、主要な原因は、「空気を伝わってきた自分の声の反響音と、他のノイズを等しく拾ってしまう聴覚」にあるという。手短かに言ってしまうと、自分の声を、空気を伝わる直接音・反響音を聴きながら調節するのが難しいので、身体を伝わる音(振動)を頼りに調節しようとして、身体を伝わりやすい「嗄れた声」を選んだのである。また、空気中を伝わる自分の声のフィードバックは(他の音と混ざるため)ワンワンとうるさいので(ヒトリ居酒屋現象)、自分の声を聞こうとして、声が大きくなってしまうのである。
綾屋さんはこうした分析にもとづいて、自分の声で無理なく話すための方法として「言葉の間隔をあける」「手話つきで話す」等の方法を実践した。実際に話すときは、発声の調整だけでなく、直前や現在の発話の意味を確認しながら、次に話す内容について思考する必要がある。綾屋さんの場合、同時に意識的に行なうことが難しい、これらのことがらを意識的に行なう必要があるため、工夫が必要となるわけである。
まず「言葉の間隔をあける」ことにより、これらのことを同時にではなく、交互に行なえるようになる。また、手話は運動指令との対応が(環境の変化に影響されないためか)明確なので、調整が無意識化・自動化しやすい。そのため、思考と手話は並列化が可能なので、自分の現在の発話の意味を自動的に確認しながら、次の発話内容の思考に専念できるのだという。

〈講演から感じたこと〉
最後に、「心の理論」や自閉症に関する仮説を検討している報告者の立場から(偏った)感想を述べてみたい。
「心が読めない」、あるいは「『心の理論』に発達の遅れがある」という自閉症・アスペルガー症候群のイメージに対して、当事者たちが指摘しているのは、彼らが実は知覚の独特さを抱えている、ということである。記憶は知覚を材料にして作られるのだとすれば、東田さんが述べていた記憶の独特さは、知覚の独特さの結果かもしれない。ただし、もちろん個人差もあるだろう。まず、二人が発表の中で指摘した知覚の独特さは同じものだとは必ずしもいえない。また、知覚が仮によく似ているとしても、それ以外では個人差があるかもしれない。総合討議でそのことを示すやりとりがあった。来場者から手が上がり、東田さんが発表中にときどき発表の文脈とは関係ない言葉を叫んでしまうことについて質問がなされたのだが、そのとき綾屋さんが「自分の場合、疲れてくると(関係ない)言葉が侵入してきて苦しいのだが、東田さんも同じように苦しいのではないか」と心配そうに尋ねると、東田さんは「単に衝動的に言葉が出てしまうので苦しくはない。心配してくれてありがとうございます。」と答えたのである。当たり前だが、当事者の体験には個人差もあるようだ。
東田さんにとって、どうして記憶が線でつながらないのか、綾屋さんのいう「思考」とは何なのか。語りきっていない点、解明されていない点は、まだまだたくさんあるものの、こうした当事者研究は、知覚、記憶、思考などの詳細なプロセスを描きだすことで、これまでの理論的研究を再考させる契機となる可能性を秘めている。しかし、問題も山ほどある。語られた内容に個人差があるという問題、そしてそもそも彼らは健常者とは異なるプロセスで言葉を獲得し、従来とは異なる方法で語っているという問題もある。当事者にとって語りとは何なのか、また研究者を含め周囲の人々はその語りをどう受け止めるべきかを、今後も議論していく必要があるだろう。
報告:朴嵩哲 (東京大学大学院総合文化研究科博士課程/UTCP共同研究員)