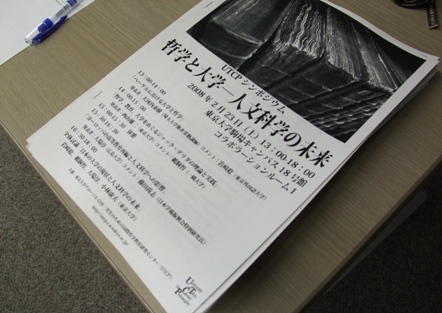【報告】土曜日の時間性―シンポジウム「哲学と大学―人文科学の未来」
本シンポジウムは、UTCPの公開共同研究「哲学と大学」の一環として開催されるものである。公開共同研究「哲学と大学」の目的は、各哲学者の大学論を批判的に考察することで、哲学と大学の制度や理念との関係を問い直すことである。「哲学と大学」の問いは日本では大学紛争の1960年代末にとくに議論され、実際に『理想』誌(1969年1月号)、『実存主義』誌(1969年4月号)などで特集が組まれている。現在、グローバルな市場原理主義によって効率性や収益性の論理が社会そして大学を席巻しているが、そうした状況において哲学や人文学の意義を再び問うてみたい、というのが本研究会の趣旨である。
1. 教養・体系・国家:ヘーゲルにおける「大学」と「哲学」
発表者:大河内泰樹(埼玉大学他非常勤講師) コメント:岩崎稔(東京外国語大学)

ヘーゲルの大学論・教育論の文献はギムナジウム校長・ベルリン大学学長としての式辞、ハイデルベルクおよびベルリン大学での教授就任演説など数少ない。だが、ヘーゲルがエンチュクロぺディー(体系)を志向したことから彼の成果すべてが教育論だったとも言えるのではないか。なぜなら、エンチュクロぺディーはそもそも円環の中にある教養(enkyklios paideia)を指し、円環運動に即して包括的知が獲得される過程であるからだ。ヘーゲルにとって、哲学教育はギムナジウムの「エンチュクロペディー」においても大学での「哲学」においても「予備学」に過ぎないとされる。しかし、哲学自体がまさに予備学であるにすぎず、予備学の向こうには何も存在しない。この意味で、ヘーゲルの教養は理想的な人間のモデルへと人間を形作ることではなく、自己否定の反復が哲学による教養の目的となる。
ヘーゲルによれば、「真理の認識はその目的を外部にもたない以上、有用ではなく」、「哲学との交通は生活の日曜日(der Sonntag des Lebens)とみなされうる」。コジェーヴが強調して有名になったこの「人生の日曜日」を、大河内は宗教から哲学への移行、『創世記』の日曜日の世俗化として解釈する。ヘーゲルは世俗化された日曜日の場所をプロイセン国家によって保証された大学とみなしていた。大学での教養や哲学の教育によって獲得されるのは、何らかの拠り所となるような有用な常識や健全な人間悟性ではない。ヘーゲルにとっての大学とは否定性が作用する安息のない日曜日の無用性そのものなのである。
岩崎稔氏はまず、国立大学の独立行政法人化反対運動への彼自身のコミットメントは、ヘーゲル哲学の研究とはどこかで重なっていたと幾分控え目な声調で告白する。「人生の日曜日」については、ヘーゲルはそもそもキリスト教的表現を世俗化する達人であり、ここにも労働と休日の関係が有用-無用の対概念でもって上手く表わされている。通常、日曜日とは労働の後で人間が自分の力を再び獲得する時間である。『創世記』にならえば、世界創造の後で神が振り返って自らの創造物を見るという認識の時間である。ヘーゲルにならえば、その役割を継承するのが哲学であり、世界史の展開を事後的に思考することが哲学を日曜日たらしめるのである。最後に岩崎氏は、教養を否定性とともに規定するヘーゲルの考え方は実に魅力的であり、今後もヘーゲル思想とともに大学や教養について批判的な考察を続けたいと力強く言葉を締めくくった。
2. 哲学、教育、大学をめぐるジャック・デリダの理論と実践
発表者:西山雄二(東京大学) コメント:鵜飼哲(一橋大学)

ジャック・デリダはフランスでは伝統的な大学制度の門外漢だったものの、哲学と教育、哲学と大学の関係を実践と理論の両面で真摯に問い続けた。発表では、哲学、教育、大学をめぐるデリダの実践と理論を概観した後、哲学と大学という主題をめぐってデリダがカントをいかに読み解いたのかが論じられた。
デリダは晩年の大学論『条件なき大学』において、大学の無条件性として〈すべてを公的に言う権利〉を提唱する。当然ながら、すべてを公的に言うことなど事実としては不可能であり、これは事実と権利の間での交渉を要求する。〈すべてを公的に言う権利〉はカントの公表性に類似しているように見えるが、しかし、それはいまだ知られざる真理を十全に開示すること(情報公開による説明責任)ではなく、むしろ、秘密や嘘、偽証といった類をも含む虚構と紙一重の権利である点でカントの公表性以上のものであるだろう。また、カントが「理性が公的に語る権利」を哲学部に求め、この権利を大学の建築術的構図の要としたのに対し、デリダは〈すべてを公的に言う権利〉を大学の主権を保存する特権(学問的自由)ではなく、大学を創造的な変形へと導く力だとする。大学における真理論と大学の制度論の結節点に働きかけるこの権利は、たしかに、大学の主権を強化することのない弱さや脆さと隣り合わせの原理である。しかし、これはきわめて両義的で微妙な点だが、〈すべてを言う権利〉は政治的、法的、経済的な力が大学を我有化しようとする場合、これらに創造的に抵抗する力としてかろうじて残余するともされる。
鵜飼哲氏はデリダの卓越した読み手として、『条件なき大学』をめぐって補足的な、だが、本質を見事に浮かび上がらせるコメントを加えた。『条件なき大学』は大学教師をめぐる職業論、労働論でもある。デリダはprofessionの語源「公的に語ること」にさかのぼり、教師(professeur)の職務をある種の信仰告白(profession de foi)として規定する。フランス語professionのドイツ語はBerufであるが、ウェーバーの分析からもわかるように、職業論は宗教と世俗に深く関わる。また、19世紀から20世紀にかけて、近代の大学モデルはドイツ(とくにベルリン大学)からアメリカへと移行したが、これはプロテスタント圏で大学モデルが形成されてきたことを意味する。デリダはこの文脈を十分に意識し、宗教と世俗の問いを絡めつつ、職業の観点から大学論を執筆しているのではないか。
また、〈すべてを公的に言う権利〉だが、明示してはいないものの、デリダはこの表現をブランショから引いている。ブランショはサドのエクリチュールを参照しつつ、「数ある自由のなかでも第一のものはすべてを言う自由である」とする。つまり、〈すべてを公的に言う〉という公表性をめぐって、カント、サド、ブランショ、デリダが複雑に絡み合い、啓蒙と脱構築、理性と狂気、文学と政治の問いが錯綜しているのである。
3. ヨーロッパの高等教育再編と人文科学への影響
発表者:大場淳(広島大学) コメント:藤田尚志(学術振興会特別研究員)

大場氏はまず、欧州における高等教育再編の流れを概観した。欧州では1999年以来、2年ごとに高等教育担当大臣の会合が開かれ、欧州高等教育圏の枠組みが議論されてきた(ボローニャ・プロセス)。EUの国際競争力を高める戦略の一環として、高等教育や研究のネットワークづくりが進められている。この過程でとくに重視されているのが、共通の学位制度の構築と高等教育の質保証である。後者については、研究教育の市場化とともに、提供される「商品」や「サービス」の質の確保が制度化されてきた。伝統的な大学の自治の論理ではなく、評価制度、情報公開、利用者(学生)の参加といった要素が大学には不可欠となる(日本では学生の参加が著しく遅れている)。さらに、大学評価を学生(利用者)がおこなう場合、例えばスコットランドのように学生自身が事前に研修を受けて、意識と学識を高めるというやり方は斬新だった。
ボローニャ・プロセスに法的拘束力はないため、各国の対応には温度差がある。逆に言えば、欧州規模での画一的な教育再編が進行しているのではなく、各国制度の多様性や質保証(市場化)の多様性が保持されているのである。そして、重要なことは、規制緩和(市場化)か大学の保護かという二者択一ではなく、各国政府が責任をもって高等教育を統制していくことである。
人文科学への影響であるが、フランスでは人文科学の学生や教員の数は近年さほど変化していない。ただ、その内部では多様な変化が生じており、美術史、社会学、心理学が90年代末に拡大し、英語以外の語学は衰退傾向にある。また、職業専門化が奨励され、職業学士が創設されると優秀な学生はそちらに流れていったという。
最後に大場氏は基礎研究を市場化から守ることの必要性を主張した。そのためには、例えば日本でも、大学人は自らの社会的な説明責任を果たしつつ、各国立大学や国大協、さらには文科省などあらゆる関係者と積極的に交渉をし、立体的な議論を展開させることが重要だとした。これはこの日もっとも印象に残った重要な主張のひとつだった。

藤田尚志氏は絶妙な語り口でコメントし、ユニークな視点から哲学と大学の問いを提示して聴衆を魅了した。哲学や思想に携わる者は自分がどのような場所で思考しているのかを問う必要がある。例えば、日本ではドゥルーズ、デリダ、フーコーと並置されるが、彼らがいかなる学術機関に所属し、哲学の教育研究制度にいかに関係したのかはそれぞれ異なっており、思想研究者はそうした基本的な差異に敏感になるべきだろう。また、ヘーゲルは日曜日だけでなく、『信と知』の末尾で聖金曜日にも言及している。日曜日が無用性の安息日だとすれば、金曜日はキリストの復活した日である。平日と日曜日、有用と無用のあいだの対立(例えば市場原理VS大学)ではなく、両者の異質な仕方での交渉を誘発することが大学や哲学の使命ではないだろうか。
4. 全体討議「日本の大学の現状と人文科学の未来」
参加者:岩崎稔、鵜飼哲、大場淳、小林康夫 司会:西山雄二

まずは、大学と新自由主義の関係をつねに問い続けてきた岩崎氏が、国立大学法人化以降の現状を力を込めて報告した。2004年に法人化が実施されて以来、ボディブローのようにその影響が旧来の大学に響いている。高知大学の学長選挙疑惑問題など、その影響が顕著となったのが2007年度だった。大学の慣習法が変質し、学長が独裁的にやろうと思えば何でもできる体制が「トップ・ダウン方式」の美名のもとに整いつつある。
次に、鵜飼氏はフランス語教師の立場から大学の第二外国語の現状について語った。英語優勢の状況下でたしかに仏独語のステータスは下がっている。だが、中国語への関心は高まり、その履修者が増加したために、第二外国語全体の意義は保持されている。今後はEUの動向を見据えながら、仏独語の中心的ヘゲモニーを弱めつつ、イタリア語・スペイン語を含めて外国語を拡充する必要がある。国際的教養を維持するために、大学では第二外国語必修を維持することが望ましいと述べた。

大場氏によれば、学長のトップ・ダウン方式と言っても、アメリカのように、大学教員と学長のあいだで双方向的な意志表示の回路が確立していることが望ましい。日本でも大学運営への学生の参加の可能性を含めて、文科省、学長、教員など関係者のあいだで意識が共有され、互いの意見をフィードバックさせる仕組みが必要である。
最後に、小林氏は人文科学の危機に言及した。ここ20-30年ほどのあいだに人類が経験している文化的変容はおそらくかつてないほど大規模なものである。つまり、人間の知が、そして知を生産する大学が「一般化された競争」のなかに完全にさらされてしまったのだ。この競争はたんに学術研究の優劣だけでなく、軍事技術に象徴される国力の競争にも通じる熾烈なものである。だから、この危機の時代に人文学にできることは、人権や民主主義といった人文主義的な概念の守護者であり続けることではないだろうか。大学という枠を越えて思考しつつ、こうした概念が地上から消えないようにすることではないだろうか――小林氏は熱い口調で語った。

その他にも興味深い議論が交わされた。
人文学と新自由主義は実は内在性という点で似た者同士かもしれない。両者とも「外部はもはやない、この舞台で競争に専念せよ、もっと早く走れ」と駆り立てられ、外部の存在に気がつきにくい。内在性の論理に惑溺することなく、いかにして外部を見出すのかが課題となるだろう。
今年は68年40周年だが、あの時代から私たちの現代までに何が変化したのか、その射程を確認する必要がある。それは研究教育の大衆化、国際化、情報化、ジェンダー性といった課題である。新たな変革を着想する前に、この前の変化を見定めることが重要だ。
領域横断的な研究は重要である。例えば、先頃来日していたドミニク・レステル氏はもともと動物行動学の専門家だった。後に哲学研究へと進路変更して彼は驚いた。動物行動学が従来の哲学的な人間観・動物観の枠組みにいかに深く規定されているのかが透けて見えたからだ。境界を踏み越える彼の視座から、動物行動学と哲学の双方が脱構築されるわけだ。領域を横断することで既成の枠組みが変容する好例である。
シンポジウム全体を通じて、大学、哲学、人文科学という問いが現代の社会状況において実に多種多様な問題を内包していることがわかった。藤田氏の卓抜なコメントを借用すると、このシンポジウムが開催されたのは土曜日である。金曜日と日曜日のあいだ、復活と安息のあいだの時間である。一方で、私たちはもはや旧来の大学への回帰や人文科学の十全な復活を夢見ることはできない。また他方で、市場原理的な競争のなかで、新たな大学や人文科学の形を模索する私たちにとって、十全に休息することなどとても叶いそうにない。だからこそ、引き続き共に問い続けることにしたい――哲学や人文科学、大学を通じて、いまなお、私たちは何を希望することを許されているのか、と。伝統の復活と競争後の安息のあいだで振動する、あの両義的な「土曜日の時間性」に踏みとどまりながら。
(シンポジウムには50余名の参加があり、大阪や山口からはるばるお越しいただいた方もいました。足を運んでいただいたすべての参加者に感謝します。)
(文責:西山雄二)