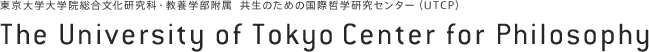書誌情報】
中島隆博
『共生のプラクシス 増補新装版 国家と宗教』2022年、東京大学出版会
ISBN:978-4-13-010155-4
【目次】
プロローグ 他者たちへの想像力
第I部 原初的な共同性をめぐる思考
第1章 小人がもし閒居しなければ──朱熹の思想
1 中国思想における公共空間
2 「小人閒居して不善をなす」
3 悪の場所
4 君子の「独」と小人の「独」──「他者を予想する境地」にいる小人
5 「誠意」という関門──小人の間の分割
6 自ら欺く──君子の場合
7 自ら欺く──小人の場合
8 「半知半不知」
9 君子は小人である──巨悪について
10 王船山の批判と他人の存在
第2章 小人たちの公共空間──明代の思想
1 小人の君子化と「知」から「良知」への移行──王陽明
2 「無善無悪」と「信」──王龍渓、銭徳洪
3 「愚夫愚婦」の「公論」──繆昌期
4 代理=代表の空間──黄宗羲
5 小人の朋党──欧陽脩、高攀龍
6 渦巻きの共同性
インタールード1 他者たちを再び結びつける地平──ジャック・デリダの思考
1 「絶対的起源の根源的差異」──デリダとレヴィナス
2 「超越論的歴史性」と〈超越〉
3 時間の超越論的エコノミー
4 返済なき贈与──『時間を与える』
5 犠牲のエコノミー、エコノミーの犠牲──『死を与える』
6 涙を流す瞬間──『盲者の記憶』
7 正義の時間──「複数の純粋な特異性を再び結びつけるだろう」
第II部 他者を再定義する仏教のラディカリズム
第3章 魂を異にするものへの態度──明末の仏教とキリスト教
1 「殺生は人のなすことではない」──雲棲袾宏の「戒殺生」
2 「殺生を戒める道理などない」──マテオ・リッチによる批判
a 魂を異にするもの──人間と動物の差異
b 魂のダブル・スタンダード──他人との差異
c 他なる人間中心主義と倫理
d 「仁の模範」と魂のエコノミー
e 肉を喰らうこととその抑制
3 〈食べること〉の肯定──李贄と戴震
4 〈美味しく食べること〉から〈殺すこと〉へ
5 殺生は断じて行うべきではない
6 「忍びざる心」を理解し直
第4章 強死せし者と死体の方へ──六朝期の仏教と儒教
1 神滅不滅論争──范縝、蕭琛、曹思文
a 范縝の形神相即論
b 仏教徒の批判
2 死者と死体
a 木と人、死者と生者
b 死体に変じる
c 死神
d 余分な死体
3 神の複数性と他者との交わり
a 神の複数性と一性
b 沈約の批判──神の名
c 二つの心──心器をめぐって
d 思慮は他の部分にもやどるのか
e 他人の心との交渉
4 人間の間の区別──形神相即論を超えたイデア的器官
5 人間の間の区別を破る──自然なる世界
a 神滅の効用
b 自然は性による人間の間の区別を破る
6 強死せし者
a 経書に記載された祭祀と鬼神
b 蕭琛の批判
c 曹思文の批判
d 強死の回避──「自然」と「独化」の死/他者との関係における死
7 マン-メイド・マス・デス(人の手による大量死)
第5章 死者を遇する〈倫理〉──仏教と生命倫理
1 現代における生命倫理と仏教
2 「自然」と「道徳」
3 捨身・布施──臓器移植を容認する仏教的言説
4 自己決定
5 「死の作法」、道徳化からの切断──臓器移植に対抗する仏教的言説
6 死の時間─神滅不滅論争の争点
7 臓器移植とカニバリズム
8 動物を殺してはならない──「戒殺生」の争点
9 死者を死者として遇すること
10 仏教のラディカリズム
インタールード2 他のものになることの倫理――ジル・ドゥルーズと中国
1 生成変化――『千のプラトー』
a 近傍と此性の構成――全く違った個体化の様態、そして世界
b 他の近傍もまた変化する
2 独立した個体の間の反自然的な予定調和
a 反自然的な共感の統合――『経験論と主体性』
b この同じ世界――『襞』
3 壁を通り抜ける技法――ドゥルーズにとっての中国
a 抽象線に自らを切りつめる
b 欲望を整序するものとしての中国
4 他なるものに化すこと――『荘子』胡蝶の夢
a 胡蝶の夢――他者の立場に立つことはできない
b 能動性を欠いた肯定による非倫理
5 内在の倫理
第III部 共生の思想としての儒教の方位
第6章 儒教の近代化の行方――中国の新儒家
1 現代新儒家の背景
2 新儒家の定義
a 宗教的であること
b 文化と哲学
c 正統と合法――「道統」について
d 新しい「外王」と「中体西用論」の後裔
3 最後の儒家か、最後の仏家か――梁漱溟
a 『東西文化およびその哲学』――─仏家から儒家へ転向したのか
b 「最後の仏家」
c 梁漱溟と熊十力(一)――「熊十力は儒家に、わたしは仏家に帰属するべきである」
4 仏教から儒家思想へ――熊十力
a 『新唯識論』と「境識同体不離」
b 儒家思想の導入――『原儒』、『乾坤衍』
c 梁漱溟と熊十力(二)――「内聖外王の学」の失敗
5 仏教の再導入――牟宗三
a 熊十力との出会い、梁漱溟との距離
b 熊十力と梁漱溟の間で――「新外王」と「曲通」の道
c 牟宗三のプログラムと「自覚的な自己否定」
d 神妙なる融即――「一心開二門」から「天台円教」へ
6 哲学化された仏教とそれを超えるもの
第7章 国家のレジティマシーと儒教――現代中国の儒教復興
1 国家のレジティマシー
2 儒教をどう捉えるのか
3 Civil Religionの系譜学(一)――ジャン=ジャック・ルソー
4 Civil Religionの系譜学(二)――─ロバート・ベラー
5 儒教と犠牲の論理
6 考えるべき論点
第8章 「批判儒教」のために――近代中国・日本における儒教復興
1 二つの世俗化概念―― secularizationとlaicization
2 儒教は宗教なのか(一)――清末から文化大革命まで
3 儒教は宗教なのか(二)――改革開放以後
4 近代日本における宗教と道徳
5 人倫の道としての儒教――和辻哲郎
6 孔子教と哲学的宗教性――服部宇之吉
7 徳教としての儒教――井上哲次郎
8 戦前日本における市民宗教の政治的意味
9 来るべき「批判儒教」
第IV部 市民に息づく宗教性
第9章 儒教、近代、市民的スピリチュアリティ
1 儒教復興
2 近代と儒教
3 台北孔廟
4 原理主義的な儒家国教論と自由主義者のキリスト教的立憲政治論
5 台湾と共和国の伝統
6 長春と市民的スピリチュアリティ
おわりに
第10章 世紀の交の霊魂論――中江兆民、井上円了、南方熊楠
はじめに
1 中江兆民の霊魂論
2 井上円了の霊魂論
3 南方熊楠の霊魂論
4 熊楠と兆民、円了の交差
5 熊楠霊魂論の政治性
6 熊楠のエコロジー
7 哲学などは古人の糟粕
第11章 ポスト世俗化の時代における市民社会
はじめに
1 重なり合う合意――チャールズ・テイラー
2 世俗的理性と宗教的理性の間の翻訳――ユルゲン・ハーバーマス
3 ポスト- デュルケーム的体制
4 今日におけるマテオ・リッチ
5 ローカルな宗教性
おわりに
エピローグ 共生のプラクシス
あとがき
増補新装版へのあとがき
公式サイトはこちら
|