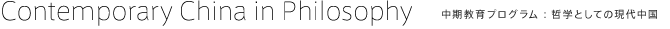水口拓寿氏講演会(2007.11.27)報告
11月27日、中国儒学班は東京大学人文社会系研究科の水口拓寿助教をお招きし、「台湾における孔子廟と釈奠儀礼の沿革―台北の事例を中心として―」というテーマで講演して頂いた。

水口氏は教養学部にて文化人類学を学ばれたあと、人文社会系研究科東アジア思想文化専門分野に進学なさり、現在は助教として教鞭をとるかたわら、風水を中心に研究なさっている。今回の講演は氏が台湾の中央研究院に留学した際、実際に台北市立の孔子廟で釈奠儀礼に参加した時の経験をふまえ、文献資料も豊富に利用して分析を加えたものである。
水口氏はまず、2001年9月28日のマスコミ報道から話を始めた。それは、台北市孔廟で八佾の舞が動員された背景に、当時の市長馬英九氏の意図はあるのか?という報道だった。八佾は『論語』や『春秋公羊伝』で天子の舞とされるものである。台北市の市長が主宰する祭祀で、天子の舞を行ったことが紙面を賑わせたのである。
中国儒学班は10月以来、中国曲阜における孔子文化節や新儒家と呼ばれる人たちの言説を分析し、儒学復興を文脈化しようと試みているが、今回の台湾の事例は、孔子廟を舞台に儒学復興を試みる中で、さまざまな政権の思惑が交錯していった事例として捉えることができる。今後の儒学班の研究にも大きな見通しを与えたと言えるだろう。
水口氏はまず、孔子廟と釈奠について、歴史的沿革から礼学的解釈までその概要をわかりやすく説明された上で、祭礼の映像を見ながら細かく解説を加えられた。礼生のかけ声とともにひとつひとつ次第が消化されてゆく様は、普段文献から儀礼を研究する者にとって大変刺激的な映像であり、祝文や供物を焼くところまで行う綿密なやり方に、曲阜の場合とはまた異なった、伝統文化復興のありかたを感じた。
孔子に対する封号は、明代に王から師へと変容したという。また、釈奠は清代最末期に中祀から大祀に昇格し八佾の舞が行われることとなったが、台湾はそれ以前に日本領となったため、その変更を経験せず、そのため六佾の舞が継続されていたという。日本統治下においては、日本の孔子廟における祭祀と同様に神式で祀ったが、戦後蒋介石によって釈奠儀礼の改制が指示された。新しい制度では漢民族の様式に復古することが目的とされ、明朝で制定されたものが復活したという。そして将来的には大祀八佾を目指すことが約定されたが、水口氏は大祀といっても供物を入れる容器の数などまでが変わるわけではなく、大成殿の外で行われる(目に見える)舞だけを拡大したに過ぎないことを指摘した。そして、改制された制度では明朝式を標榜しながらも、物量的に豊かで「荘厳な」清朝様式を部分踏襲したのではないかと自身の見解を述べられた。
水口氏は孔子廟改制のスタンスとして「正しい礼楽」と「誤った礼楽」を、また「我らに繋がる伝統」と「彼らに由来する伝統」を弁別した上で、それぞれ前者を補強し、後者を排除するという態度を指摘したが、実に的を射た指摘だと言えよう。曲阜の場合、このような態度を同じように見出すことはできるのだろうか。和を標榜していた曲阜での事例は、礼楽の正誤の弁別を行えるのだろうか。そして、彼らにとって何が「我らに繋がる伝統」だったのか。
今回の講演から読み取るべきことはあまりに多く、私自身まだうまくまとめることができない。以下に述べる内容は、あくまで個人的な感想に過ぎないということを了解願いたい。
今回改めて気づかされたのは、祭られる対象が、伝統中国で祭祀の対象として最も重視されていた天や地の祭祀ではなく、孔子であるという事実である。そして天や地の祭祀は確かに規模は大きいものであったのだろうが、ここまで一般の人々が巻き込まれる仕組になっていただろうか。今回見た映像では児童が楽舞を行う場面があったが、水口氏によれば、これらの教習は学校という場を介して行われ、祭祀当日子どもたちは朝早くから準備し、祭祀が長時間にわたるため身体的負担も小さくないようだ。師である孔子の祀りにおいて、学生である児童が一生懸命楽舞を奉納するという構図は、ある意味孔子廟における祭典のあるべき姿を体現しているとも言えよう。また、祭祀の主献を市長がつとめ、分献を市長に次ぐ役職の者がつとめ、礼生には地元の教員などがあたるという、非常に地域密着的なあり方は、国際を標榜する曲阜の例とはやはり異なるあり方だろう。
国家祭祀の中心は天や地で、それらを祀るのは皇帝の役目であり、皇帝以外の者が祀るのは許されなかった時代と比べるとどうだろうか。国民は堂々と「現代の大祀」に参加できるのである。参加できるどころか、学校という場を介して子供にまで参加することが求められる状況である。このように考えるならば、台北の孔子廟をめぐる儀礼は、単なる儒学復興というだけでは足りない力をもって現代によみがえっているのではないか。儒学というものが以前持っていた力よりももっと強いものを抱え、大いに人びとを巻き込んで迫ってきているのではないだろうか。
(田中有紀)