
|
Title: | UTCPワークショップ「近代東アジアの思考を解きほぐす――中国語圏の文学から」終了しました |
||
|---|---|---|---|---|
| Date: | 2010年12月21日(火)17:00-19:00 |
Place: | 東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム4 [地図] |
|
東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター」(UTCP)
中期教育プログラム「近代東アジアのエクリチュールと思考」主催
ワークショップ
近代東アジアの思考を解きほぐす――中国語圏の文学から
近代以降の東アジアでは、人々の様々な表現行為を担う「文体」のシステムと、それによって表現される「思考」とは、相互に影響し緊密に絡み合いながら複雑な転換を遂げていく。本ワークショップでは特に形式としての「文体」が持ちえた影響力に焦点をあてて、三名の若手研究者による報告を行う。魯迅研究・広東語研究の専門家である代田智明・吉川雅之両氏をコメンテータに迎え、フロアを交えた討論を展開していただく予定である。
2010年12月21日(火)17:00 - 19:00
東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム4
使用言語:中国語・日本語(報告は訳稿配付、質疑応答のみ逐次通訳有り)
入場無料・事前登録不要
プログラム (報告60分、コメント30分、討論30分)
報告:
張麗華(シンガポール南洋理工大学)
越境する文学ジャンル――魯迅「狂人日記」とアンドレ-エフ「心」(Mysl')の対照を中心に
(文類的越界旅行――以魯迅《狂人日記》与安特来夫《心》(Mysl')的対読為中心)
⇒アブストラクト(提要)
李婉薇(香港嶺南大学)
啓蒙と革命と文人的戯れと――清末民初の広東語創作
(啓蒙‧革命‧遊戲:清末民初的粤語写作)
⇒アブストラクト(提要)
津守陽(UTCP)
「いなかもの」は夢を見るか――沈従文と泉鏡花の文体比較から
(“郷下人”会做什么夢?――以沈従文和泉鏡花的文体比較為切入点)
⇒アブストラクト
コメンテータ:
代田智明(東京大学)
吉川雅之(東京大学)
⇛【報告】
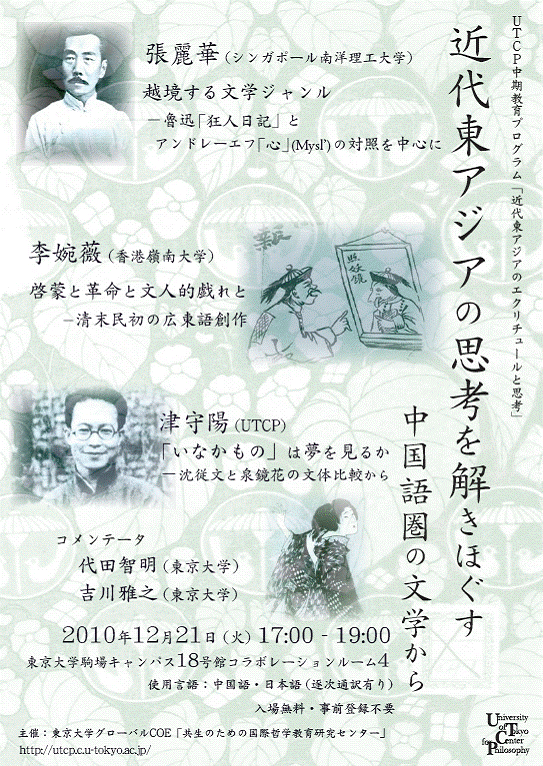
アブストラクト:
張麗華
越境する文学ジャンル――魯迅「狂人日記」とアンドレ-エフ「心」(Mysl')の対照を中心に
20世紀中国における「短編小説」というジャンルは、大抵の場合Short Story(英米)やConte(法)、Erzählung(独)など欧米のジャンルの概念が直接移植されたものとみなされてきた。しかし文化を横断する文学交流や伝播の過程において文学ジャンルを理解するとき、それが文学伝統や文化心理・読者集団などの移植不可能な要素に関わってくる以上、ジャンルの概念は決して透明な存在ではありえなかった。文化を越えるジャンルの「旅」が遭遇した改竄や変形をたどれば、そこには異なる文学や文化の系統が接触したときに発生する拮抗や妥協の痕跡を見出すことができる。本報告は魯迅(1881-1936)の著名な短編小説「狂人日記」を例にとり、この作品の文学上の「先輩」の一人である短編小説、すなわち形式の上で非常に似通った特徴を持つ、ロシアのアンドレ-エフ(Leonid N. Andreev, 1871-1919)の小説「心」を照らし合わせて読んでみたい。これによって、魯迅が海外の文学ジャンルを移植・転換した過程を描き出すだけでなく、魯迅がこれを基礎として近代中国における短編小説というジャンルにどのような文学形式上の意義を築き上げたのかについて探りたいと思う。
「狂人日記」は明らかに「心」(本報告は清末の陳冷血による漢訳本を用いた)の形式と構図を模倣しているが、その主人公と世界の関係については根本的な転倒を行っている。「心」の主人公は自ら外部の世界と手を切っている、無限に拡大する自己意識の一種として描かれる。しかし「狂人日記」は「狂人」の内面世界に関する直接の描写を一掃し、「狂人」の自己意識を周囲の世界との「見る-見られる」といった相互関係の中にうちたて、これによって外界に対する批判の視点を獲得した。「狂人日記」が築き上げた、主人公と外部世界が相互に対象化を行うこうした構図は、魯迅の以後の短編小説を特徴付ける重要な風格の一つとなっていく。またそれだけでなく、この構図は葉聖陶・廃名・台静農ら同時代の作家の短編小説作品にも重大な影響を及ぼしているのである。
文类的越界旅行:以鲁迅《狂人日记》与安特来夫《心》的对读为中心
二十世纪中国的“短篇小说”,在很大程度上,被视为是域外文类如Short Story(英美), Conte(法), Erzählung(德)等的直接移植。然而,在跨文化的文学交流与传播的过程中,文类却并非透明的因素,因其中涉及到文学传统、文化心理乃至读者群体等无法移植的要素;通过关注文类在跨文化的“旅行”中所遭遇的篡改与变形,恰恰可以捕捉到不同文学与文化系统相遇时所产生的对抗或协商的痕迹。本文将以鲁迅(1881-1936)的著名短篇小说《狂人日记》为例,通过将它与其文学上的“先辈”之一——在格式上非常类似的俄国作家安特来夫(Leonid N. Andreev, 1871-1919)的小说《心》(Mysl’, 1902)的对读,来呈现鲁迅对域外文类的挪移与转换,并在此基础上探讨他为现代中国短篇小说这一文类所奠定的形式意义。
《狂人日记》明显模仿了《心》(本文以清末陈冷血的中文译本为根据)的格式与构图法,但同时又对其主人公与世界的关系进行了根本的倒转:《心》的主人公是一个自绝于外部世界的无限扩张的自我意识;而《狂人日记》却放逐了对“狂人”的内面世界的直接描写,而是将“狂人”的自我意识建立在与周围世界的看与被看的相互关系之中,并由此获得了一种对外部世界的批判视角。由《狂人日记》所奠定的这种主人公与外部世界的相互对象化的构图,成为鲁迅此后短篇小说的重要的风格化特征,同时也深刻地影响到同时代的其他作家如叶圣陶、废名、台静农等人的短篇小说作品。
李婉薇
啓蒙と革命と文人的戯れと――清末民初の広東語創作
近代中国の歴史において、民族共通語の確立は重要な変革であった。曲折に満ちたその過程は清末に端を発する。当時の中国はいまだ言文不一致の状態にあり、書くときには文言が、話すときには「母語」、すなわち各地の方言が用いられていた。しかし北方においては、通俗的新聞や雑誌が北京語(北京方言)のような口語を書面語として用いる試みを始めていた。そして南方において、このように自分たちの方言を漢字で直接書記することのできる省はきわめて少なかった。本報告が扱う、広東・広西・香港・マカオ一帯に流通している広東語(粤語)はこの数少ない方言のうちの一つである。
北京語は上記のような南部地域では通行していなかったので、革命思想を広く伝えて民智を啓蒙するためには、広東語は必須の道具となった。革命の志士やジャーナリストたちは広東の説唱文芸を改編し、一般大衆に受容させるべき新しい知識(「種族革命」や迷信の打倒など)を盛り込んだ。これらの説唱文芸は、従来はわりあい文学的で書面的な広東語で書かれ、その題材はたいへん画一的なものであった。しかし新しい内容に適応させるため、それらは非常に口語化された広東語で書かれ、題材も拡大されて、新時代の色彩を鮮明に映し出すこととなる。梁啓超(1873-1929)が横浜で執筆した脚本はその好い一例を示している。またこのころ、ある種の文人たちは広東語による古典詩歌の創作を行っていた。彼ら自身内心では方言の作品は二流のものに過ぎないと感じてはいたが、広東語の生き生きとしたエネルギーに魅せられてこの言葉を手放す気にもなれなかった。そこで一種のてすさび、遊戯的な態度で創作を行ったのである。これらの詩歌は形式上は格調高く、しかし語句は世俗的であり、雅俗の間に位置する一種の文学実験とも呼べるだろう。
北方方言がしだいに主流となりつつも文言がいまだ権威として君臨していたこの時代、清末民初の広東語創作は、全く異なる境地を切り開く一つの対抗的試みとして重要な意味を有している。
啟蒙・革命・遊戲:清末民初的粵語寫作
民族共同語的確立,是現代中國發展歷程上重要的變革。這個曲折的過程是從晚清開始的。當時中國仍然處於言文不一的階段,寫的是文言文,說的是母語,即各地方言。但是,在北方,通俗報刊開始使用北京話這種口頭語言作為書寫的文字。在南方,只有少數省份能夠直接用漢字書寫自己的方言,流行於廣東(Guangdong)、廣西(Guangxi)、香港(Hong Kong)、澳門(Macau)一帶的粵語(Yue),便是其中一個例子。
北京話並不通行於這些南部地區,為了宣傳革命、開啟民智,粵語成為必要的工具。革命志士和報人改編廣東的說唱文藝,譜寫他們要百姓接受的時代信息,例如:種族革命、不可迷信等等。這些說唱文藝,以前都用比較文雅的、書面的粵語,題材很單一化。現在為了配合新的內容,都用了非常口語化的粵語,題材也得以擴大,表現了鮮明的時代色彩。梁啟超(Liang Qichao)在橫濱寫作的一個劇本便是一個好例子。同時,一些文人用粵語寫作古典詩歌。雖然他們心裏認為方言作品是次一等的,但又因為粵語生動活潑的風格而欲罷不能,於是以一種遊戲的態度來寫作。這些詩歌的體式是高雅的,文字卻是世俗的,可說是雅俗之間的文學實驗。
在北方話漸成主流,文言文尚屬權威的時候,清末民初的粵語作品是一次別開生面、意義重大的抗衡。
津守陽
「いなかもの」は夢を見るか――沈従文と泉鏡花の文体比較から
報告者は近代中国の作家沈従文(しんじゅうぶん、1902~88)の作品を通して、中国における〈郷土〉の概念を考察してきた。〈郷土〉は本来「ふるさと」「特定の地方」を指す言葉であるが、しばしば使用者によって「西洋近代に侵食される前の伝統的中国」を具体的に体現してくれる一種の国民的「原風景」として想像される。興味深いのは、この想像が否定的・肯定的態度を問わず、きまって郷里空間的ディテール――「純朴な人情」や「静止した時の流れ」など――を伴うことである。報告者は近代以降に急速に形成されたこの想像力について、沈従文の文学作品がどう関わってきたのかを検討してきた。
これまでに明らかになったのは、沈従文による「いなかむすめ」の表象が、純朴な「原風景」を読者に強力に提供した一方で、同時に一種の文体実験によって「空白の内面」などの特徴を内包したことで、中国〈郷土文学〉における「いなかもの」像や、内面の描写を重視した近代文学の主流とも一線を画す、異色の存在となっていることであった。
辺境に住まう人々の内面を、愛をこめて「(彼らの)夢」と表現した沈従文は、その異色の文体でどんな「夢」を表出したのか。本報告では彼の「いなかもの」の異色性を位置づける試みとして、沈従文同様しばしば圧倒的な存在感を持つ女性形象によって作品舞台の空間そのものを規定した泉鏡花(1873-1939)を比較対象とすることで、日本の「いなか」「郷里空間」表象に関する視点を導入したい。切り口は主に二点を予定している。一つは、「いなかもの」の言葉に地方色彩を与える方言使用の様相、もう一点は、「内面を詳述しない」文章表現が、一種の「国民」に対するセルフ・イメージ(=「原風景」想像)行為との交接点において有する意義である。以上の二点によって張麗華氏・李婉薇氏の報告と対話を成すことを期待するものである。






