【報告】declinationes philologiae
declinationes philologiaeと題された表象文化論研究室主催(UTCP共催)の国際シンポジウムが、事業推進担当者でもある高田康成教授の司会のもと、去る3月17日に開催された。フランス語とドイツ語を主要言語として用いた会だったが、多くの聴衆を迎え、発表後の質疑応答と議論も極めて活発であった。

Emanuele Coccia, Paradosis. Le commentaire philosophique dans le système des genres.
エマヌエーレ・コッチャの発表では、文献学と哲学という二つの学問領域をめぐる知の体制の歴史が古代から現代まで(セネカ、クィンティリアヌスから、シュレーゲルを経て、ニーチェ、ホフマンスタールまで)総攬された。なかでも集中的に検討されたのはルネサンスの人文主義者アンジェロ・ポリツィアーノの事例である。フィレンツェ大学で修辞学の教鞭を執っていたポリツィアーノは、1488‐89年よりアリストテレスの文献学的解釈を開始する。同時代の哲学者たちはこれを修辞学/哲学の境界侵犯とみなし、哲学著作の字句注釈を激しく排撃したが、対するポリツィアーノは、この自称哲学者たちを伝説の吸血鬼ラミアになぞらえて弾劾し、自身は哲学者ではなく「文法家」と称した。それは古代以来、哲学、文献学、その他の知を包括する「文字一般」の学に従事する者の呼称であった。こうしたポリツィアーノの挙措は、コッチャによれば、一方で哲学に対する拒絶(declinatio)の表明であるとともに、他方で、哲学自身の活用変化(declinatio)を含意してもいた。コッチャはこの分析をさらに展開し、哲学的注釈のうちで「言語のふるまい」(アンドレ・ヨレス)の位相が前景化することを指摘した。発表の主導語として選ばれた「パラドシス」という語は、まさに、こうした言語そのものの必然的生成変化、すなわち文字が思弁へと変貌し、また思弁が文字へと変貌する、僥倖の瞬間を指し示していた。

Tatsuya Nishiyama, Hormathos. Une longue série de cercles philologiques à partir de l'Ion.
本発表は、フィロロギアについての哲学的アプローチの事例として、プラトンの対話篇『イオン』を精読した。この対話篇においてソクラテスは、ホメロス朗誦者のイオンを前に、注釈・解釈(ヘルメネイア)の技術に関する自説を展開するが、それによれば、ヘルメネイアは技術によって行われるものではなく、むしろ「神的な力」による透明な伝達であるという。発表者が注目するのは、この透明な伝達(磁力の伝達に喩えられる)の説明に際して効果的に用いられている hormathosという形象である(533E, 536A)。大抵の場合この語は「鎖」と訳されるが、ギリシア語の原義はむしろ「数珠つなぎ」もしくは「セリー」(系列)であり、同箇所で用いられている動詞hormaô(駆り立てる)とも共鳴しながら、「駆り立てられ、掴み取られ、宙吊りにされる」というヘルメネイアの発生状態を記述している。発表者は、近代解釈学においてhormathosが「理解の循環」という形象へと再翻訳されたという思想上の連関を確認したうえで、解釈学からの転回を表明したハイデガーが『言葉についての対話』において解釈学的循環への抵抗を表明するとき(Cf. ナンシー『声の分割』)、そこに内包されているのがまさしくhormathosの他なる解釈の可能性であるという仮説を提示し、発表を締めくくった。
(以上、報告は西山達也)

Shinobu Iso, Hormê. Aristoteles´ Philologie des Belebenden.
磯忍は、アリストテレスがカテゴリー論で挙げるにもかかわらず、のちにカテゴリー表からは抜け落ちる「持つ」を意味するエケイン[ἔχειν](そしてその名詞形であるヘクシス[ἕξις])に注目し、その理由を明らかにするプログラムの概要を提示したのち、まずその内実がいかなるものなのかを明らかにした。アリストテレスによれば、ヘクシスと行為は区別される。しかし、その場合、ヘクシスはいわば状態であって、行為のような「精神的な」、あるいは意図・意志を持ったものとはみなされることはない。それは行為の実現態としてしかみなされないのである。しかし、このような区別ないし関係は維持されるものではない。磯は、アリストテレスの読解に基づき、実はヘクシスこそが、行為の前提であり、かつ行為のうちに維持されているものであることを示そうとする。この関連で提出されるもうひとつの概念が、『形而上学』の第5巻第20章および第23章でヘクシスと同時に用いられ、通常は衝動と訳されるホルメー[ὁρμή]である。磯はこの言葉が語源的に流れるものであることを考慮しながら、ヘルダーリンのピンダロス断片の注釈「生を与えるもの Das Belebende」の流れと生の隠喩的な連関を参照し、ホルメーが流れることを可能にする流れそのもののうちにある流れと堰きとめの弁証法そのものであることを示しながら、ヘクシスとホルメーの機能の同一性を強調する。ヘクシスにしろホルメーにしろ、行為そのものに内在する限りなく記述不可能な契機なのである。最後に磯は、ヘクシスのこのような分析が人格(=ペルソナ)やそのハビトゥスの概念の新たな解釈に接続しうることを示唆して、発表を終えた。

Dan Morita, Rhythmus. Walter Benjamins Philologie des Ursprungs.
本発表は、『ドイツ悲劇の根源』において根源の概念が説明される際に用いられる「リズム Rhythmik」の語に注目し、ベンヤミンの歴史認識の理論を解明しようと試みた。リズムは、オイゲン・ペーターゼンの『リズム』(1917)によると、その語源的な意味、つまり流れることに関係するのではなく、本来は形態、タイプ、特徴(Zug)を意味する。つまり、一定の時間内における特定の反復ではなく、むしろ、そのような反復から浮かび上がる形態こそがリズムなのである。この文献学者による解釈は、ベンヤミンのリズムの用法によく当てはまる。「根源のリズム」とベンヤミンが言うとき、問題であるのは、根源の具体的な形態なのである。またペーターゼンによれば、リズム=形態の語を最もよくあらわすのは、運動全体の表象であり、そのとき最も極端な形態こそが運動全体を表出することができるという(ペーターゼンによれば、振り子を描くとき、それが振り切ったときを描くことによって振り子の運動全体を定着することができる)。このようなリズムに内包されている意味(極端なものの表出)を考慮するとき、ベンヤミンの根源のリズムという表現が、ある歴史、ある時代の行程全体を表出する形態を指示していること(バロックの場合、それがアレゴリーである)が明らかになる。発表の最後には、このリズム概念とベンヤミンの歴史概念の交叉において、メシア的なものが解釈されねばならないことを示唆した。「神学的‐政治的断章」では、「メシア的な自然のリズム」と言われるからである。
(以上、報告は森田 團)

Yoshikazu Takemine, Kapital. Alexander Kluges Philologie der ideologischen Antike.
つづいての竹峰の報告では、ドイツの映像作家・小説家・TVプロデューサーのアレクサンダー・クルーゲ(1932‐)が2008年秋に発表した全長9時間を超える映画版『資本論』(『イデオロギー的古典古代からのニュース:マルクス‐エイゼンシュテイン‐資本論』)をめぐって、映像メディアによる歴史表象が孕みもつ文献学的な次元と、現在において「マルクス主義」という過去のイデオロギーにアプローチするうえでのクルーゲの批判的戦略とを解明することが試みられた。そこでは、ベンヤミンの翻訳論を手掛かりとして、クルーゲの『資本論』映画の企図が、歴史の経過のなかでマルクスのテクストがたどった「翻訳」のプロセスを考古学的=文献学に探究することであること、そして、この作品を特徴づけるラディカルなモンタージュが、誤読と教条化と挫折に織りなされた「死後の生」を批判的に浮き彫りにするための手段であることが示された。つづけて、クルーゲの最終的な狙いとは、マルクス主義という「イデオロギー的な古典古代」を過去の遺物として改めて葬り去ることではなく、むしろ、過去の素材を断片へと破砕し、アイロニカルに組み合わせるなかで、汲みつくされなかった希望や現実化することのなかったユートピア的な理想をアレゴリー的に表現するような新たな布置状況を構成することであったのではないかという問題提起がなされた。
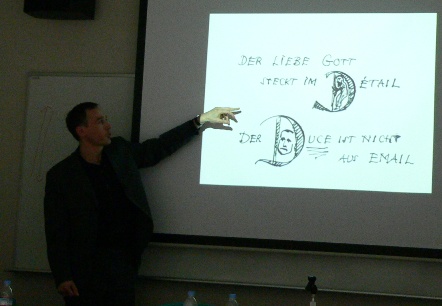
Davide Stimilli, Divinatio. Aby Warburgs Philologie der Zukunft.
コロキウムの掉尾を飾るのは、ダヴィデ・スティミッリによるアビ・ヴァールブルクに関する報告であった。まずスティミッリは、ヴァールブルクの師にあたるヘルマン・ウーゼナーや友人のパウル・ルーベン、息子のマクス・アードルフなどの文献学をめぐるテクストを参照しながら、ヴァールブルクの文献学の思想史的な系譜を丹念に跡づけた。そのなかで、とりわけウーゼナーとヴァールブルクを繋ぐモチーフとして重視されたのが、「divinatio(予見)」というタームであり、古典期には「予言」という意味しかなかったこの言葉が、ルネサンス時代において文献学上の用語として定着したこと、さらに、神々の名の語源学的な究明がルネサンス文献学の新たな課題となったことが、ヴァールブルクの文献学を考察するうえで決定的に重要であることが示された。さらに、「予言」と文献学との関連においてスティミッリは、ヴァールブルクのフランツ・ボル受容を検証しつつ、スキファノイア講演に登場する「怪物 Monstrum」という形象がヴァールブルク文献学の方法論の核心に潜んでいると示唆することによって議論を締めくくった。
(以上、報告は竹峰義和)
私たち六人が扱ったのは、ヨーロッパの思考を支えてきた根幹語ないしは、その活用形と言いうる言葉であった。各々の発表者は、まさにこの言葉の「文献学的」な探求が、同時に「哲学的」な探求であるような交叉点に焦点を絞り、思考が語とそれが持つ記憶や伝統に対する絶え間ない闘い、「いくつかの数少ない同じ言葉を叙述することをめぐる闘い」(ベンヤミン)の帰結であることを示そうと試みた。言い換えれば、哲学はつねに「文献学の活用(変化)」でしかありえないのである。私たちの発表そのものもまた、仏独の言語を用いることを含めて、この活用の実践たらんとした。






